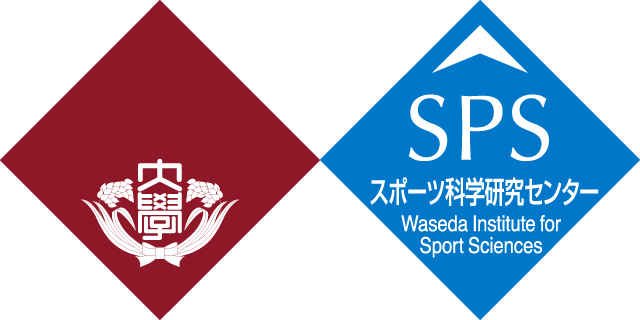- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2007年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2007年度)
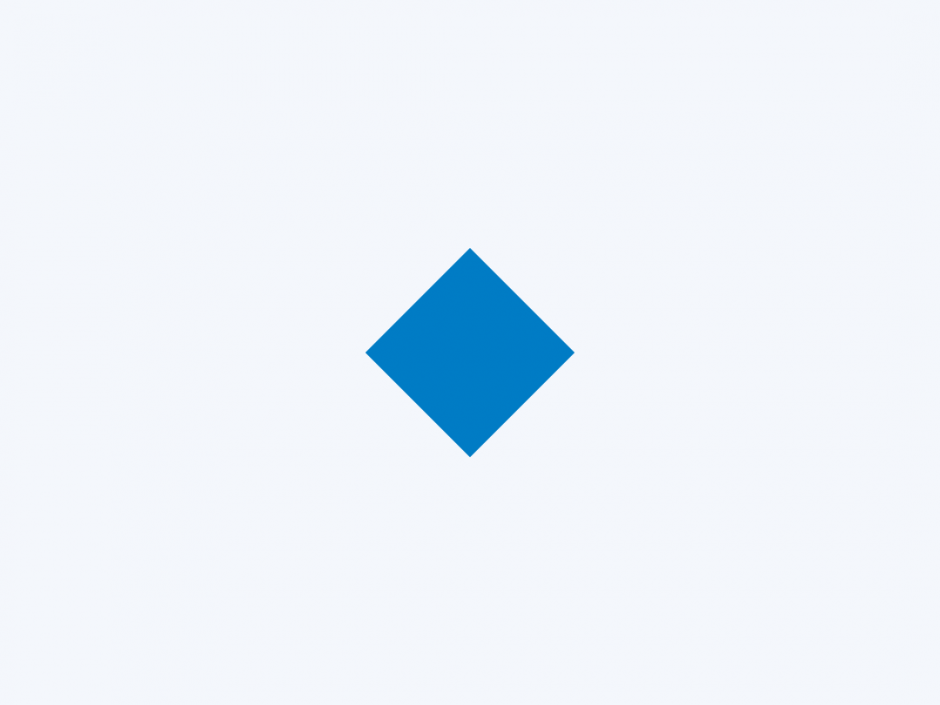
- Posted
- Sun, 02 Dec 2007
第50回 2007年12月18日
演題1
持久的トレーニングに対する骨格筋適応における転写因子PPARδの役割
演者
寺田 新先生(Washington University School of Medicine、Section of Applied Physiology、早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構)
内容
骨格筋に発現している転写因子PPARδは持久的トレーニングによって増加することが報告されている。しかしながら、その機能については不明な点が多く残されていた。
そこで、本研究では、持久的トレーニングに対する骨格筋の適応、特に糖・脂質代謝機能の改善機序にPPARδが関与しているという仮説のもと、分子生物学的手法を用い、マウスの骨格筋組織および培養骨格筋細胞にPPARδを高発現させ、どのような変化が生じるかを検討したので、その結果を報告する。
演題2
高齢期からの運動による心臓・血管への効果と分子機序
演者
家光 素行先生(奈良産業大学 教育学術研究センター ・ (独)国立健康・栄養研究所 健康増進プログラム)
内容
加齢に伴い、心臓・血管の機能は低下し、心血管疾患の罹患率を増大させる。その予防策の一つとして、習慣的な運動が注目されている。運動による心臓・血管の機能、形態、代謝への改善効果には、巧みな分子制御により、関連する遺伝子やタンパク発現の調節が行われていることが考えられるが、その詳細は不明である。
我々は、老齢ラットを用いた高齢期からの運動トレーニングによる検討から、(1)心収縮能の改善にthyroid hormone receptorによるミオシン重鎖や筋小胞体Ca2+-ATPaseの遺伝子発現増大の関与、(2)心収縮に必要なエネルギーを産生する機能の改善にPPAR-αによるβ酸化の酵素遺伝子の発現増大の関与、(3)酸素供給に必要な毛細血管の血管新生能の改善に血管内皮細胞増殖因子(VEGF)のシグナルカスケードの関与、(4)動脈硬化の抑制に内皮型NO合成酵素(eNOS)やエンドセリン(ET)-1による内皮機能改善の関与を見出した。
このように、運動による心臓や血管への刺激が、機能、形態、代謝のそれぞれに関連する分子制御(遺伝子やタンパクの発現調節)の変動を促すことによって、高齢期からの運動効果に関与していると考えられる。
第49回 2007年11月27日
演題1
上・下肢の律動的な協調運動の制御機構
演者
坂本将基先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
ヒトの歩行時には、上肢と下肢の律動的な協調運動がみられる。無意識な歩行状態では上肢と下肢が180度の位相差をもって対称的に動くが、ヒトは歩行時に上肢を意識して止めることも、また足と同じ方向に動かすことも可能である。このような上肢と下肢の協調関係が、どの程度無意識に(反射性に)調節されているのか、また、脳を中心とした意識的な制御がどのように遂行されているのかについては不明な点が多い。
近年、ペダリング運動を制御する神経機構が歩行運動のそれと類似する可能性が示唆されたため、ペダリング運動がヒトの歩行運動の神経機構を検討する運動モデルとして用いられてきている。さらに、上肢と下肢のペダリングを同時に遂行することにより、歩行中にみられる上・下肢の律動的な協調状態を再現する試みもなされている。そこで本研究では、上肢と下肢の同時ペダリング運動を用いて、上・下肢の律動的な協調運動にかかわる神経機構について検討を加えた。特に、脳および脊髄神経機構の活動を詳細に観察した。
演題2
動脈圧反射と筋機械受容器反射の相互作用
演者
山元健太先生(早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構)
内容
動脈圧反射は日常生活における血圧の安定化に極めて重要な機構である。この動脈圧反射は、頚動脈洞や大動脈に存在する圧受容器が血圧を感知しながら、自律神経系を介して血圧を調節する負帰還調節機構である。身体活動中は動脈圧反射に加え、上位中枢からのcentral command、活動筋からの求心性入力が循環中枢で統合され、血圧が調節されるが、その統合様式は複雑である。本研究は平衡線図解析や伝達関数(白色雑音法)という手法を用いて、活動筋からの求心性入力の一つである筋機械受容器反射が、動脈圧反射の静的および動的入出力関係に及ぼす影響を定量化した。麻酔下のウサギにおいて、圧受容器が存在する頚動脈洞を体循環から外科的に分離することにより、負帰還機構のループ(閉ループ)を開ループの状態にし、筋機械受容器反射活性化中の動脈圧反射の入出力関係を同定した。その後、開ループ状態で同定した動脈圧反射の静特性と動特性を解析的に閉ループ(生理的状態)に戻し、二つの反射の統合様式を検討した。その結果、筋機械受容器反射は、動脈圧反射による血圧調節を高速化させることが示唆された。また、この活動筋からの求心性入力などが存在しないと、ランニングや自転車運動のような動的運動時の血圧が低下する可能性が示された。
第48回 2007年7月24日
演題1
戦後の雑誌にみる女相撲に関する言説とその変遷
演者
一階千絵先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
日本の民族スポーツである相撲は、男性だけでなく女性も行ってきた。しかし女性の相撲(以下「女相撲」と表記)は猥褻な見世物とされ、従来の相撲文化研究において研究対象とされることが少なかった。
本研究では、戦後に発行された雑誌の記事をもとに女相撲に付された猥褻的イメージの様相とその変遷を追った。
女相撲に関する記事を多数掲載していた『奇譚クラブ』(1947~1975、曙書房)における記事には、女性の格闘に見出す美をさす「女闘美(めとみ)」と称する概念を通じ女相撲の理想像を描くものが多数見られた。寄稿家により美や魅力を見出す点に多少の違いはあるものの、女相撲の魅力をエロティシズムと密接な関連を持つものとして語る姿勢は共通している。
同誌以後の雑誌においては、女相撲は美意識よりもサディズム・マゾヒズムとの関連のもとに競技性が排除される文脈で語られることにより、女相撲は力と技を競うスポーツではなく特殊な性的娯楽の一形態であるとする言説の発生が見られる。
演題2
自律神経による心拍数調節:システム解析を用いた内部構造の理解
演者
水野正樹先生(国立循環器病センター研究所 先進医工学センター 循環動態機能部)
内容
心拍数は交感神経と迷走神経による二重の神経性調節を受けている。交感神経活動の亢進は心拍数を増加させ、迷走神経活動の亢進は心拍数を減少させる。それぞれの神経への直接電気刺激に対する心拍数応答を観察すると、交感神経と比して迷走神経の方が速い心拍応答を示す。この現象は、伝達関数を用いたシステム解析によって、交感神経刺激から心拍数への伝達関数は2次遅れ低域通過特性で、迷走神経刺激から心拍数への伝達関数は1次遅れ低域通過特性で近似することができ、それぞれの神経系の応答速度の差異を定量的に説明(システム同定)することが可能である。さらに、これらの心拍数の動的特性の差異は、それぞれの神経系における神経伝達物質の洞房結節への作用機序の違いや、その下流に存在する細胞内伝達機構の差異によるものであると考えられている。今回は、迷走神経が有する迅速な心拍数制御を担う内部構造(サブシステム)の理解に焦点を絞り、システム生理学的研究法を用いて概説する。
第47回 2007年6月26日
演題1
ナッブートの民族誌
演者
瀬戸 邦弘先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
エジプト・アラブ共和国の上エジプト地方では聖者を祝う祭りに際して、ナッブートと呼ばれる民族スポーツの競技会が開催される。ナッブートとは本来アラビア語で「杖」を指す言葉で、上エジプト人は祝祭の折にこの杖を用いて、剣道やフェンシングのような形態の格闘技の試合を行う。本研究ではこのナッブートの競技会を通して、当該地域の人々が如何に地域に対するアイデンティティを確立し、それを維持・再生産するプロセスを考察する事をその目的とする。また、本競技には実修者達のみに共有される身体観が存在し、その身体観を基とした身体技法が確立されており、現地における参与観察を通して、研究者のエティックな視点はもとより、実修者のみが知りうるイーミックな視点の両視点からのナッブートの研究も行われる。
本研究ではナッブートを包含する祭り全体という大きな枠組みから、競技会の運営に関わる人々、参加者、競技空間など競技会を取り巻くさまざまな構成要素もあわせて考察が展開され、その意味では伝統な民族スポーツ「ナッブート」を巡る総合的な文化研究といえる。
演題2
生体電気インピーダンス法を用いた筋量および腱伸長量測定法の開発
演者
太田めぐみ先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
トレーニングや加齢により骨格筋量(以下、筋量)や腱伸長量は変化する。筋量や腱伸長量の簡便な推定法として、生体電気インピーダンス(bio-electrical impedance:BI)法が適用可能かどうかを検討した
- 体幹部筋量の推定:全身重量のおよそ50%を占める体幹部の筋量を推定するため、新たなZ誘導法を開発・検討した。競技者12名を含む28名から体幹部のZを誘導し、体幹のBI indexを算出した。その結果、BI indexとMRI法で求めた筋体積の間には有意な相関関係が認められた(r = 0.844、p < 0.05)。また得られた関係式(体幹筋体積の推定値 = 143.6×体幹BI index + 45.2)に交差妥当性があることが示された。
- 腱伸長量推定に関する研究:等尺性肘関節屈曲筋力発揮中の上腕部のZを誘導し、超音波法で定量した腱長変化との関係を検討した。両者の間には非線形の関係が認められ(y = – 0.044×2 + 0.704x + 0.111、 R2 = 0.988、p < 0.001)、BI法で腱長変化が推定可能であることが示された。しかしながら、Z変化の感度には個人差が大きいことから(0.24~0.89% / mm)、腱伸長量の推定式確立に向けては、更なる検討が必要である。
第46回 2007年4月24日
演題1
生活習慣病に関連するミトコンドリアゲノム多型およびハプログループ
演者
福典之先生(東京都老人総合研究所 健康長寿ゲノム探索研究チーム 主任研究員)
内容
ミトコンドリアは独自のDNA (mitochondrial DNA、 mtDNA)を持ち、核DNAとは独立して複製される。また、mtDNAの遺伝様式は母性遺伝である。mtDNAを詳細に解析することにより約15万年前にアフリカで誕生した人類がどのような経路を辿って日本まで到達したかを知ることができる。すなわち、北方経由で寒冷に適応した人類か否かなどを知ることも可能である。このような人類の移動により細胞内小器官であるミトコンドリアもその環境に適応するために多様な変化をしたと推定される。このようなミトコンドリア機能の違いがエネルギー代謝能を変化させ、現在においては、生活習慣病などに対する易罹患性に影響を及ぼしていると考えられる。我々は、これまでに、生活習慣病や長寿および陸上競技長距離選手などを対象にmtDNA多型との関連性について検討してきた。そして、mtDNA多型の解析からミトコンドリアハプログループに分類すると、いくつかのハプログループは糖尿病・メタボリックシンドロームおよび長寿と関連することが分かってきた。また、日本人の若干名ではあるがトップアスリートのミトコンドリアハプログループについても解析した。本研究会ではこれまでに我々の研究グループで得られた知見について紹介する。
演題2
Environmental and Genetic Determinants of Elite Athletic Performance:Examples from Africa
演者
Robert Scott先生(Post-doctoral Researcher, Faculty of Biomedical and Life Sciences, University of Glasgow)
内容
At every major international athletic competition, it is likely that the majority of finalists in the 100m sprint will be of west African origin, and that those enjoying success in distance running events will be of east African origin. Many explanations have been proposed for this phenomenon, including the belief that African athletes have a genetic advantage in sport. While it is becoming evident that there is a genetic component to the determination of elite athletic performance, the extent of its influence is unclear. Also, the extent to which genetic differences between populations account for inter-population differences in performance are also unknown. In this talk, I shall review the available evidence for the domination of African athletes in international sport and present data from our studies of elite African athletes investigating both environmental and genetic determinants of their success.
第45回 2007年2月27日 2006年度修士論文発表コンテスト
セッション1
座長
時澤健(村岡研究室)
15:05 光学非接触式3次元人体形状計測法に基づく日本人女性の体表面積の推定式作成
設楽佳世(福永研究室)
15:18 若年成人女性の身体組成と基礎代謝量について
高橋恵理(樋口研究室)
15:31 動作の方向と筋活動のタイミングが同側手足の協調動作に与える影響
大部隆志(彼末研究室)
15:44 プロ野球私設応援団の文化論—福岡ソフトバンクホークス—
岡田依子(寒川研究室)
15:57 近世における起倒流柔術の歴史的実態
中島哲也(志々田研究室)
16:10 スポーツ、アイデンティティ、「国民」概念—その関係と歴史—
池端宏之(トンプソン研究室)
セッション2
座長
勝亦陽一(福永研究室)
16:35 足部運動解析の新展開
深野真子(福林研究室)
16:48 反復的な足関節底屈運動中の腓腹筋内側頭およびヒラメ筋の動態からみた筋力低下の規定因子に関する研究
光川眞壽(川上研究室)
17:01 平面的および空間的位置関係の知覚の相互変換に関するfMRI研究
金松慶(内田研究室)
17:14 Hypoxia-inducible factor-1αの一塩基多型が低酸素刺激に対する応答の個人差に及ぼす影響
梶川悟(村岡研究室)
17:27 携帯電話のメール機能を活用したウォーキング行動促進プログラムの開発
山脇加菜子(中村ょ研究室)
17:40 わが国の球技系トップリーグ観戦者に関する研究—クラスター分析を用いた観戦者の分類—
高田一慶(原田研究室)
優勝
光川眞壽(川上研究室)
二位
深野真子(福林研究室)
三位
設楽佳世(福永研究室)
特別賞
池端宏之(トンプソン研究室)
第44回 2007年1月30日
演題1
体操競技の運動技術
演者
村田浩一郎先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
男子体操競技は6種目(床、鞍馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒)からなり、跳馬を除く5種目は、約10個の「技」で構成される「演技」として実施される。また、その勝敗は審判員のシステマティックな採点によって序列化されることで決定する。審判員は採点規則(2006年度版採点規則)をもとに、価値点(A得点)の算出と実施に対する減点(B得点)を行い、その合計が競技者の得点となる。したがって、競技者が高得点を獲得するためには、高難度の技をできるだけ多く、かつ減点されずに実施しなければならない。今回はいくつかの種目を取り上げ、運動技術に関する最新情報と、その解明への糸口となるであろう研究アプローチについて紹介する。
演題2
1910年代における「呼吸健康法」の流行について
演者
佐々木浩雄先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
1910~20年代には、国家による健康・体力向上のための施策が推進される一方で、呼吸法、強健術、食餌療法、霊術など様々な健康法や癒しの技法が広がった。その中でも「岡田式呼吸静坐法」「藤田式息心調和法」「二木式腹式呼吸法」が三大健康法と呼ばれたように、「呼吸健康法」は精神修養的な意味合いも持ちつつ、肺結核予防や虚弱体質改善を目指す「積極的衛生」の方法として1910~20年代に流行した。これらは、技法に違いはあるものの、いずれも〈丹田〉や〈気〉といった概念を用いて身体・精神を総合的に捉えようとしている点、坐を伴い、丹田に意識をおく腹式呼吸法を基本としている点で共通している。
本発表では、急速な近代化を進める社会において健康観がどのように変容し、「呼吸健康法」にみられる伝統的な身体技法がどのように位置づけられたのかという関心から、1910年代における「呼吸健康法」流行の背景について述べ、そこから読みとれる生理学・解剖学的知見に立った近代的身体観と心身一如の思想に裏づけられた東洋的身体観との揺らぎの状況について論ずる。
- Tags
- 研究活動