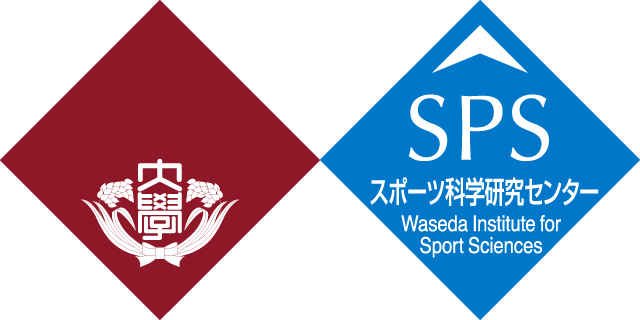- ニュース
- Elucidation of The Effect of Flossing on Improving Joint Range of Motion/フロッシングによる関節可動域改善効果の解明
Elucidation of The Effect of Flossing on Improving Joint Range of Motion/フロッシングによる関節可動域改善効果の解明
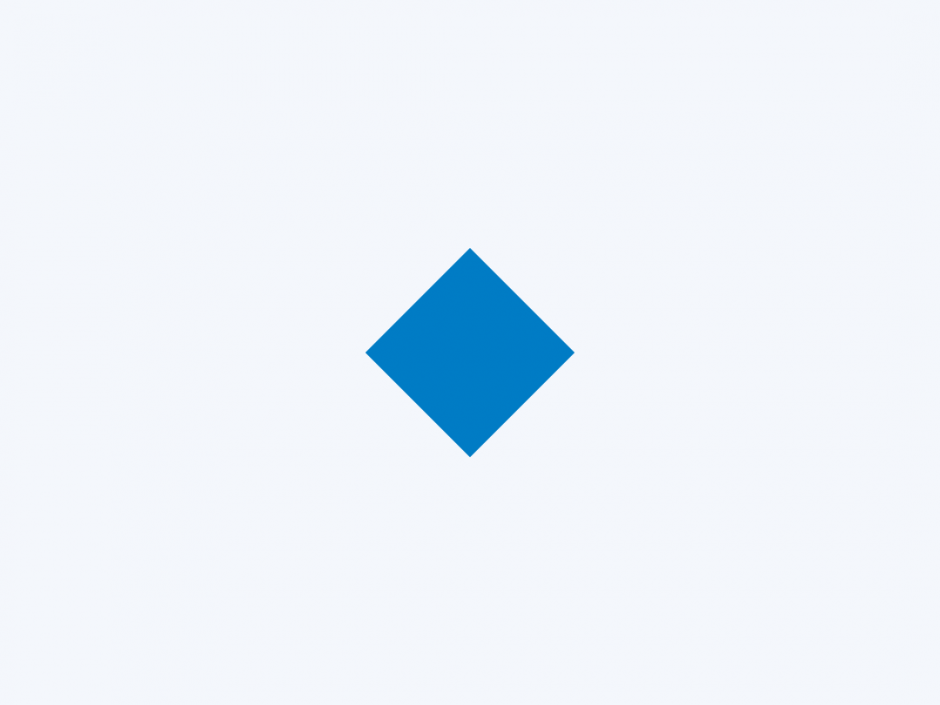
- Posted
- Tue, 04 Feb 2025
概要
フロッシングはスポーツ現場で用いられるコンディショニング手法の1つです。使用目的の1つとして筋膜の滑走性向上による関節可動域の改善・向上が考えられていましたが、筋膜に影響を与えているのか、関節可動域が実際に変化しているのか、これまで明らかではありませんでした。本研究結果より、腓腹筋上部における筋膜硬度の減少と足関節背屈可動域の増加が確認されました。これにより、筋膜間の滑走性向上が関節可動域の改善・向上に寄与する可能性が明らかになりました。
(1)これまでの研究で分かっていたこと
これまでの研究や知見から、フロッシングというマイオファシャルリリースの一種が、関節可動域(Rage of motion: ROM)の改善・向上や筋肉・筋膜の硬さに影響を与える可能性があることがわかっています。フロッシングは、筋肉や関節にゴムバンド(フロスバンド)を巻きつけ、圧力を加えながら運動を行う方法で、これにより上述の効果が得られることが期待されています。フロッシングもその一環として、特に筋膜の硬さを減少させ、組織間の滑りを改善することが示唆されています。その結果、ROMの増加や筋力の向上、さらには筋肉痛の軽減にも効果があるとされています。一方で、フロッシングが具体的にどの組織、特に筋膜や筋肉にどのように作用するのかについては、まだ十分に解明されていませんでした。これまでの研究では、フロッシングが筋膜の硬さを改善し、組織の滑走性を向上させることが仮定されていますが、これらの効果が実際にどのように発生するのかについてはさらなる研究が必要でした。
(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
本研究では、フロッシングがROM及び筋肉・筋膜の硬さに及ぼす具体的な影響を超音波診断(Shearwave Elastography: SWE)を用いて評価することを目指しました。特に、フロッシングによる筋肉・筋膜の硬さの変化を定量的に解析し、そのメカニズムを明らかにすることを目的としました。
(3)そのために新しく開発した手法
今回の研究では、新しい技術の開発というよりも、既存の手法を効果的に組み合わせることで、フロッシングの効果を科学的に評価する点に注力しました。まず、筋肉・筋膜の硬さを客観的に測定するために、SWEを活用しました。これにより、従来の主観的評価では困難だった硬さの定量的評価を可能にしました。また、フロッシングという圧迫手法と運動を組み合わせた介入方法を実施し、その即時的な効果を筋肉・筋膜の硬さの変化、さらにROMの改善という観点から分析しました。特に、フロッシングの圧迫方法や運動内容を標準化することで、介入条件の再現性を確保し、得られた結果の信頼性を高めました。このように、本研究ではSWEを用いた定量的評価と標準化された介入方法を組み合わせることで、フロッシングの有効性を科学的に示し、スポーツ現場やリハビリテーションにおける実践に役立つ新たな知見を提供しました。
(4)研究の波及効果や社会的影響
本研究の成果は、スポーツ現場やリハビリテーション分野、さらには一般の健康管理において幅広い波及効果や社会的影響をもたらす可能性があります。具体的には、フロッシングが筋肉・筋膜の硬さを軽減し、ROM改善する即効性のある手法であることが確認されたため、スポーツ現場でのウォームアップやクールダウンの新しいアプローチとしての普及が期待されます。また、リハビリテーションにおいても、非侵襲的で短時間の介入手法として新たな治療選択肢を提供する可能性があります。さらに、本研究はこれまで経験的に用いられてきたフロッシングの効果を科学的に証明した点で、エビデンスに基づく介入の重要性を強調し、科学的根拠に基づいたトレーニングやリハビリ手法の普及を促進します。また、特別な機器や高度なスキルを必要としないフロッシングは、一般の人々にもセルフケアとして活用でき、慢性的な筋肉の硬さや柔軟性の低下に悩む人々の健康促進や生活の質向上に寄与することが期待されます。
(5)今後の課題
本研究の成果を踏まえ、今後の課題として以下の点が挙げられます。第一に、フロッシングが長期的にどのような影響を及ぼすのかについては明らかになっていません。定期的なフロッシングの実施が筋肉や筋膜の硬さ、柔軟性、ROMに与える持続的な影響を検証する必要があります。第二に、今回の研究対象は健康な被験者でしたが、年齢や性別、さらには特定の疾患やスポーツの種類によって効果が異なる可能性があるため、幅広い対象への適用可能性を探る研究が求められます。また、フロッシングの効果を他の介入法(ストレッチング、マッサージなど)と比較し、その相対的な有効性を明確にすることも重要です。これにより、適切な治療法の選択肢を提供できるようになります。さらに、フロッシングの効果を支える生理学的メカニズム、特に血流改善や筋膜の滑走性向上に関する具体的な変化を解明することも、科学的な裏付けを強化するために必要です。最後に、圧迫の強さ、巻き方、実施時間、運動内容などのプロトコルを最適化することで、フロッシングの効果を最大化するための具体的な指針を構築することが求められます。これらの課題に取り組むことで、フロッシングの科学的基盤がさらに強化され、スポーツや健康維持における活用の幅を広げることが期待されます。
(6)研究者のコメント
本研究では、フロッシングが筋肉や筋膜の硬さに及ぼす影響を科学的に検証し、その可能性を示すことができました。この成果は、スポーツパフォーマンスの向上やリカバリー、さらにはリハビリテーション分野における新たなアプローチとしての応用が期待されます。特に、簡便で手軽に実施できる点は、多くの人々にとって日常生活に取り入れやすいメリットと言えると考えています。今後もフロッシングのメカニズムや最適なプロトコルの探求を通じて、健康増進やスポーツ現場に貢献できる方法を追求していきます。
(7)用語解説
・フロッシング
ゴムバンドを用いて筋肉や関節を圧迫し、その後解放することで血流を促進し、筋肉や関節の可動性を改善する手法。リハビリテーションやスポーツパフォーマンスの向上を目的に用いられる。
・筋膜
筋肉や臓器を包み込む結合組織で、身体の柔軟性や動きに重要な役割を果たしている。近年、この筋膜の健康が身体機能や痛みに影響を与えることが注目されている。
(8)論文情報
雑誌名/Journal:Journal of Sports Science and Medicine
論文名/Title:Elucidation of The Effect of Flossing on Improving Joint Range of Motion
執筆者名・所属機関名/Authors and Affiliated Organisation:
前道俊宏*(早稲田大学スポーツ科学学術院)、小川祐来(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科)、若宮知輝(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科)、山口龍星(早稲田大学大学院スポーツ科学研究科)、永元英明(早稲田大学スポーツ科学研究センター)、熊井司*(早稲田大学スポーツ科学学術院)
*:責任著者
Publishment Date(Local Time):2025年3月1日
Publishment Date(Japan Time):2025年3月1日
URL:https://www.jssm.org/jssm-24-75.xml%3EFulltext
DOI:https://doi.org/10.52082/jssm.2025.75