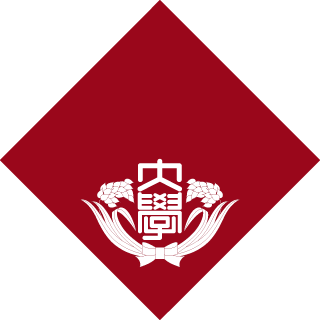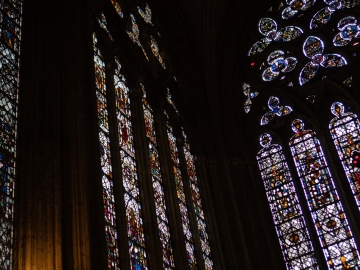- 海外派遣学生
- 中村 凪Nagi NAKAMURA
中村 凪
Nagi NAKAMURA

- Posted
- Mon, 25 Mar 2024
基幹理工学研究科 修士2年 中村 凪 Nagi NAKAMURA
- 派遣期間:2023年7月~10月
- 派遣先大学:シェフィールド大学
- 派遣先国・地域名:イギリス・シェフィールド
海外派遣希望理由
私が留学を希望したのは、価値観の多様性や英語スキル等の日本で学びにくいものを肌で感じるため、そして逆に、外部からの視点で日本での自分の環境や生活を見直すためです。私は高校の時の短期交換留学などの経験から大学入学当初よりどこかのタイミングで留学してみたいと考えていた一方で、めんどくさがりな性質が災いして必修科目やコロナ禍、就活等々を理由に留学にずっと足踏みをしていました。転機となったのは修士1年の冬に出席した国際学会です。国内外の他研究室の方々との交流から、視点や価値観、生活スタイルの多様さに驚き、自分の不寛容さ、また英語能力やセルフマネジメントの不足を痛感しました。そして残りの学生生活を考えるとここが学びのラストチャンスだと思い立ったため、募集に出願しました。こうした寛容さや英語スキル、マネジメント能力等を学びたいというのが1つ目の希望理由です。また、対外的な1つ目の内容とは逆に、海外の方が優れていると思ってしまう盲目的な視点に常々疑問を持っていたというのも関係しています。ないものねだりではなく、日本の環境はどこが魅力的で、どう主体的にその長所の恩恵を活かしていくのか、外部に一旦出てみることで客観的に考えられるようになりたいというのが2つ目の希望理由です。
現地での研究内容・成果
The University of SheffieldのDepartment of Automatic Control and Systems Engineeringにおいて、Dr Shuhei Miyashitaのもとで、複数の形態に変形する折り紙ロボットの研究を行いました。日本で私は折り紙を用いた電子デバイスの研究を行っており、関連分野として先方で取り扱っている折り紙ロボット、特にその基礎的な変形機構を制作しました。既存の研究では、基本的に折り方は1通りで扱いますが、私は折り方Aから一旦展開して、折り方Bに移るロボットを目標としました。例えば、将来的には体内での誤飲した異物除去を行う折り紙ロボットにおいて、圧縮形態からグリッパ形態に移行するといった利用シーンが考えられます。その過程で必要となる,外部刺激によって勝手に展開し、かつ折りたたみするヒンジの製作が中心的な研究成果です。具体的には、遷移のために一度折られたシートを水という刺激で自己展開し、その後熱という刺激によって再び自己折りたたみます。3ヶ月の派遣期間において、水で膨張する乾燥アガロースゲルと熱で収縮する熱収縮フィルムを組み込んだヒンジ構造の試行錯誤を行い、完成したヒンジを用いたいくつか折り線パターンのサンプル制作を行いました。これらの研究内容をまとめ、現在ジャーナルへの投稿を目指し論文執筆中です。
学校環境
特に日本と異なっていたのはルールの厳しさと細かさです。研究室の開室時間は平日AM8:30~PM6:00と厳しく設定されており、かつ現地博士生以外は鍵を持てないため、外部生かつ修士生の私は他の学生に開室・閉室してもらう必要がありました。またとても厳しい安全管理のためのルール、リスクアセスメントの徹底等の必要もありました。英国大学の中でも厳しい方だと聞きましたが、初めは日本とのギャップに戸惑いました。しかしながらうまく研究をやりくりすることを学びたかったため、いい機会だったと思っています。イギリスでは大学の所要年数が日本とは異なり、私の周りでは学部3年、修士1年、博士4年といった流れの学生が多数でした。博士生の数は明らかに日本よりも多く、学部生、修士生は入れ違いで半期ずつしか研究室自体には顔を出す必要がないため、私の滞在期間では1/3が修士、2/3が博士と行った様子でした。また、日本と比較すると学生主体の研究室運営であると感じました。というのも、先生ももちろんアドバイスをくださいますが、特に学生同士の助け合いが顕著で、研究自体の話から運営的な話まで一日中どこかで誰かがディスカッションをしており、チームワークの強さを感じたためです。
国際交流
先生夫婦が研究室を共有して運営しているため、常に交流できる学生の数が他よりも多かったのは私にとって幸運でした。イギリス・フランス・イタリア・エジプト・中国・キプロス等々といった様々なナショナリティの学生が所属しており、毎回一緒に食べていた昼食ではそれぞれの国の文化に関する話が鉄板の話題でした。その中でも、中国人留学生の数は圧倒的で、大学ランキングが高かった年の代は学部の半分が中国人だったそうです。研究室の閉室後に地元のサッカーチームの応援にいったり、ディナーや映画に出かけたりしたのはいい思い出です。そういったタイミングで友達の友達と繋がることができるため、研究室以外の学生とも多く交流することができました。また、縁があって休日に麻雀をしているグループに加わったり、日本で博士を取ったポスドクの方と仲良くなったりという出来事もありました。どこに行っても人と人が気軽に話しかけ合う雰囲気があり、結果的に活発にディスカッションが生まれる土壌となっているため、見習いたい性質だなと感じました。
住居環境
留学決定から出発までの準備期間がタイトだったことと、ちょうどハイシーズンであったこともあり、連続した宿泊施設が確保できず、滞在中に2回引越しをしました。どれも研究室から徒歩20~30分の距離にあり、Sheffield市街の南側の地域に住んでいました。引っ越しがあったのは色々と手間がかかった一方でいい機会でもあり、1軒目が70歳くらいの女性の家での居候、2軒目が4組入居できるシェアハウス、3軒目が40代くらいの男性の家で2組の居候がいるという異なる住環境を体験することができました。どこも基本的に手前に一坪くらいの庭があり、真ん中に家部分があり、裏に2坪くらいの庭があるイギリスの一般的な家屋構成でした。また、イギリスでは戸建てが横一列に連結した昔ながらの家が多く並んでいますが、今回滞在した宿はどこもその形態でした。日本や世界中が猛暑に襲われる中、イギリスは20℃程度の涼しい気候でしたが、それでも友達は“今年は猛暑だ”と言っていました。確かに、涼しいとはいえ25~26℃に至る日もあり、そんな日には煉瓦造りの家はオーブンのように熱を溜め込むため暑いと感じることは少なくありませんでした(普通の家にはエアコン・扇風機が常備されていません)。
周辺環境
シェフィールドは西にマンチェスター、ピークディストリクト国立公園、北にヨークと言った観光地があるようなイングランド中部の中規模都市です。昔は鉄の生産で有名でしたが、今は大学が2つある、学生の街です。私は衣食住に関して基本的には、店がなくて困るということは感じませんでした。イギリス全土的にそうですが、個人経営のお店が日本より多くて栄えていると思います。一方で、大きい買い物施設がないので、例えば日本でいうビックカメラ、ドンキホーテ、東急ハンズのような、大体行けば探しているものがあるという店がほぼ見られませんでした。そのため、通販を多く利用することになりました。イギリスだと基本的に再配達も置き配もないのでどうするかというと、近所の人に配達員が品物を預けます。みんな横に連結した家に住んでいるのでお隣さんとの関係もまた日本とは違うように感じました。宅配ロッカーを使うことも可能です(基本満杯ですが)。交通についてはロンドンや東京とは異なるので、基本的に通勤・通学圏内は街で閉じており、徒歩圏orバス圏に住んでいる人がほとんどでした。シェフィールドの場合は街中に学生用アパートが乱立しているので、大学から徒歩5分以内のところに住んでいる学生が大多数だったように思います。鉄道は出かける時に使うものというイメージでした。また、地域により治安の差があり、シェフィールドだと東や東北方向が良く、家も大きいです。一方、北や南、また中心街から離れると急に雰囲気が変わります。私は南の方に住んでいたため、夜中はあまり出歩かないようにしていました。思っていたよりも治安の差や経済格差があると感じたことは今回の派遣で印象的だったことの一つです。
書きそびれましたが、石造りのため年季の入った建造物が至る所にあり街全体に見所が多いです。現地のホームセンターではドア、窓、バスタブなど石造りの家の中身だけをリフォームするための資材について品揃えが多く、古い建物を使い続ける文化の違いを感じました。
現地の文化など日本との違い
行く前から意識していた食文化は確かに大きな違いでした。現地では安くお腹を満たせるただ甘いものが多いと感じました。また、お弁当(ミールディール)や外食は割高な一方、野菜などの材料は種類が多く物価に対して割安なので、留学生は基本的に材料を揃えて自国の料理を家で作っていました。一方、住居のホストの様子を含めても、イギリスの家庭料理は手間のかかる下準備を要する料理ではなく、”入れて焼く・煮るだけ”の料理が多く、そう言った意味で”食に興味がない”という印象を受けました。材料自体は美味しいです。レストランは高くてあまり行けませんでしたが美味しいです。また、雨の多い気候や災害の少なさ、ヨーロッパの近さといったよくある内容のほかに印象的だったのは、人の陽気さです。日本が大好きな宿のホストは私に、イギリス人は自己中心的だけど日本人は優しく礼儀正しいから素晴らしいという意見を言っていましたが、私としてはイギリスに住む人が、他人にすぐに話しかける陽気さを持っている点が素晴らしいと感じました。他の人が困っていそうな時に話しかけたり、レジやエレベーター、電車等で初対面の人同士がよく世間話をしたりと、シャイさが邪魔をするような場面で進んでコミュニケーションをとることができる性質をイギリスに住む人は持っていると思います。
海外でのトラブル
滞在中にいくつか困ったこともあったので、参考になればと思い書き残します。まずひとつ目は洗濯についてです。私が渡航したのは7月の半ばでしたが、そこから1ヶ月弱はほとんど毎日雨が降っていました。渡航前のイメージでは、雨が多いのだから洗濯機には乾燥機能が当然ついているだろうと思っていたのですが、そんなことはなく宿泊した3軒とも乾燥機はついていませんでした。学生アパートには完備されているという話でしたが、下宿などの昔ながらの建物の場合、キッチン下の小さいスペースに収まる洗濯機しか導入されていないのが普通なので、その点に関しては事前にイメージをつけておくのが良いと思います。
次に、2つ目は帰国便でのトラブルです。マンチェスターからドバイ乗り継ぎで帰国する予定でしたが、家を出る直前に1本目の飛行機が2時間遅延する旨のメールが届きました。しかしながら、ただの通知で、対策や補填に関して何も記載も問い合わせ先情報もなく、かなり不安になりました。また、電車も駅に着いてみると通知なく欠便になっており(なんとかして空港までたどり着いたのですが)困りました。飛行機が遅刻すると乗り継ぎの最短時間を満たさないため、チェックインカウンターで振替があると思っていたのですが、係の人に聞いても埒が開かなかったので、とりあえずドバイまで行ってみることにしたのですが、さらに遅延が悪化しており、乗り継ぎが不可能になり2便目の振替が行われました。振替便は丸一日後の便であったので、ホテルを予約する必要が生じ、空港会社の窓口に電話して補填してもらえるように交渉しました。(国際電話で30分もかかってしまいましたし,最初は断られたのでかなり粘りました。)予想外にドバイで1日過ごす羽目になった上、スーツケースは返却されないので、着替え等を用意できなかったのは少し困りました。このトラブルの教訓としては、予想外の足止め対策として、帰国便でも1日は過ごせるだけの荷物(特に充電器)を機内持ち込み荷物とすることと遅延情報に精神的に振り回されすぎないようにすることです。
海外派遣を経て今後の目標
私は派遣を通して外国を肌で感じることと日本について客観的な視点を得ることを目的としていました。完璧ではないと思いますが、そのどちらも満足できるレベルで達成できたと思っています。留学生の多い大学であったこともあり、イギリスだけではなくより様々な国々の人々の価値観や文化に触れることができ、また比較して日本との違いについても多く考えました。
その中で私が感じたことは2つあります。1つめは”日本”を、他人に自分の視点で説明することができるべきだということです。そして、国際情勢・経済,国の政策や人口構成、競争力などを見て、自分の人生のプライオリティを日本のこれからに求めることができるのか、求めたいのか、ということについてフラットに考え、他人に対して言語化して説明できるようになるという目標が得られました。
2つめは英語の意思疎通能力の必要性です。正直今回の派遣では、1、2番目に挑戦したいことがセルフマネジメントと研究で、英語は3番目くらいの優先度のつもりでした。しかしながら、結果として感じたのは英語で躓かないことが上記の2つをもっと長期で学ぶために必須であると感じました。
今回の派遣は終わりましたが、今後、むしろより力を入れて勉強をしたいと思います。ある意味、世界の広さや学びの深さの再認識ができたように思います。就職後は積極的に海外派遣や社会人博士のチャンスを狙っていきたいと思うような良い経験でした。もし、留学に行きたいとは思っていたけどなかなか実行に移せなかったという方がいたら、M2でも遅くないので行くべきだと伝えたいです。