- ニュース
- 【著作紹介】『非認知能力の発達:生涯にわたる変化と影響』(文学学術院教授 小塩真司)
【著作紹介】『非認知能力の発達:生涯にわたる変化と影響』(文学学術院教授 小塩真司)
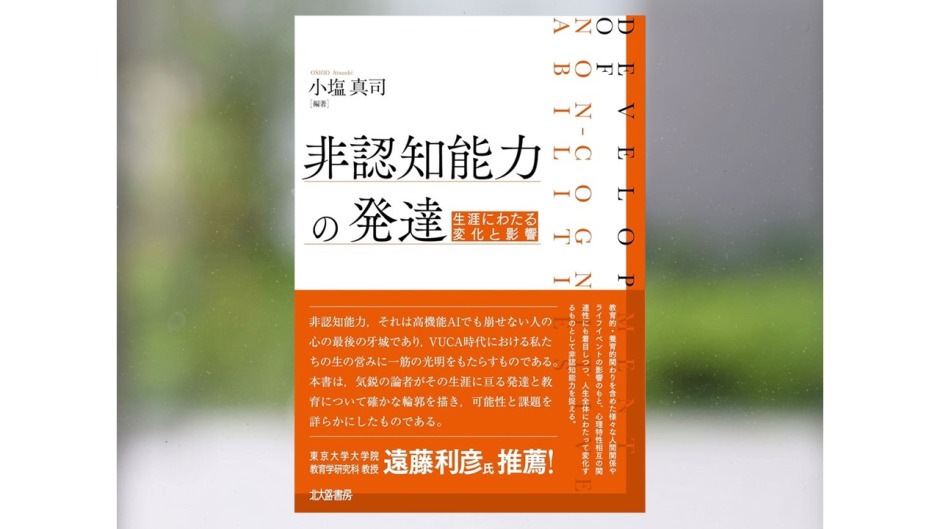
- Posted
- Mon, 18 Aug 2025
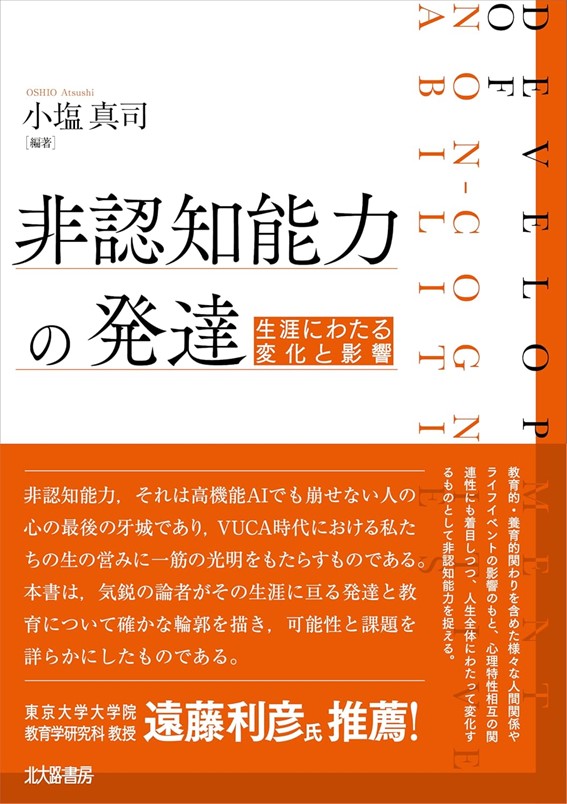
北大路書房 初版 2025年4月21日 336ページ ISBN-13 : 978-4762832826
「非認知能力」という言い回しも,一種,流行のようになっています。この言葉は,心理学を専門とする研究者からすると,大きな違和感を抱く言葉でもあるのです。なぜなら,心理学で【認知能力】といえば,人間が知覚・理解・記憶・思考・学習・問題解決・意思決定などの精神的処理を行うための基本的な能力全般を指すからです。そしてこの考え方に基づけば,「『非』認知能力」と言ったとき,「認知能力以外にいったい何が残るのか?」「認知能力以外のいったいどの部分を指すのか?」と困惑してしまうことになるからです。
一方で,「非認知能力」という概念が出てきた背景には,「知能」という,こちらも心理学にとっては歴史的に重要な概念と,「知能検査」そして「知能指数(IQ)」という,測定手法と表現手法の存在があります。「非認知能力」という言葉が生まれた背景には,知能を伸ばそうとする介入の実践活動の中で,知能「以外」の心理学的特性が注目されてきたという経緯があるのです。
「非認知能力」という言葉における「非」以外の「認知能力」というのは,「知能検査で測定されるもの」そして「学力テストで測定されるもの」を指します。これは,心理学における広い範囲の【認知能力】を指すわけではないのです。従って,「非認知能力」という言葉には,心理学における広い範囲の【認知能力】(つまり,知能検査や学力試験で測定されるような認知能力以外の広い範囲の認知能力)も含め,広範囲にわたる心理学的な特性や機能が含まれることになります。実際に,多種多様な心理学的な特徴や特性,機能が「非認知能力」という枠組みの中に含まれています。
さて,本書は,このような複雑な背景をもつ「非認知能力」について,特に発達的な形成,変化,また教育や介入の可能性について概観しようと試みるものです。全体は14章で構成されていますが,それぞれの章を専門とする研究者がまとめています。非認知能力というものに注目した場合に,どのように生涯発達とつながっていくのか,全体的に理解する助けとなることが期待されます。
〈研究内容紹介〉
人間(だけではないのですが)の心理学的な個人差に関連して,どのような法則が存在しているのかを広く研究しています。平たく言うと「性格」のようなものを研究しているのですが,多くの研究は調査を基礎としており,統計的な法則を見出そうとすることが中心となっています。
早稲田大学文学学術院教授
小塩 真司(おしお あつし)
名古屋大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育心理学)。中部大学人文学部を経て,2012年より早稲田大学文学学術院准教授,2014年より現職。専門はパーソナリティ心理学,発達心理学。書籍は『性格とは何か』(中央公論新社,2020年)など多数。
(2025年8月作成)
