- ニュース
- 【著作紹介】『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、西城戸誠)
【著作紹介】『芦別 炭鉱〈ヤマ〉とマチの社会史』(文学学術院教授 嶋﨑尚子、西城戸誠)
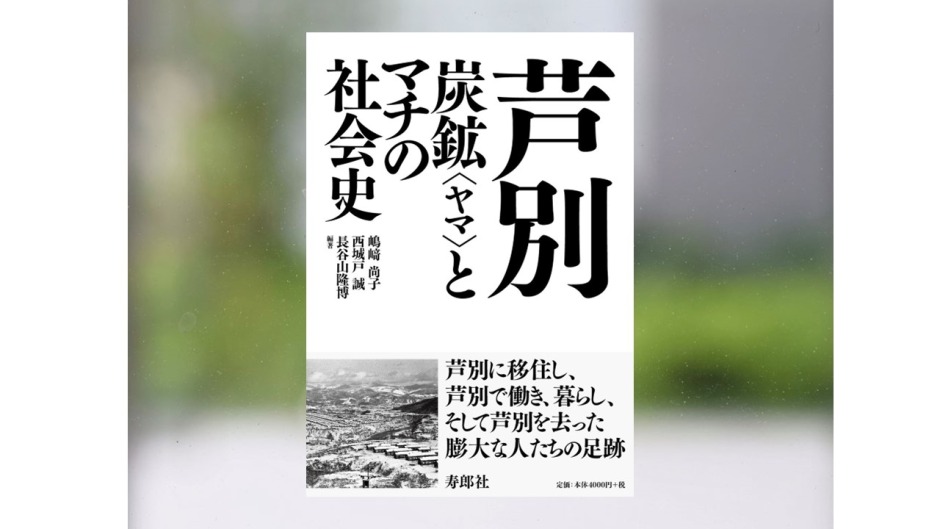
- Posted
- Fri, 20 Sep 2024
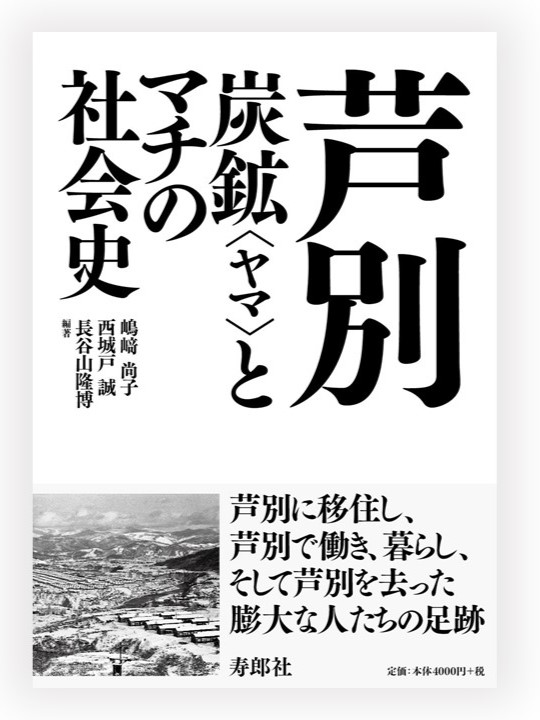
寿郎社、初版刊行日2023/12/28、B5判 340頁 並製(口絵52頁)、ISBN978-4-909281-56-2)
本書は、北海道芦別市にある空知炭田に位置し、北海道内で最後まで残った三井芦別炭鉱に対象にした地域史である。芦別市制施行(1953年)からビルド鉱としての苦闘の過程、1992年の閉山とその後の芦別の産業・社会構造の変容について、炭鉱労働者の仕事や賃金、労働力の移入と移出、労働組合や炭鉱事故、炭鉱の住まい、女性の活動や子どもなどに着目し、炭鉱のマチから地方都市への変貌した芦別の社会史を描き出した。
本書の特徴は、第1に「地域博物館」として芦別五山や芦別市内の諸組織による刊行物など多様な資料を網羅的に整理・収蔵した、「芦別の宝箱」ともいうべき芦別の星の降る里百年記念館の収蔵資料を用いたことだ。第2に本書は学術書だけではなく芦別という地域の記録集という側面もある点である。本書の第一部「写真記録 昭和の芦別」の100枚の写真は、芦別に移入し生活し、そして去っていった膨大な人びとの「懐かしい思い出のアルバム」である。実際に芦別に縁がある方々から大きな反響を頂いている。
この写真記録を始め、芦別の膨大な資料収集・整理は本書の編者の一人である、元・星の降る里百年記念館館長の長谷山隆博さんが行った。長谷山さんは考古学が専門の学芸員であるが、1993年の同館開設にあたって「芦別のことは全部知っている人」になろうと決意し、長い期間をかけてそれを実現した。私たちは膨大な資料をもとに長谷山さんと議論を重ねて本書の刊行に至った。だが、大変残念なことに長谷山さんは本書刊行の喜びもつかの間、2024年2月9日に逝去された。長谷山さんのこれまでのご功績に敬意を表し、心からご冥福をお祈りするとともに、長谷山さんと共に本書を創ることができたことに感謝したい。
〈研究内容紹介〉
本書の編著者である嶋﨑尚子と西城戸誠は、2008年に発足した産炭地研究会に所属している(代表は中澤秀雄(上智大学教授))。産炭地研究会では、日本国内・国外の産炭地を対象に、社会学ならびに経済史の視点から石炭産業史、炭鉱での労働・仕事、地域社会の動態に関する調査研究活動を進めてきた。研究プロジェクトの具体的な目標として、炭鉱に関心がある研究者や学芸員のネットワーク化、旧産炭地で散逸しつつある資料整理や統合作業によるアーカイブズの構築、旧産炭地における生活史の聞き取りや、国際比較やアーカイブズによる地域再生の研究を掲げ、『炭鉱と「日本の奇跡」』(青弓社、2018年)、『太平洋炭砿』上・下(釧路市教育委員会、2019年)、『〈つながり〉の戦後史』(青弓社、2020年)、『戦後日本の出発と炭鉱労働組合』(お茶の水書房、2022年)、『台湾炭鉱の職場史』(青弓社、2024年)などの研究成果を出してきた。
早稲田大学文学学術院教授
嶋﨑 尚子(しまざき なおこ)
専攻はライフコース社会学、家族社会学。共著書に『〈つながり〉の戦後史』(青弓社)、『炭鉱と「日本の奇跡」』(青弓社)、『太平洋炭砿』上・下(釧路市教育委員会)、『現代家族の構造と変容』(東京大学出版会)、共著に『近代社会と人生経験』(放送大学教育振興会)など。
早稲田大学文学学術院教授
西城戸 誠(にしきど まこと)
専攻は環境社会学・地域社会学。著書に『抗いの条件』(人文書院)、共編著に『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか』(新泉社)、『震災と地域再生』(法政大学出版局)、共著に『戦後日本の出発と炭鉱労働組合』(お茶の水書房)、『避難と支援』(新泉社)など。
(2024年9月作成)
