- ニュース
- 【著作紹介】『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』(文学学術院教授 三浦清美)
【著作紹介】『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』(文学学術院教授 三浦清美)
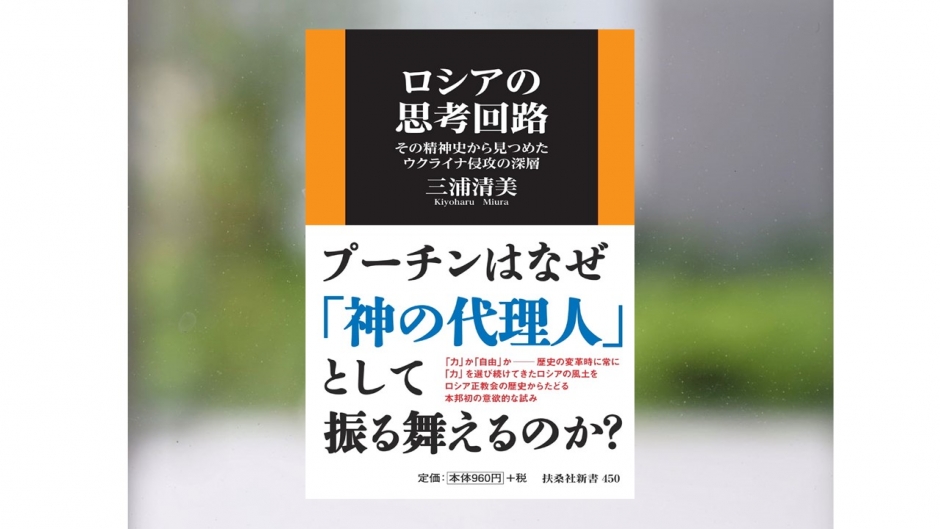
- Posted
- Thu, 13 Apr 2023
ロシア・ウクライナ戦争の歴史的背景を解説する本
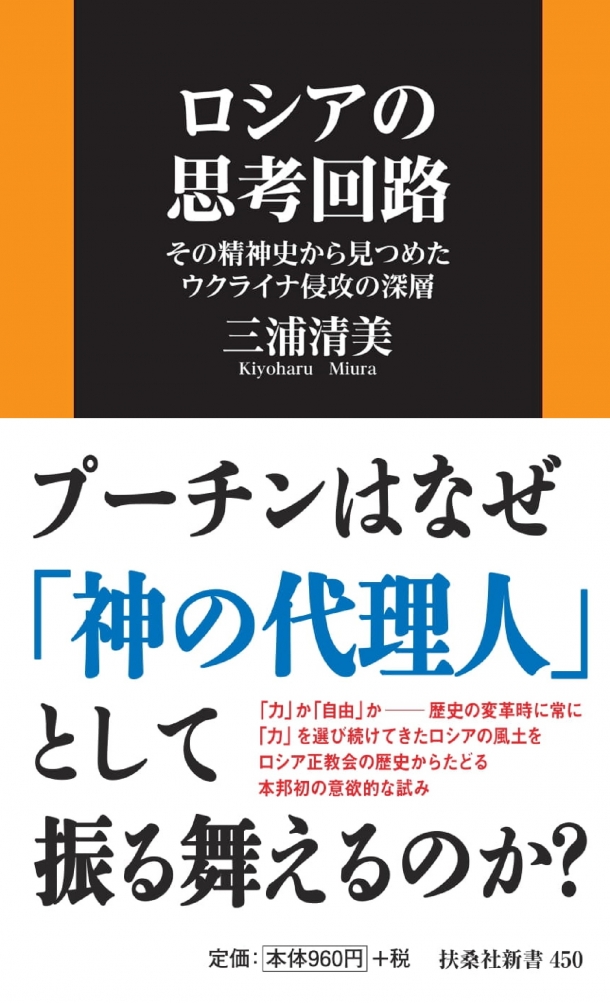
扶桑社、2022/11/1、新書版、296頁、ISBN978-4-594-09319-8
2022年2月24日、ロシア政府と軍はウクライナに傀儡政権を樹立する目論見で戦争をはじめ、これに対してウクライナが徹底抗戦して、2023年3月現在、戦況は膠着しています。国際社会はこれを、暴力による現状変更の危険な試みであると非難、断罪しているのに対して、ロシア大統領のウラジーミル・プーチンは、1000年の歴史をもつ「ルーシの世界」の一体性を護るための正義の戦争であると主張しています。本書は扶桑社からの誘いを受け、もっとも古く遡ることができる史料からピョートル大帝の西欧化改革までを通史的に振り返り、今回のこの不幸な戦争に一刻も早く終止符を打つための一助になりうるものを提供できればという思いのもとに著しました。帯には、「プーチンはなぜ『神の代理人』として振る舞えるのか?」といささかセンセーショナルな文句が並んでいますが、内容はマニアックとも言えるくらい詳しく歴史の動きに立ち入っているので、読むのに苦労するかもしれません。その歴史観は、『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(松籟社、2022年)の解説を、時間軸、空間軸ともにそのレンジを広げたものです。
〈研究内容紹介〉
西方キリスト教と異なる東方正教
歴史的背景の解説の基盤となっているのは、ロシア正教をはじめとする東方のキリスト教を、ローマ・カトリック、それから派生したプロテスタントなどの西方キリスト教とはかなり深いところで異なっている別の宗教だと捉える認識です。本書の第1章「『ルーシの世界』のはじまり」では、この違いを①イエス・キリストの捉え方、②言語への態度、③暦の在り方、④過去への姿勢、⑤統治機構の構造の5つの観点から解説しています。今般のロシア・ウクライナ戦争をロシア側から捉えると、西方キリスト教と東方正教との宗教戦争と捉えることができるというのが私の考えです。ロシア・ウクライナ戦争は、2001年の9.11事件と同じ性質をもつ、根の深い宗教戦争であることから、慎重な対処が必要であり、ウクライナを無垢な天使、ロシアを悪の化身とする単純化された理解からは抜け出さなくてはならないというのが私の主張です。
各章の内容
本書は6つの章からなっています。
第1章では、ユダヤ教、西方キリスト教、東方キリスト教、イスラームの一神教のなかで、ロシア、ウクライナ、ベラルーシがどのような位置を占めるのかを解説しています。
第2章「キエフ・ルーシの改宗」では、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの共通の祖先であるキエフ・ルーシが、ローマではなくコンスタンティノープルからキリスト教を受容することになった経緯を、年代記『過ぎし年月の物語』を軸に語っています。ビザンツ帝国には、統治者である皇帝を「天上の神パントクラトールの地上における代理人アウトクラトール」と捉える考え方がありましたが、この考え方をキエフ・ルーシがいかに受け止めたのかを解説しています。

アンドレイボゴリュプスキイ
第3章「統治者は『地上における神の代理人』とたりえるか」では、ビザンツ皇帝に遠慮してアウトクラトールたることをはばかって来たキエフ・ルーシの指導者のなかから、自らがビザンツ皇帝に変わるアウトクラトールになろうとする者(アンドレイ・ボゴリュプスキイ公)が現れるが、結局、トゥーロフのキリルをはじめとする宗教者の支持を得ることができず、自滅するに到ったことが語られます。

モスクワウスペンスキイ聖堂
第4章「『ロシア』の誕生」では、モンゴルの侵寇によって壊滅したキエフ・ルーシの北東部から、モスクワが頭角を現し、新しい時代を切り拓いていく様が描かれます。モスクワが卑劣な手段もいとわずもたらした平和のなかで、荒野修道院創設運動が進展することによって、ロシアの国土ができていきます。
第5章「ウクライナの誕生」では、モスクワによる平和から外れた南方地方で、独立武装自営農民であるコサックたちが、ポーランド・リトアニア、トルコ系騎馬民族との闘争のなかで、東方正教を軸にウクライナという新しい国を建国するに到ったことが描かれます。

コサック
ウクライナ、ベラルーシの国政を支えたのは、スラヴ起源の兄弟団という自治組織でした。
第6章「宗教的原理主義の行方」では、16世紀後半のイワン雷帝の統治以降、東方正教の原理主義国家と化して、反西欧の思想的変更のために身動きの取れなくなったモスクワ・ロシアに対して、早くから西方の文化を取り入れたウクライナ、ベラルーシの知識人たちが、ロシアがルネサンス、宗教改革を経て進化した西方の文化を受容することを助け、ピョートルの西欧化改革を助けたことが語られます。西欧化によって、ロシアは西洋列強に伍する国家になりました。
本書は、以上の経緯を具体的な文献に依拠しながら描き出しています。犠牲になった方々に哀悼の誠を捧げると同時に、一刻も早く戦火が止むことを願わずにはいられません。
早稲田大学文学学術院教授
三浦 清美(みうら きよはる)
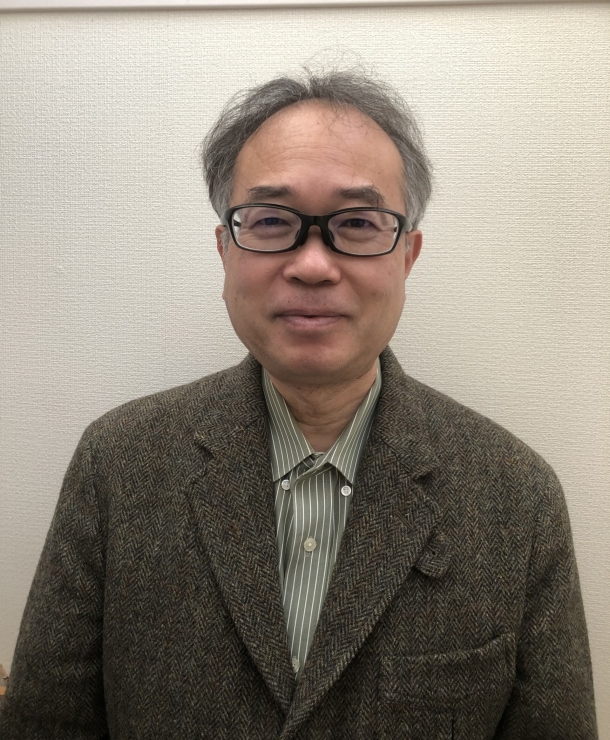
1965 年(昭和40年)、埼玉県生まれ。専攻はスラヴ文献学、中世ロシア文学、中世ロシア史。博士(文学)。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、サンクトペテルブルク国立大学研究生、電気通信大学(1995年から)を経て2019年から現職。著書に『ロシアの源流-中心なき森と草原から第三のローマへ』(講談社)、『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』、訳書に『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(松籟社)、『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(松籟社)、『中世ロシアの聖者伝-モスクワ勃興期編』(松籟社)、ペレーヴィン『眠れ』(群像社)、ストヤノフ『ヨーロッパ異端の源流-カタリ派とボゴミール派』(平凡社)、ヤーニン『白樺の手紙を送りました』(共訳、山川出版社)がある。
