- ニュース
- 【著作紹介】『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(文学学術院教授 三浦清美)
【著作紹介】『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(文学学術院教授 三浦清美)
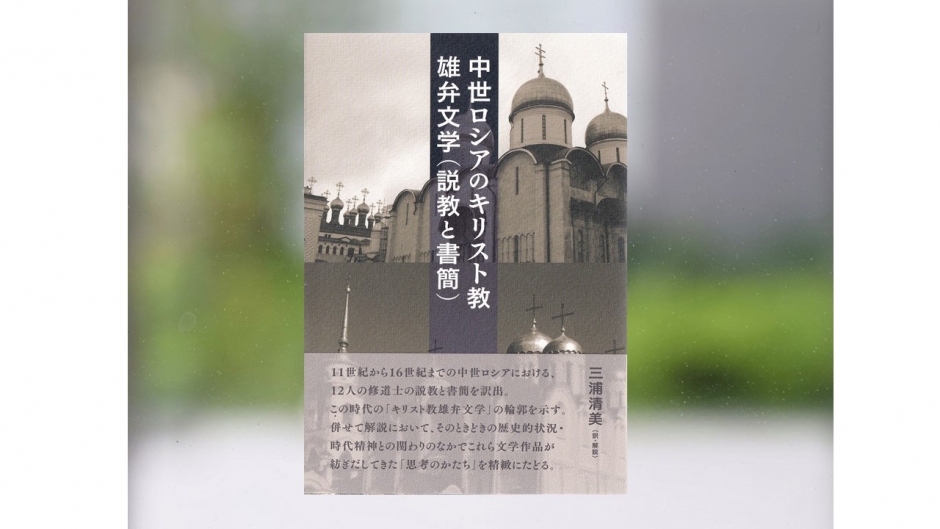
- Posted
- Wed, 15 Mar 2023
中世ロシアの人々の肉声を伝える作品集

松籟社、2022/3/1、507頁、ISBN978-4-87984-422-4
本書は、中世ロシアの思想史の流れを伝える12人の修道士たちの著作を翻訳、紹介したものです。イエス・キリストの真似びのなかで生きた、これらの修道士たちを貫くものは、「テオーシス」という思想です。テオーシスとは、イエス・キリストにおいて神が人間になってくださったのである以上、キリストに近づくことを通じて、人間も神になることができるし、自らの救済のためには、そのための努力は惜しんではならないという肌感覚の思想です。
中世ロシアの思想史の流れ
ロシアにおいて「中世」とは、988年にキエフ大公ウラジーミルのもとでコンスタンティノープルからキリスト教を受容して以来、18世紀の初頭にピョートル大帝のもとで、皇帝の強大な権力によって西欧化が実行されるまでの時代のことです。先ほど述べたテオーシスとならんで、イエス・キリストの真似びとしての統治者の概念「アウトクラトール」、すなわち「天上の神パントクラトールの地上における代理人」という考え方が強い影響力を持っていました。
ビザンツ皇帝がアウトクラトールとして君臨していたキエフ・ルーシの時代には、アウトクラトール理念の発現は抑制されていましたが、ビザンツ帝国が滅亡する15世紀中葉以降、モスクワがビザンツの後継者であるという意識を強めると、モスクワではアウトクラトール理念が俄然、力をもって来ました。本書の125頁におよぶ解題「中世ロシアの歴史とロシア思想展開の諸相」では、こうした思想史の流れを、本書に収めた説教と書簡に基づいて解説しています。
〈研究内容紹介〉
キエフ・ルーシの思想の特徴

キエフのソフィア聖堂
キリスト教の受容によって、キエフ・ルーシの東スラヴ人(ロシア人、ウクライナ人、ベラルーシ人の共通の祖先)はようやく文明世界の仲間入りしたわけですが、東スラヴ人たちは100年経つと今度は、自分たちの先生であったビザンツのキリスト教文学の成果に較べても見劣りしない、素晴らしい文学を生み出していました。スモレンスク人クリメントとトゥーロフ主教キリルの説教はその代表例です。

アンドレイ公が建立したウスペンスキイ聖堂(ウラジーミル)
トゥーロフのキリルは、モンゴル侵寇直前のキエフ・ルーシの文化の爛熟期に活躍しました。その当時キエフ・ルーシは領地の私有の意識の発達によって、親戚であった諸公間の領地の奪い合いが激しくなり、社会的に混乱していました。トゥーロフのキリルはそうした時代状況を背景に、絶望から歓喜に駆け上がる期待に溢れた格調の高い散文を残しました。しかしながら、この社会的混乱を統治者のアウトクラトール化による権力の集中によって克服しようとするアンドレイ・ボゴリュプスキイ公の改革には断固として反対しました。アンドレイ公が根拠地とした北東ルーシから、やがてモスクワ大公国が出ることになります。
モスクワ・ロシアでの思想の展開

ウスペンスキイ聖堂(モスクワのクレムリ)
これに対して、モンゴル侵寇の壊滅状態から勃興したモスクワ・ロシアでは、テオーシスに立脚したアウトクラトール理念が鮮やかな隈取りのもとに顕れてきます。それを代表するのがプスコフのフィロフェイの書簡です。「神を愛し、キリストを愛する者よ、そなたは知るがよいでしょう。すべてのキリスト教諸帝国は終末に到り、預言者の書に書いてあるとおり、我らが君主の唯一つの教会に集まったことを。すなわち、これこそがローマ帝国であることを。二つのローマは没落しました。三つ目のローマは立ち、第四のローマは存在しないでありましょう。」この思想はやがて、ヴォロクのヨシフによってもう一歩進められ、西方キリスト教起源の思潮を暴力によって排除しようとする指向性を生み出します。
以上のような思想史の流れを、中世ロシア人の肉声によって知ることができるのが、本書の特徴です。
早稲田大学文学学術院教授
三浦 清美(みうら きよはる)
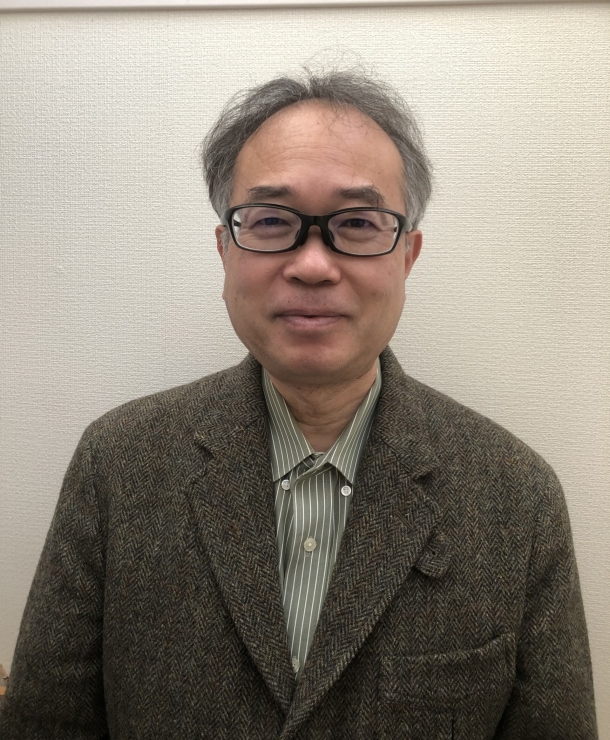
1965 年(昭和40年)、埼玉県生まれ。専攻はスラヴ文献学、中世ロシア文学、中世ロシア史。博士(文学)。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了、サンクトペテルブルク国立大学研究生、電気通信大学(1995年から)を経て2019年から現職。著書に『ロシアの源流-中心なき森と草原から第三のローマへ』(講談社)、『ロシアの思考回路-その精神史から見つめたウクライナ侵攻の深層』、訳書に『キエフ洞窟修道院聖者列伝』(松籟社)、『中世ロシアのキリスト教雄弁文学(説教と書簡)』(松籟社)、『中世ロシアの聖者伝-モスクワ勃興期編』(松籟社)、ペレーヴィン『眠れ』(群像社)、ストヤノフ『ヨーロッパ異端の源流-カタリ派とボゴミール派』(平凡社)、ヤーニン『白樺の手紙を送りました』(共訳、山川出版社)がある。
