- News
- 研究部門「境界の溶解と再編をめぐる学際的研究」主催◆公開研究会「『強制不妊手術』と優生政策について考える」開催(18.10.13)のお知らせ
研究部門「境界の溶解と再編をめぐる学際的研究」主催◆公開研究会「『強制不妊手術』と優生政策について考える」開催(18.10.13)のお知らせ
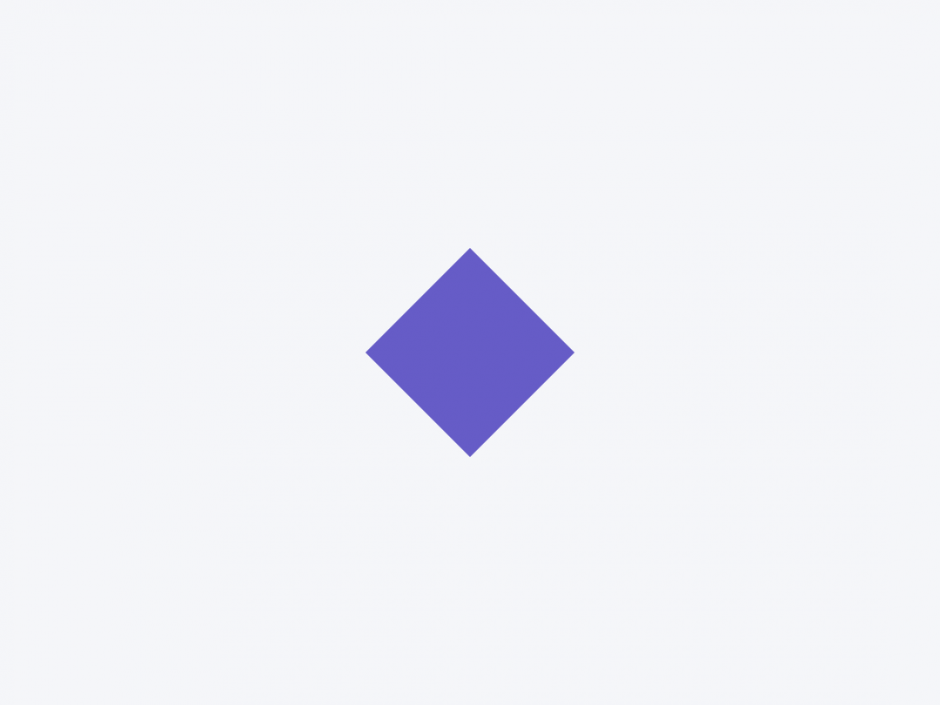
- Posted
- Fri, 21 Sep 2018
主催:早稲田大学総合人文科学研究センター研究部門「 境界の溶解と再編をめぐる学際的研究 」
後援:ダイバーシティ推進室
「強制不妊手術」と優生政策について考える
日時:2018年10月13日(土)14:00~16:30
場所:早稲田大学戸山キャンパス 33号館7階702号室(現代人間論系室)
報告:上東 麻子(毎日新聞 記者)、豊田 真穂(文学学術院教授・ボーダー研研究員)
司会・コーディネーター:岡部 耕典(文学学術院教授・ボーダー研研究員)
タイムスケジュール
14:00~14:10 趣旨説明 岡部 耕典
14:10~14:40 「強制不妊手術」と毎日新聞の取り組み 上東 麻子
14:40~15:10 GHQと優生保護法:「強制不妊手術」を中心に 豊田 真穂
15:10~15:20 休 憩
15:20~16:30 「強制不妊手術」と優生政策のこれまでとこれから
対談 上東 麻子×豊田 真穂 進行 岡部 耕典
※報告時間には前半の報告の質疑応答、参加者の発言が含まれる
企画概要
相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」での殺傷事件でクローズアップされた優生思想は、つい20年前まで優生保護法として制度化されていた。実際、同法に基づき多くの障害者が政策的に断種・不妊手術を強いられていた。本企画は、「優生」という究極の差別・排除の〈境界〉/線引きを「強制不妊手術」と戦後の優生政策を手掛かりに確認し、その再編と溶融をめざす試みである。
まず、この問題に対し精力的に取り組んできた毎日新聞の上東麻子記者が、その問題意識や背景、旧優生保護法下で行われた強制不妊手術の実態、現在各地で起こされている当事者からの訴訟の現状と政府の対応の問題点の概説を行う。
続いて、米占領下の日本における生殖の管理について研究を行ってきた豊田真穂本学教授は、障害者・ハンセン病者に対して行われた強制不妊手術に関する優生保護法の規定が占領下で制定されたことに注目し、人権や民主主義を重視したはずのGHQがなぜこれを許容したのか、それに対して日本政府はどのように対応したのかといった歴史的研究を踏まえつつ、戦前・戦後の連続性および戦後の長い期間これが放置され続けられてきたのかを検討する。
前半のふたつの報告を踏まえ、後半は上東×豊田の対談形式で、強制不妊手術と今なお日本の政策や社会規範に内在する〈優生〉について、参加者を交えてインテンシブに議論したい。その射程は、新型出生前診断や「尊厳死」法制化などの現代社会の「ソフトな優生」にも及ぶかもしれない。そのような〈これから〉に開かれた営みとして本公開研究会は企画されている。
入場無料・事前予約不要
(学内外のどなたでも参加できます)
お子さま連れの参加者向けのサテライト室を用意しています。
参加にあたり特別な配慮が必要な方は事前にご相談ください。
(情報保障のご希望は原則一カ月前にお願いします)
問い合わせ先 岡部耕典([email protected])
チラシは、こちら
