- News
- 【開催報告】2024年度英語論文ライティング・ラウンドテーブル
【開催報告】2024年度英語論文ライティング・ラウンドテーブル
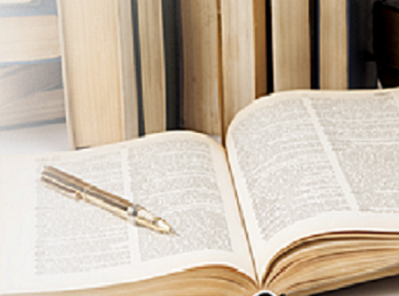
Dates
カレンダーに追加0314
FRI 2025- Place
- 早稲田大学戸山キャンパス31号館1階103教室
- Time
- 15:05-16:45
- Posted
- Tue, 18 Mar 2025
早稲田大学総合人文科学研究センターでは、キャリア初期研究者支援の一環として2018年度より英語論文ライティング講座を実施している。今回(2024年度第3回)は昨年度に引き続き、英語による学術書籍出版や論文掲載の業績をお持ちの研究者をパネリストとしてお招きし、それぞれの経験談をお話しいただいた。本講座は対面とZoomを利用したオンラインのハイフレックス形式で開催され、文学研究科に在籍する大学院生を中心に対面1名、オンライン9名の計10名が参加した。全体の司会・進行は本センターの副所長であるリーブズ・クリストファー先生が務めた。
まずリーブズ先生が本講座の趣旨を示し、今回の目的は「英語論文を執筆しジャーナルに投稿する際に直面した困難や実体験などの実践的なアドバイスを提供することにある」としながら、お招きした2名のパネリストを紹介した。

リーブズ・クリストファー(文学学術院准教授・総合人文科学研究センター副所長)
大平氏は「カナダやアメリカなどの英語圏でアカデミックな訓練を受けてきた自分にとっては、英語で論文を書く方が日本語よりも自然な選択である」ことに加え、「主張、論旨、結論がより明快な英語の方が自分の研究対象や方法論にあっていた」とし、自身のこれまでのキャリア、研究内容、共同研究プロジェクトなどを振り返りつつ、英語での共同研究や学会発表がきっかけとなって英語論文や学術書籍の出版に至った経緯について詳細に語った。さらに、国際学会や国際会議に積極的に参加することはもとより、たとえ日本国内の学会であったとしても、英語で発表することによって海外の研究者の目にとまり、英語の研究業績につながることがあるとした。大平氏がとくに強調したことは、国際会議や招待講演の依頼があれば、たとえどんなに逼迫した状況であったとしても「イエス」と承諾すべきということである。なぜなら、後に振り返ってみれば、そのときの交流や出会いが研究者人生の礎になるからである。最後に、英語論文の執筆からジャーナルへの投稿・掲載までのプロセスを仔細に解説している書籍を紹介し、発表を締め括った。

大平和希子(上智大学グローバル教育センター 助教)
次に、髙橋氏はイギリスで修士号と博士号を取得したこれまでのキャリアと、同国を拠点とする国際的な学術誌に携わっている経験に基づいたお話をされた。また、ロンドンにワーキングホリデーや短期留学で英語を学びにくる日本人女性の世話役のような仕事をした経験が自身の研究内容(「ロンドンに住む日本人女性のコミュニティ」といった中流階級の移民・移住問題)につながったことを明かした。さらに、学術論文では自分が書きたいことや伝えたいことよりも、ジャーナルの歴史や特徴を理解したうえで、編集者や査読者に求められていることを書くことが重要であるとした。論文執筆が自分本位のものではなく、編集者や査読者との共同作業であることを認識すべきであり、そのような意識をもつことで自らの研究内容を客観的に構築し発展させることができるとした。次に、国際的な学術誌の編集者としての立場から、ジャーナルの査読システムについて詳細に語った。例えば、査読に進むことなく最初の審査で却下されるデスクリジェクトが半数以上を占めていることなど、国際的な査読誌の内情が披瀝された。最後に、「あなたの作品によりふさわしい場所が見つかることを願っています」という編集者が頻用するフレーズを引用しながら、たとえリジェクトされたとしても、自分の論文に相応しい場所(「推し」のジャーナル)を見つけて欲しいと伝えた。

髙橋 薫(東京大学大学院教育学研究科 特任研究員)
各パネリストの発表後、会場とオンラインに向けても回線が開かれ、参加者から寄せられた質問について、リーブズ先生を含めた3人が回答した。まずリーブズ先生が「学部と大学院でレベルは異なるだろうし、具体的なジャーナルの選び方や読み方について、あるいは、論文と書籍で読み方や書き方は変わるのだろうか」と両パネリストに問いを投げかけた。両者はそれぞれ、学部や大学院時代の経験に基づきつつ、どのようにして本格的なジャーナルや専門書を読めるようになったのかについて語り、結果的には指導教授やゼミでの教えを通じて、文献を大量に読んでいくうちに次第に読めるようになり書けるようになったと答えた。それを受けてリーブズ先生は、「とにかく、慣れること。ジャーナルにはそれぞれ独自の性格があり、独自の語彙があり、独自のコミュニティがあり、内輪のジョークや内輪の情報もある。それに慣れる必要がある。でも、それはとても重要なことだ」と補足した。

参加者を交えたディスカッションの様子
そのほか、「大学のポストに応募する際に求められる業績やその選び方、ポストを得るまでに結果的にしてよかったこと」についての質問が寄せられたが、論文数にこだわらず、共同研究、教歴・学生指導の経験、海外の研究者との交流といったさまざまな指標をアピール材料とすべきだと回答した。また、日本でポストを見つけるためには英語論文だけではなく、日本語論文の業績も求められることが付け加えられた。
会場の参加者からも「関係性や縁のないジャーナルに投稿しても大丈夫か?」といった質問があったが、それに対しても、「まったく問題ない。むしろ、関わりのないジャーナルに投稿した方が、透明性が保たれ、新しいネットワークの構築にもつながる」と応答した。
これらのほかにも質問や議論は多岐に渡ったが、本ディスカッションは各パネリストの貴重な経験が語られただけでなく、受講者からの積極的な質問があり、それに応答するかたちでさらに別の論点や情報が引き出されるといった双方向的な展開がみられ、参加者同士が同じ問題を共有して意見を出し合う貴重な場となった。今後も、本講座が英語で論文を書く意欲のあるキャリア初期研究者にとっての一助となれば幸いである。
以上
(記録:村山雄紀)
開催詳細
- 日時:2025年3月14日(金)15:05-16:45(100分)
- 形式:対面(早稲田大学戸山キャンパス31号館1階103教室)・オンライン(Zoom)併用
- パネリスト:
- 大平和希子(上智大学グローバル教育センター 助教)
- 髙橋 薫(東京大学大学院教育学研究科 特任研究員)
- 司会・進行:リーブズ・クリストファー(文学学術院准教授・総合人文科学研究センター副所長)
- 使用言語:英語
- 参加者:対面1名、オンライン9名
