- ニュース
- 【著作紹介】『ヴェーバー後、百年 ―社会理論の航跡 ウィーン、東京、ニューヨーク、コンスタンツ』(文学学術院教授 森元孝)
【著作紹介】『ヴェーバー後、百年 ―社会理論の航跡 ウィーン、東京、ニューヨーク、コンスタンツ』(文学学術院教授 森元孝)
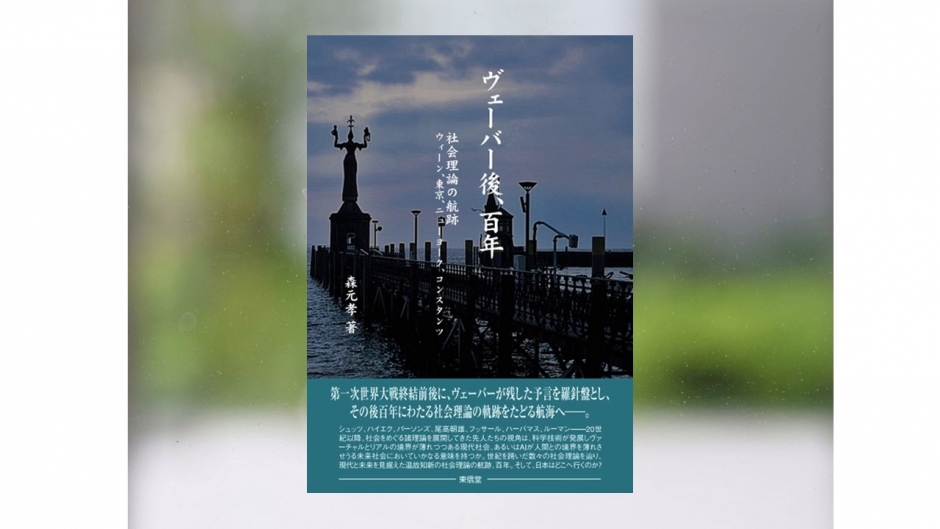
- Posted
- Mon, 30 Oct 2023

東信堂 初版 刊行日2023/10 判型 A5 ISBN 9784798918693
マクス・ヴェーバーは、1905年『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、その最終部分で、次のような予言をしている。「こうした文化発展の〈最後の人たち〉にとって、次の言葉が真理となる。〈精神なき専門人、心情なき享楽人。この無こそ、人間存在がこれまで達したことのないところに達したと自惚れるのだ〉」と。
さて、文化発展の最後とはいつのことか。1920年か、1933年ヒトラー政権誕生か、1945年ドイツ、日本の降伏か、1989年日本のバブルか、ベルリンの壁崩壊か、あるいは2022年プーチンによるウクライナ侵攻か。2030年「戦争放棄」の放棄か。
ヴェーバーは、1919年「職業としての政治」でも予言している。「残念ながら私はあれやこれやいろんな理由から、どうも悪い予感がしてならないのだが、10年後には、反動の時代がとっくに始まっていて、諸君のうちの多くの人が―正直に言って私もだが―期待していたことのまずほとんどは、まさか全部でもあるまいが、少なくとも外見上たいていのものは、実現されていないであろう」と。
1930年代、予言どおり、ドイツは反動の時代となり、世界戦争を引き起こし、日本もその顰みに倣っていく。
その少し前、第一次世界大戦が続く1918年6月、ウィーン大学で講じていたヴェーバーは、当時のオーストリア・ハンガリー帝国将校団を前に、「社会主義」と題する講演を行っている。そこでも戦後を予言している。
1.民主主義の徹底、政治的民主主義から社会的民主主義へ
2.官僚制の徹底、伝統的・人格的支配から没人格的・合法的支配へ
3.資本主義への国家干渉と統制
4.「共産党宣言」の希望と挫折
1917年のロシア革命を受けて、ありうる戦後についての見透しである。たしかに、程度の違いはあるが、西ヨーロッパから北米、そして日本も含めて、この方向に世界が進んでいった。
この4つの根本問題について「ヴェーバー後、百年」を問い、最後の2章は、近未来、人間とAIとの関係を問いながら、シンギュラリティの時代について考察した。
〈研究内容紹介〉
私は、社会学、経済学、政治学を軸にした社会科学の方法論と、現代日本の民主政治について、1980年代の神奈川県逗子市で発生した池子米軍家族住宅建設反対運動について、当時の第一文学部社会学専修の実習ゼミ生たちと、大規模な社会調査研究をつうじて、民主政について議論をしたのを出発に、学問を学問として研究するとともに、同時に、若いみなさんの世代と、とりわけ現代日本社会について議論をしながら考察をしてきました。
*著作については、以下のようなものがあります。
1995年 『アルフレート・シュッツのウィーン ―社会科学の自由主義的転換の構想とその時代』新評論,『モダンを問う ―社会学の批判的系譜と手法』弘文堂.
1996年 『逗子の市民運動 ―池子米軍住宅建設反対運動と民主主義の研究』御茶の水書房.
2000年 『アルフレッド・シュッツ ―主観的時間と社会的空間』東信堂.
2006年 『フリードリヒ・フォン・ハイエクのウィーン ―ネオ・リベラリズムとその時代』新評論.
2007年 『貨幣の社会学 ―経済社会学への招待』東信堂.
2014年 『理論社会学 ―社会構築のための媒体と論理』東信堂.
2015年 『石原慎太郎の社会現象学 ―亀裂の弁証法』東信堂.
2016年 『石原慎太郎とは? 創られたイメージを超えて』東信堂.
2018年 『未来社会学 序説 ―勤労と統治を超える』東信堂.
*YouTubeでは、以下のようなものがあります。
早稲田大学文学学術院教授
森 元孝(もり もとたか)
1955年大阪生まれ。1979年早稲田大学教育学部社会科学専修卒業。1985年同大学文学研究科社会学専攻博士課程修了。早稲田大学第一文学部助手、第一、第二文学部専任講師、助教授を経て、1995年教授。2007年より文化構想学部社会構築論系教授。博士(文学)。
19歳のとき、東京に出てきて、たまたま早稲田大学に入ることになって以来、丹下隆一先生、子安美知子先生という強烈な個性たちに遭遇する機会に恵まれ、かけがえのない友たちと出会い、学部から大学院、助手をへて教員へと、途中、博士学位取得をする留学にはほど遠い、ウィーンへの放浪遊学などがあったが、博士学位取得の後も、ほぼ同じ所でこれまで仕事をすることができ、社会科学、社会学、パーソンズ、ウィーン、オーストリア・マルクス主義、ハーバマス、社会運動論、ルーマン、シュッツ、コンスタンツ、ハイエク、貨幣論を聞き知り学び、経験的社会調査を繰り返し、キャンパスにおいても、世界各所においても、その時々ひときわ輝く知性たちと、少なからず邂逅することができたことは何よりの幸運であったと思う。それらすべてに心より感謝したい。
(2023年10月作成)
