- ニュース
- 【著作紹介】『「友だち」から自由になる』(文学学術院教授 石田光規)
【著作紹介】『「友だち」から自由になる』(文学学術院教授 石田光規)
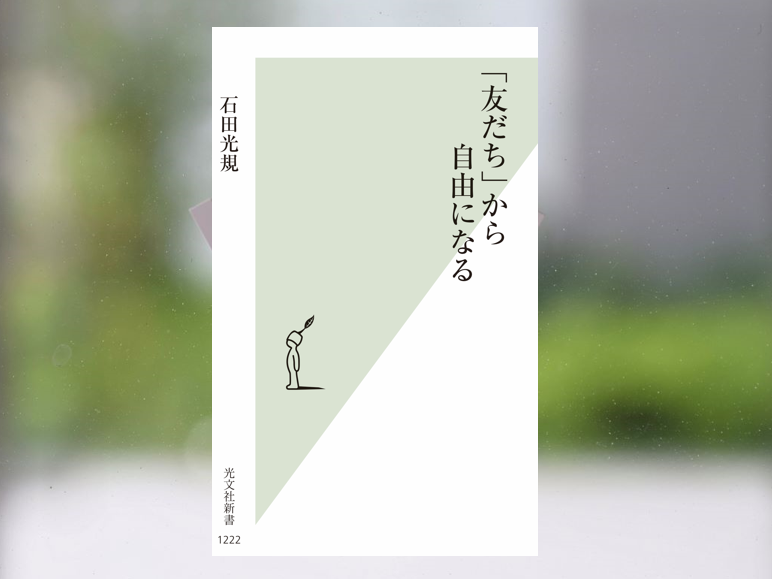
- Posted
- Tue, 30 May 2023
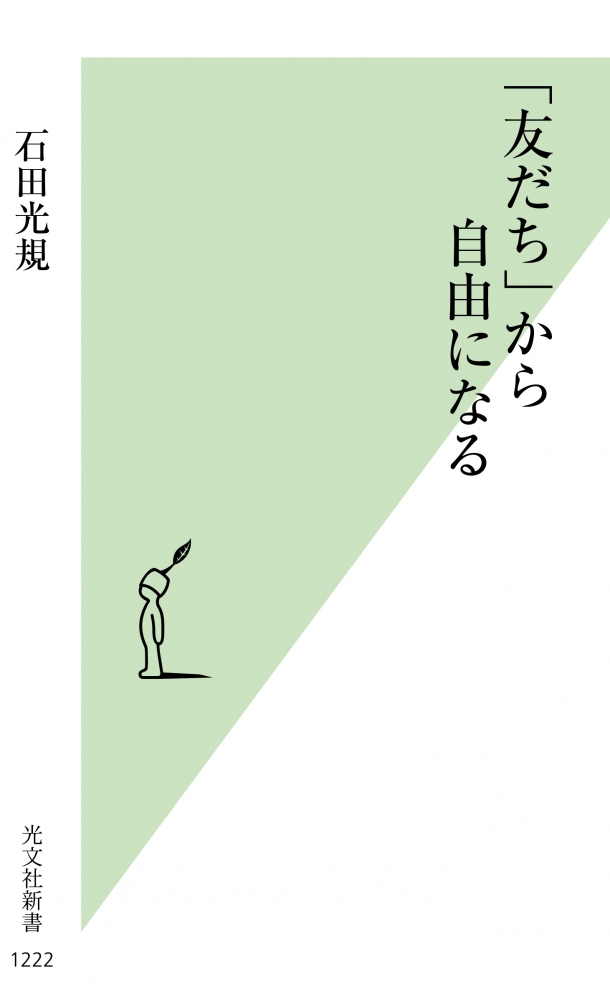
光文社新書 初版 刊行日 2022年9月14日 新書判ソフト 219ページ ISBN978-4-334-04629-3
本書は友だち作りの指南書ではない。私たちは「友だち」をどうとらえ、また、「友だち」という存在とどうつきあってゆけばよいのか考察した書籍である。
ふだん、ゼミなどで学生と接していると、「友だちと接していると疲れてしまう」「サークル、アルバイト、ゼミに所属しているけれど、本音を話せる友だちはいない」といった言葉をよく耳にする。その一方で、私たちはスマホをつうじて四六時中「友だち」とつながっている。私たちは疲れを感じたり、寂しさを感じたりしながらも、つねに「友だち」とつながっている、という不思議な状況におかれているのである。
友だちや友情の研究をひもといてゆくと、その起源はとても古く、古代ギリシア哲学の時代にまでさかのぼることができる。当時、友だち(友情)はつながりの中でも理想のものと見なされていた。それから2000年の時が過ぎ、私たちの友だちのあり方はどのように変わったのだろうか。その点をさまざまなデータや言説から読み解き、現代社会における友だち関係について考察したのが本書である。一連の考察を踏まえて、今を生きる学生に私が提案するのは、「友だち」というつながりのあり方からもう少し自由になることだ。「友だち」という存在あるいは概念を、今一度、深く考えてみたいという方に是非手にとってもらいたい。
〈研究内容紹介〉
私が「友だち」を研究しようと思った最大の理由は、「友だち」という概念や考え方が苦手だったからだ。誰かを「友だち」というと、ある関係性に対して線引きをしているような気がするし、「俺たちって友だちだよな」とか確認するのもどうも気恥ずかしい。その一方で、「友だちが一人もない」という状況だと、社会から置いてきぼりにされたような、人として何かが足りないような感じがして、それはそれでばつが悪い。そんなわけで、「友だち」という関係性のあり方を苦手としていた。
「いったい私はなんでこんなに友だちに悩まされるのだろう」「友だちとはいったい何なのだろう」そうした考えが私を友だち研究に導いていった。私および周りの人が「友だち」に振り回されるのは、社会として「友だち」のとらえ方が変わったからかもしれない。そのような考えのもと、「友だち」に関するデータや新聞記事などを集め研究を進めていった。「友だち」といった身近なテーマが研究材料になるところが、社会学の面白さだと思う。
早稲田大学文学学術院教授
石田 光規(いしだ みつのり)
東京都立大学大学院社会科学研究科単位取得退学。博士(社会学)。大妻女子大学専任講師、准教授、早稲田大学文学学術院准教授を経て2016年より現職。専門はネットワーク論、人間関係論、孤独・孤立研究。著書として『「友だち」から自由になる』(光文社、2022年)、『「人それぞれ」がさみしい』(筑摩書房、2022年)、『友人の社会史』(晃洋書房、2021年)などがある。
(2023年5月作成)
