- ニュース
- 【著作紹介】『「人それぞれ」がさみしい』(文学学術院教授 石田光規)
【著作紹介】『「人それぞれ」がさみしい』(文学学術院教授 石田光規)
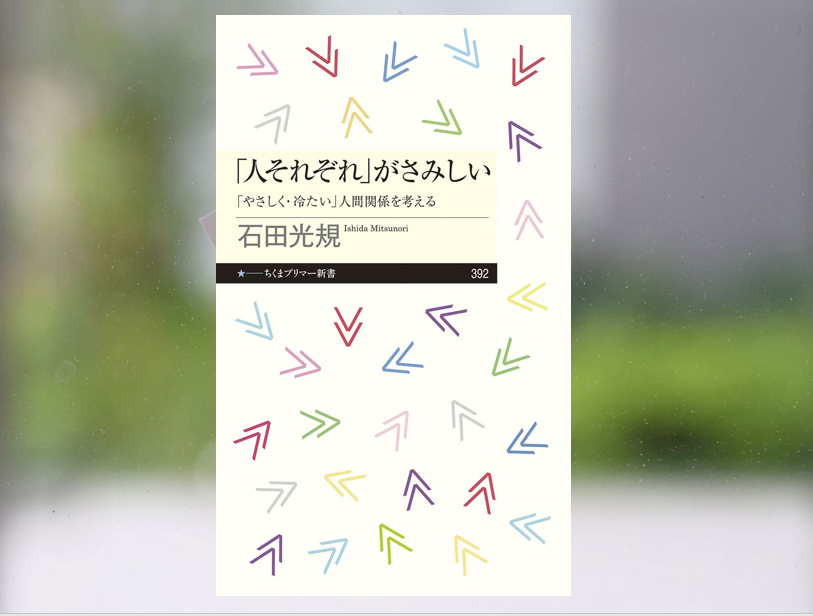
- Posted
- Tue, 30 May 2023
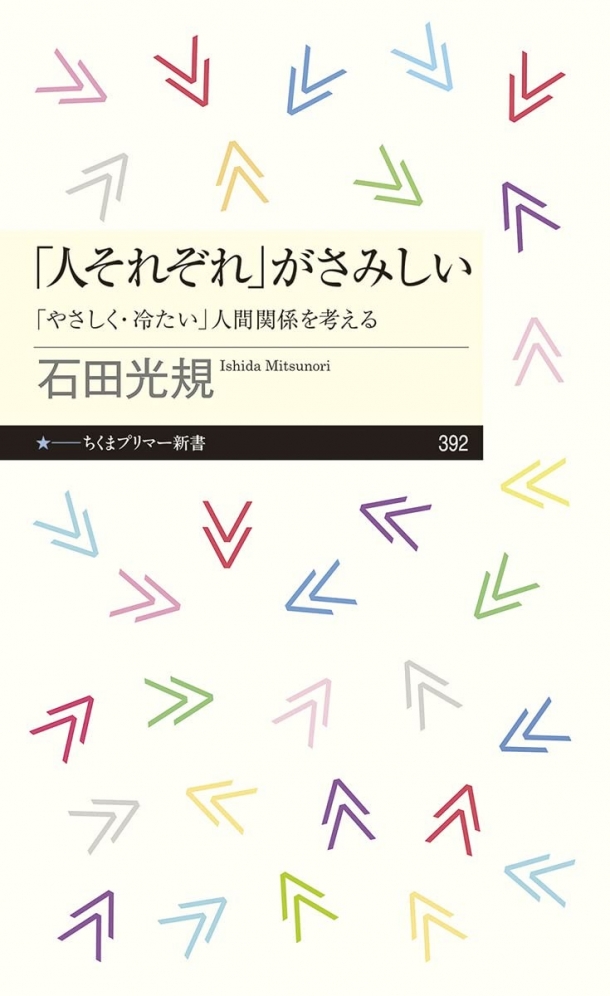
ちくまプリマー新書 初版 刊行日: 2022/01/05 新書判 208ページ ISBN:978-4-480-68417-2
大学生に限らず、誰かと話していると「人それぞれ」という言葉を頻繁に耳にする。
OL1「私、ずっとシングルでいるつもり」
OL2「ま、人それぞれだからね」
教員「今日は、スマホの使用を制限するべきかどうかについて議論してください」
学生「そんなの人それぞれでよくね」
とこんな具合だ。
「人それぞれ」というのはとても都合がいい言葉だ。この言葉を発しておけば人との対立は防げるし、なんとなく相手を受け入れているようなニュアンスも出せる。しかし、「人それぞれ」という言葉には、どことなく冷たい雰囲気がただようのも事実である。何かを話題にしたとき「人それぞれだから」と言われると、突き放されたような気持ちになるのは私だけだろうか。本書は、いろいろなことを「人それぞれ」と片付ける社会の問題点について、さまざまな事例をもとに考察してゆく。
「人それぞれ」を多発する社会は、先に述べたように、他者を受け入れているようで、他者との境界を明確にする個別化された社会である。同時に、格差にまつわるさまざまな現象を「人それぞれ」と片付ける冷たさももつ。私たちは懇親会に参加するもしないも、集まりに行くも行かないも「人それぞれ自由」と認めつつ、コミュ力のない人をつながりの輪からはじき出していく。
また、「人それぞれ」の社会は私たちが想像するほど自由ではない。マスクをつけるのもつけないのも「人それぞれ」のはずなのだが、相変わらず私たちの多くはマスクをつけている。「人それぞれご自由に」と言われても、自由にならないことはたくさんあるのである。
「人それぞれ」や「多様性」を強く意識させられる社会とうまく折り合いがつかない。どことなく今の社会が息苦しいと感じる方々に、是非とも読んでいただきたい。
〈研究内容紹介〉
1999年に大学院に入り研究生活に始めてから、一貫して注目し続けたのは、人と人とのつながりであった。「なぜ、個性を求められるのか」「人に趣味を聞かれたときにたじろいでしまうのはなぜなのか」「つながりをつくるとはどういうことなのか」そんなことを考えながら25年近くが過ぎた。結局、何一つ答えは出ていないのだけれど、だんだん考えが広がってきたことは間違いない。一つの回答に到達すると、一つの疑問が立ち上げられ、問いは無限に広がってゆく。そんな中で、「人それぞれ」というテーマに出会った。手前味噌だが、今の世の中の人間関係を象徴するよい切り口だと思う。
早稲田大学文学学術院教授
石田 光規(いしだ みつのり)
東京都立大学大学院社会科学研究科単位取得退学。博士(社会学)。大妻女子大学専任講師、准教授、早稲田大学文学学術院准教授を経て2016年より現職。専門はネットワーク論、人間関係論、孤独・孤立研究。著書として『「友だち」から自由になる』(光文社、2022年)、『友人の社会史』(晃洋書房、2021年)、『孤立不安社会』(勁草書房、2018年)などがある。
(2023年5月作成)
