文学学術院は、文化構想学部、文学部、文学研究科、総合人文科学研究センターの体制をとっています。
この2学部・1研究科・1センターが、一元化された運営組織の中で、幅広い人文学研究のスケールメリットを活かし、より充実度の高い柔軟な教育研究活動を展開しています。
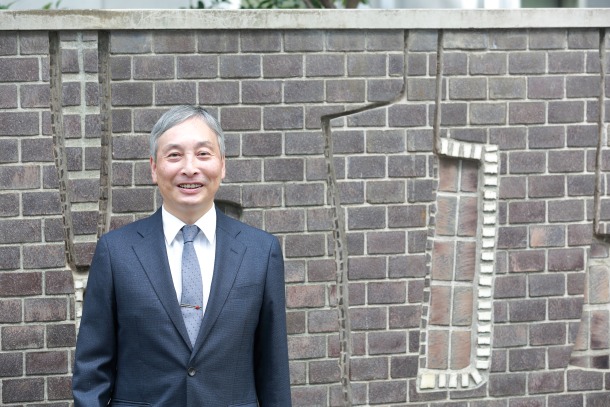
文学学術院長 柳澤 明
早稲田大学戸山キャンパスでは、長く第一文学部(昼間)、第二文学部(夜間)に大学院文学研究科を加えた体制で教育・研究が展開されてきましたが、2004年に2学部・1研究科を統合する「文学学術院」という組織ができました。いまから約20年前のことになります。さらに、2007年には、第一・第二文学部が文化構想学部・文学部という二つの学部に再編されました。第一文学部の卒業生である私にとっては、つい最近のように思えますが、いまでは文化構想学部・文学部の名前も定着し、第一・第二文学部を覚えている人の方が少ないかもしれません。
二つの学部の特徴は、私たちは「1・3制」と呼んでいますが、新入生が入学時に専門の課程に分かれず、1年間にわたって基礎教育を受けながら、文化構想学部6論系、文学部18コースのいずれかを選ぶ仕組みになっている点です。受験を終えて学部に入学する時点では、自分が何を深く学びたいのか、はっきりとは定まっていない人が多いと思われますが、そうした人に向いたシステムです。しかし、両学部が立ち上がってから10年以上が経つ中で、1年次の基礎教育が2年次以降の専門教育に必ずしもうまくつながっていない部分があるのではないかとの反省が生まれ、手直しできる部分がないか、議論しているところです。
もう一つの特徴は、何といっても規模の大きさでしょう。学生数は、文化構想学部・文学部・文学研究科を合わせて約7,000人に上ります。科目数は、両学部の学生がともに受講できる講義科目──通称「ブリッジ科目」──だけでも約1,100科目に及びます。
では、このような巨大な2つの学部と1つの研究科で、私たちはいったい何を学び、研究しているのでしょうか。この問いに答えることは、実はなかなか容易ではありません。一言でいえば「人文学」ということになりますが、文学学術院の扱う学問分野は実に多岐にわたっていて、中にはほとんど理系といえるような手法を用いる分野もあります。各分野に一歩踏み込むと、それぞれの知識の体系が果てしない海のように広がっています。一つ一つの学問の特徴やおもしろさをすべて語っていたら、字数がいくらあっても足りません。
しかし、多くの分野に分かれてはいても、ここで学生のみなさんに学んでほしいことの根幹には、共通の事柄があるような気もします。その一つは、「根拠をもって語る」ということです。昨今、インターネットやSNS上には、さまざまな言説があふれています。中には、国際問題や社会問題に対して鋭い考察を加えていて、なかなかおもしろいものもあります。しかし、そうしたコメントや評論の多くは、大学という場で作られ発信されるアカデミックな言説とは、質的に少し異なるところがあります。
アカデミックな言説においては、何かを主張するときに、必ず根拠を示さなければなりません。しかも、ただ適当に参考文献を挙げるだけでは不十分です。たとえば、日本の戦国時代のある事件について、ゼミ論文である解釈を提示しようと考えたとします。では、その根拠は何ですか?「〇〇先生の□□という本に書いてあります」。確かにそうですね。でも、それだけでは〇〇先生の受け売りです。そこで考えてみます。〇〇先生はその事件を実際に見聞きしたのでしょうか? そんなはずはありません。何か他の資料によっているはずです。それを探っていくと、ある戦国大名が発した文書に行き当たります。なるほど。では、〇〇先生の文書に対する解釈は果たして的確なのか? 異なる見解を導きうる他の資料があるのではないか? こんなふうに、既存の研究を批判的に読み解き、根拠の確かさをとことん追求するところから、あらたな発見が生まれてくるのです。
根拠となりうる資料のありようはさまざまです。文学や芸術を研究対象とするなら、作品それ自体が有力な資料になりますし、人の心のはたらきや現在の社会問題を対象とするなら、実験、インタビュー、アンケート調査などを通じて、資料を「作り出す」こともできます。しかし、どういうタイプの資料を使う場合でも、根拠の選び方が適切かどうか、用いる根拠と結論の結びつけ方が妥当かどうかを、よくよく考え抜くことが求められます。そうしてこそはじめて、自分の語りを、単なる「意見」ではなく、学問的な議論や批判の対象となりうる、大学という場にふさわしい言説に高めることができるのです。戸山キャンパスで学ぶみなさんには、ぜひこのような知の手法を磨き上げて、卒業していってほしいと思います。
とはいえ、根拠を突き詰める作業をいくら進めていっても、実は本当に「正しい答え」が得られるとは限りません。入学試験の問題は正解が出るように作ってありますが、歴史や現代社会の中にあふれる多くの問題は、正解を一つに定めることができない場合が多いのです。それでもなお根拠を突き詰め、「正しい答え」に向かって少しでも近づこうとする、それが学問というものの姿です。
 (左から順に)
(左から順に)
文学学術院は、創立150周年(2032年)を見据えた、将来構想を策定しました。
これらは文学学術院の構想段階のものであり、大学として決定したものではなく、今後議論を深め、必要性と適切性が認められるものについては、正規の手続きを経て順次開始していきます。
 早稲田大学文学部は、東京専門学校文学科創設(1890年)以来、人文科学、文化科学の蓄積を時代に翻弄されず未来に継承すること、人類が直面する課題に向き合いその解答を模索することを使命にして、多彩な人材を育成してきました。
早稲田大学文学部は、東京専門学校文学科創設(1890年)以来、人文科学、文化科学の蓄積を時代に翻弄されず未来に継承すること、人類が直面する課題に向き合いその解答を模索することを使命にして、多彩な人材を育成してきました。
今後も「学問の自由」「清新な気風」「個性豊かな在野の学風」という建学の精神のもと、教育・研究のさらなる充実を推進して参ります。
| 1882 明治15年 |
大隈重信により東京専門学校創立 |
|---|---|
| 1890 明治23年 |
坪内逍遙博士らにより文学科創設 |
| 1891 明治24年 |
『早稲田文学』創刊 |
| 1902 明治35年 |
早稲田大学と改称、大学部文学科となる |
| 1904 明治37年 |
専門学校令による大学となる |
| 1920 大正9年 |
新大学令による大学となり、文学部となる |
| 1928 昭和3年 |
演劇博物館開館 |
| 1945 昭和20年 |
敗戦の翌月から授業再開 |
| 1949 昭和24年 |
学制改革による新生早稲田大学となり、夜間学部として第二文学部創設、第一文学部・第二文学部の呼称スタート |
| 1951 昭和26年 |
大学院文学研究科 修士課程創設 |
| 1953 昭和28年 |
大学院文学研究科 博士課程(現在の博士後期課程)創設 |
| 1957 昭和32年 |
記念会堂完成 |
| 1962 昭和37年 |
戸山キャンパス完成 |
| 1968 昭和43年 |
小汀利得氏からメタセコイアが寄贈される |
| 1973 昭和48年 |
第一文学部指定校推薦入学を開始 |
| 1982 昭和57年 |
創立100周年記念式典開催 |
| 1991 平成3年 |
『早稲田文学』100周年記念展開催 |
| 1992 平成4年 |
戸山図書館開館 |
| 1996 平成8年 |
第二文学部社会人入試開始 |
| 2004 平成16年 |
文学学術院設置 |
| 2007 平成19年 |
第一文学部・第二文学部を再編し、文化構想学部・文学部を設置/大学院文学研究科を人文科学専攻の一専攻に改編/文学研究科 博士後期課程にアジア地域文化学コース新設 |
| 2008 平成20年 |
文学研究科とコロンビア大学人文科学大学院東アジア言語文化研究科との間で、修了時に両大学の学位を取得できるダブルディグリー・プログラムを開始 |
| 2010 平成22年 |
文化構想学部・文学部が完成年度/文学学術院120周年記念行事/文学研究科 修士課程および博士後期課程に表象・メディア論コース新設/33号館建て替え工事着工 |
| 2011 平成23年 |
文化構想学部・文学部で初の卒業生を輩出/文学研究科 修士課程に現代文芸コース新設 |
| 2012 平成24年 |
総合人文科学研究センター設置 |
| 2013 平成25年 |
総合人文科学研究センター研究誌「WASEDA RILAS JOURNAL」発刊 |
| 2014 平成26年 |
文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」(トップ型)に、「Waseda Ocean構想」が採択、文学学術院に国際日本学拠点を設置 |
| 2015 平成27年 |
新33号館高層棟・低層棟竣工/角田柳作記念国際日本学研究所を開設 |
| 2017 平成29年 |
文学研究科 修士課程および博士後期課程に中東・イスラーム研究コース新設/文学部に中東・イスラーム研究コース新設/文化構想学部 多元文化論系に中東・イスラーム文化プログラムおよびGlobal Studies in Japanese Cultures Program(JCulP:国際日本文化論プログラム)新設 |
| 2018 平成30年 |
文学研究科 博士後期課程に国際日本学コース(Global-J)新設 |
| 2019 平成31年 |
戸山キャンパスに早稲田アリーナが竣工 |
| 2021 令和3年 |
国際文学館(村上春樹ライブラリー)開館 文学研究科 修士課程に国際日本学コース(Global-J)新設 |
| 2025 令和7年 |
文学研究科 修士課程に社会構築論コース新設 |