「3.11」以後、私たちの心に響く「なかま」という言葉。なぜ、今「なかま」に引かれているのか。時代の空気を色濃く反映する小説から考えてみましょう。

文学学術院 教授 高橋 敏夫(たかはし・としお)
1952年香川県生まれ。早稲田大学文学部卒。同大学院文学研究科博士課程修了。専門は日本近代・現代文学研究、文芸批評。著作は『ゴジラが来る夜に―「思考をせまる怪獣」の現代史』(集英社文庫)、『藤沢周平―負を生きる物語』(集英社/新書第15回尾崎秀樹記念・大衆文学研究賞受賞)など。
私は長らく文芸批評家として、小説の言葉と向き合ってきましたが、あの「3.11」は日本人の思考を解体したと考えています。もちろん、過去の大事件や災害が及ぼした影響も大変大きいものでした。それでも影響は局地的であり、全国民が当事者となった今回の「原発震災」とはまるで違う。それをよく表しているのが、「3.11」を経験した私たちの心に響く「なかま」という言葉です。
本題に入る前にまず、小説のジャンルについて触れたいと思います。推理小説、SF小説、恋愛小説といった辺りがすぐに思い浮かぶと思いますが、もっと決定的な分類に「純文学」と「大衆文学」があります。実は、純文学には「なかま」を探し出すことができません。なぜなら芥川にしろ太宰にしろ、純文学が「何があっても一人で生きる」孤独な個人の文学だからです。そのため、エンターテインメントと呼ばれる大衆文学、中でも最初に登場した歴史・時代小説に注目して「なかま」を見ていく必要があります。
90年代、ファンタジーブームが起こりました。なぜブームになったのか。それは、米ソ冷戦の終結という時代の変わり目に始まったバブル崩壊、長引く不況、そんな「動かなくなった現実」をどんな形でもいいから動かしたいと思った人々の心の表れだったと思います。ファンタジーの世界へ行くこと自体が、ある意味「動き」だったのです。しかし、現実の社会では雇用の非正規化が進み、職場とのつながりが弱まっていく。それは、戦後の高度経済成長のにぎやかさの陰で、気付かないうちに希薄になっていた人間関係を、皆が思い知るきっかけであったともいえるでしょう。
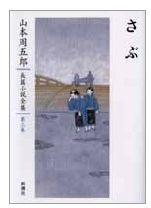
『山本周五郎長篇小説全集』(新潮社)。山本周五郎の作品にはあらゆるところで「なかま」が登場する。今、彼の全集が出版されるのはどこかで「なかま」の問題とリンクしているからではないだろうか。
このように、「なかま」を潜在的に求める人々の心を考えると、1929年に小林多喜二が発表した『蟹工船』が2008年になってベストセラーを記録したのにもうなずけます。小林は本作で、過酷な労働を強いられながらも「なかま」と共に団結して立ち上がるまでの人々の姿を描きました。プロレタリア文学という当時の政治課題を色濃く映した作品でも、読者によって新しい意味付けがなされるものなのです。
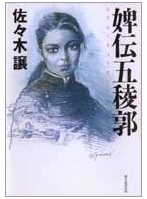
佐々木譲『婢伝五稜郭』(朝日新聞出版)。国からなかまづくりを強要されるのではなく、なかまのために何をするのかという「下からのなかまづくり」が描かれた作品。3.11 以後、ますます意味のある小説になった。
そして1990 年代以降、日本文学史上最大と言っていいほどのブームとなっているのが、歴史・時代小説です。このジャンルの作品の多くに「なかまづくり」のテーマが内包されており、とりわけ佐々木譲の「五稜郭」三部作『五稜郭残党伝』『北辰群盗録』『婢伝五稜郭』では、箱館戊辰戦争終結後の後日談として印象的な「なかまづくり」が描かれています。作中、榎本武揚が夢見た「共和国」とは何だったのか。それは、どんな人とどんなふうに生きるのかという問い掛けであり、対する答えが榎本に力を貸した一人ひとりの「なかま」の存在でした。私はこれを、困難に直面しそれと戦う「下からのなかまづくり」と位置付けており、「3.11」直後から強調されるようになった「なかま」や「絆」とは対極にあると考えています。どういうことかというと、「上からのなかまづくり」は困難を隠すための全員一致の強制でしかないのです。ですから、「五稜郭」三部作は「3.11」を経て、作品の持つ意義がますます大きくなっているように感じています。
当たり前のことですが、人間は一人では生きていけません。大衆文学はいわば「一人で生きられない者たちの文学」であり、時代の空気が色濃く反映されます。そして、現実の社会に足りないものに大衆の欲求は向けられます。だからこそ、「3.11」後の破局的にも思える現状において、私たちは小説の想像の世界に新たな思想を見つけることができるのではないでしょうか。私は、文学批評によって社会のたどり着く場所に触れることを試みたいと考えています。
(『新鐘』No.82掲載記事より)








