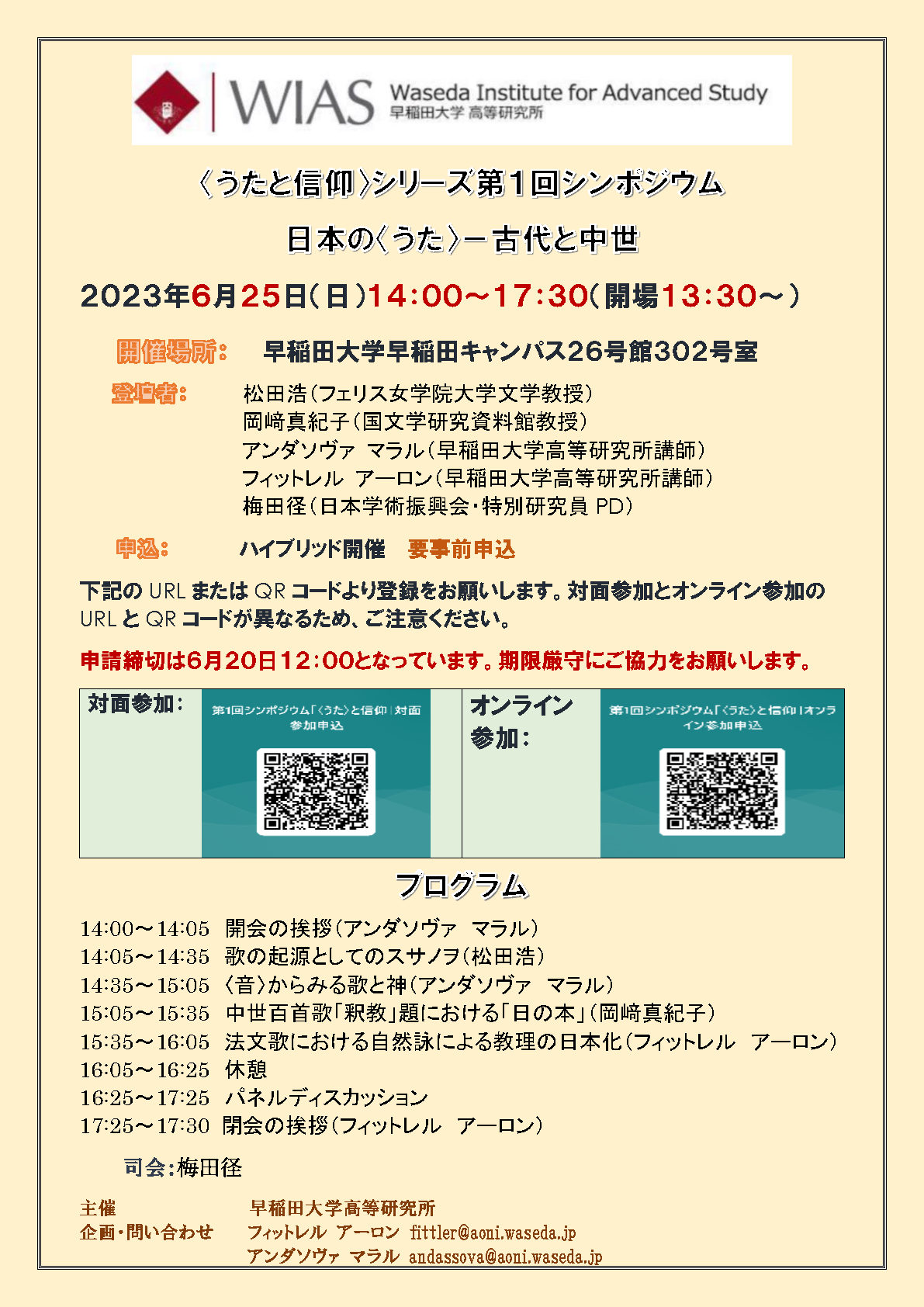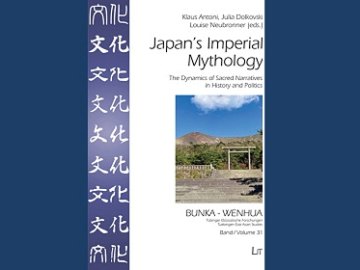<うたと信仰>シリーズ第1回シンポジウム「日本の<うた>-古代と中世」(6/25)
趣旨説明
〈うた〉を担う者たちはどのように神的なるものと向き合っていたのであろうか。また、その宗教活動はその文化や時代をどのように意味づけていたのであろうか。本シンポジウムでは、日本列島に光をあて、『古事記』、『日本書紀』にみる古代歌謡をとりあげ、さらに、仏教信仰、仏教儀礼における釈教歌などの仏教関係の和歌の役割について考察する。〈うた〉と神への祭祀、〈うた〉と仏教信仰・儀礼の関わり方が古代と中世のテクストをどのように意味づけるか、よみ解いていく。神的領域に踏み入る者たちの言語活動の宗教性に関して、〈うた〉というキーワードからそのエッセンスを抽出し、新たな問題提起を試みる。
登壇者
講演者:
松田浩(フェリス女学院大学文学部 教授)
主要業績に『日本文学の見取り図ー宮崎駿から古事記まで』共編著、ミネルヴァ書房、2022年、「伊須気余理比売の歌二首の景と喩とー御子の資質とその起源ー」『古代文学』62号、2023年3月などがある
アンダソヴァ・マラル(早稲田大学高等研究所 講師)
主要業績は『古事記 変貌する世界』ミネルヴァ書房、2014、『ゆれうごくヤマトーもう一つの古代神話』青土社、2020
岡﨑真紀子(国文学研究資料館 教授)
主要業績は『やまとことば表現論―源俊頼へ』笠間書院、2008年、『極楽願往生和歌・発心和歌集新注』青簡舎、2017年
フィットレル・アーロン(早稲田大学高等研究所講師)
主要業績に「和歌における同音異義表現の物象と人事との間の関連性について」『人文』21号、2023年3月、学習院大学、 47~68頁、「平安時代の和歌と草木成仏説」『国語国文』 88(10)、2019年10月、京都大学、 1~21頁がある
司 会:
梅田径(日本学術振興会・特別研究員PD)
主要業績に『六条藤家歌学書の生成と伝流』勉誠出版、2019、『書誌書目シリーズ118 続・古典籍索引叢書 —宮内庁書陵部蔵『類標』— 全10巻』(編集・解題)ゆまに書房、2020~2022などがある
日 時
2023年6月25日(日)14:00~17:30
会 場
ハイブリッド形式(要事前申し込み)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス26号館302号室
参加をご希望の方は以下<事前登録フォーム>またはポスターのQRコードからご登録ください。
※事前登録締切:6月20日 12時まで。
※対面参加とオンライン参加のURLとQRコードが異なるため、ご注意ください。
◆会場参加<事前登録フォーム>
◆オンライン参加<事前登録フォーム>
言語
日本語
プログラム
| 14:00~14:05 | 開会の挨拶(アンダソヴァ マラル) |
| 14:05~14:35 | 歌の起源としてのスサノヲ (松田浩): 『古今和歌集』両序にも言及されているように、地上世界においてはじめて三十一音の歌を歌ったのはスサノヲノミコトである。『日本書紀』・『古事記』における神話においても、初めて現れる歌がスサノヲのものであることに照らせば、歌の起源としてスサノヲを位置付けることは上代にまで溯ることとなる。では、いかにしてスサノヲという神は歌の起源の神たりえたのだろうか。この点を『記』『紀』においてスサノヲがいかなる神格(神としての性質)を持つ神として造型されているかを分析することによって論じてみたい。スサノヲはその誕生から成人の姿になるまでずっと泣き続ける神であり、その行為は山・河・海と連動し、さらにはモノの妖を引き起こす。こうしたスサノヲのあり方と、はじめて歌をつくる神となることとの関係を読み解くことによって、古代における歌とは何か、さらには歌そのものが内包する信仰的要素にまで説き及ぶこととしたい。 |
| 14:35~15:05 | 〈音〉からみる歌と神(アンダソヴァ マラル): 言語を、荻原千鶴が定義したように「混沌として摑みえないエネルギーを、秩序へと向かわせるもの」として捉えたとき、その秩序から外れる領域の位置づけが問われてくる。荒ぶる神としてのスサノヲや神性を有するホムチワケは、啼泣と啞という、言語によって保たれている秩序に属さない存在として描かれ、葦原中国の不穏な様子は「さやぐ」音で表現されていることが想起される。すなわち〈音〉は非言語的なもの、混沌としたものの現れであり、言語と声とを細分化したときの要素でもある。神的なる空間を秩序化する上で、〈音〉がなす役割は何か。本発表では歌を通して神の〈音〉をあらわす神武天皇のサヰ河での歌に注目し、分析を試みる。 |
| 15:05~15:35 | 中世百首歌「釈教」題における「日の本」(岡﨑真紀子): 『嘉元百首』は、十三番目の勅撰和歌集である『新後撰和歌集』の撰集資料とするために後宇多院が召した百首歌である。その「釈教」題で、『新後撰集』撰進の補佐にあたった一人である定為が詠んだ歌に、「晴るる日の本より知りぬ閻浮の身にあまねく照らす光有りとは」がある。本発表ではこの一首に着目し、「代代たえず法のしるしを伝へきてあまねく照らす日の本の国」(続千載集・雑体・後宇多院)も参照しながら検討することを通して、仏の威光と日の光のイメージの類縁性や、中世に浸透する国号「大日本国」の由来を語る説、その説の背景にある天照大神と大日如来の習合の思想が、和歌表現の根源にあることを示し、応製百首の「釈教」題において詠み手がどのような発想を指向して歌を詠進したかについて考察する。 |
| 15:35~16:05 | 法文歌における自然詠による教理の日本化(フィットレル アーロン): 仏教経典の文言を和歌に仕立てるという法文歌の詠作方法として十二世紀から、経文に見られる教理や仏・菩薩を自然景物に譬え、和歌表現と融合させる趣向が顕著になり、主流となった。そのなかに、経文から逸脱し、歌人独自の発想により、景物を通して法文題を和歌に仕立てる例も見られる。藤原定家が、菩薩の十地を詠んだ十首の歌に、知恵の光が顕わになる地である明地を、次のように和歌で表した。「あきらけきあさひのかげに愛宕山雪も氷も消えぞくだくる」(『拾遺愚草』七九三)。この歌では菩薩の智恵の現れが春の到来という四季の移ろいを表す景物で表現されている他、神仏習合の地である愛宕山も詠み込まれている。このような和歌の詠作は教理を和歌の自然観と融合させる行為であり、布教の際にも適格な手段である他、日本の自然信仰と仏教の融合、神仏習合が強くなり、多様化するきっかけともなる。本発表では藤原定家の釈教歌を中心に、和歌と自然と仏教の関係について考えたい。 |
| 16:05~16:25 | 休憩 |
| 16:25~17:25 | パネルディスカッション |
| 17:25~17:30 | 閉会の挨拶(フィットレル アーロン) |
対 象
学部生・大学院生・研究者・教職員
主 催
早稲田大学高等研究所
企 画
早稲田大学高等研究所講師 フィットレル アーロン
早稲田大学高等研究所講師 アンダソヴァ マラル