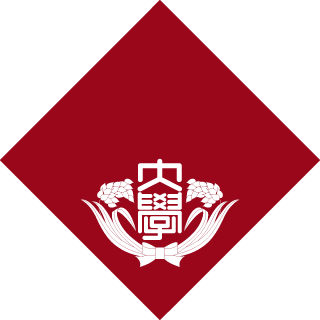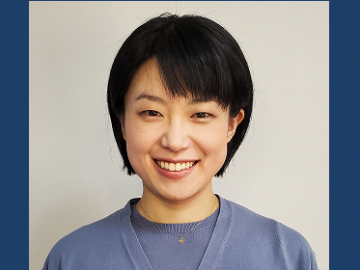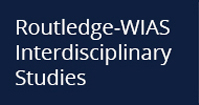社会における株式会社の役割
世の中には、株式会社、合名会社、合資会社など、さまざまな会社形態があります。これらのうち、株式会社は、日々の生活に必要となる商品やサービスを提供するだけでなく、従業員や株主として関わる場や年金資金の投資先としての側面もあり、私たちの生活にきわめて密接な形でかかわっています。株式会社は社会や経済に広く影響を及ぼす会社形態であり、株式会社が正常に機能することは、社会が正常に機能するために非常に重要なこととなります。
こうした株式会社はどのような規制の下にあるのでしょうか。株式会社の基本的な仕組みや機能は「会社法」という法律によって規制されています。会社法は株式会社の設立から資金調達・組織運営の方法まで、多岐にわたり定めていますが、実際にはその内容は国によって少しずつ異なります。このような違いは、法制度の歴史や株式会社がその国の社会において果たす役割によって生まれるものです。
株式会社の起源
株式会社はいつ、どこで生まれたものでしょうか。この点についてはいくつかの異なる見解がありますが、一般的にオランダ東インド会社が挙げられることが多いと思います。フランスで初めて株式会社という会社形態に関する法律規定が置かれたのは1807年商法典においてです。最初の頃は株式会社の設立には政府の許可を得ることが必要でしたが(設立許可主義)、1867年に条件を充足すれば設立ができるとする完全な設立準則主義へと移行し、これを機に次々と株式会社が設立されていきました。しかし、1807年以前に現在の株式会社の特徴とされるものを部分的にそなえた会社形態が存在していなかったわけではありません。その例を2つだけ紹介しましょう。
中世フランスのトゥールーズという都市を流れるガロンヌ川沿いには多くの水車小屋が建設されていました。これらの水車小屋群の所有権は複数の「持分」に分けられ、その保有者であった地域住民は持分数に応じて一定の時期に小麦を受け取ることができる仕組みになっていたとされています。粉ひき事業を営む共同事業体に一種の投資を行い、その見返りを小麦としてもらっているということになります。特に興味深いのは、水車小屋群に対する所有権を表象する持分を他の者に譲渡することができたことです。
もう一つ、まったく異なる性質のものとしてフランス東インド会社があります。最初のフランス東インド会社は1664年に設立されました。フランスの東インド会社は、先に存在していたオランダ東インド会社をモデルとしたこともあり、国家権力と密接な関係を有するものでした。植民地化といった政策上の意図もありましたが、貿易を行うことを主たる目的とするものです。しかし、事業を行うためには、船舶の購入や船員の雇用など多額の費用がかかるため、こうした初期費用の捻出方法として、事業に必要となる金額を予め算定して、それを資本金の額とし、その資本金を均等な複数の株式に細分化して、それらの株式の引受人を募る、という形がとられました。株式を引き受けた者はその株式の価格分を出資して、設立された会社の株主となります。そしてこれらの株主は、持株数に応じて見返り(配当)を受け取ることになります。この時点で現在の株式会社の形にきわめて近いものが出現しています。東インド会社の一つの特徴は、発行した株式が市場に流通していたことにありますが、これはのちにバブルを生じさせる原因となりました。このバブルはその後のフランスにおいて長らく記憶され、株式市場への不信感を大衆に根付かせることになったともいわれています。
株式会社は「契約」か「制度」かという議論が示唆するもの
1807年商法典において株式会社に関する定めが置かれたときには、株式会社は会社(ソシエテ)の一種であるため、「契約」にその基礎を置くものとされました(民法典第1832条)。この規定は、現在も存在するものです。ここで問題となるのが、株式会社を実際に「契約」として捉えてよいのかということです。前に挙げた株式会社の原型とされる二つの例を見てみますと、水車事業体は地域住民のつながりに基づいているため人的な関係を色濃く有するものであり「契約」という見方になじむ側面があるとも考えられますが、東インド会社のように、株式を引き受ける(または設立後に株式を市場で取得する)という行為によってのみ会社とのつながりを取得する者は、互いに知り合いである必要はなく、お互いに関係のない者です。この点は現在の株式会社についてもいえることでしょう。こうしたケースにおいて、会社制度の根幹にある「契約」という見方やこれに基づく各種会社制度の説明の仕方がどこまで適合するかという点が、後にフランス会社法の発展の一つの大きな課題となります。
この課題は、株式会社の性質をめぐる有名な議論につながっています。その議論とは、株式会社の性質を「契約」と見るか「制度」と見るかというものです。「契約」とみるのであれば、小規模団体のように一人ひとりの構成員の意思を重視する考え方に基づいた法制度が生まれます。しかし、多数の者を擁する会社形態においてはそうした制度は負担となり、場合によっては事業の遂行それ自体にマイナスの影響を与える可能性があります。こうした問題を汲み取ったのが20世紀初頭に展開された「制度(institution)」理論という公法を原点とする考え方です。この考え方には簡単にいうと、株式会社にその出資者である株主とは別個の存在意義を認めて、会社が主体的に動けるようにすることを可能にする利点があります。「契約」と「制度」という考え方の対立が実際に株式会社制度や株式会社に関する判例の展開においてどのように表れ、それが何を意味するのかを検討することに取り組んでいます。
現代フランス株式会社法の課題
株式会社制度の発展を考えるうえで、現代において看過できないのが他国における法制度の動きです。フランスは他国との競争にさらされていて、経済発展などの観点から、企業法制を魅力的なものにすることをせまられる部分が少なからずあり、その際にどのような部分をフランスの強みとしていくか、そしてこれに合わせてどのような点を変更し、何を維持していくかを選択していく必要があります。こうした選択の過程に、株式会社の本質が何かを読み取る鍵があると考えています。そこにはフランス社会特有の価値観が表れる可能性がありますが、そのなかにわが国も共有しうる普遍的な部分があるのではないかと思っています。
取材・構成:秦千里
協力:早稲田大学大学院政治学研究科J-School