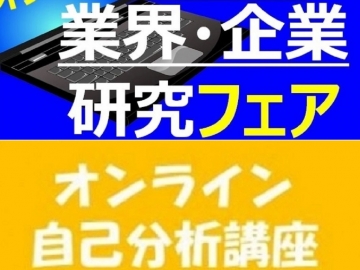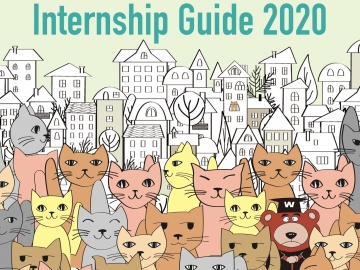学校は『箱』。そこに入れる中身を充実させよう
記者・ビデオジャーナリスト シッラ・アレッチ


法律事務所「モサック・フォンセカ」の前で抗議活動を行う人々(AFP PHOTO / Ed Grimaldo)
2016年、世界を震撼(しんかん)させた「パナマ文書」報道。パナマにある法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した1,150万点超の文書類に、世界各国の企業や富裕層によるタックスヘイブン(租税回避地)の利用実態が記載されていたため、課税逃れが暴露されるのでは、と世界中が注目したニュースだ。
この「パナマ文書」報道で重要な役割を果たしたのが、調査を担当した米非営利組織「ICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)」(※)。そして、ICIJ「パナマ文書プロジェクト」で日本担当を務めた4人のうちの1人が、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース(J-School)卒業生のScilla Alecci(シッラ・アレッチ)さんだ。
そこで今回の「先輩に乾杯」では、シッラ・アレッチさんにインタビュー。ジャーナリストを志したきっかけや、早稲田大学で学んだこと、これからのメディアの在り方などを聞いた。
※2017年4月、ICIJはパナマ文書報道の功績により、米国の優れた報道に贈られる「ピュリツァー賞」を受賞した。
“学校で学んだ日本”よりも、“本物の日本”、“事実に近い日本”を語りたい
「イタリアでは、『キャプテン翼』『北斗の拳』『ヤッターマン』といった日本アニメが大人気。1970〜80年代生まれのイタリア人のほとんどは、日本のアニメを見ながら育ったと思います」
そう語ったのは、イタリア・ローマ生まれのアレッチさん。彼女もまた、気が付けば日本文化と日本語に魅了されていたという。
「日本語は、言葉の音も面白いし、漢字・平仮名・カタカナを使い分ける点も複雑な言語です。ローマ大学で東洋学について学んでいたころは、『将来、日本語言語学の教授になりたい』と考えていました」
ローマ大学大学院を修了後、奨学金を得て東京外国語大学に留学したアレッチさん。しかし、実際に日本に来てみると、イタリアでの日本に関する報道に疑問を感じたという。
「来日して分かったのが、イタリアで報じられている日本の情報には偏りが多かった、ということ。すしと芸者についての記事がやたらと多いんです。そして、“学校で学んだ日本”よりも、“本物の日本”について興味を抱くようになりました。日本語と日本文化をより深く知った私は、もっと“事実に近い日本”について語りたくなり、記者になろうと決意。ジャーナリズムの基礎を学ぶため、早稲田大学大学院の政治学研究科ジャーナリズムコース(J-school)に入学したんです」
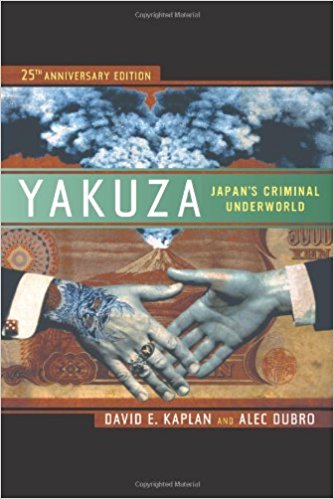
米国行きの契機となった『Yakuza: Japan’s Criminal Underworld』は、ヤクザに関して初めて英語で書かれた本とされる
J-school在学中、アレッチさんが選んだ修士論文のテーマは「経済ヤクザ」について。イタリアにおける「マフィア」報道と、日本での「ヤクザ」報道の違いについて、谷藤悦史政治経済学術院教授の下で研究を重ねた。その際、参考文献としたのがDavid E. Kaplan(デイビット・E・カプラン)共著『Yakuza: Japan’s Criminal Underworld』(University of California Press)。このことが、アレッチさんのその後の進路に大きな影響を与えることになった。
「当時、カプランさんがICIJの編集長だった縁で、ICIJでインターン記者として働かせていただくことになりました。それ以前、通信社(一般向けニュースや経済・金融情報の収集、配信を行う組織)での経験しかなかった私にとって、初めて『データジャーナリズム』や『調査報道』(※)の世界に入った気がしました」
J-Schoolと米ミズーリ大学との交換留学制度を活用して渡米し、ICIJのアスベストに関する国際的な調査報道に参加。アレッチさんが担当した記事は日本のメディアでも報じられ、優れた調査報道に贈られる「Investigative Reporters and Editors」(IRE)の中でも最高の作品に与えられる「IREメダル」(2010年度)を受賞した。
※データジャーナリズム:膨大なデータを分析してそこから得られた情報を分かりやすく提供する、報道手法の一つ。
※調査報道:警察・検察や行政官庁、企業発信の情報に頼らず、取材者がさまざまなソースから情報を集めて新事実を発見しようとする報道手法。
学校は『箱』。その箱に入れるコンテンツを決めるのは自分しかいない

英国でもキャメロン前首相の亡父が課税逃れをしていたことがパナマ文書で明らかになり、大規模なデモが起こった(AFP PHOTO / NIKLAS HALLE’N)
早稲田大学大学院を修了後、2015年には米コロンビア大学ジャーナリズムスクール(調査報道コース)で修士号を取得したアレッチさん。その年の6月、ICIJ「パナマ文書プロジェクト」に携わることになった。
「プロジェクトへの参加を提案されたときは、光栄に感じました。もちろん、調査は簡単なことではありませんでした。ファイルの量も膨大で、テーマ自体も複雑です。でも、日本チームのメンバーのおかげで少しずつ興味深いネタにたどり着くことができました。何よりも、記者として成長できたと思います」
結果として、パナマ文書報道をきっかけにアイスランド首相が辞任するなど、世界の政治・経済にも影響を与えるインパクトを残した。これほどのプロジェクトに関わったことで、アレッチさん自身の考え方や価値観に変化は起きたのだろうか。

ワシントンD.C.にあるICIJのオフィスで同僚たちと
「『記者としての責任』について考えさせてくれました。普段、記事を書いたり、あるいは報道映像を制作したりする過程において、そのストーリーがどのように受け取られるかについては、以前も考えていました。でも、その次の社会に対するインパクトについてまでは、考えが及んでいませんでした。だからこそ、パナマ文書報道における世界的な影響度を見るにつけ、調査報道の意味についてあらためて気付かされました」
そして、アレッチさんが気付いたことがもう一つ。それが、調査を担当した記者たちの役割の重要性だ。

ピュリツァー賞受賞の瞬間
「特に、『報道の自由』があまり発達していない国の記者の勇気は尊敬に値すると思います。また、パナマ文書の成功のおかげで、報道の世界における『メディア同士のコラボレーション』が多くなった気がします。今後、国際的なテーマを取り上げたい記者にとっては、他国の同業者同士の協力はもっと必要になってくるはずです」
今後は記者として働き続けながら、記者を目指す若い学生たちに国際調査報道の意義とやりがいを伝えたい、と語るアレッチさん。早稲田大学の学生に向けてもメッセージをもらった。
「学校というのは『箱』です。その箱に入れるコンテンツ(内容)を決めるのは自分しかいません。その箱とコンテンツは、どこへ行ってもずっと自分と一緒に持っていく荷物になります。ならば、今のうちにさまざまなことを試して、自分とは違う人生を送っている人と話をして、普段過ごす環境とは違う場所に赴いて、自分のアイデンティティーを確立させることが必要です。失敗しても構いません。結局、その箱に入るのは失敗そのものではなくて、その失敗から学んだ教訓なんですから」
【プロフィール】
Scilla Alecci(シッラ・アレッチ)
ジャーナリスト。1982年イタリア・ローマ生まれ。2007年、ローマ大学大学院東洋学研究科修了。東京外国語大学を経て、2011年、早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース修了。2015年、米コロンビア大学ジャーナリズムスクール(調査報道コース)にて修士号を取得。ブルームバーグニュース、ハフィントン・ポストなどを経て、現在はICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)で記者、ビデオジャーナリスト(※取材だけではなく、撮影や映像編集なども行う)として活動中。著書に『報じられなかった パナマ文書の内幕』(双葉社)。