- Featured Article
「総合知」を育むGlobal Education推進事業
特集:総合知、世界へのまなざし
Mon 10 Nov 25
特集:総合知、世界へのまなざし
Mon 10 Nov 25
世界人類に貢献する人材の育成を目指す早稲田大学は「Global Education Center(GEC)推進本部」のもと、「総合知」を育む教育を全学で展開・拡充しています。推進本部長を務める須賀晃一副総長(早稲田大学名誉教授)が、教育事業の方針を説明します。
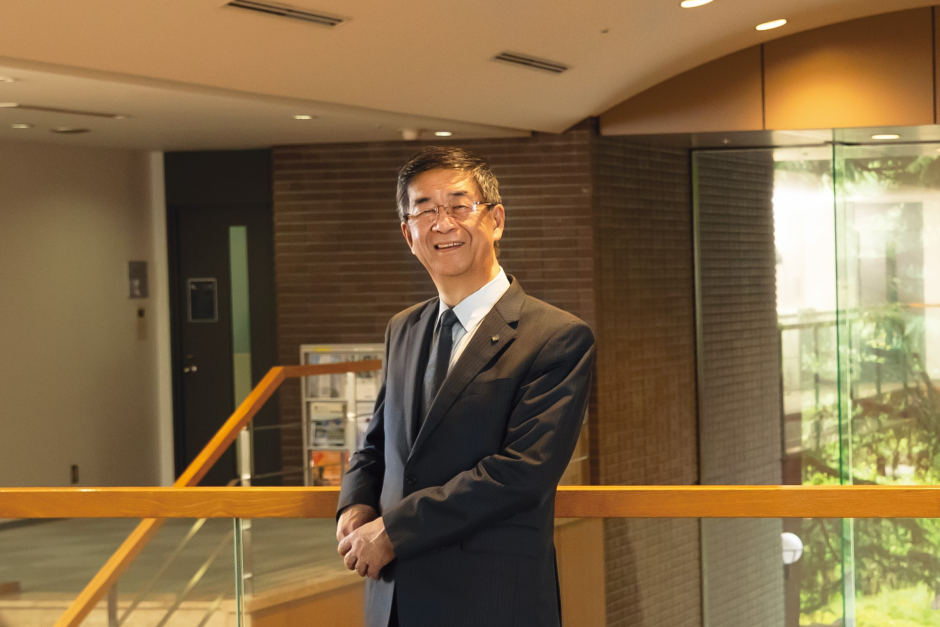
専門の垣根を越え、総合知を養うために
複雑な課題へとアプローチする総合知の可能性
2032年に創立150周年を迎える早稲田大学は、世界人類に貢献しつづける大学へと進化すべく、「研究」「教育」「貢献」 の三つの柱から事業を推進しています。その中心にあるのが、「総合知」という概念です。現代の複雑な社会問題は、一人の人間の力だけでは解決できません。例えば気候変動へのアプローチでは、自然のメカニズムを解明する科学のみならず、法、経済、倫理、歴史など広範な視点が必要です。多様な専門知が枠を超えて集まり、相互に影響し合いながら、新たな価値を創造する。この知のネットワークこそが、「総合知」 だといえます。そこでは個人のレベルでも、複合的な知を内在させ、他者の考えに対し理解を深めていく人間性が求められるでしょう。こうした背景から、本学はGEC推進本部のもと、「総合知」 を養う教育プログラムを全学で展開・拡充しています。
自ら主体的に知の体系をつくる全学共通の教育プログラム
「総合知」を身につける上で重要になるのが、学部で学ぶ主専攻とともに、多様な学問分野へアクセスすることです。本学は全ての学部生が履修できる共通科目「全学オープン科目」を基軸に、学生一人ひとりが自分だけの“知の体系”をつくる機会を拡充しています。GECでは、2,400以上の「全学オープン科目」とともに、体系化された科目群により第二の専門分野を習得できる「全学副専攻制度」を導入しています。全学副専攻制度は、特定の学問分野を掘り下げる「学術的副専攻」、一つのテーマを複数の学問から分析する「学際的副専攻」から構成され、修了者は証明書を取得することが可能です。現在、「政治学」「ソフトウェア学」「カーボンニュートラルリーダー」「地域連携・地域貢献」など、25の副専攻を提供し、2026年度には「アントレプレナーシップ」に関する副専攻を新設する予定です。同時に大学院でも、研究科を横断する「大学院分野横断型副専攻」を充実させていきます。
また、全ての学問で求められる必須スキルを学ぶ「基盤教育」にも注力しています。基盤教育を構成するのは、五つのアカデミックリテラシー、①学術的文章の書き方を学びながら思考力を鍛える「アカデミック・ライティング」、②数学の素養と論理的な思考力を身につける「数学」、③文理の枠を超え、AIによるビッグデータの解析法として学ぶ「データ科学」 、④データサイエンス時代を支えるICT能力を養う「情報」、⑤少人数レッスンで英語発信力を鍛える「英語」です。いずれも体系的なプログラムを通じ、在学期間を通じて段階的にレベルを高められます。
さらに、26もの多彩な外国語を学べる「言語教育」、Global Citizenship Center(GCC)と連携し、ボランティアや企業連携、リーダーシップ、キャリア形成などを理論と実践を通じて学ぶ「人間的力量育成」により、社会貢献や自己実現に必要なスキルを磨くこともできます。加えて、国際的な視野を広げる上では、多様な価値観と出会うことも重要です。留学センターの「中長期留学プログラム」を活用すれば、世界各国の大学でも知の体系を広げられるでしょう。そして、多くの外国人留学生が集う早稲田大学のキャンパスでは、ICC(異文化交流センター)のイベントなどを通じ、日常的に異文化に触れることも可能です。
世界人類に貢献する人材を早稲田から輩出するために
主専攻で専門分野を究めながら、自然・社会・人文科学の垣根を越え、知を統合させていく学びのプロセスは、今後の世界において、ますます重要となるでしょう。2032年の先にある未来を見据え、早稲田大学は未知なる社会課題に挑む人材を育成すべく、教育機能のさらなる充実に努めてまいります。

