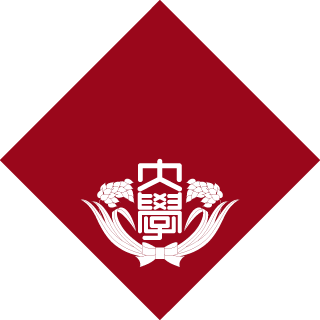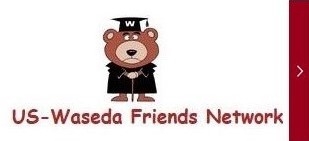- Featured Article
私を変えた留学、次世代へ託す想い
Tue 26 Aug 25
Tue 26 Aug 25
ダグ・エッツェル氏 -若者の留学を支えるという選択-
オレゴン留学奨学金は、毎年1名の早稲田大学生が米国オレゴン州で留学する際の経済的支援を目的に、2024年に新設されました。この奨学金は、米国実業家であり、かつて早稲田大学への留学経験を持つダグ・エッツェル氏の多大な寄付により実現しました。エッツェル氏に、日本との出会い、早稲田大学での留学経験とその後の日本とアメリカでのキャリア、そして将来の留学学生を支援する奨学金を設立した動機についてお話を伺いました。
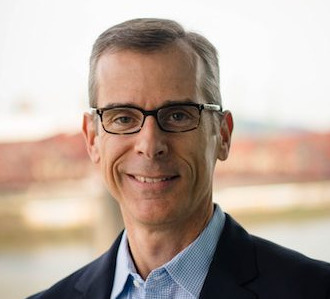
ダグ・エッツェル氏


日本との偶然の出会い
ダグ・エッツェル氏は、オレゴン州のポートランド市から約50マイルのカイザー市で生まれ育ちました。オレゴン州立大学(OSU)で電気工学を学び始めた際、彼は「日本に関する興味や関心も、アメリカ国外への旅行経験もなかった」と述べています。
あるとき、親友から大阪で英語を教えるアルバイトに誘われ、突如として日本を訪れることになりました。それは1986年の夏のことでした。「大きな衝撃でした。田舎で育った私が、突然大阪という大都市の真ん中で生活することになったのです。全てが新鮮で、興奮するものばかりでした」 と、彼は言います。
エッツェル氏は大阪を非常に気に入ったため、滞在期間を3ヶ月から6ヶ月に延長しました。「あまりに多くのことが新しくて、頭が追い付かないほどでした」と彼は説明します。「とても親切で、陽気なホストファミリーに迎えられ、活気あふれる大阪の下町での生活は、私にとってはかけがえのない経験となりました。神戸での英語教師のアルバイトから帰ると、ホストファミリーが経営していたお好み焼き屋の手伝いをし、地元の常連のお客さんたちと日々会話をしました。その当時、私は日本語がほとんど話せず、近所からやってくるお客さんたちも英語を話せなかったのにもかかわらず、本当に楽しい経験だったのです。」
その後、エッツェル氏は大学を卒業するためにアメリカに帰らなければなりませんでした。しかし、日本語学習への情熱と、日本に戻って働くという強い思いが彼の中に芽生えていたそうです。それは、日本を訪れる前には想像もできなかったことだったと、当時を懐かしみながら語ります。
魅了された日本へ再び
OSUを卒業後、エッツェル氏は日本の企業であるセイコーエプソン株式会社のポートランド支店で就職し、1年間の研修のために日本の長野県に派遣されました。その間、彼は日本語の学習とスキル向上に励みました。
研修終了後にまたアメリカに戻り、彼はポートランド州立大学(PSU)で日本語の勉強をパートタイムで続け、この頃、日本で働きたいと決意するようになりました。そして1989年、PSUが学生交流協定を交わしている早稲田大学への留学の機会を得たのです。
「日本で暮らし、働くことに強く惹かれていました。だからこそ、その実現を最優先に目指していました。」と彼は回想します。「ポートランドで良い仕事に就いていたのに、辞めるのは簡単な決断ではありませんでしたが、思い切って退職し、日本に再び渡ることを選びました。それが、早稲田大学に通うことになったきっかけです。」
早稲田大学留学中は、オレゴン州からの学生を長年受け入れてきた早稲田大学の元教授宅でホームステイをしました。この時期のエッツェル氏は日本語の向上にとても熱心に取り組みました。その努力も実り、当時の日本語コースのなかで最も高いクラスに入ることが出来ました。

ホストファミリーと、日本を訪れていた母親と、エッツェル氏(下段、右から2番目)
早稲田大学での留学中、エッツェル氏は学業に励むほか、バスケットボールサークルでも活躍し、当時の国際部(※旧国際部:海外の協定大学から留学により在学する外国人学生のための課程、2004年の国際教養学部開設に伴い、改廃 )の留学生たちとも親交を深め、その多くは現在も交流を続けています。
エッツェル氏は、「早稲田で過ごした時間は、単に日本語の習得が進んだだけでなく、日本での暮らしのあらゆる面に慣れるための、かけがえのない経験だった」と振り返ります。彼にとっては、髪を切ることから病院に行くことまで、すべてが新鮮な挑戦でした。「こうした小さな経験の一つ一つを通して、やり方を学び、日本語で表現する方法を習得するたびに、小さな達成感のようなものを感じていました。そうすることで、自分が目指す目標を達成することができるのです」と彼は振り返ります。

エッツェル氏(右から3番目)と他の早稲田大学の留学生たち。1991年6月のジャパンタイムズに掲載


日本とアメリカ、二つの国で築いた人生の礎
エッツェル氏が日本語の向上に費やした時間と努力は報われ、1990年に早稲田大学での1年間の留学を修了後、神奈川県の米国テクノロジー企業NCRの日本支社で就職することができました。
これが、米国と日本を往復しながら複数の外国のソフトウェア企業で働く長いキャリアの始まりでした。「日本に4~5年ほど住んで、アメリカに機会があれば数年間戻る、という生活をしていました」と彼は語ります。「あるとき結婚したため、妻とアメリカに戻り、カリフォルニア州立大学バークレー校の大学院に通い、その後また日本に戻り、数年間住みました」
エッツェル氏は、ソフトウェア企業Veeva Systemsでアジア事業部の社長として約10年間務めた後、プロフェッショナルキャリアを締めくくりました。
次世代に思いを託して -奨学金の設立-
退職後もVeeva Systemsのアドバイザーとして活動を続ける一方で、エッツェル氏は多様な慈善団体や社会貢献活動支援に尽力したいという思いを抱くようになりました。なかでも、自身の生涯とキャリアの進路を大きく決定づけた「留学」という経験を振り返り、留学を志す若者たちを支援したいという考えが芽生えました。
「最初はここポートランドで始めました」と彼は語ります。「PSUの日本研究センターの諮問委員会に参加しました。非常に優れたプログラムがあり、これに深く関わるにつれ、妻と私はオレゴンから日本への留学を支援したいと思うようになりました。」 こうして彼はPSUに「エッツェル日本語学習留学奨学金」を設立しました。この奨学金は、毎年1~2名の学生を早稲田大学、または同等の日本の教育機関に留学することを支援しています。
「その奨学金設立の経験を通して、今度は早稲田からオレゴンへの奨学金も設立できないかと考えるようになりました。なぜなら、オレゴンは日本の交換留学生にとってとても良い留学先だと考えていたからです」と彼は言います。

最初の奨学金を設立したポートランド州立大学
その後、米国における早稲田大学の国際交流および卒業生支援拠点であるWaseda USAのサポートを経て、2024年にエッツェル氏の思いが「オレゴン留学奨学金」として実ることになりました。これは、毎年1人の早稲田大学の学生がオレゴンへの留学を実現できるように、経済的支援を提供するものです。
オレゴン留学奨学金の最初の受給者である木地谷美慧(キチヤ ミエ)さんは、2024-25年におけるPSUでの1年間の留学を無事に終えました。次回の受給者も既に選出されており、2025年秋学期からの留学を予定しています(インタビュー実施時点)。
経験が導いた支援のかたち -次世代への橋渡し-
早稲田大学と日本、またはオレゴン州の教育コミュニティへの支援を決意した動機について、エッツェル氏は次のように述べています。「今の私は慈善活動や社会貢献に還元できる立場にあります。留学は私の人生を変えてくれました。だからこそ、他の若者の人生も変えられるのではないかと信じているのです。」
同じように人生の節目を迎え、何らかの形で社会に恩返しをしたいと考えている早稲田大学の卒業生や留学経験のある人達に向けて、彼は、こう続けます。「自分自身が特別なつながりや思い出を持っている分野や活動を選ぶことが、支援の意義を深める鍵になるのです。」
「早稲田は私の人生と経験にとても深く結びついている場所です。交換留学を経験した人ならだれでも、学生として過ごした時間は、誰もが特別な思い出を抱えるものです。だからこそ、私が過ごした早稲田でこの奨学金制度を設立できたことは、非常に嬉しく、満足感のあることなのです。」
次世代を担う若者への思いをこめて、エッツェル氏は次のように締めくくります。「なによりも大切なのは、こうした奨学金によって恩恵を受ける学生たちの存在です。オレゴン州か他の場所かに関わらず、海外での生活を経験すること -そこにある喜びも困難も挑戦も含めて- が、若者にとってかけがえのない価値ある経験だと強く信じています。」
「日本の若者にとって、海外に出て経験を積むことは、本当に素晴らしいことだと思います。もし、その機会が得られるなら是非挑戦して欲しい。私たちがこの奨学金で目指しているのは、そうした若者たちを支援することです」
PROFILE
ダグ・エッツェル
アメリカ合衆国・オレゴン州出身。IT業界で35年以上の経験を有し、そのうち18年はアジア、主に日本において活動。オレゴン州立大学で電気工学の理学士号を取得後、カリフォルニア大学バークレー校のハース経営大学院でMBAを取得。1989年から1990年にかけて、早稲田大学に交換留学生として留学。現在は引退し、オレゴン州ポートランド在住。