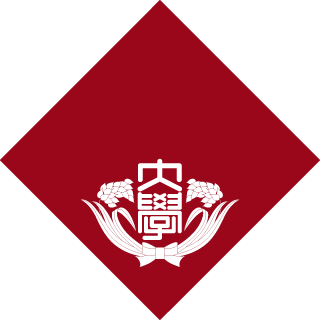宮川和芳教授
2050年カーボンニュートラルの 達成に向けたエネルギー改革に対応するエネルギー、推進、インフラ機械機器の整備に備えて、様々な流体機械システムの高機能化、高性能化、高信頼性化が求められています。本研究所においてもカーボンニュートラルの達成に貢献するための機械システムの研究開発を実施していますが、特に、CO2を排出しない再生可能エネルギーの開発、普及およびCO2排出削減のための機械システムのエネルギー効率の向上を目指した取り組みに注力しています。
達成に向けたエネルギー改革に対応するエネルギー、推進、インフラ機械機器の整備に備えて、様々な流体機械システムの高機能化、高性能化、高信頼性化が求められています。本研究所においてもカーボンニュートラルの達成に貢献するための機械システムの研究開発を実施していますが、特に、CO2を排出しない再生可能エネルギーの開発、普及およびCO2排出削減のための機械システムのエネルギー効率の向上を目指した取り組みに注力しています。
再生可能エネルギーの中でも天候に左右されず安定で優良な中小規模の水力発電は、コスト低減と性能、信頼性向上が求められます。計画、生産から消費までの地産地消の電源を目指してバリューチェインの最適化が必要です。地点として開発がほぼ終わっている大規模水力発電は、既設機の取り替え需要は多くあり、最近のシミュレーション技術を駆使して効率の向上や、大きな流量、落差変動でも対応可能なエネルギーを有効利用できるプラントとして生まれ変わっています。従来、原子力発電の需給調整を担ってきた、揚水発電は、最近、風力や太陽光など変動の大きな再生可能エネルギーの需給調整として、大容量バッテリーとして期待されています。揚水発電には、系統安定化の機能もあり、現在、活用方法が模索されています。これらの電力会社、自治体、メーカーのニーズに応えるべく、活動を展開していきます。その他、エネルギー機械の効率向上により省エネルギー化を支援し、CO2排出削減に貢献します。
本研究所では、液体水素や液体CO2の輸送のための技術開発、要素技術研究にも注力していきます。二次エネルギーである水素のカーボンフリーのためのエネルギーとしての地位確立に向けて、輸送、貯蔵のためのエネルギーキャリアシステムの大型化/コストダウンと、各種利用シーンでの製品競争力強化を加速するために、流体機械・機器の開発基盤技術の構築を進めます。また、CO2の輸送に伴う課題の解決にも取り組み、研究成果を機械・機器の性能、信頼性向上およびコストダウンへと展開いたします。
これらの研究開発は、外部からの委託、共同研究、公的研究を利用して実施いたします。大学でのシーズと企業、自治体などのニーズを合致させ、タイムリーな成果を創出するためのマネージメントを機構、学協会との協力のもと進めてきます。長期的、短期的なロードマップを引いて、社会の要求であるカーボンニュートラルの実現、災害に対する有効なインフラ整備、地産地消のエネルギー源の構築などを目指して研究開発を実施いたします。