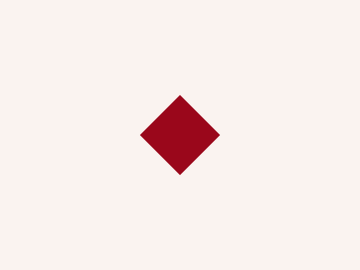インキュベーション・オン・キャンパス(IOC)本庄早稲⽥は、新製品‧新技術の研究開発や、新分野への進出を⽬指す中小・ベンチャー企業等への支援を、大学との共同研究、大学からの情報提供をはじめとする産学連携の強力な推進によって実現していくために、早稲田大学のキャンパス内に整備されました。IOC本庄早稲田はA棟・B棟・V棟に分かれており、A、B棟は大学の研究・教育施設で、V棟は主に中小・ベンチャー企業向けの賃貸型事業施設になっております。この記事では2年間⼊居されている株式会社電知様に迫ります。

本庄発、「電池診断」ベンチャーが描く近未来
――EV時代に求められる技術を社会実装する
2023年11月に開催された「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」(一般社団法人日本自動車工業会主催)の「Pitch Contest & Award」にファイナリストとして参加した株式会社電知。創業3年という短いスパンで、 主力製品・サービスの研究、開発、実装を実現した経緯と、世界中の名だたる企業が牽引する「EVシフト」の潮流の先にある「電池診断」需要について、代表取締役CEOの向山大吉氏と代表取締役CTOの向山公一氏に伺った。

右:代表取締役CEO 向山大吉氏/左:代表取締役CTO 向山公一氏
EVの先にある「リユース市場」
――本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、最初に起業のきっかけについて教えてください。
向山大吉CEO(以下、向山CEO):よろしくお願いいたします。私が大学で電気化学インピーダンスという方法を用いた「電池評価」の研究をしていたことが起業のきっかけで、プログラミングが得意な弟のCTOと一緒に、2020年7月に会社を立ち上げました。しばらくは、私が研究開発、CTOが開発と実装を担当する形で受託開発をメインに活動していたのですが、ベンチャーの醍醐味は自前の製品・サービス開発にあることに思い至り、非破壊で電池の安全性や寿命等を診断できるツールの開発に着手しました。
――ホームページ掲載の主力製品「EV車載電池用診断装置」はどのようなシーンでの活用を想定して開発されたのでしょうか?
向山CEO:製品名にもあるように「EV車載電池」の性能や劣化具合を、急速充電のポートに挿すだけで診断することができます。私が研究室に所属していた経験と知見をベースに、アカデミックな情報とつなぐことで、従来の手法では把握できなかった種類のデータを取得できる点が大きな特徴の1つです。当初、「そこまで詳細な情報はいらないのではないか」というお声もいただいてはいたのですが、私たちは近い将来、EVのリユース市場が拡大するだけでなく、EVの電池を他の製品に転用するケースが増えると予想して開発を進めました。
――実際に製品をローンチされたあとの反響はいかがでしたか?
向山CEO:製品を開発するにあたり、埼玉県の補助金を活用させていただいたのですが、おかげさまで補助金の対象期間終了後 すぐの2023年3月には、EV用DC急速充電規格の技術開発と充電インフラの普及等を手掛けているCHAdeMO協議会さんで当社の技術をご紹介することができました。その後は、ありがたいことに想定以上の反響とお問い合せをいただき、2023年はその対応だけで終わってしまったという状況です。
「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」で得た確信
――昨年は世界5大モーターショーの1つに数えられる「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」の「Pitch Contest & Award」にもファイナリストとして参加されました。
向山CEO:初めての大規模会場でのピッチで、圧倒されているうちに終わってしまったというのが正直なところですが、 EVをはじめとするモビリティ業界の現在地を知ることができ、とてもよい経験になりました。
向山公一CTO(以下、向山CTO):私が注目したのは、「未来の東京」を描いたプログラム「TOKYO FUTURE TOUR」です。移動はもちろん、物流、スポーツ、遊び、災害対策等、あらゆるシーンでモビリティが活躍している未来を体験しながら、「多種多様な機械、製品に電池が使われている」ことを再認識するとともに、いま以上に「電池診断」のニーズは高まるという確信を得ることができました。

――「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」に出展するにあたり、インキュベーション・オン・キャンパス(IOC)本庄早稲田に入居する企業の支援があったと伺っています。
向山CTO:お恥ずかしながら、最初に出展のお話をいただいたときは、「自分たちでチラシを製作して、当日プリントアウトして 持参すればいいだろう」くらいに考えていました。しかし、お話を伺ううちに、来場者100万人超というとんでもない規模の イベントであることに気づき、慌てて、公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパークさんにご相談したところ、大規模な見本市等でブースの設営等を多数手掛けてこられた株式会社ランタさんをご紹介いただき、無事に出展することができました。
向山CEO:それだけではなく、リサーチパークさんには日々、さまざまなシーンでお世話になっています。たとえば、経済産業省のGo-tech事業に応募し、採択された際にも、多大なるお力添えをいただきました。
IOC本庄早稲田から未来を拓く
――そもそも、なぜIOC本庄早稲田に拠点を構えようと思われたのでしょうか。
向山CEO:もともと所属していた研究室が本庄早稲田キャンパスの部屋をお借りしていたご縁がきっかけですが、入居を希望した理由は大きく3つあります。1つ目は、実験開発に必要な設備が整っている点です。私たちのように実験が必要な企業にとっては、物を動かせるスペースはもちろん、安全性がもっとも重要なポイントになります。2つ目は、アクセスのよさです。 本庄早稲田駅から東京駅までは新幹線で50分かからない距離ですし、何よりも車で通勤している私たちにとって、関越自動車道へのアクセスのよさは必須の条件でした。
向山CTO:私はいま移住先の群馬から通っているのですが、大きな渋滞に遭遇することはほとんどなく、快適な通勤ができています。
向山CEO:3つ目は少し定性的な話になりますが、起業に先立ち、世界のインキュベーション施設を視察した際に魅力的に感じた、自然が豊かで静かな環境であることに加え、自由な雰囲気がある点に惹かれました。大学の研究室とは直接関係のない企業に対しても門戸が開かれているのは、私たちのようなベンチャーにとってはとてもありがたいですね。

――最後に、今後の展望についてお聞かせください。
向山CEO:兄弟2人で立ち上げた会社ということもあり、組織としては未熟なところがありましたが、VC(ベンチャーキャピタル)からの資金調達の目処も立ち、新しいメンバーの加入も決まっていますので、2024年は、組織としても盤石な体制で、製品・サービスの普及を図っていきたいと考えています。
向山CTO:社会全体が期待しているEVをはじめとする新しい技術・製品開発には「電池」が必須のアイテムであり、そのために欠か せない「電池診断」という技術にさらに磨きをかけて、未来に貢献していきたいと思います。
――本日は貴重なお話をありがとうございました。
向山CEO・向山CTO:ありがとうございました。
【ご略歴】
向山大吉(むこうやま・だいきち)
株式会社電知代表取締役CEO。1976年、埼玉県生まれ。14年間にわたり、早稲田大学にて電池の内部状態評価の研究に従事後、起業。
向山公一(むこうやま・こういち)
株式会社電知代表取締役CTO。1978年、静岡県生まれ。SIerにおいて業務システム開発に従事した後、独立。15年間にわたる多数のソフトウェアプロダクト開発を経て、現職。
【ライター情報】 池口 祥司(いけぐち しょうじ)

1984年、山口県生まれ。早稲田大学法学部卒。2008年、株式会社PHP研究所入所。第一普及本部東京普及一部(書店営業)、企画部、特販普及部を経て、ビジネス出版部にて書籍の編集業務に従事。現在は、2018年に参画した天狼院書店の「取材ライティング・ゼミ」講師の他、フリーランスの編集・ライターとして書籍、雑誌、企業会報誌、ウェブメディアの編集・執筆に携わる。担当した書籍に『経営者になるためのノート』(柳井正著)、『大人はもっと遊びなさい』(成毛眞著、以上PHP研究所)などがある。

インタビューの様子