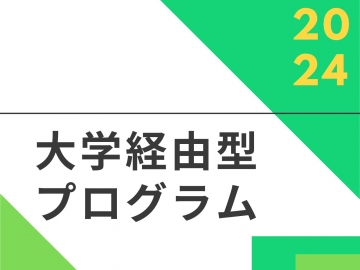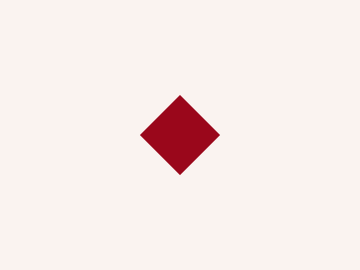2019年度参加者の声
就業機関:中日新聞社
社会科学部1年(就業当時)西山綾乃さん
私は高校時代新聞部に所属し主に取材に力を入れていた。取材を通して一つの物事を追いかけそれを伝えることの面白さに惹かれ、記者を志すようになった。1年生からメディア業界でのインターンシップを積んでおきたかったため、このプログラムの受講を決意。過去にマスメディアコースにおいて1年生の受講者があまりおらず不安があったが、早い段階から就職について知り、メディア業界での就業体験ができたことは大きな収穫になった。
私は小学生から親しんできた中日新聞で就業した。社会部と整理部でそれぞれ5日間ずつ体験させていただいた。社会部では取材の同行や記事の執筆をし、整理部では主に記事に見出しを付けた。これらの活動を通して語彙力の無さや話題の切り口の乏しさが課題であると気づけた。そのほかに記者の方々とお話しする機会もあり、就職活動や仕事と子育ての両立など私たちの疑問や相談に応じてくださった。
今回の就業体験では多くの学びがあったのと同時に自分がこれから伸ばすべき力を把握できた。低学年でも臆せず挑戦してみてほしい。
就業機関:沖縄タイムス社
文学部3年(就業当時)勢島康士朗さん
2年生の冬に自分自身の将来を考える中で、社会的マイノリティや社会問題の当事者に向き合っていきたいという思いから記者を志すようになりました。実際に記者の仕事を体験しながら、基地問題や戦争の歴史に向き合う当事者に会うことができるこのインターンに魅力を感じ、志望しました。
インターンでは社会部、政経部、学芸部、中部支社と様々な部署や支社での仕事を日替わりで体験しました。実際に辺野古に赴いて基地移設の反対運動を見たり、ガマや沖縄戦の記念館に行ったりと沖縄の抱える問題について学び、大きな財産を得ることができました。しかし同時に、英語教育に関するフォーラムの取材や沖縄伝統芸能の取材など、普段の沖縄の姿の見える取材もとても意味のあるものでした。普段の姿を取材していく中で、沖縄の人が本当に苦しんでいることを知り、私自身もその苦しみを押し付ける当事者だと気づくことができました。
長いようであっという間だったこの2週間の中で、これから記者として生きるために必要なことを多く学ぶことができました。
2018年度参加者の声
就業機関:上毛新聞社
内定先:出版業界
文学部3年(就業当時)永井優希さん
マスコミ業界に漠然とした憧れがあった。そのため「マスコミ業界は胸が躍るところなのか」を確かめるために、インターンシップに参加することを決めた。3年生になり、何かしなければならないと焦っていたこともあった。
「日航ジャンボ機墜落事故について知っていますか?」これはインターンシップ初日に投げかけられた質問だ。私は答えられなかった。勉強不足の自分を恥じると同時に、単独機では史上最悪の死者数のこの事故が知られていないことに驚いた。また「慰霊の灯篭流し」を取材させていただいた際にある言葉が心に響いた。「30年経ってようやく口を開くことにした」という遺族の言葉だ。遺族にとっての事故の大きさ、そして重い口を開くほど風化させたくないと願っていることがありありと感じられた。事件事故や戦争など知るべきことは多くあり、私自身がこれらを伝えたいと思った。しかし報道では中立性が求められる。私は時間をかけて人々に寄り添いたいと考えた。その時に浮かんだ道が出版社であった。
進路を決めるきっかけとなった10日間であった。
就業機関:琉球新報社
文化構想学部2年(就業当時)黒川 尚子 さん
ドキュメンタリー作品のなかで米軍基地問題や沖縄戦の歴史を抱える沖縄の姿を見て、正直愕然とした。沖縄の現状をこの目で見たい、これが琉球新報でのインターンを志望するきっかけであった。
実習では様々な部署を体験させていただき、取材や記事執筆も行った。記者の方と共に米軍基地や沖縄戦戦跡に訪れる機会もあり、沖縄への理解を深めることができた。沖縄の記者の方々の言動の端々から、「読者である沖縄の人々のために記事を書く」という姿勢を強く感じた。沖縄の不条理な現状に報道の力で立ち向かおうとする記者たちの姿がとても印象的で、民主主義のためのジャーナリズムという日本の報道機関の理想像が感じられた。
以前は、「大手メディアに就職したい」という甘い考えを持っていた私だが、このインターンを通して、マイノリティに寄り添う報道の大切さとその存在に気付かない恐ろしさに気付き、自分の進路について考え直そうと思えた。就職活動開始まで余裕のある2年生のうちに、自分の将来について考えることができて良かったと思う。
就業機関:中日新聞社東京本社
教育学部3年(就業当時)冨田 駿 さん
将来、記者になりたいと思っていた私は、10日間にも渡って就業体験ができることに魅力を感じ、WINに参加しました。私が志望したのは、東京新聞です。最も興味のある政治部で就業体験ができる新聞社を選びました。
東京新聞のインターンでは、編集局各部と支局を日替わりで体験できました。例えば、政治部では、官房長官の定例記者会見や国民民主党代表選を見学しました。政治の現場を直接見ることができ、興味深かったです。また、運動部では相撲部屋の朝稽古を見学するなど、日頃は立ち入れない多くの現場に行くことができました。経済部や特別報道部では取材を行い、翌日の紙面に掲載されたものもありました。
10日間を通して、記者の仕事について理解を深めることができました。記者の仕事の面白さは、「名刺1枚でいろいろな場所に行けて、いろいろな人に会えること」だと実感し、「記者になりたい」という思いが一層強くなりました。
10日間もインターンに参加できる機会は、少ないと思います。記者に興味がある学生は、参加することをお勧めします。
2017年度参加者の声
就業機関:沖縄タイムス社 内定先:日本放送協会(記者職)
教育学部4年(就業当時)岡本 なつみ さん
「社会問題の発端は地方にある」という問題意識から、地方紙でのインターンを志望した。中でも沖縄タイムスは取材同行が多く、現場に最も近い体験ができると考えて就業を決めた。
記者を含めた沖縄の人々は、当事者意識のない本土の人間に辟易していた。例えば基地問題は沖縄だけの問題ではなく、沖縄に基地を置くことで恩恵を受けている国全体の問題である。全国の諸問題において「特定の地域に押し付ける」姿勢が解決を阻んでいることに気付かされた。
また、そうした各地の問題を全国に発信する難しさも大きな壁だと学んだ。沖縄で言えば、その問題に最も精通しているのは沖縄タイムスや琉球新報の記者である一方、地方紙という特性上、全国に発信する手立てが限られている。そう教えてくれた記者の言葉の端々に悔しさが滲んでいた。
勉強不足や記者という仕事の難しさを痛感したが、それでも記者になりたい気持ちが再確認できた機会でもあった。この2週間で体験したことや、記者一人一人からかけられた言葉は今後の記者人生の礎となり、忘れることはないだろう。
就業機関:上毛新聞社
法学部3年(就業当時)河野 千怜 さん
神奈川県出身の私にはほとんど馴染みのない、地方新聞での就業体験は大変貴重な体験でした。
取材に同行し記事を書かせていただいたり、印刷工場を見学したり、とにかく密度の濃い二週間でした。特に最終日の御巣鷹山での慰霊祭はジャーナリズムや公共性に関して改めて考えさせられる経験になりました。現場に行って五感を使うことの大切さを知りました。
また、記者の方と一緒に行動する機会が多くあったので、思いついた質問をどんどんぶつけることができました。記者という職業についてはもちろん、働くということ、社会人とは何なのかなど漠然とした質問にも真摯に答えて下さいました。
地域に密着し、地域のニュースを届けようと日々奮闘している記者や社員の方の姿を間近に見ることで、今後の就職活動やキャリア形成における軸が出来ました。将来どのような職業に就くとしても、今回お世話になった方々の姿勢や言葉は忘れないでいたいと思います。
就業機関:琉球新報社
商学部2年(就業当時)砂川 侑花 さん
将来は記者になりたい、と高校時代から思っていた私だが、この時期少し迷いが生じていた。2年生なので最初は少し気が引けたが、WINでのインターンシップを受けて本当に良かったと感じる。
私が志望したのは沖縄の地方紙、琉球新報社。なぜこの社を選んだかというと、米軍基地問題や沖縄戦の歴史を抱える地にて働くことは、これから記者という仕事を見つめ直すのにいい機会になると思ったからだ。
現場の記者はどういう思いを持って取材しているのか、現地の人はどういう思いで暮らしているのか。そんな思いで臨んだこのインターンだが、結果として私は新聞記者になりたい、という気持ちがより強くなった。
沖縄2紙は偏向していると言われているが、県民の意見をしっかり反映してその上での偏向なのだと、ジャーナリズムの理想的なあり方だなと感じた。自分が影響されやすいからかもしれないが、ここで働きたい、と思った。
2年生だからといって遠慮することはなく、2年生だからこそ、参加してもらいたい。自分の進む道を見直すことができるだろう。