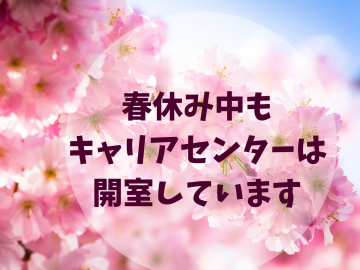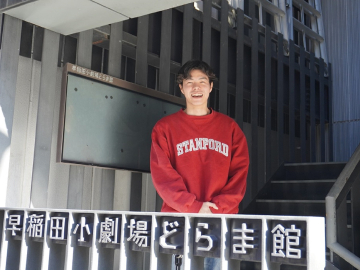「総合商社からMBA、さらに国際機関の舞台へ」
~興味のある事?せっかくだからやってみよう~
何度も悩みつつ、挑戦し続ける国際機関職員
今回の企画は、本学卒業生であり、かつ在職中に大学院を卒業された先輩にインタビューを行いました。
お話を伺ったのは、国際連合の専門機関であるILO(国際労働機関)ジュネーブ本部にお勤めの、桑島麗奈 様(2011年政治経済学部卒・2022年経営管理研究科修了)です。
政治経済学部卒業後、住友商事株式会社に就職され、在職中にMBA取得。転職後、現在はILOで活躍されている桑島様にMBA取得後もさらに挑戦し続ける姿勢、またその力の源についてなど、たっぷりと伺いました。
―― 学生時代 についてご紹介お願いします。
2007年に早稲田大学政治経済学部政治学科に入学し、主に中国政治・経済について学びました。
中国に関心を持つようになったバックグラウンドには、幼少期に父の仕事の都合で中国に約5年間住んでいたということがあります。小学校時代を中国で過ごし、自然と中国や日中関係への関心が高まりました。そこで、北京大学への留学が可能で、さらにダブルディグリー制度のある早稲田大学を進学先として選びました。学生時代は中国政治経済と中国語の勉強を頑張り、興味のあった模擬国連というサークルに入って活動していました。卒業後は、新卒で住友商事株式会社※1に入社し、在職中に早稲田大学大学院経営管理研究科でMBAを修了し、2024年に現在勤務しているILO(国際労働機関)に転職しました。
(住友商事株式会社※1:総合商社。貿易と投資を二つの柱として、エネルギー、資源、化学品、輸送機、メディアなど多岐にわたる分野でグローバルに事業を展開している。)
――国際機関に関心があったと伺ったのですが、小さいころから国際機関の存在を意識されていたのですか。
そうですね。幼少期に父の仕事の都合で中国に住んでいたのですが、当時の中国は貧富の差が非常に大きく、街中には生活に困窮している人々の姿が当たり前にありました。子どもながらにその光景に衝撃を受けて、「どうしたら困っている人の役に立てるのかな」と、すごく悩んでいました。ただ、悩んだところで小学生だった私は何もできず、ずっとモヤモヤした気持ちを抱えていました。その後、中学生の時に、夏休みの宿題で職業インタビューをする機会がありまして。社会課題に取り組んでいる職業の中で、国連が一番分かりやすいと思い、「あの、国連について夏休みの宿題で調べていて、お話を聞かせてください。」と思い切ってUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の駐日事務所に電話をしてみたんです。すると、その事務所でお話を聞かせてもらえることになりました。当時を振り返ると、今よりもフットワークが軽いなと思います(笑)。そのインタビューでお伺いした職員の方の意識の高さや、仕事する上でのマインドセットやパッションにすごく感銘を受けたんですよ。これが国際機関との出会いのきっかけですね。
――総合商社を選んだ理由を教えてください 。
総合商社を選んだ理由は、業界を俯瞰して、社会課題のある分野・地域に対して、自分でビジネスアイデアを考えて、色んな業界・企業・人を繋ぎ合わせて0から仕事を作れるというクリエイティブさに興味を持ったからです。大学時代のサークル等の経験から、そのような仕事の仕方は自分の強みとの親和性が高いかなと思いました。
――日本と中国の関係を専門とする職業は選ばなかったのですか。
そうなんですよ!中国に特化した仕事がしたいなと思ったので、それは悩みました。
でも、OB訪問で、総合商社で働かれているOBの方から「若いころは中国に専門を絞らず、まずはもっと色んな世界を見た方がいい」というアドバイスを頂き、総合商社を選びました。
――ILOに転職した理由を教えてください
住友商事で働いて4年目の時、アメリカの子会社にトレーニーで出向しました。現地で働く中で、ある社員の方から「あなたの会社が出資したことで、海外での事業展開が進んで、私自身も海外での事業に興味を持つようになって、自分のキャリアの幅が広がったよ。ありがとう。」と言って頂いたんです。この言葉がとても印象に残っていて、自分の仕事が誰かの人生の選択肢を広げることに繋がる、そんな経験に大きなやりがいと喜びを感じました。この経験が、「より多くの人が労働を通じて人生の可能性を広げられる社会をつくりたい」という思いに繋がり、ILOへの関心へと繋がっていきました。
また、ILOを選んだ理由としては、ILOの理念に共感したからです。ILOが掲げる「decent work for all」という理念は、私の価値観と深く重なって、この価値観を共有できる人と共に働きたいと思いました。実際にILOの職員の方々とお話した際に、皆さんが「decent work for all」の実現に向けて強い意志を持って働かれているのを感じ、「この環境で、この志を共有する人たちと働きたい」と確信し、転職を決断しました。
――ILOの概要とご自身の仕事内容について教えてください。
ILOは国連の専門機関の一つで、仕事の創出、社会的保護の拡充、社会対話の推進、仕事における権利の保障に取り組む機関です。私はILOの本部で「雇用・投資部」に所属しています。特に国連では専門性、即戦力が重視され、私は総合商社で培った貿易・投資という専門性を活かすようにしています。具体的には、貿易や投資が雇用に与える影響を中心にリサーチを行い、COP(気候変動枠組条約締約国会議)のサイドイベントや各国政府関係者向けのフォーラム等でその結果を発表しています。また、リサーチ業務と並行して、実際に現場で雇用を創出するプロジェクトの立ち上げにも携わっており、今年は南アフリカのリンポポ州において、若者の失業と環境問題の両面にアプローチする「電子廃棄物リサイクルと若者の雇用」のプロジェクトを実施予定です。このプロジェクトでは、若者や女性、障害のある方々を対象に、電子廃棄物のリサイクルに関する技術的スキルやビジネス研修などを通じて、循環経済の分野での雇用創出を目指しています。

アフリカ連合本部での国際会議に登壇(エチオピア・アディスアベバ)
――日本の企業とILOでの働き方の違いはありますか。
大きな違いは、国際機関ではより強く「自主性」が求められる点だと感じています。日本の民間企業では、「チーム一丸となって目標に向かって進もう」という協調性を重視する文化が根付いており、「社員を長期的に育てていく」という前提での働き方が一般的です。
一方で、国際機関では「個」の力がより重視されます。自ら課題を見つけ、上司に積極的に提案していかないと、仕事は与えられませんし、待っているだけでは新しい仕事が回ってくることもあまりありません。少し極端に聞こえるかもしれませんが、放っておかれるくらいの覚悟と主体性が求められる環境です。自ら動かなければ、仕事の機会も評価も得られないという厳しさがあります。また、国際機関の職員には有期契約が多く、すでに専門性を持つことが前提とされているため、日本の企業のように長期的に人材を育てるスタイルとは異なります。
その分、自分の考えを形にできる自由度と、それに伴う責任の大きさには大きなやりがいを感じます。また、「個」に任される部分が大きいからといって、決して孤立するわけではありません。上司や同僚からは必要に応じて的確なフィードバックが得られますし、自分の課題意識や努力次第で、プロとして大きく成長できる環境だと感じています。
――確かに、日本の働き方とは大きく違いますね。
そうなんですよ!日本の企業でももちろん、自分から提案して、積極的に動く姿勢は大切だと思います。ただ、組織としての目標や方向性が比較的はっきりしていて、そこに向かって自分が果たすべき役割も明確だったので、ある意味では仕事の進め方が見えやすかったと感じます。でも、国連では、自分から動いて、どんな役割を果たしたいか、どんな仕事をしたいかを周囲に積極的に伝え、機会を掴みにいかなければなりません。
また、先ほども触れたように、雇用形態の面でも大きな違いがあります。国際機関では有期契約が多いので、継続して働くためには、日々自分の価値をアピールして、実績を積みあげていく必要があります。自分で社会課題を見つけ出し、政府や関係機関にプロジェクトを提案して立ち上げていくこともあります。日本の安定した雇用環境と比べると、やはり国際機関はハードな面もありますね。
――ここからは大学院について質問させていただきます。まず、直接大学院に進学しなかった理由は何ですか。
「いつか国際機関で働きたい」という考えは、大学生の頃から漠然と持っていました。国際機関で働くには修士号が求められることが多いので、国際機関を目指すのであれば、どこかのタイミングで大学院進学が必要になるだろうとも思っていました。
ただ、それ以上に当時は「総合商社で働いてみたい」という気持ちが強くありました。先ほど触れた通り、多様な国や業界を繋ぐダイナミックなビジネスの現場で、自分もその一員としてクリエイティブな仕事に挑戦したいという思いがありました。
実際に働く中で、現場での経験や出会いを通じて、「自分はこういうテーマに関心がある」といったことが少しずつ明確になっていきました。結果として、自分の関心や強みを見つける大きなきっかけになったと思っています。
もちろん、学生時代に専門性が定まっていれば直接大学院に進学するという道もあったと思います。ただ、人生は必ずしも一直線でなくてもいいと思っていて、「これだ」と思えるものに出会えた時に、必要な学びをそのタイミングで学び直せばいいのではないかとも思います。
――大学院に進学して得られた考え方の違いはありますか。
大学では、当時の日本と中国の関係に興味があったので、ダブルディグリー制度で北京大学に留学し、その興味・関心を素直に突き詰めて学んでいました。一方で、MBAは社会人経験を経てからの学び直しだったので、「仕事にどう役立てるか」という意識で学びました。そういった意味で、学びへの姿勢や考え方には違いがあったかもしれないですね。
大学では、どちらかというと先生から教わることが中心の受動的な学びだったのに対して、大学院では、「自分の仕事の課題を解決するには、この授業で習ったビジネス理論をどう活かせるかな」といった、より能動的な姿勢で臨みました。実務と結びつけながら学ぶことで、学びの定着や応用も深まりましたし、結果として、考え方にも実践的な問題解決志向の視点が加わったように感じています。
――大学院で学べて良かった点はありますか。
ありますね。ILOの仕事の大きな柱の一つは、「雇用の創出」ですが、その実現のためには、民間企業との連携も重要です。そこで、企業がどのような課題を抱え、何を重視して経営しているのかという視点を持って仕事をしたいと思っています。大学院では、そのような部分について体系的に学ぶことができました。
例えば、私は住友商事ではでIR(インベスターリレーションズ)の部署に所属しており、その中でESG(環境・社会・ガバナンス)を担当していました。当時からESGが企業経営において重要なテーマであることを実務で実感していましたが、大学院では改めてこれについても体系的に学び、その背景や国際的な動向、企業の意思決定とのつながりをより深く理解することができました。ILOとしても、ESGの潮流をどのように捉え、国際機関の立場からどう貢献していくかが問われています。実務経験と大学院での学びが融合していることは、自分にとって大きな強みになっていると感じています。

早稲田大学経営研究科(MBA)卒業式にて(日本・東京)
――大手総合商社からの転職は、非常に悩まれたと思いますが、なにかきっかけはあったのですか。
まず、多くの方がコンフォートゾーンから抜け出すことにためらいを感じるのは自然なことだと思いますし、私自身もまさにそうで、正直なところかなり時間がかかりました。
私にとって、転職の大きなきっかけになったのが、子どもの誕生だったんです。一般的には、子どもが生まれるタイミングというのは、安定を優先する方が多いかもしれません。実際、私も最初はそう考えていました。
でも、ちょうど子どもが生まれたときに、「自分はどういう母親になりたいか」「この子にどんな背中を見せたいか」ってすごく考えて。たとえ少し遠回りになったとしても、自分の人生を前向きに楽しんでいる背中を見せることが、きっとこの子の人生にもいい影響を与えてくれるのではないかと感じたんです。
もちろん、ものすごく葛藤がありました。国際機関で働くというのは簡単な道ではありません。仕事は基本的に有期契約が想定され、勤務地も海外が中心となり。特に、私の夫は東京勤務なので、家族が離れて過ごすことになります。それでも、国際機関に挑戦することを選んだのは、「人生を前向きに楽しんでいる背中を子どもに見せたい」「新しい仕事に挑戦している姿を見せることが、この子にとってもきっと意味がある」と思えたこと、そして夫が私の背中を押してくれたことが、最終的な決断につながりました。
今は、私が子どもと一緒にジュネーブで生活し、夫とは日本とジュネーブをお互いに行き来しながら日々を過ごしています。夫も私も、それぞれの仕事に真剣に向き合いながら、互いの選択を尊重し合い、支え合っています。私の挑戦を理解し、温かく背中を押してくれた夫には、本当に感謝しています。まだ道の途中ではありますが、これからも「自分の選んだ道が正しかった」と胸を張って言えるよう、仕事にも家庭にも誠実に向き合い続けたいと思っています。

ILOジュネーブ本部にて家族とともに(スイス・ジュネーブ)
――早大生へのアドバイスをお願いします。
学びって、本当に「いつ・どこで・どう」役に立つか分からないものだな、と感じています。
修士・博士で学んだ知識だけでなく、それ以前・以後の経験や学びも、思いがけないタイミングでそれぞれが繋がってくることがあります。「Connecting the dots」っていう言葉がありますが、私が国連に転職したときも、まさにこの言葉の通りでした。
私がアプライしたILOのポストは、偶然ちょうど住友商事で担当していたテーマとぴったり一致していたんです。そのテーマは、当時の私にとって社会のニーズや事業の課題に応じて、自分が興味を持って深堀したいと感じて、自然と夢中で取り組んでいたことでした。積極的に狙って将来のキャリアと結びつけて考えていたわけではありませんでしたが、関心を持って取り組み続けてきたことが、結果的にILOでのニーズと重なりました。国連に対する思いが強まったのが、修士号を取得したタイミングでもあり、ILOにアプライできる要素が揃って、dotsが繋がり、自然と道が開けていきました。このように、今すぐ目の前の学びや興味が、将来にどう繋がるかは、なかなか自分でも予測できません。でも、きっとどこかでそれが繋がり、活きる瞬間が訪れると思います。
だからこそ、今は「これ、興味があるかも」と思ったことに素直に飛び込んでみるのがいいと思います。もしかしたら、興味のある分野の学びが、就職や将来にすぐ繋がらないのではないかと、心配になることもあるかもしれません。でも、学生のうちにすべてを見通すのはとても難しいですし、人生は長いです。自分の「好き」や「興味」を大切にして学び続けていれば、ある日ふと、それまでdotsだったものが繋がり、思いがけない形で自分だけの道が開け、自分の人生を豊かにしてくれると信じています。
もしまだ自分の興味が明確に見つかっていないとしても、いろんなことを学び、会社や業界を見ていく中で「面白そう」と思える分野に出会えるかもしれません。まずは働いてみて、その中で「もっと学びたい」と思ったときに大学院に行く、という道も十分にありだと思います。
ぜひ、「自分は何に興味があるのか」「どんなことにワクワクするのか」を大切にして、柔軟に道を切り開いていってくださいね!

<参考ご提供写真>
左:北京大学留学中に模擬国連大会で議長を務めた時(中国・北京)
右:電子廃棄物リサイクルプロジェクトにて、南アフリカ政府関係者と(南アフリカ・プレトリア)
――ありがとうございました。
――インタビューを通して
-「挑戦し続ける」・「コンフォートゾーンから抜け出して自由に。」-
ただ文字に起こすと、表面的には格好良く見えるフレーズです。しかし、この短い文字だけでは表現できない、その考えに至るまでの桑島様のバックグラウンドや葛藤、挑戦などを知る事で、これらの言葉の意味を自分自身に取り込めたように感じます。卒業後もキャリアを維持するのではなく、悩みつつ、自分の関心を突き詰めていく先輩に、これからの人生を励ましていただいたようなインタビューでした。自身も悩むことから逃げず、目の前のことにどんどん挑戦してまいります。(里地)