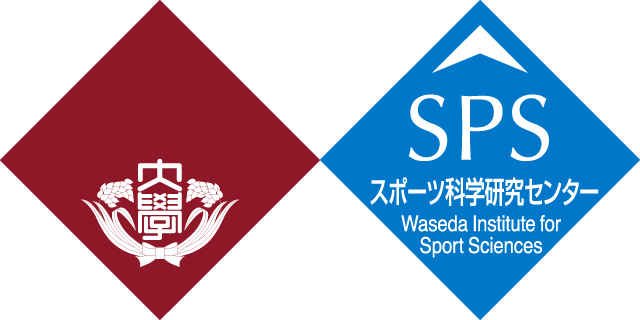- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2005年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2005年度)
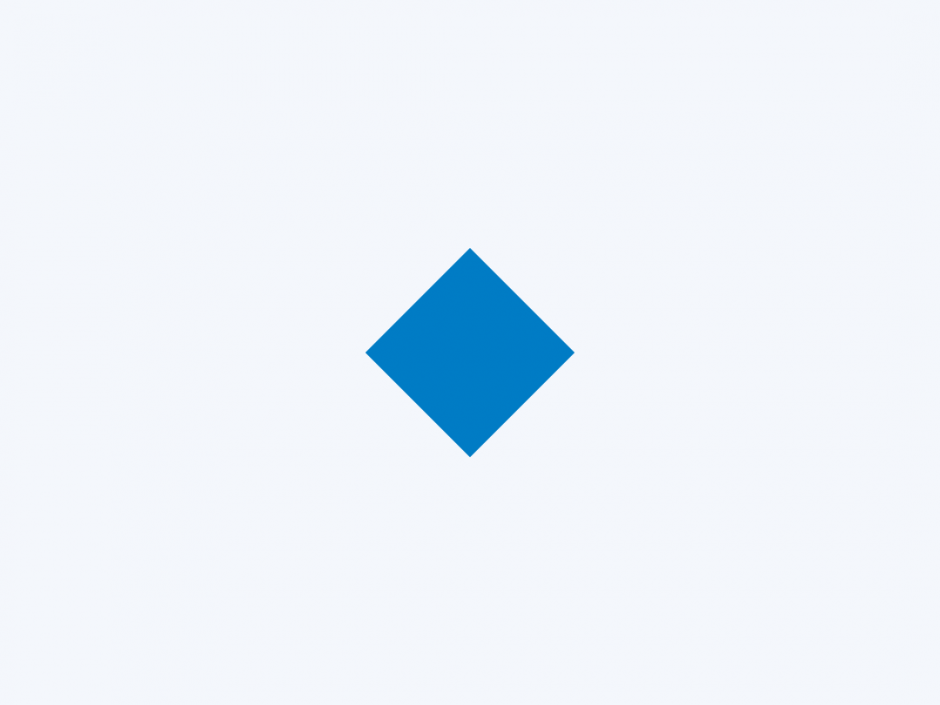
- Posted
- Fri, 02 Dec 2005
第31回 2005年12月6日(火)
演題1
「ヴィクトリア/エドワード朝のイギリスにおける柔術ブーム―身体文化・社会ダーウィニズム・帝国的身体―」
演者
岡田桂氏(早稲田大学スポーツ科学学術院)
内容
19世紀後期から20世紀の初めにかけて、イギリスで柔術ブームが沸き起こったことは、あ まり知られていない。本発表では、なぜこの時期に、遠い東洋の小国・日本の格闘技がイギリスの人々の興味を引き、浸透していったのかについて、同じく当時ブームとなった「身体文化(Physical Culture)」との関係から考察する。
演題2
「17世紀のオリンピック:イギリスの伝統的競技会「コッツウォルド・ゲーム」の起源をめぐって」
演者
石井昌幸先生(早稲田大学スポーツ科学学術院)
内容
イギリスで毎年5月、通称「コッツウォルド・オリンピック」と呼ばれる小さな競技会が開かれている。この競技会は1612年にロバート・ドーヴァーという人物によって創始されたと伝えられる。発表では、この競技会の起源を当時の政治的・宗教的文脈のもとに考察する。
第30回 2005年11月15日(火)
演題1
「Point cluster法による6自由度膝関節微細運動の計測」
演者
井田博史先生(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部)
内容
Point cluster法(Andriacchi et al, 1998)は新規の動作計測法であり、身体部分表面に貼付した5~20個の多数のマーカ座標データから、膝関節の3次元6自由度微細変位を観察することが可能である。
演題2
「膝靱帯損傷の受傷メカニズム―ビデオからの解析―」
演者
福林徹先生(早稲田大学スポーツ科学学術院)
演題3
「Point Cluster Tecnique の臨床応用―片脚着地における性差およびトレーニング効果―」
演者
永野康治氏(早稲田大学人間科学研究科)
第29回 2005年11月1日(火)
演題
「高次脳機能障害者を守るということ」
演者
中島八十一先生(国立リハビリテーションセンター感覚機能研究部部長)
第26回 2005年10月25日(火)
演題1
「トップスイマーへのサポート活動(仮称)」
演者
岩原文彦先生(日本体育大学助手)
内容
岩原先生は チーム北島の参謀役として活躍。早稲田大学スポーツ科学部の非常勤講師もなさっておられます。
演題2
「競泳のコーチング(仮称)」
演者
奥野景介先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助教授、早稲田大學水泳部 競泳部門監督)
第25回 2005年7月25日(月)
演題1
陸上競技短距離選手に見られる加速走中の下肢スティフネスの変化
演者
土江寛裕先生(富士通、早稲田大学スポーツ科学学術院非常勤講師)
内容
走パフォーマンスを評価する際、Spring-Massモデルを用い、下肢のスティフネスとしてシンプルに表すことは、複雑な走運動を表すのに有効であ る。下肢のスティフネスは走速度やピッチ、ストライドのに伴い変化することは報告されているが、加速中の動作や速度の変化に伴うスティフネスの変化は明らかになっていない。本研究では、五輪代表短距離選手における、加速中の速度に伴うピッチとストライドおよび下肢のスティフネスの変化を調べることを目的とする。
演題2
短距離のモデリング ―コーチングの視点から―
演者
磯繁雄先生(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)
第24回 2005年6月28日(火)
演題1
レジスタンストレーニングと動脈
演者
宮地元彦先生(独立行政法人国立健康栄養研究所)
内容
習慣的な有酸素性運動は動脈硬化や高血圧などの循環器病の危険因子を改善することが知られている。その一方で、もう一つの運動形態であ るレジスタンス運動の実施が循環器病危険因子にどのような影響を及ぼすかについては十分明らかになっていない。我々は、横断的、縦断的研究手法を用いて、レジスタンストレーニングが動脈のコンプライアンス(柔軟性)や血圧に及ぼす影響について検討した。その結果、レジスタンストレーニングは頚動脈や大動脈といった中心動脈のコンプライアンスを低下させることが明らかとなった。血圧には影響を及ぼさなかった。また、中心動脈コンプライアンスは加齢とともに低下して、循環器病を引き起こす原因となるが、レジスタンストレーニング実施者では加齢による中心動脈コンプライアンスの低下が運動しない人より速いことも示唆された。
第23回 2005年5月31日(月)
演題1
複数体肢運動時の循環系調節
演者
時澤健氏(人間科学研究科博士課程2年・村岡研究室)
内容
ヒトが日常で行う動作やスポーツ活動では、複数の体肢を同時に働かせて目的の運動を行っています。しかしながら、そのときの循環系応答がどのように調節されているかについては、十分に明らかとなっていません。本研究では、運動によって活性化される骨格筋内の感覚受容器に注目し、末梢血流の配分にどのような働きを持つかについて検討しました。
演題2
筋と腱の強さの関係
演者
村岡哲郎氏(早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構)
内容
筋力が大きいほど腱は硬い? 腱は太いほど硬い? スポーツ動作を通して筋・腱に高い負荷を長年に渡ってかけ続ければ、筋・腱は強くなる? これらの疑問について、横断的研究により検証を試みた。
第22回 2005年5月16日(月)
演題
Neural Correlates of Symmetry Perception in Humans and Monkeys
演者
Yuka Sasaki, Ph. D.(NMR center, Massachusetts Genral Hospital, Harvard Med School, MA, USA.)
内容
Humans often create and appreciate visual symmetry in their environment, and the underlying brain mechanisms have been a topic of increasing interest. Here, symmetric versus random dot stimuli produced robust fMRI activity in higher-order regions of human visual cortex (especially areas V3A, V4, V7 and LO), but little activity elsewhere in brain. This fMRI response was found both with and without attention controls. Moreover, it was highly correlated with the psychophysical perception of symmetry. Similar symmetry responses were found using line-based stimuli, and dot stimuli at a wide range of stimulus sizes and geometric configurations. Weaker symmetry responses were found in analogous regions of macaque visual cortex, using fMRI techniques with higher sensitivity. This evidence suggests that visual symmetry is specifically enhanced in human brain, but that the underlying neural mechanisms may nevertheless be resolvable in non-human primates.
第21回 2005年4月25日(月)
演題1
一致タイミング制御におけるベイズ統合
演者
宮崎真先生(早稲田大学人間総合研究センター)
内容
我々の外的・内的環境は、ノイズ (変動) に満ちている。身体運動制御系は、そのノイズをいかに処理しているのか?本発表では、一致タイミング制御にあ たって、ヒトの運動制御系は、ベイズ統合という方略を用いて、その最適処理を行っていることを示す。
演題2
上腕動脈阻血が体性感覚誘発電位とα運動神経に与える影響
演者
宝田雄大先生(早稲田大学スポーツ科学学術院)
内容
虚血の末梢神経の伝導に対する影響を調べるために、自然血流下と虚血下での正中神経刺激によるSEPとM波の比較をおこなった。SEPの潜時及び最大振幅とM波の積分値を両条件で比較したが変化はみられなかった。
第20回 2005年3月11日(火)2004年度修士論文発表コンテスト
司会
内藤健二
演題1
Relation between muscle plasticity and muscle protein synthesis in rats.
演者
谷端淳(今泉研)
演題2
腓腹筋内側頭の形状および機能に及ぼす関節角度の影響
演者
若原卓(福永研)
演題3
弾性エネルギーの入出力関係に基づく伸張-短縮サイクル
演者
保原浩明(鈴木秀研)
演題4
シニアのQOL向上を目的とした運動プログラム開発の試み
演者
トンプソン雅子(中村好研)
司会
太田めぐみ
演題5
Muscle strophy-induced changes of cathepsin and dipeptide levels in rats.
演者
本橋紀夫(今泉研)
演題6
アスリートと非アスリートの単純運動による脳賦活の差異について:fMRI研究
演者
宇佐美由布子(内田研)
演題7
等尺性運動時における半腱様筋の筋活動動態
演者
久保田潤(鳥居研)
演題8
動的筋力発揮中の腱組織における弾性エネルギーの利用
演者
杉崎範英(福永研)
演題9
野球の打撃動作におけるinterctionトルクの有効性
演者
坂本圭祐(鈴木秀研)
第19回 2005年2月22日(火)
演題1
体重負荷による筋力トレーニング動作の筋活動水準の定量への試み
演者
高井洋平氏(早稲田大学大学院人間科学研究科)
演題2
筋活動レベルが関節トルクに応じて決定する機序:二関節筋の存在が意味すること
演者
野崎大地先生(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究部)
第18回 2005年1月18日(火)
演題1
手足の協調運動の解析
演者
大部隆志氏(早稲田大学人間科学部4年)
演題2
運動制御における皮膚反射の意義
演者
小宮山伴与志先生(千葉大学教育学部教授)
- Tags
- 研究活動