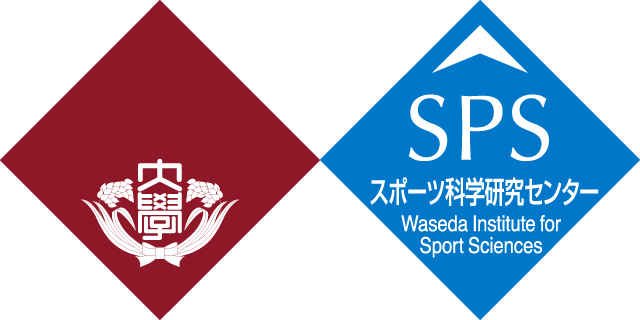- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2006年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2006年度)
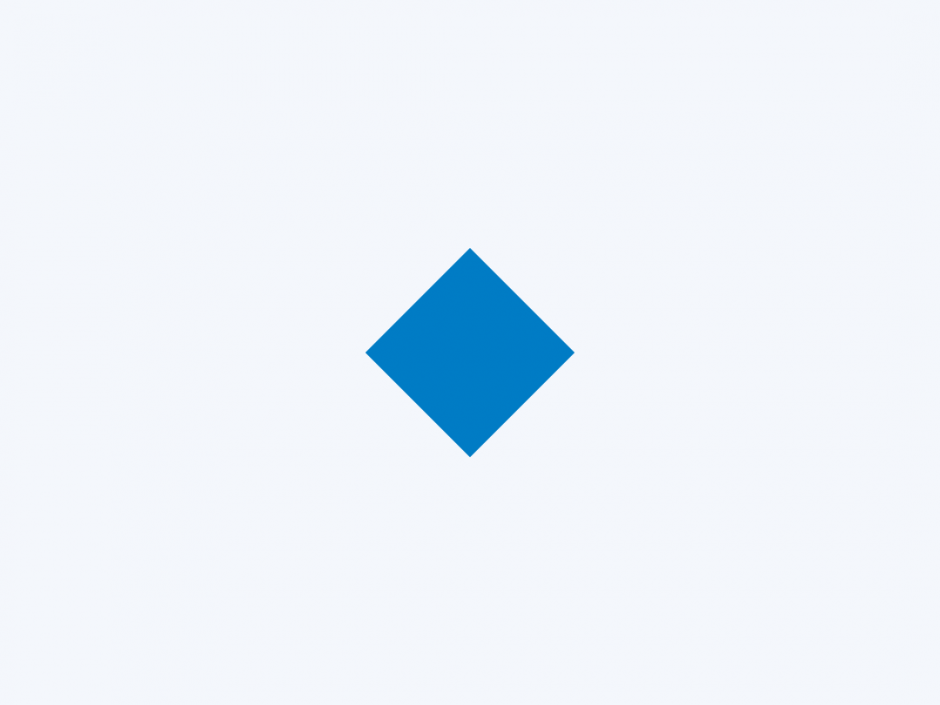
- Posted
- Sat, 02 Dec 2006
第43回 2006年12月26日
演題1
都市における運動空間としての「公園」に関する研究—日比谷公園に注目して—
演者
小坂美保先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
本研究は、1903(明治36)年に日本で初めて洋風公園として誕生した日比谷公園に焦点を当て、公園という空間が都市においてどのような目的で設置され、どのような役割を果たしていたのかについて検討していくことを目的とするものである。
日比谷公園に注目する理由は、近代都市空間を具現化する装置としてのこの「公園」に、開園当初から、園内施設として「運動場」・「運動器械」(青年用5種、幼年用3種の計8種)が設置されていたからである。日比谷公園は、明治後半以降の日本の都市公園のモデルともいわれる。このような場所に運動空間としての機能が付与あるいは期待されたのはなぜなのか。誰によってどのような目的のもとに運動施設が設置されたのか。また、公園や運動空間としての「公園」建設が、当時の国家レベルの思想とどう結びついていくのか。さらには、運動空間としてどのような演出がされ、これらの空間を利用者がどのように受容していたのか、といった視点から公園についてみていきたい。
演題2
運動による免疫細胞の分布変化のメカニズムとその意義について
演者
奥津光晴先生(早稲田大学生命医療工学研究所講師)
内容
身体運動は生体の免疫応答を変化させます。その原因の1つとして免疫細胞の体内分布変化があげられます。細胞の分布および移動を制御する中心的役割を担っているのがケモカインとケモカイン受容体の相互作用です。我々は、一過性の高強度運動で増加するコルチゾールがリンパ球や単球に発現するケモカイン受容体を増強させることを明らかにしました。また単球は、動脈壁へ浸潤後、酸化LDL等を取り込むことで動脈硬化症を発症することが知られていることから、コルチゾールによる単球のケモカイン受容体の発現の増強は、免疫応答の制御のみならず、循環器疾患の発症をも制御する可能性を示唆しています。本研究会では、これらの内容と現在行っている動物実験から得られた最新の知見を合わせて紹介します。
第42回 2006年11月28日
演題1
超音波法による骨格筋の定量とフィールド研究への応用
演者
真田樹義先生(早稲田大学生命医療工学研究所講師)
内容
現時点では、磁気共鳴映像法(MRI法)やコンピュータ断層撮影法(CT法)が骨格筋の定量法として最も精度の高い測定方法である。しかし、フィールド研究に応用できる安価でかつ正確な骨格筋の定量法は現在でも開発されていない。超音波法は、生体での筋サイズを正確に評価できるとともに、その装置はコンパクトで持ち運びができ、比較的安価であり、測定にかかる時間もきわめて短いという特徴がある。そこで本研究は、超音波法を用いた簡易で正確な骨格筋量推定法を開発した。超音波法による推定値は、MRI法による値との間に男女とも有意な相関関係が認められ、独立した被験者においても、推定値と実測値との間には有意な差は認められなかった。結論として、超音波法による筋組織厚は全身および局所骨格筋量を正確に推定することができた。さらに本研究では、大規模な被験者を対象とした日本人における骨格筋量の参照値を提示するとともに、生理学的パラメーター(有酸素能力や骨量)における骨格筋量の標準化(normalization)について検討した。
演題2
大学相撲選手の器官・組織レベルからみた身体組成およびそれらを用いた安静時代謝量の推定
演者
緑川泰史先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
1950年代から、スポーツ選手の身体的特徴を探る研究は、体重を体脂肪量と除脂肪量とに2分類する方法で評価が行われてきた。その研究成果の一つとして、スポーツ選手は一般成人に比べ、除脂肪量の絶対値が大きいことが広く知られるようになった。しかし、50年以上経つ現在でも、スポーツ選手と一般成人との間にみられる除脂肪量の差の「中身」について明確に示したデータは報告されていない。これまでの身体組成研究では、両者の除脂肪量の差は、そのほとんどが筋肥大による骨格筋量の増加であり、臓器重量にはほとんど違いがないと考えられてきた。そこで本研究は、大きな除脂肪量を有する大学相撲選手を対象に、MRI法を利用して器官・組織レベルからみた身体組成、特に骨格筋および肝臓・腎臓の量的特徴を一般成人との比較から明らかにした。その結果、大学相撲選手は骨格筋量だけでなく、肝臓・腎臓重量も一般成人より大きいという特徴が観察された。この結果は、継続的なレジスタンス・トレーニングや高強度トレーニングを行うと、骨格筋量だけでなく、臓器重量も同時に増加するという新たな可能性を提示した。さらに、この研究成果を応用し、古くからの研究テーマである安静時のエネルギー代謝とスポーツ活動との関連性について、特に大型スポーツ選手の安静時代謝量が高い値を示す原因解明に取り組んだ。
第41回 2006年7月12日
演題1
長時間運動時の体温調節と全身循環を改善するスポーツウエア
演者
鷹股亮先生(奈良女子大学生活環境学部助教授)
内容
立位運動を特に暑熱環境下で長時間行うと、一定負荷で運動を行っていても体温上昇に伴い心拍数が徐々に上昇する。これは、cardiovascular drift として知られているが、一定運動を行っていても長時間運動時には時間とともに相対的運動強度が高くなることになる。また、立位での運動では一定以上の体温になると、体温上昇に対する体温調節反応の増加が抑制される。即ち、体温調節反応のレベルオフが起こる。体温調節反応の抑制や心拍数の増加の少なくとも一部には、中心血液量の減少が関与していると考えられている。そこで、我々はスポーツウエアを用いて静脈還流量を維持して中心血液量の減少を抑制することにより、長時間運動時の体温調節と全身循環を改善することが出来るのではないかと考え、実験を行った。スポーツウエアを用いることにより、体温調節反応や全身循環を改善することが出来る可能性が示されたので紹介する。
演題2
基礎代謝と身体組成の関連および加齢・閉経の影響
演者
薄井澄誉子先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
近年、中高年者の生活習慣に関連する疾病が問題となっている。それらを予防し、健康で充実した生活を営むためには、年齢や生活活動強度に基づく適切なエネルギーを摂取し、消費するというサイクルの中での生活が望ましい。それを実現するためには、その基準となる基礎代謝量(basal metabolic rate; BMR)についてよく知ることが重要である。本発表では、健康な中高年女性を対象としたBMRと身体組成および加齢・閉経との関連を報告する。
第40回 2006年6月23日 兼講演会
演題
3次元動作解析におけるトルク非直交分解法(3次元投球動作への適用)
演者
平島雅也氏(東京大学大学院 情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻)
内容
スポーツバイオメカニクスでは、観測した運動データから関節トルクを算出するという逆動力学計算が広く用いられてきた。従来の3次元動作解析では、トルクベクトルを直交3成分に分解する方法が一般的である。しかし、本研究では、トルクと3次元関節回転の因果関係を正確に把握するためには、トルクベクトルを非直交3成分に分解する必要があることを示す。また、関節トルクだけではなく、セグメント間の相互作用によって生じる相互作用トルクの算出法についても述べる。最後に、この方法を3次元投球動作に適用し、スポーツスキルの評価や指導への有効性についても考察する。
第39回 2006年6月28日(水)
演題1
日常生活動作を利用したトレーニング動作の有用性
演者
高井洋平氏(早稲田大学スポーツ科学研究科 博士後期過程)
内容
筋量及び筋力を増加させるためには日常生活水準以上の筋活動水準が必要である。そこで、体重のみを負荷とする日常生活動作を利用したトレーニング動作が、トレーニングとして有用であるか否かについて、筋電図を用いて検討した。
演題2
学問におけるスポーツ科学の位置づけ
演者
高井昌吏先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
「社会学」という文科系の一分野(「村社会」と言いかえてもよい)に属していたわたくしは、早稲田大学スポーツ科学部助手に着任して以来、いわゆる理系の学問と接するようになった。「文理融合」という声が高まっているにも関わらず、わたくしは不勉強がたたり、理系の方の発表がほとんど理解できないこともしばしばである。テクニカルタームを知らない、あたまの回転が遅いなど、理由は多々あるであろう。しかしながら、自身の学問と皆様方(理系)の学問のあいだに、ある種の問題意識を共有したいという欲望にかられていることも事実である。本発表では、「社会学村」という立場からみたスポーツ科学について言及し、皆様方にご指導、ご鞭撻をいただければと考えている。
第38回 2006年5月31日(水)
演題1
Surgical treatment of gait disturbances in neuromuscular diseases based on gait analysis
演者
Dr. Hyun Woo Kim(Department of Orthopaedic Surgery, Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul, KOREA)
第37回 2006年5月18日(木)
演題1
睡眠中の眼球運動と夢見の精神生理学的検討
演者
小川景子先生(スポーツ科学学術院)
内容
私達が寝ている間に見る”夢”について、夢を見ているときに脳はどのような活動をしているのか、脳波を使って検討し、夢の発生メカニズムを解明したいと考えています。具体的には、夢をよく見る時期であ るレム睡眠期に焦点を当てて、レム睡眠中に生じる急速眼球運動とそれに関連する脳電位活動を検討した結果をご紹介します。
演題2
運動トレーニングで骨密度は変化するか?
演者
劉莉荊先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
pQCT法(末梢骨定量的CT法)を用いた研究では、長期間の運動トレーニングによる骨強度の増大は骨の体積骨密度の増大ではなく、骨形態の変化によるものであ ると考えられる。今回の発表は、現在までの様々な実験結果と先行研究を纏めて、総説として紹介する。
第36回 2006年4月26日(水)
演題1
骨格筋ミオシン重鎖成分へのHeat Shock Protein 72の関与
演者
緒方知徳先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
生体へのストレスに対する防御応答の代表的なものとしてHeat Shock Protein(HSP)72の発現増加が挙げられる。HSP72はストレスに対する保護機能のみならず生体タンパク質の形成を補助する分子シャペロンと呼ばれる機能も有していることが知られている。本研究では、運動や発育などによって起こる身体の適応現象(筋肥大や筋線維タイプの変化)へのHSP72の関与を検討した。
演題2
跳躍能力の優劣はいつ何によって決まるのか?
演者
田内健二先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
本研究は、運動課題の異なる2種類の跳躍運動、すなわち垂直跳とリバウンドジャンプの遂行能力をもとにして個人の跳躍能力の特性を評価し、その特性に影響を及ぼす要因を明らかにすることを目的としている。本発表では、これまでの成果および途中経過を発表する。
第35回 2006年4月5日(水)
演題
Effects of practice and time pressure in dual tasks studied with ERPs
演者
Werner Sommer教授(ドイツ・フンボルト大学)
内容
In many situations we have to simultaneously process and respond to multiple pieces of information. The problems arising in multitasking situations have been experimentally studied in the overlapping task paradigm, usually employing behavioral measures like reaction times. A more detailed view of the mechanisms at work in such situations is provided by recordings of electrical brain potentials, such as the lateralized readiness potential. Recently we have conducted experiments on the mechanisms of two possible strategies of overcoming dual task costs, time pressure and practice. As it turns out both strategies are similarly effective on a behavioral level, but the underlying mechanisms are to a large part quite different.
第34回 2006年3月13日(月)
演題
ヒトの伸張性筋活動に伴う筋損傷と遅発性筋痛
演者
野坂和則先生
内容
Edith Cowan University, School of Exercise, Biomedical and Health Sciences(Australia)
収縮している筋が伸張される動作を伴う運動(伸張性運動)によって、筋の微細構造の変化が生じ、筋機能の低下、筋の腫脹、遅発性筋痛(DOMS)、筋タンパク質の血液中への逸脱や、核磁気共鳴や超音波画像の変化も生じる。本発表では、いくつかの伸張性運動モデルに伴うこれらの変化について示し、伸張性運動に伴う筋損傷と適応のメカニズムを考察し、筋損傷やDOMSの予防、対処法について最近の知見を紹介したい。
第33回 2006年2月15日 2005年度修士論文発表コンテスト
開会の挨拶
内藤健二(修士論文発表コンテスト実行委員)
セッション1
座長
時澤健(村岡研究室)
15:03 野球のバッティングの再現性
大室康平(彼末研究室)
15:16 ジャパンラグビートップリーグ観戦者の観戦動機に関する研究
中植弘満(原田研究室)
15:29 安静時と等尺性筋活動時における肘関節屈筋群の筋形状と肘関節屈曲トルクの関係
赤木亮太(福永研究室)
15:42 発揮筋力の視覚的フィードバックが最大筋力発揮と前頭前野ヘモダイナミクスに及ぼす影響
福田誠(内田研究室)
15:55 ヒトのヒラメ筋におけるホフマン反射の運動後増強について
植松梓(鈴木研究室)
16:08 高強度・短時間運動トレーニングによる骨格筋GLUT-4の発現の機序に関する研究
藤本恵理(樋口研究室)
16:21 身体的特徴及び投球動作から見た成長期の野球選手における肘障害の発生要因
秋山裕介 (鳥居研究室)
セッション2
座長
武田典子(中村研究室)
16:43 ストレッチングと等尺性筋活動が筋および腱の伸長性に及ぼす影響
加藤えみか(川上研究室)
16:56 野球の投球動作における上肢帯の機能と役割
小林裕央(鈴木研究室)
17:09 小学校体育における社会性の育成
眞榮里耕太(寒川研究室)
17:22 野球選手における筋形態および筋機能からみた投球速度の決定要因
勝亦陽一(福永研究室)
17:35 初心者の身体表現における認識過程の変化
山下麻里子(野嶋研究室)
17:48 足部形態の発育・アーチ構造の発達と関連因子の検討
荒木智子(鳥居研究室)
18:15 表彰式&懇親会
一位
福田誠
二位
加藤えみか
三位
大室康平
特別賞
荒木智子
第32回 2006年1月31日(水)
演題
「各種スポーツ(ボート・カヌー・陸上競技・柔道・相撲・ショートトラック等)及び学校体育の指導へのバイオメカニクス研究の導入・貢献」
演者
植屋清見教授(山梨大学教育人間科学部)
- Tags
- 研究活動