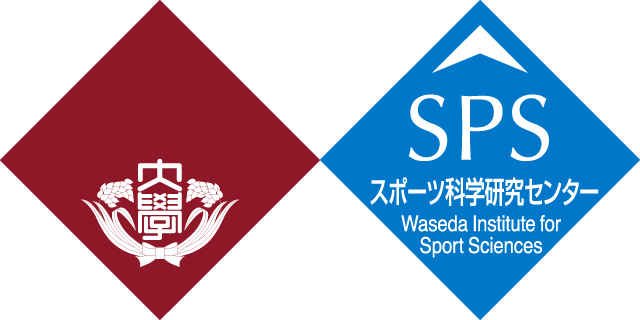- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2009年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2009年度)
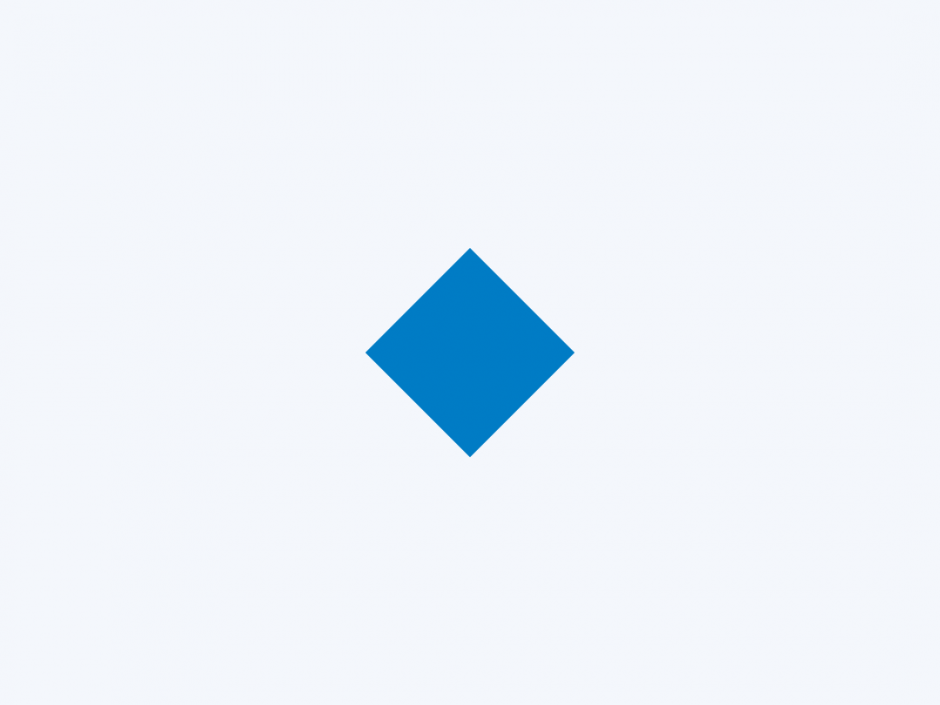
- Posted
- Mon, 01 Mar 2010
第76回 2010年3月3日(水) 特別講演
(*本講演は諸事情により、中止となりました。参加を予定されていた方々には、心よりお詫び申し上げます。)
演題
Do we sit too much and does it matter? Sedentary behaviour and health
演者
Dr. Biddle
(Professor of Exercise & Sport Psychology President,
International Society for Behavioral Nutrition & Physical ActivitySchool of Sport, Exercise & Health Sciences, Loughborough University, UK)
内容
There has been a great of attention focused on physical activity patterns and often it is assumed that technological change has been at least partially responsible for less than adequate levels of physical activity in the population. Such factors mainly include TV viewing and the use of computers – often referred to as screen time. This presentation will focus on screen time and other sedentary behaviours as an important and potentially problematic behaviour from the view point of health.
Drawing on our own primary and review-level research evidence, I will address three key questions in respect of young people:
- Is sedentary behaviour bad for your health?
- When do the key sedentary behaviours take place and does this matter?
- Can we reduce sedentary behaviour?
We are entering a new era of research on sedentary behaviour. New technologies are juxtaposed
with physical activity and the picture is a complex one. However, there is evidence that many people are attracted tosedentary technology and that this may have adverse health consequences.
We need critical thinking and research on how physical activity and sedentary behaviour are interrelated and how we might reduce excessive screen time. This is a challenge for all.
第75回 2010年2月12日 2009年度 修士論文発表コンテスト
セッション1
座長
庄子博人(中村好男研究室)
タイムキーパー
小西真幸(坂本研究室)
12:50 現代日本のスポーツ空間における女性像の社会的認識変遷の一考察 ~Sports Graphic Numberを例に~
枝元一将(トンプソン研究室)
13:05 施設入居高齢者の心理・社会的機能改善プログラムの開発
東海林郁子(荒尾研究室)
13:20 日常生活における身体活動量の違いが高齢者の認知機能と運動出力に及ぼす影響
ベ ソンリュウ(山崎研究室)
13:35 陸上競技のスプリントトレーニングが野球における走パフォーマンスに及ぼす影響
岩野祐太(礒研究室)
13:50 大学ラグビー選手における4ヶ月のトレーニングがホルモン分泌応答に及ぼす影響
山田優香 (坂本研究室)
14:05 子どもの靴の適合性と足趾の変形との関連性
伊藤朋香(鳥居研究室)
14:20 運動技能学習における昼寝の効果
守田優子(内田研究室)
14:35 事前の筋活動の時間および強度がその後の単収縮トルクおよび最大随意短縮性トルクに与える影響
福谷充輝(矢内研究室)
セッション2
座長
元安陽一(矢内研究室)
タイムキーパー
塩田耕平(内田研究室)
15:00 野球のボール回転がバッティングパフォーマンスに及ぼす影響
諸星潤(彼末研究室)
15:15 廃用性萎縮に対する低周波鍼通電療法の影響について
恩田明子(福林研究室)
15:30 日本人トップアスリートの身体運動能力を規定するミトコンドリアDNA多型の探索
三上恵里(樋口研究室)
15:45 高強度持久性運動が皮膚の感染防御機能に及ぼす影響
枝 伸彦(赤間研究室)
16:00 プロスポーツチームの地域における経済的価値評価
石坂 圭三(間野研究室)
16:15 カルチャーセンターにおけるスポーツ講座の受講者に関する研究
吉井 弘樹(作野研究室)
16:30 スポーツ消費者の求めるベネフィットに関する研究−日本のプロ野球スタジアムの観戦環境に着目して−
酒井俊和(原田研究室)
審査員(博士課程大学院生):
浅香明子、橘内 基純、水口暢章、野倉圭輔、塩田耕平、小西真幸、庄子博人、高泉佳苗
総合一位(最優秀賞)
三上恵里(樋口研究室)
〈文系領域)
一位:石坂圭三(間野研究室)
二位:酒井俊和 (原田研究室)
〈理系領域)
一位:三上恵里(樋口研究室)
二位:枝 伸彦(赤間研究室)
第74回 2010年1月26日(火)
演題
分泌型免疫グロブリンAと身体活動
演者
清水 和弘先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
唾液分泌型免疫グロブリンA(secretory immunoglobulin A:SIgA)は,病原体の口腔粘膜下への侵入を防ぐ役割を持つ.またSIgAは,運動によって変動することからストレスマーカーとしても知られている. 高強度・長時間の一過性運動を行うと唾液SIgA分泌量が低下する.一方,長期間の高強度トレーニングを行うと安静時のSIgA分泌量が低下した状態が続く.また,唾液SIgA分泌量は加齢とともに低下することが知られている.しかし, 適度な身体活動量を維持している高齢者は,身体活動量が少ない高齢者と比較して唾液SIgA分泌量が高いことが示されている.さらに,運動習慣の無い高齢者が 定期的な運動トレーニングを行うことによって,安静時の唾液SIgA分泌量が増加することも示されている. 運動による唾液SIgA分泌の応答のメカニズムについて,詳細は明らかになっていないが,一過性高強度運動によって唾液腺中の多量体免疫グロブリン受容体の 発現が減少することが示されており,これが高強度運動後のSIgA分泌の低下の一因として考えられている. 唾液は非侵襲的に簡便にサンプリングが可能であり,スポーツ現場においては,唾液SIgAは免疫機能の評価やストレス測定のための検体として有用であると考えられる.
第73回 2009年12月8日(火)
演題1
Exercise and Hormesis
演者
Dr. Zsolt RADAK, Ph.D(Semmelweis University, Budapest, Hungary)
内容
Physical inactivity leads to increased incidence of a variety of diseases and it can be regarded as one of the end points of the exercise-associated hormesis curve. On the other hand, regular exercise, with moderate intensity and duration, has a wide range of beneficial effects on the body including the facts that it improves cardio-vascular function, partly by a nitric oxide mediated adaptation, and may reduce the incidence of Alzheimer’s disease by enhanced concentration of neurotrophins and by the modulation of redox homeostasis. In addition, it appears that oxidation of guanine in DNA, RNA and telomere can also described by hormetic dose response. Exercise-induced repair of DNA damage varies in nucleus and mitochondria, which could have special role in oxidative stress related adaptation. Single bouts of exercise increase, and regular exercise decreases the oxidative challenge to the body, whereas excessive exercise and overtraining lead to damaging oxidative stress and thus are an indication of the other end point of the hormetic response. Based upon the genetic setup, regular moderate physical exercise/activity provides systemic beneficial effects, including improved physiological function, decreased incidence of disease and a higher quality of life.
第72回 2009年11月24日(火)
演題1
ヒト脳機能計測機器を用いた随意運動抑制過程に関する研究
演者
中田 大貴先生(早稲田大学スポーツ科学学術院GCOE次席研究員)
内容
運動を遂行する際、我々は、外界からもたらされる様々な刺激を知覚し、そして得られた 情報を瞬時かつ正確に判断した上で、最終的な実行の意志決定を行っている。このような一 連の情報処理過程の結果として現れる動作は、日常生活の中で意識的に、そして時に無意識 のうちに当たり前のこととして遂行されている。また反対に、運動を発現しない、言い換え れば「運動を抑制する」という決定が脳内でなされることもある。つまり我々の日常生活 は、ほぼ運動遂行と運動抑制を巧みにコントロールすることによって成り立っていると言っ て良い。
本研究会では、ヒトの運動遂行過程と運動抑制過程について、それぞれの情報処理が、「い つ・どこで・どのように」脳内において働いているのか、そのメカニズムの一端を紹介す る。その際の実験手法として、電気生理学的手法である脳波(EEG)、脳磁図(MEG)、経頭蓋 的磁気刺激法(TMS)、表面筋電図(EMG)、脳機能イメージング手法である機能的磁気共鳴断 層画像法(fMRI)を、実験の内容に応じて組み合わせる学際的研究を紹介する。
演題2
最大酸素摂取量のNon-exercise推定式の開発-客観的に測定された身体活動指標を用いて-
演者
:曹 振波先生(早稲田大学スポーツ科学学術院GCOE次席研究員)
内容
最大酸素摂取量(VO2max)は健康に関連する体力の重要な指標の一つである。一方、 VO2maxの実測は困難が伴うことより、健康運動指導の現場で、より簡便にVO2maxを推 定し、それを利用できるように、VO2maxのNon-exercise推定式が提案されている。しか し、従来の推定式では、身体活動量の評価に質問紙を採用していることによる個人の主観 的バイアスが大きいため、これらの推定式を別の被験者に応用すると、大きな推定誤差が 生じることが確認されている。 近年、歩数計や加速度計などによる身体活動量の定量法は、客観的手法として有効性が確 認されている。しかし、客観的に測定された身体活動指標である歩数や身体活動強度など を用いてVO2maxを推定する研究はない。そこで、本発表では、VO2maxと健康関連因子 である身体組成、歩数及び身体活動強度との関連性を検討した上、こちらの変数を用い て、VO2maxのNon-exercise推定式の開発と、その妥当性について検討した研究結果を紹介する。
第71回 2009年10月20日(火)
演題1
身体サイズおよび筋力との関連からみた投球スピードの発達
演者
勝亦陽一 先生(スポーツ科学学術院助手)
内容
【緒言】本研究は、発育期における投球スピードの発達について、定期的に投球を行う野 球競技選手および競技として投球を定期的に行っていない男子を対象に、身体サイズおよ び筋力との関連から検討した。【方法】対象は7-24歳の野球選手および野球競技未経験者 とした。測定項目は投球スピード、身長、体重、四肢および体幹部の筋厚(超音波法)、 筋力(肘および膝関節屈・伸)を計測した。【結論】野球競技経験の有無に関わらず、発 育期における投球スピードの発達には、身長の増加および第二次性徴に伴う四肢長あたり の筋厚の増加が影響していることが示された。当日は上記の内容に加え、これまでの取り 組みや最新のデータも紹介する。
演題2
脂質異常症の予防・改善に向けた運動の勧め:分割運動による食後中性脂肪の上昇抑制効果
演者
宮下政司先生(早稲田大学スポーツ科学学術院GCOE次席研究員)
内容
食後の中性脂肪の著しい上昇およびその日常化は, 動脈硬化を促進させ, 心血管疾患の独立した危険因子の一つとされている.多くのヒトの日常生活では, 一日の大部分が食後の 状態になっていることから, 食後中性脂肪の上昇を抑制することは, 心血管疾患のリスクを軽減する上で重要なことである.先行研究において, 1回あたりの運動時間を10分以上とし た1日通し計30分以上の分割運動および分割運動と同等の運動量でおこなった一過性運動は, 食後の中性脂肪の上昇を同程度に抑制させるという報告がある.我々は, 分割運動によ る食後中性脂肪の上昇抑制効果を再検証するために, 一過性運動との比較を踏まえ, 次の二点に着眼し研究をおこってきた;1)活動的である毎日30分以上運動する人でさえ1回の運 動時間10分を超えて運動していない点, 2)もし総運動量が健康づくり効果に影響しており,十分なエネルギーを消費する運動であれば1回の運動時間は問題ではないと仮定できる 点.本セミナーでは, 1回あたりの運動時間を10分以下とした一日通し計30分の分割運動による食後の中性脂肪の上昇抑制効果に関して, 最近の我々の知見を紹介したい.
第70回 2009年9月15日(火)
演題1
推奨身体活動促進のための効果的な支援方策の提案
演者
柴田愛先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
近年、身体活動量の減少は、生活習慣病の危険因子として注目されており、全世界的な公衆衛生上の問題となっている。我が国では、国民の身体活動・運動量の増加を目指して、2006年度に厚生労働省により「健康づくりのための運動基準2006」(EPAR2006)が策定さ れた。身体的側面に及ぼす推奨身体活動量(推奨量:23メッツ・時/週)の影響については科学的に検証されている一方で、精神的側面に及ぼす影響ついては明らかにされていない。身体活動と健康アウトカムとの関連性を実証することは、身体活動促進の科学的な根拠となるために、極めて重要な研究局面であるといえよう。また、実施率を把握することは、身体活動促進のための効果的な支援方策の開発・普及など公衆衛生的活動が必要であ るかどうかを確認するためにも重要である。しかしながら、実際に推奨量を満たしている国民の割合を調査した研究はない。さらに、推奨量の実施に影響を及ぼす人口統計学的、心理的、社会的、環境的な要因についての探索は、不活発な人々の効率的な特定や、その要因の修正に焦点を絞った効果的な介入方法の開発に不可欠な情報である。しかしながら、我が国において身体活動の関連要因を解明するための研究はほとんど行われていないのが現状である。したがって、本発表では、以上の3点について検討した結果をもとに、推奨量を満たす成人を増加させるための効果的な支援方策について提案する。
演題2
ヒト活動時の血圧調節-末梢性反射 調節の複合作用-
演者
西保岳先生(筑波大学人間総合科学研究科・准教授)
内容
高強度運動には、酸素を活動部位に運搬するために循環調節が重要となる。本セミナーでは、循環調節の中で、特に、末梢性反射調節(動脈圧受容器反射、筋代 謝受容器反射、 心肺圧受容器反射)の複合作用に焦点をあてて、血圧調節メカニズムに関して、我々の研究結果を中心に説明する。 動脈圧受容器反射とは、血圧の変動を入力刺激として、中枢を介して、出力反応として交感・副交感神経活動を調節することによって、血圧変動を調節する、 いわばフィード バック調節である。この調節に関して、入力(血圧変化)に対する出力(心拍、血圧、交感神経活動)の関係(刺激ー反応曲線)から研究が主に なされている。しかし、1)反応 の動的特性(刺激に対する時間的応答)、2)反応の確率的応答(一定の刺激回数に対する反応の割合)に着目した研究はほと んど無い。さらに、実際の運動時においては、上記 末梢反射は複合的に作用していると考えられるが、単独作用の研究はあるが、複合作用に関する研究は少な い。高強度運動時には、筋代謝受容器や心肺圧受容器反射が重要な役割 を演ずると考えられるため、それらの動脈圧受容器反射への影響を、上記1)、2)から検討した。実験結果を総合して、筋代謝受容器反射や心肺圧受容器反射活動時には、動脈 圧受容器反射の動的特性や刺激に対する確率的応答は変化し、この変化 は、ヒト活動時の血圧調節に重要な役割を果たすことが示唆された。
第69回 2009年8月21日(金)
演題
ハイレベル・パフォーマンスを支えるスポーツ心理学―プロ・スポーツ,芸術,医療におけるパフォーマンス強化―
演者
Dr. Leonard D. Zaichkowsky, Ph.D. (Boston University)
内容
Dr. Zaichkowskyは,現在,ボストン大学において新しく開始された学際的プログラム「教育学研究科および医学部医科学研究科のジョイントプログラム」の教授であり,さらに医学部におけるメンタルヘルス・行動医学部門大学院スポーツ・運動心理学プログラムのヘッドである.彼は,長年,応用スポーツ心理学の領域で多くの研究を行ってきたが,とりわけ最近では,脳・神経科学の視点でパフォーマンス強化に果たす実践研究を行っている.その適用は,スポーツ分野だけにとどまらず,芸術や外科手術など,優れたパフォーマンスが必要な様々な分野にもおよんでいる.この研究では,例えば,対象者が感情を自己制御できるように新しいタイプのバイオフィードバック技術を駆使し,その研究対象となる類い希なるパフォーマーはレアルマドリードのサッカー選手(http://www.soccer-new-england.com/Real-Madrid-BU-MIT-Join-Forces.html)をはじめとして,デューク大学医学部における有名外科手術者にも及んでいる.もう一つの研究は,脳イメージ研究である.彼は,カナダ・ナショナルチームに帯同する心理学者と共同で,水泳選手がパフォーマンスに成功,または失敗するイメージを想起させ,その際の脳活動をfMRI スキャナーを用いて測定・分析し,水泳選手のパフォーマンス向上に役立てている.講演会では,Dr. Zaichkowskyがコーチ,体育教師およびスポーツ選手に影響をもたらす神経・脳科学研究における最新の知見をわかりやすく紹介してくれることを期待している.
第68回 2009年7月24日(金)
演題
Can we reconcile the musculoskeletal mechanics of human plantarflexion and dorsiflexion from a macro to a micro-perspective?
演者
V. Reggie Edgerton, Ph.D. (Department of Physiological Science, Neurobiology, Brain Research Institute,University of California, Los Angeles, USA)
内容
Although extensive detail is known about the mechanics of single molecules of actin and myosin in a dish and of sarcomeres of single fibers in situ as well as a reasonably detailed description of the mechanics of the ankle joint, it remains unclear how the actomyosin dynamics within and across many sarcomeres within and among muscle fibers generates the specific joint displacement and velocities that occur routinely in vivo. With our present level of understanding of all of the components of the musculoskeletal that generates and transfers forces and displacements, the mechanical properties of these routine movements at the macro level do not match the dynamics in the micro-level. Over the last decade several laboratories have begun to develop imaging technologies that have revealed a new level of understanding of the strain related to events that occur within and among musculotendinous units in small and large mammals, including humans. This presentation will focus on new MRI technologies that have allowed us to image the dynamics of different components of the musculotendinous units that are largely responsible for plantarflexion of the human ankle. As best can be done at the present data available, I will attempt to determine the degree to which the micro-and macro dynamics of plantarflexion in the human can be reconciled.
第67回 2009年6月16日(火)
演題1
西島壮先生(首都大学東京)
演者
運動による海馬神経活動の活性化とその生理学的意義
内容
生活習慣は脳機能に様々な影響を及ぼし、積極的な学習活動や余暇活動、そして運動などにより脳活動レベルの高い生活を営むことは、脳機能の維持・向上に有益である。しかしながら、なぜ神経活動を高めることが脳機能の維持・向上に貢献するのか、その疑問に答える神経科学的メカニズムは未だ明確でない。そこで、本セミナーでは、1)運動時に脳神経活動が活性化するか、2)なぜ神経活動を高めることが脳機能の維持・向上に有益であるのか、について、これまで得られた知見を紹介する。前者では、特に記憶・学習を担う脳部位である海馬に焦点を当てる。この海馬が走運動時に活性化するか否かを、レーザードップラー血流計を用いた海馬局所血流量のリアルタイム測定から検討した。後者では、主に肝臓から分泌されるインスリン様成長因子(IGF-I)に着目する。血中IGF-Iは、様々な神経保護作用を発現するホ ルモンであり、これまでに運動による有益な作用(神経損傷の軽減など)を仲介し、また脳実質内からアミロイドβを除去しアルツハイマー病予防に貢献することなどが報告されている。血中IGF-Iが血液脳関門および血液脳脊髄液関門を介して脳実質内にも取り込まれることが報告されているものの、どのようにIGF-Iの脳内移行が調節されているかは全く明らかになっていない。そこで我々は、「神経活動が血中IGF-Iの脳内移行を調節する」と仮説を立て、現在はその分子機構の解明を進めている。
演題2
伸張性筋収縮による筋損傷および遅発性筋痛が運動制御機構に与える影響
演者
遠藤隆志先生(国立障害者リハビリテーションセンター研究所)
内容
収縮している筋が伸張される伸張性筋収縮を含む激しい運動後には、筋の微細構造は損傷し、最大筋力や関節可動域が低下すること、またこの微細な損傷が引き金となって、その運動の約24時間後には遅発性筋痛が発症することは広く知られている。このような筋損傷や遅発性筋痛が生じている時に、中枢における運動制御機構がどのような影響を受けているのかについてはこれまで不明であったが、近年、我々のグループを含めて、この伸張性筋収縮後の筋損傷および遅発性筋痛時における運動制御動態に少しずつ明らかになっている。本発表では、皮質運動野を刺激する経頭蓋磁気刺激、脳波および筋電図を用いて、皮質脊髄路の興奮性および抑制性、皮質運動野と脊髄運動ニューロンプールの同調的活動および体性感覚系の変化などの観点から伸張性筋収縮による筋損傷および遅発性筋痛が運動制御機構に与える影響について検討を加えた我々の研究結果を紹介する。
第66回 2009年5月19日(火)
演題1
特定健診・保健指導の認知度の変化に影響を及ぼすメディアの検討
演者
李恩兒先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
【目的】
特定健診・保健指導の認知度の経時変化と、認知度の変化に影響を及ぼすメディアの参考状況を明らかにし、健康情報を伝達するための有効なプロ モーション方策について検討した。
【方法】
40-59歳の社会調査モニターを対象として、2007年11月 (T1)および2008年12月(T2) にWeb調査を実施し、525名を解析対象とした。なお、認知度に影響を及ぼしたメディ アに関しては、2007年度の非認知群を対象(274名)に分析を行った。統計解析は、経時 変化に関しては、Wilcoxonの符号化付き順位検定、人口統計学的変数およびメディア参考有無に関しては、ロジスティック回帰分析、参考メディアの平均数の比較は、t検定を行った。
【結果】
T2(77.3%)の特定健診・保健指導の認知度は、T1(47.8%)と比較し、有意に高かった(z=-10.7,p<.001)。T1で非認知群(274名)において、人口統計学変数としては、「女性」(OR=2.92, 95%CI=1.05-8.14)、メディアの参考有無については、「病院・薬局のパンフレット」(OR=2.44, 95%CI=1.14-5.24)を参考にしていることが、T2の認知を有意に予測していた。なお、参考メディアの平均数は、非認知群は4.1±3.4個、認知群は6.1±3.1個であり、認知群の方が参考にしているメディアの数が有意に多かった(t(272)=4.824,p<.001)。
【結論】
今後、健康情報を伝達するためのメディアの有効なプロモーション方法について考える必要がある。
演題2
わが国の女子体育教師と教材としてのダンスをめぐるポリティクス
演者
稲葉佳奈子先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
スポーツ・フェミニズムの文脈では、スポーツとは、男性を基準に――つまり、男性の平均的な身体的特性が有利にはたらくようなかたちで――制度化され、男性を中心に組織化されてきた文化であり、スポーツ実践を通じたマスキュリニティの獲得を称揚する文化でもある。また、学校体育は、男性中心のスポーツ文化が教育の領域に移入されたものとみなされる。そうした共通認識もとで、これまで多くの場合、ジェンダーの視点をもった「啓蒙」や「教育」によるスポーツ文化の変革が主張されてきた。 先行する上記の議論に対する批判的検討をふまえ、本報告では、わが国の「体育教師社会」における女子体育教師のアイデンティティ・ポリティクスについて論じる。なかでもとくに、体育教材としてのダンスをめぐって、「体育的価 値」という側面からどのような言説実践が展開されたのかという点に注目し、その政治性について考察す る。この議論は、「スポーツや体育の男性中心主義を変革する」という意味でのスポーツ・フェミニズムの政治的困難あるいは不可能性の提示であると同時に、スポーツや体育と性をめぐる議論のオルタナティヴを模索することにつながるものでもある。
第65回 2009年4月28日(火)
演題1
膝前十字靭帯損傷リスクファクターの検討
演者
永野康治先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
膝前十字靭帯(Anterior Cruciate Ligament; 以下ACL)損傷のリスクファクターとして運動時の動作に注目し、バイオメカニクス的手法を用いて検討することを目的とした。
【実験1; 片脚着地動作における膝関節運動の性差の検討】
片脚着地における膝関節運動および筋活動の解析を行い、その性差の検討を行った。その結果、女性において脛骨内旋が大きく、大腿四頭筋優位の筋活動を示し、ACL損傷リスクが高いと考えられた。
【実験2; 着地・切り返し動作におけるACL損傷リスクの検討】
ACL損傷好発動作である着地や切り返し動作の中から、片脚着地-切り返し、片脚着地、両脚着地における膝関節運動の比較を行った。その結果、片脚着地—切り返しでは片脚着地に比較し、脛骨内旋変位量、外転変位量が大きく、ACL損傷リスクが高いと考えらた。
【実験3; ターン動作における体幹位置と膝関節運動の関連および性差の検討】
ターン動作における体幹位置と膝関節運動の解析を行い、その関連を検討すること。また、その性差の検討を行った。その結果、膝関節運動のみならず動作中の体幹位置もACL損傷リスクファクターとして考えられた。
以上の研究からACL損傷リスクの高い動作が明らかになった。今後、リスクファクターに 対するACL損傷予防プログラムの効果検証の必要性が示唆された。
演題2
睡眠中の脳機能研究 ~レム睡眠中の夢を手がかりに~
演者
小川景子先生(早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
これまで発表者はレム睡眠中の夢を手がかりに睡眠中の脳機能研究を行ってきました。一晩の眠りではノンレム睡眠とレム睡眠が交互に繰り返されていますが、レム睡眠中でより鮮明でありありとした夢見体験が報告されます。またレム睡眠中には覚醒中の眼球運動(サッケード)と形態が類似した急速眼球運動が生じ、夢見体験との関連も指摘されています。そこで我々は急速眼球運動が生じる際の脳活動の様子を、時間分解能に優れ特定の事象に関連した一過性の脳活動を検討できる事象関連電位(ERP;event-related brain potential)を用いて検討しました。
検討の結果、急速眼球運動の開始前には記憶や情動に係る海馬傍回・扁桃体の賦活、急速眼球運動の開始に伴い運動イメージや運動実行、情報のバインディングに係る運動野・頭頂連合野の賦活、そして急速眼球運動の停留に合わせて視覚情報処理に係る後頭部視覚野の賦活が観察されました。レム睡眠の中でも急速眼球運動が出現する区間では出現しない区間に比べてより鮮明な夢見体験が報告されています。本研究結果より、急速眼球運動に伴って観察されたこれらの一過性の脳活動が鮮明な夢見体験の生成に関与する可能性が示唆できました。今後は、急速眼球運動との関連が観察された脳活動のうち特に海馬傍回・扁桃体、運動野を取り上げ、なぜ夢見過程で記憶再生や情動・運動の知覚過程が体験されるのか、日中の経験と睡眠中の脳活動を指標に検討して行きたいと考えています。
第64回 2009年2月27日(金)
演題
「Circulatory regulartion during exercise」
演者
Niels H. Secher. Professor (The Copenhagen Muscle Research Center University of Copenhagen (Denmark))
第63回 2009年2月10日 2008年度 修士論文発表コンテスト
セッション1
座長
中村真由美(彼末研)
タイムキーパー
岡部祐介(友添研)
13:05 クロスカントリースキーのV2スケーティング滑走動作における運動力学的分析
藤田善也(礒研究室)
13:20 独立リーグ観戦者の観戦満足を規定する要因に関する研究—BCリーグにおけるサービスクオリティに着目して—
岡野紘二(間野研究室)
13:35 膝前十字靱帯再建術後の半腱様筋腱の再生と膝関節屈曲機能
野村由実(福林研究室)
13:50 バリ舞踊における基本姿勢(チャンケット)の定着過程
國寶真美(寒川研究室)
14:05 急性睡眠遮断後の20分または2時間仮眠の自律神経系、運動耐容能、内分泌機能および精神状態に及ぼす影響
小西真幸(坂本研究室)
14:20 bjリーグの活動継続意欲に関する研究
磯谷美穂(木村研究室)
14:35 中高年男性における習慣的なローイング運動の健康維持・増進効果
浅香明子(樋口研究室)
14:50 高等学校における長距離歩行行事の意義と運営上の問題点およびその対処方法
木内虹平(中村好男研究室)
セッション2
座長
原田和弘(中村好男研)
タイムキーパー
東田一彦(樋口研)
15:15 Influence of touching an object on corticospinal excitability during motor imagery
水口暢章(彼末研究室)
15:30
九鬼まどか(土屋研究室)
15:45 エキナセア摂取がアスリートのコンディションに与える影響
荘雅筑(赤間研究室)
16:00 プロ野球観戦者の消費者行動に関する研究—スタジアム環境要因および滞留希望に注目して—
吉倉秀和(原田研究室)
16:15 両側性筋力低下に主働筋および関節角度の違いが及ぼす影響
福井俊太郎(矢内研究室)
16:30 回旋腱板筋ならびに三角筋の形態および機能的検討—一般人と大学生テニス選手の比較および成長に伴う変化について—
奥村幸治(鳥居研究室)
16:45 体育における授業評価の方法に関する研究
望月敦夫(友添研究室)
優勝
水口暢章(彼末研究室)
二位
小西真幸(坂本研究室)
望月敦夫 (友添研究室)
特別賞
浅香明子(樋口研究室)
第62回 2009年1月19日
演者
Charles H. Hillman, Ph.D.(Director of the Neurocognitive Kinesiology Laboratory University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
内容
It is well-established that the early and late phases of the human lifespan are characterized by inefficient cognitive functioning, with the extant literature indicating a curvilinear relationship. Specifically, children and older adults exhibit relative deficits in performance, when compared to young adults, across a variety of tasks involving cognition and action. These deficits are due to alterations in brain structure and function, and lead to performance decrements that are disproportionately larger for tasks that entail extensive cognitive control. The study of physical activity influences on cognitive function has grown in interest over recent decades due to growing public concerns for a decrease in health status. Research has indicated that increased physical activity participation is associated with improvements in both general and selective aspects of cognition with the strongest relationship observed for tasks requiring extensive cognitive control. Thus, understanding controllable lifestyle factors (e.g., physical activity behavior) that may promote the health and maintenance of specific brain regions is important to improving cognition or protecting against cognitive loss. The overall goal of this area of research is to determine factors that improve cognition, maximize health and well-being, and promote the effective functioning of individuals as they progress through the human lifespan.
- Tags
- 研究活動