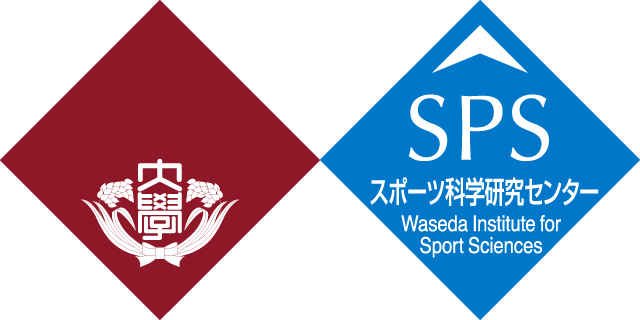- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2011年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2011年度)
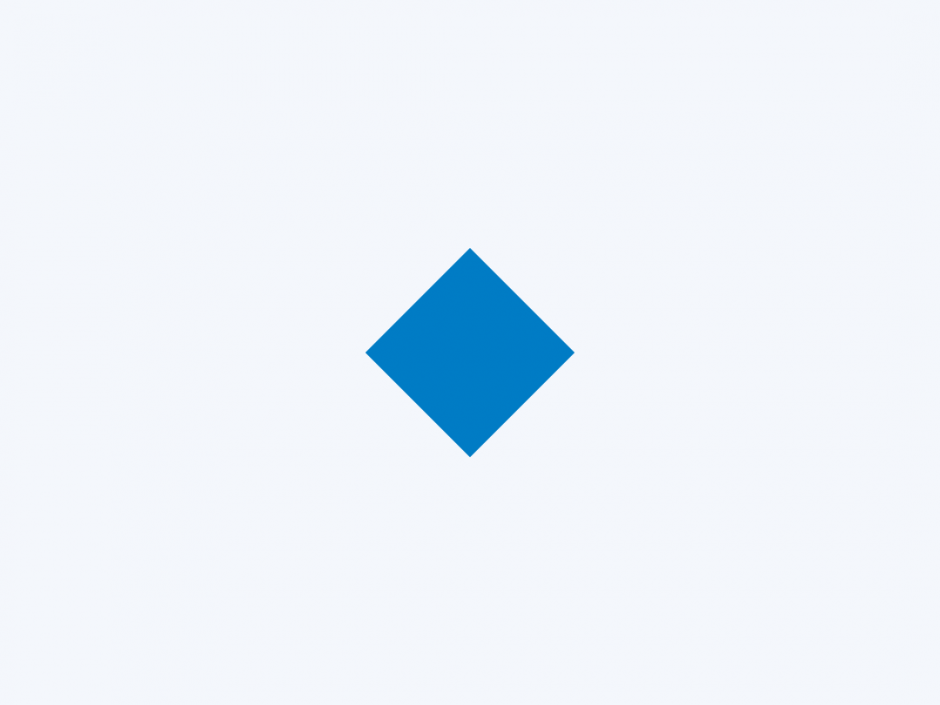
- Posted
- Mon, 01 Feb 2010
第100回2月2日(木 ) 15:00より
演題
A series of investigations related to softball and baseball performance
: 1.Implications for the importance of force application for pitching velocity and strength development to improve base running and change of direction ability
2.Monitoring neuromuscular and perceptual fatigue during a baseball tournament
演者
Dr. Sophia Nimphius (Edith Cowan University)
内容
Muscular strength, power, speed and change of direction performance are critical components of many athletic pursuits. Improvements in strength and power have been shown to have both significant and non- significant relationships with improvements in performance measures such as speed and change of direction performance and therefore many researchers continue to investigate this relationship. It is believed that the relationship between these variables is modified by the sport played by the athlete, gender,training history and training phase and should therefore be studied longitudinally in the athletes of interest. This research was specifically interested in high-level softball players and of additional interest in this population is pitching velocity. Small increases in the velocity of a pitched ball can decrease the reaction time afforded to a batter and has been shown to greatly modify the offensive capability of softball athletes Therefore, investigating if force production and pitch velocity have a relationship during the windmill pitching motion could provide insight into mechanisms for improving pitch velocity. Finally, the ability for teams (in both baseball and softball) to perform at their highest level repeatedly over a tournament is crucial for winning championships during most semi-professional and professional competitions. Therefore, identifying a method to easily monitor fatigue (especially neuromuscular fatigue) is important for ensuring optimal performance of each player. All of the aforementioned variables combine to be a large part of what contributes to athletic performance capabilities in both softball and baseball; therefore it was the purpose of a series of investigations to: 1.Investigate the cross-sectional relationship of strength, power, and performance variables in trained female athletes and determine if these relationships change over time (longitudinal). 2. Examine the relationship between percentage change in muscle architecture variables and percentage change in strength, speed and agility performance. 3. Determine the relationship between ground reaction forces and pitch velocity in elite fastpitch softball pitchers. 4. Determine if a relationship exists between a physiological measure of neuromuscular fatigue and perceptual fatigue. 5. Monitor and describe perceptual fatigue experienced by players during a national baseball tournament.
第99回 1月26日(木)16:30より
演題
加齢および運動習慣等による動脈コンプライアンスの変化と運動時の左室後負荷
演者
大槻毅先生(流通経済大学スポーツ健康科学部 准教授)
内容
大動脈および頸動脈等の中心動脈は伸展性に富んだ脈管であり、血 液輸送のための導管としてだけではなく、血圧および血流の拍動を緩 衝する役割を有する。この緩衝機能(コンプライアンス)が低下する と心臓左室後負荷(心ポンプ機能に対する抵抗)は増大し、左室にお ける後負荷と収縮力とのバランスが一定の範囲から逸脱すると、心筋 のエネルギー効率は低下する。動脈コンプライアンスは動脈の容量が 低下するほど、あるいは動脈の硬度(スティフネス)が増大するほど 低下する。動脈スティフネスは加齢により増大するが、有酸素性運動 は、加齢に伴う動脈スティフネスの増大を抑制したり、増大した動脈 スティフネスを低下させたりする。また、若年者においても、持久性 アスリートの動脈スティフネスは非トレーニング者のそれに比べて低 値である。 本研究会では、動脈コンプライアンないし動脈スティフネスの運動ト レーニングおよび加齢等による変化についての過去の研究を紹介す る。次いで、運動時の左室後負荷調整における動脈コンプライアンの 役割について、これらの変化と関連付けながら検討した研究成果を紹介したい。
第98回 2012年1月23日(月) 12:10より
演題
膝前十字靱帯損傷発生メカニズム解明への試み ̶反応課題を用いたステップ動作の解析
演者
佐保 泰明 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
スポーツ動作の受傷メカニズムの解明のため、受傷動作を想定した ジャンプ着地やターン動作などの三次元解析が行われている。我々は これまでにPoint Cluster法(以下PCT)を用いて膝関節運動解析を 行ってきた。これまで用いた動作は、助走やジャンプ着地からのカッ ト動作というような対象者にあらかじめ動作や運動方向を指定してい た。しかしながらスポーツのプレー中には必ずしも動作や運動方向が 決定はおらず、状況に応じて素早く動くことが要求されることが多 い。運動方向を事前に決定している場合(予測条件)と、動作直前に 運動方向を決定する場合(反応条件)で動作に違いがあると考えら れ、本研究ではサイドステップとクロスオーバーステップの2種類の動 作を用いて、予測および反応条件下で膝関節および体幹運動に違いが 生じるか検討した。その結果、反応条件下では体幹の側方傾斜が大き くなり、膝前十字靱帯損傷の受傷姿勢に近づくことが明らかとなっ た。 近年では、国際サッカー連盟が傷害予防プログラムを作成し、日本 サッカー協会もその普及に力を入れている。本研究会ではその傷害予 防プログラムの紹介をし、そのプログラムの介入効果として反応条件 下のステップ動作に反映されているか検討したので紹介する。
第97回 :2011年 12月21日(水) 17:00より
演題
演動器の血流評価という新たな可能性について
演者
奥野 祐次 先生(クリニカET血管内治療部/慶應義塾大学医学部総合医科学研究センター)
内容
生体には栄養や酸素を供給するために血管がくまなく分布されてい る。ただし厳密に観察すると、生体には血管が存在しない組織がいくつ かある。眼の角膜やレンズはその結晶構造を保つ必要性から、血管が まったく進入していない。また心臓の弁も同様に強靭な構造を保つべく 血管の侵入を許していない。これらの組織では、偶然血管が浸入してい ないのではなく、血管が入り込むことを防ごうとする物質を、自らが絶 えず産生していることが分かっている。そして運動器においては軟骨、 靭帯、腱が同様にして血管の侵入を防ぐ機構を備えた強靭組織である。 一方で生体は様々な局面で血管を増やす機構を働かせる。このとき、 軟骨や腱や靭帯においては、血管の侵入におけるせめぎ合いが生じるこ とになる。代表的には成長期、慢性炎症、組織の損傷と修復、そして加 齢が挙げられる。これらの状況では、正常状態では観察できない血流を 観察することが出来る。さらに重要なことにこれらの血管は通常の生理 的血管とは質的に異なることが知られている。 超音波診断装置が飛躍的な進歩を遂げたことで、運動器の分野におい てこれらの異常な血流をリアルタイムで可視化することが十分に可能に なっている。また超音波装置は血流の質的診断にも寄与する可能性を秘 めている。 今回はこれらの血流に関する最新の知見を踏まえたうえで、実際の症 例における超音波カラードップラ所見と血管撮影の所見を交えながら、 運動器における血流を観察することの意義と有用性を解説していきた い。
第96回 :2011年 12月19日(月) 12:10より
演題
Stabilization exerciseの体幹筋活動様式と介入効果
演者
大久保 雄 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
スポーツやリハビリテーション現場では,体幹安定性を高める体幹筋 トレーニングとして,Stabilization exerciseが盛んに行われている. 腰椎の安定性には,体幹深部筋(腹横筋や多裂筋)の機能が重要である ことが報告されており,Stabilization exerciseは体幹深部筋を含めた 神経筋協調性を向上させるためのエクササイズである.しかし,数多く あるStabilization exerciseの中で,どのようなエクササイズが体幹深 部筋の賦活化に有効であるかは明らかでない.そこで我々は,ワイヤ筋 電図を用いて様々なStabilization exercise時の体幹深部筋活動を測定 し,腹横筋や多裂筋を賦活化させるエクササイズを検討した.さらに, それらのStabilization exerciseと従来から行われている腹筋・背筋ト レーニングを行わせ,運動パフォーマンスに対する介入効果を比較検討 した.本研究会では,Stabilization exercise時の体幹筋活動様式を実 技を交えながら紹介し,その介入効果について報告する.
第95回 :2011年12月7日(水) 17:00より
演題1
筋力・筋パワーの測定技術に関する研究 ‐測定結果を競技力向上へ役立たせるためには?
演者
小林 雄志(国立スポーツ科学センター スポーツ科学研究部 契約研究員)
内容
筋力測定装置があれば等尺性や等速性筋力を計測することは比 較的容易にできる。しかしながら、それらの測定結果から競技パ フォーマンスを予測することは難しく、またレジスタンストレー ニングの効果を評価する指標としても適当でない場合が多い。そ れに比べ、等慣性(isoinertial)の負荷を用いた筋力・筋パワー 測定は、加・減速を伴う実際のトレーニングやスポーツ競技にお ける動作に比較的近く、競技パフォーマンスを予測したり継続的 なトレーニングによる個人内の変化を追跡していくのに適してい ると考えられている。こうした背景から、我々は等慣性負荷の最 大努力挙上を複数の重量で行うことより同定される負荷と仕事率 との関係(L-P プロット)を指標とした評価法の可能性について 検討を行ってきた。そこで本セミナーではこれらの評価法につい て、ベンチプレスやベンチスロー(挙上終了時にバーを投げ上げ るベンチプレス)を行った場合の測定結果を中心に紹介していき たい。また、これらの同定で用いられるワイヤレス加速度計やリ ニアポジショントランスデューサの信頼性、測定結果を解釈する うえで注意すべき点等についても紹介したい。
演題2
低酸素環境での運動時の筋エネルギー代謝動態
演者
本間 俊行(国立スポーツ科学センター チーム「ニッポン」マルチサポート事業 特任スタッフ)
内容
近年、高地(低酸素)トレーニングは、持久的な競技種目のみなら ず、比較的短時間で終了する競技種目においても実施されている。高 地トレーニングに対する生理的適応については、血液性状、運動時の 血中乳酸濃度、最大酸素摂取量などの全身的な生理指標による検討は 多く報告されているが、骨格筋の代謝的な適応については不明な点が 多い。そこで我々は、低酸素環境での運動時の骨格筋のエネルギー代 謝動態を明らかにし、効果的な高地トレーニングを実施するための基 礎資料を得ることを目的として検討を行った。 磁気共鳴装置内で膝伸展運動を行わせ、運動中の筋エネルギー代謝を リン31‐磁気共鳴分光法および近赤外分光法を用いて測定した。実験 は、同一プロトコールでの運動を、常酸素下と低酸素下とで行った。 その結果、最大下の同一絶対強度での運動時の筋酸素消費量、筋内ク レアチンリン酸(PCr)濃度、筋内pHは、常酸素下と比較して低酸素下 で低かった(P<0.05)。また、高強度運動の疲労困憊時において、 筋内PCrは両条件でほぼ枯渇し、条件間で差がなかったものの、筋内pH は常酸素下よりも低酸素下で低値を示した(P<0.05)。以上の結果 から、常酸素下と比較して、低酸素下での運動時には骨格筋レベルで は無酸素性エネルギー供給の動員が大きく、特に高強度の運動時には 解糖系によるエネルギー供給の差が顕著になることが示唆された。
第94回 :2011年11月21日(月) 12:10より
演題
競泳台上スタートのバイオメカニクス
演者
武田 剛 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
競泳競技のパフォーマンスはレース所要時間の大半を占める泳ぎの局 面(ストローク局面)によって決まる。一方でスタート・ターン局面の スタート台・壁からの蹴り出し時にこのストローク局面の泳速度より高 い速度が達成される。ストローク局面の泳速度はこのスタートとターン 局面の蹴り出し速度に依存していると考えることが出来るため、パ フォーマンスに占めるスタート局面の重要度は高い。近年、競泳競技に おける日本人選手の国際大会での活躍が顕著であるが、日本競泳界の課 題は短距離種目にあるとされる。この短距離種目のパフォーマンスとっ てスタート局面の重要度は大きい。したがって、競泳競技のスタート局 面のパフォーマンス向上を目指した研究の現場の指導者と選手からの ニーズは高い。このスタート局面の台上動作に関するバイオメカニクス 的研究を本研究会にて紹介する。これまでに複数の台上動作技術のキネ マティクス的特徴や、陸上競技で使用されるスタートティングブロック のようなバックプレートを導入した新型スタート台のパフォーマンスへ の影響を調査してきた。あわせて、現在進行中の新型スタート台に対応 したトラックスタートの四肢の反力測定システムを用いたトラックス タートのキネティクス分析の試みも紹介する。
第93回 :2011年10月28日(金) 16:30より
演題
効果的な脂肪燃焼の亢進を目指した基礎研究
演者
橋本健志 先生(立命館大学スポーツ健康科学部・スポーツ科学研究科 准教授)
内容
メタボリックシンドロームに代表される代謝疾患が深刻化している現代におい て、脂肪燃焼を効果的に実行できる方法の確立は重要な課題である。脂肪燃 焼を効率よくするためには、脂肪分解刺激(e.g. 運動によるアドレナリン)に対 する脂肪細胞の反応性を高めること、そして骨格筋・心筋が脂肪細胞由来の 脂肪酸を活発に燃焼することが肝要であると考えられる。これまで、脂肪燃焼 の場である筋細胞のミトコンドリアの機能については、その亢進に対する分子 機序が運動生化学分野において精力的に研究されてきている。一方、脂肪動 員の初発段階であるにもかかわらず、脂肪細胞での脂肪分解制御機構につ いては未解明な部分が多い。本セミナーでは、ここ数年演者が取り組んでき た「脂肪細胞での脂肪分解制御機構」と「脂肪分解の亢進が期待できる生理 的ストレス」について紹介したい。
第92回 :2011年9月22日(木) 16:00より
演題
Application of dynamic postural control during locomotion and sports
演者
Heng-Ju Lee先生(National Taiwan Normal University/台湾師範大学 助理教授)
内容
後日掲載
第91回 2011年7月11日(月) 12:10より
演題
低強度の身体活動と動脈硬化
演者
丸藤 祐子 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
日本人の約3割は、心疾患・脳血管疾患によって死亡しており、この割合 は現在も増加している。心疾患や脳血管疾患を引き起こす大きな原因は、 加齢による動脈硬化であるが、心肺体力を向上させるような中高強度 (3METs以上)の身体活動は、加齢による動脈硬化を抑制するということが 明らかとなっている。一方で、心肺体力の向上には貢献しないような低強 度(3METs未満)の身体活動・運動と動脈硬化との関係を明らかにした研究は ない。低強度の身体活動と動脈硬化との関係が明らかにならなかった原因とし て、「低強度の身体活動」を正確に測定することが難しく、また記憶する ことも難しいため評価するのが困難であったということが背景にある。た とえば、「この一週間であなたはどのくらい立位でいましたか?ゆっくり 歩きましたか?家事をどれだけしましたか?」と聞かれても答えることは 難しく、そのため低強度の身体活動量の評価を質問紙に組み込んだ研究は ほとんどない。またこれまで主流であった1次元加速度計においても、中強 度以上の活動強度は正確に評価できるが、 低強度の活動は誤差が大きく正 確性に欠けてしまい、評価することが難しいとされてきた。そこで我々 は、低強度の身体活動でも高精度で測定できる3次元加速度計を用いて、 低強度の身体活動時間と動脈硬化との関係を検討した。その結果、高年者 において、低強度の身体活動時間が多いものでは、加齢に伴う動脈硬化が 抑制されている可能性が示唆された。
第90回 2011年6月27日(月) 16:30より
演題
適切な研究デザインとは?‐減量プログラム効果検証のための ランダム化比較試験の概要と統計解析‐
演者
中田 由夫 先生 (筑波大学人間総合科学研究科 助教)
内容
ランダム化比較試験(randomized controlled trial: RCT)は、対照を含む2つ以 上の介入方法をランダムな順で割り当てた一連の個人において、効果を定量的 に比較する試験であり、適切にデザインされ適正に実施されたRCTは介入の有 効性についての最良のエビデンスを提供すると言われている。ここで、適切なデ ザインと適正な実施とは何を指すか?端的に言えば、臨床試験登録システムに 研究内容を事前登録し、CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trials)声明に基づき、研究デザインと実施内容および報告内容の質を高めるこ とである。本研究会では、我々がおこなっているRCT「減量プログラムにおける資 料提供と集団型減量支援の効果検証のためのランダム化比較試験」 (UMIN000001259)の研究デザイン(日本公衆衛生雑誌, 2010)と6ヵ月間の短期 的減量効果の検証結果(Obesity Facts, in press)について紹介するとともに、 RCTを計画する際に必要となる統計手法(サンプルサイズの計算、多重性の問 題)について解説する。
第89回 2011年6月8日(水) 17:30より
演題
スポーツと痛み-遅発性筋痛発生メカニズムを中心に-
演者
水村 和枝 先生(中部大学生命健康科学部理学療法学科)
内容
スポーツに関連して起こる痛みには、激しい運動中に起こる痙攣や虚血・相対的酸素不 足のために起こる痛みや、外傷による痛みがある。このほかに、運動直後は特に痛みが ないが翌日あたりから痛みが生じる遅発性筋痛がある。これは特に治療しなくても数日 で軽快するので通常医療の対象とはならないが、運動選手が新しい技術を習得するとき や違った種目に参加する時などに問題となる。また、運動習慣のない人に運動をさせよ うとするときにも問題となると思われる。遅発性筋痛は、運動後痛みのない時間がしば らくあってから痛みが生じるので、不思議な現象と思われてきた。従来、伸張性収縮に より生じた微細筋損傷とそれによる炎症が痛みのもとである、とするものが主流であっ た。しかし、痛くなった段階では消炎鎮痛薬はほとんど無効であり、また、炎症像が出 てくる時間と痛みが生じる時間とのズレも見られる。また、動物実験では組織像や血液 生化学の報告は多くあっても、痛みを評価したものがなかった。そこで私たちはまず ラットに伸張性収縮を負荷し、筋性痛覚過敏が生じるか調べた。予想通り、翌日より三 日間、筋機械逃避反応閾値の低下がみられた。しかし、このラットで最も機械痛覚過敏 が顕著な運動負荷後2日目の筋組織標本を観察しても、光顕レベルの損傷像は見られず、 また炎症細胞の浸潤も見られなかった。そこで、運動中に筋で遊離される物質に焦点を あてて、薬理学的に解析してみた。その結果、運動中に遊離されるブラジキニンがB2受 容体を介して、約12時間遅れて筋における神経成長因子(NGF)の産生を増強し、この NGFが筋細径求心線維(痛み受容器)の機械刺激に対する感受性を増大させ(感作)、その結 果痛覚過敏が生じることが明らかになった。NGF産生の遅れが遅発性筋痛の発現の遅れの 原因であろうと考えられる。目下、NGFを産生する細胞を検索中である。 また、運動前に消炎鎮痛薬を投与すると遅発性筋痛が生じにくいとの報告があり、ラッ トで試してみたところ、COX-2阻害薬が運動前投与の場合にのみ筋機械痛覚過敏の発生を 抑制することが明らかになった。しかし、COX-2阻害薬はNGF産生増大を抑制しなかった ので、機械痛覚過敏を起こす別の物質の産生を阻害している可能性が考えられた。検索 した結果、グリア細胞由来神経栄養因子(GDNF)がCOX-2の下流にあることが分かった。 遅発性筋痛には、このように2つの経路があることが分かったが、相互の関係は不明で、 目下解析中である。セミナーではこれらの点と、関与するチャネルについての検索結果 も紹介したい。 遅発性筋痛は、治療を必要としないため生理的とも考えられるが、完全に回復しない 場合には慢性の筋の痛みのもとになっている可能性が考えられる。セミナーではこの点 にも多少触れたいと思う。
第88回 2011年5月30日(月) 12:10より
演題
Throw-like movementにおける肩の機能
演者
近田 彰治 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
野球における投球やテニスサーブのような投球様式の運動(Throwlike movement)における上肢のスイング動作の特徴として、肩を支点と して上腕を外側へ大きく捻った(外旋運動)後、高速に内側へ捻る運動 (内旋運動)が高い競技力を獲得することに大きく貢献していることが 挙げられる。このとき、外旋‐内旋という一連の回旋運動の可動域は 180°にまで達する。このような大きな可動域にわたる運動は、肩甲骨を 含めた肩の自由度の高さに起因すると考えられるが、これまでのスポー ツパフォーマンスの力学的分析において、肩甲骨の動きは全く考慮され てこなかった。そこで我々は、肩甲骨の動きを実測することにより、肩 甲骨の動きを含めた総合的な肩の機能に着目してきた。テニスサーブに おける肩甲骨と上腕の運動を計測した結果、上腕が大きく外旋された肢 位では、肩甲骨が上腕の外旋と同じ方向に大きく傾斜する運動が観察さ れた。これは、肩甲骨が上腕の複雑な動きに合わせて、その向きを適切 に変化させるという肩の機能的な協調運動を示すものであった。本発表 では、Throw-like movementにおける肩甲骨の役割や肩の機能に関するこ れまで行った研究について紹介する。
- Tags
- 研究活動