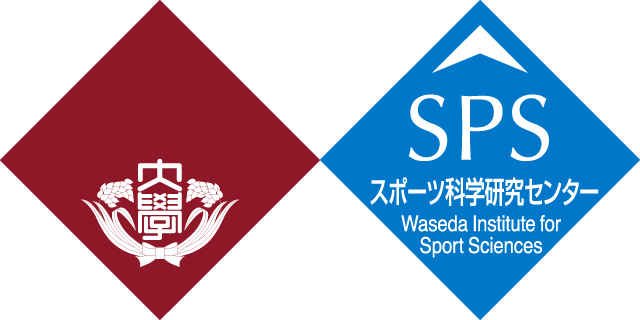- その他
- 所沢 スポーツサイエンス研究会(2013年度)
所沢 スポーツサイエンス研究会(2013年度)
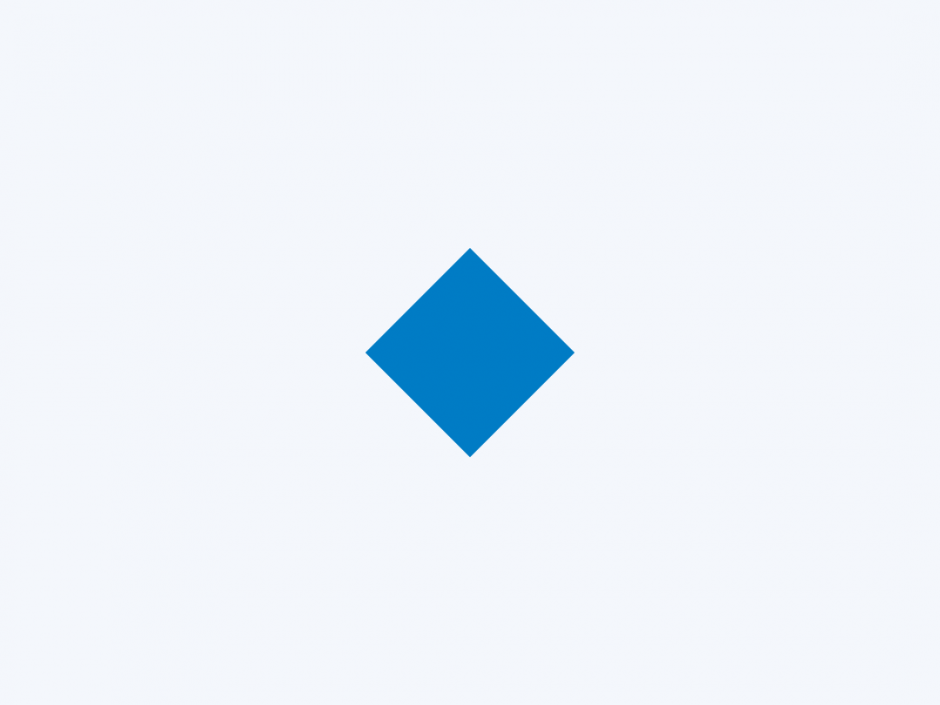
- Posted
- Sat, 01 Feb 2014
第134回 兼 2013年度 修士論文発表コンテスト 2月10日(月)13:00より
<セッション1> 座長:枝 伸彦 先生
- スポーツ観戦動機尺度の再検討
本間崇教(松岡研究室) - 体育における学力に関する研究
三好和人(吉永研究室) - サッカーのボレーキックにおいて足部の速度およびインパクト位置がボール速度に及ぼす影響
谷茂樹(矢内研究室) - 現役プロサッカー選手のセカンドキャリア準備度を規定する社会心理的要因
守山隆司(間野研究室) - 大学女子サッカー選手における膝前十字靭帯損傷予防の科学的検証
馬越博久(福林研究室)
<セッション2> 座長:小西 真幸 先生
- 異なる運動様式における筋細胞内脂肪とインスリン感受性の関係
伊勢龍顕(樋口研究室) - 韓国ポータルメディアにおける対日ナショナリズム--ミニ韓日戦を中心に--
金東賢(トンプソン研究室) - 発育期におけるサッカー活動が膝アライメントに与える影響
岡本海斗(鳥居研究室) - 武田千代三郎の「アマチュアリズム」概念に関する研究―武田の「競技道」概念との関係に着目して―
根本想(友添研究室) - 疲労困憊運動誘導性腎傷害に対する好中球およびマクロファージの関与
溝上翼(鈴木研究室)
<セッション3> 座長:高橋 将記 先生
- 日本と中国における妊娠期女性の生活習慣の比較研究
項密(坂本研究室) - ゴルフパフォーマンスとライフスキルの関係―大学ゴルフ部員に着目して―
斉藤麗(木村研究室) - 主働筋の筋放電量および力-長さ関係の使用領域が最大随意伸張性足関節背屈筋力の関節角速度依存性に与える影響
菱川啓太(川上研究室) - 大学生アスリートの睡眠と気分に関する調査研究
野口史織(内田研究室) - 男子ラクロスにおける前十字靭帯損傷発生率とその発生要因の検討
西川亜夢子(金岡研究室)
結果
第1位 溝上翼(鈴木研究室)
第2位 守山隆司(間野研究室)
第3位 本間崇教(松岡研究室)
第4位 菱川啓太(川上研究室)
第133回 1月27日(月)17:00より
演題
計算神経科学が明らかにする歩行走行の神経制御機構
演者
横山 光 先生 (東京大学大学院総合文化研究科)
内容
私たちが何気なく普段行っている運動は、実はとても複雑な制御から成り立っている。特に意識せず行っている歩行走行も、どの程度膝を挙上するか、どのような軌跡で足部のクリアランスを行うか、さらにそれを実現する筋骨格系の組み合わせも含め無限のパターンが存在する。こうした冗長性を神経系がどう解決し、運動を実現しているかについては未だに明らかになっていない。これを解決する有力な仮説としてmodule 仮説がある。複数の筋群のまとまった活動である「module」という機能単位が存在し、これを大脳皮質等の上位中枢により駆動し運動が実現している、という考えである。また近年、運動時の筋活動を数学的手法を用いて、module を「筋シナジー」として分離できることが明らかになってきた。本研究会では、まず計算神経科学を用いた過去の研究やその背景知識を紹介する。そして、ある速度の歩行走行におけるmodule を用いて他の速度の筋活動を再構成する手法により、歩行走行の神経制御機構の解明を行う、私自身の研究を紹介する。
第132回 11月15日(月) 16:30より
演題
競技者の増量に適した食事方法の検討
演者
田口 素子 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院准教授)
内容
競技者がパフォーマンスを向上させるためには、競技に適した体重と身体組成を有する身体づくりとウエイトコントロールが必要である。実際に競技者が増量を行う際には、過食や偏った栄養摂取、サプリメントの過剰摂取などを行っているケースが多く、やり方によっては健康リスクを増加させる危険性を孕んでいる。国際的なスポーツ栄養コンセンサスでは、骨格筋量を効率よく増加させるためにエネルギー消費量を上回るエネルギー摂取をすることが推奨されているものの、増量時の栄養摂取の量的・質的基準の具体的な記載はされていない。また、日本人競技者に適したウエイトコントロール方法について、エビデンスを蓄積していく必要がある。本発表では、増量時のエネルギーバランス、3大栄養素のエネルギー比率、食事回数に着目して日本人競技者を対象として実施してきた食事介入研究について紹介し、現場応用について議論したい。
第131回 11月11日(月) 16:00より
演題
座位行動研究の最前線
演者
岡 浩一朗 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院教授)
内容
現代社会では、様々な生活場面(余暇、仕事、移動など)において長時間の座位行動(座り過ぎ)が蔓延している。日常生活における座位時間の多寡が、心血管代謝性疾患のバイオマーカーや2型糖尿病、ある種のがん、早世のような健康アウトカムと関連があるという証拠が急速に蓄積されつつある。重要なのは、これらの関連が身体活動の実施時間とは独立して認められることである。本話題提供では、成人を対象にした座位行動研究について、その最新動向を紹介する。具体的には、座位行動(座り過ぎ) と健康リスクとの関連、自己報告および機器を用いた座位行動の評価方法、座位行動に影響を及ぼす要因、座位時間を減らすための効果的な介入方策、座位時間を減らすことや中断することに関する指針・声明・勧告といった視座から話題を提供する。また、座り過ぎによる健康障害は、どのような機序で起こるのか、どのような種類の座位行動をどのくらいの頻度・強度で中断すれば健康障害を予防できる可能性があるのかを解明するための実験研究の必要性など、この分野の研究における今後の方向性について議論したい。
第130回 10月22日(火) 16:00より
演題1
アスリートの基礎代謝量
演者
大嶋 里美 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院研究助手)
内容
基礎代謝量は、人が生きていくうえで必要な最小のエネルギー消費量と定義されており、一般的に、性別や年齢の他に身長や体重などの身体組成に基づき推定を行う。その中で除脂肪量は、基礎代謝量を決定づける一因とされ、基礎代謝量の60-80%は除脂肪量で説明可能であると報告されている。そのため、国立スポーツ科学センターは、典型的に除脂肪量が多いアスリートにおいて、除脂肪量に基づき基礎代謝量の推定を行う方法を推奨している。しかし除脂肪量は、様々な代謝率を持つ肝臓、心臓、骨などの臓器や組織から構成されており、これらの臓器量も独立して基礎代謝量に影響を及ぼすと報告された。アスリートは体作りのために減量や増量を頻繁に行うが、それらが臓器量や基礎代謝量へおよぼす影響は明らかにされていない。本研究会では、基礎代謝量に関するこれまでの研究や、主に増量に着目をして我々の研究グループが行ってきた、増量が臓器量および基礎代謝量へ及ぼす影響に関する研究内容を紹介する。
演題2
野球投手の投じる“直球”の回転
演者
永見 智行 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院研究助手)
内容
野球投手の投球に関するバイオメカニクス研究では,その投球パフォーマンスをボールの移動速度(球速)やコントロールの正確性・再現性といった定量的な指標で評価することが多い.一方,指導や実践の場では,「この投手の直球はキレが良い」,「今日はノビが無かった」等といった定性的な表現がよく用いられる.これらは非常に重要視されているにも関わらず,いったい何を指しているのか,定量的に表すことができるのかはよく分かっていない.ただ,こういった表現は投じられたボールの様子を見たコーチや捕手,相手打者等から発せられるものであることから,ボールの飛翔軌道の差異を表したものと考えられる.回転しながら空中を飛翔するボールには,その回転効果によって揚力が働き,またその揚力の働く方向や大きさは,回転速度や回転軸の向きに強く影響される.そのため,「キレが良い」,「ノビがある」と言われるような一流投手のボールの回転は他の投手のそれとは異なる可能性がある.本発表では最も基本的な球種である“直球(ストレート、fastball)”の回転に着目し,その個人差や経時的な個人内変動について,これまでの研究成果を基に紹介する.
第129回 9月24日(火) 13:30より
演題
Toward more Empowering Coaching™: An introduction to the aims, methods and initial findings stemming from the European-wide ‘PAPA’ Project
演者
Nathan Smith (University of Birmingham, UK)
内容
In this overview presentation, the background to and focus of the European Commission FP7 Health) funded PAPA project (Promoting Adolescent Physical Activity; www.projectpapa.org) will be described. The PAPA project customized for grassroots football and implemented a coach training programme (i.e., Empowering Coaching™; Duda, 2013; www.empoweringcoaching.co.uk), that pulls from achievement goal frameworks, Self Determination Theory as well as principles of behavioural change. Using mixed-methods, we rigorously evaluated the impact of the programme upon the motivational climate operating in youth football and examined relationships between empowering and disempowering coach-created climates with motivation regulations, basic need satisfaction and other outcomes (e.g., self esteem, enjoyment, anxiety, physical activity levels, intentions to dropout) reported among 7769 grassroots players (6641 males, 1020 females, (M age = 11.56, SD = 1.40) from France, Greece, Norway, Spain and UK. Coaches completed questionnaires and sub-samples were observed and/or participated in post-intervention focus groups. Preliminary findings will be highlighted with particular emphasis placed on the multi-dimensional observational instrument that was developed in the PAPA project and our results to date regarding this assessment tool.
第128回 9月19日(木) 16:00より
演題
ヒトのロコモーション動作に内在する神経制御機構の特異性
演者
小川 哲也先生(早稲田大学スポーツ科学学術院次席研究員・研究院助教)
内容
歩行をトレーニングすることで走行のパフォーマンスは向上するか?また、その逆(走行トレーニング→歩行)は?運動パフォーマンスの向上には各々の運動の遂行に関わる神経制御機構を適切な機能変化に導くことが必須であり、従って、パフォーマンス向上を目的としたトレーニング戦略の構築にあっては各々の機構の特性をよく理解しておかなければならない。ヒトの歩行と走行動作はともに、下肢の各関節の屈曲、伸展動作の繰り返しによって起こり、従って、動員される筋や、筋への最終共通路であるα運動ニューロンといった出力部分については大部分がモード間で共有されるものと推察される。一方、主に水棲動物の移動動作を対象としたこれまでの研究では、運動モードに依存して動員される制御機構が異なるとの見解が脊髄介在ニューロンや脊髄固有ニューロンの細胞内電位記録により示されてきた。ヒトでの運動モードに依存した制御機構の有無について検討するために、ヒトの主要な移動運動モードである歩行と走行を対象に検討を実施した。これまで主に上肢の単純な動作を対象にモデル化されてきた運動学習を基盤とした行動科学的な検証に取り組んだ。その主たる結果を報告し、また、前述の疑問(歩行と走行のトレーニングとパフォーマンスの関連性)について考察したい。
第127回 7月8日(月) 16:00より
演題
Feedback Expectation During Skill Learning
演者
Dr. Steven Hackley (University of Missouri, Columbia)
内容
Rapid and accurate feedback is critical for learning a new skill. Evidence from primate neurobiology has highlighted the central role of the reward system in this process. According to the leading theory (Schultz, 2002), the discharge of dopamine neurons upon receipt of feedback depends on whether the outcome was better or worse than expected. The experiments to be presented are concerned with developing a measure this expectation in humans using the methods of psychophysiology (EEG, startle-blink) and neuroimaging (fMRI). Central or peripheral nervous system activity is recorded as participants await reward or punishment in various gambling tasks. By comparing healthy older adults to those with Parkinson’s disease, it is possible to draw conclusions regarding the dopamine system. Some of this research was conducted in collaboration with Dr. Hiroaki Masaki, of Waseda University.
第126回 7月8日(月) 16:00より
演題
スーパーオキシドディスムターゼによる骨格筋萎縮予防
演者
奥津 光晴 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院助教)
内容
心疾患や癌、糖尿病などの慢性疾患や加齢は、骨格筋の萎縮と運動機能の低下を引き起こす。この原因として悪液質(カヘキシー)の増加にともなう酸化ストレスや炎症性サイトカインの増加が知られている。骨格筋の萎縮は、単なる筋量の減少という形態学的変化のみならず、筋肉の代謝機能や筋力低下による活動範囲の制限が生活の質を低下させることから、骨格筋萎縮の分子メカニズムを解明し筋萎縮の予防に応用することは重要な課題である。骨格筋萎縮の予防および抑制について酸化ストレスの軽減に着目し検討した研究は国内外で数多く報告されているが、酸化ストレスを効率的に軽減する方法はいまだ確立されていない。本研究会では、骨格筋萎縮の分子メカニズムについて、骨格筋のスーパーオキシドディスムターゼ(superoxide dismutase: SOD)の発現に着目し、骨格筋萎縮の効率的な予防方法の確立と骨格筋萎縮予防における運動の重要性について紹介する。
第125回 6月20日(木) 17:30より
演題
睡眠中の時間認知機能 -これまでの研究とスポーツ科学への応用-
演者
有竹 清夏先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院助教)
内容
次の日が旅行や試験などで、「明日は○時に起きなければならない」。そのような時、予め起床する時刻を決めて、目覚まし時計をセットし、床につくことはよくある。ところが翌朝、時計のアラームが鳴る少し前に自然と目を覚ましてしまったという経験はないだろうか。人によっては、これを日常的に行い、予め決めた時刻に目覚まし時計なしに起床できる人がいる。このような現象は「自己覚醒」といわれ、ヒトの睡眠中に時間認知機能がはたらいているためと考えられている。 これまで時間認知機能については、覚醒中に限定した研究が数多く行われ、内分泌系、活動量、生体リズムとの関係についても検討されてきた。最近では画像研究が行われ、覚醒中の時間認知機能の神経学的基盤が解明されつつある。一方、睡眠中の時間認知機能については、朝の予定起床時刻に向けACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が上昇することが報告され、睡眠中の時間認知機能への関心がさらに高まったが、時間認知機能と睡眠の深さ、量や質との関連やその脳内メカニズムについては明らかにされていなかった。 本研究会では、自己覚醒に代表される睡眠中の時間認知機能のこれまでの研究と我々の研究で得られた知見、最近の動向について概説し、スポーツ科学分野への取り組みについても紹介したい。
第124回 6月10日(月) 12:10より
演題
レスベラトロールの抗肥満・糖尿病効果
演者
東田 一彦 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
近年、ポリフェノールの一種であるレスベラトロールの抗肥満・抗糖尿病効果や寿命延長作用に関する報告が増加しており、今やレスベラトロールは薬局でも気軽に買えるサプリメントとなっている。その作用機序として、レスベラトロールが長寿遺伝子Sirt1を活性化することで様々な代謝適応を引き起こしていると考えられている。骨格筋ではレスベラトロールがSirt1を活性化・タンパク質の脱アセチル化を引き起こすことで、ミトコンドリアの代謝機能を亢進し、抗肥満・抗糖尿病効果を示すと考えられている。一方で、レスベラトロールとSirt1の抗肥満・抗糖尿病効果に関しては非常に多くの反証論文が発表されている。本研究会では、レスベラトロールとSirt1の機能について解説し、レスベラトロールが骨格筋のエネルギー代謝・ミトコンドリア機能調節に及ぼす影響に関する知見を紹介する。
第123回 6月3日(月) 12:10より
演題
韓国における競技スポーツ政策の制度と実施過程に関する研究
演者
金 永聖 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
韓国のスポーツ政策は、国によって競技スポーツ政策が重点的に行われてきた。例えば、1962年の国民体育振興法の制定、1982年のスポーツを専門に担当する中央行政機関である体育部(部は日本の省にあたる)の設置、1986年のアジア大会と1988年のソウルオリンピック競技大会の開催、1993年の国民体育振興5ヶ年計画の策定など、韓国においては、法令、行政組織、国際競技大会の誘致・開催、行政計画の実施など、具体的な制度や施策に基づいて国策として競技スポーツ政策が実施されてきた。また、韓国における競技スポーツ政策は、メダル獲得率から見てみると、1984年のロサンゼルスオリンピック大会では世界10位、1988年のソウルオリンピック大会では世界4位、2008年の北京オリンピック大会では世界7位、2012年のロンドンオリンピック大会では世界5位と世界的にみても優秀な競技成績を残している。しかし、なぜ韓国がこのような顕著な成果をあげているのか、その制度的または政策的な要因については十分な研究は行われていない。本研究会では、韓国のスポーツ政策の中でも最も重点的に実施されていると考えられるこの競技スポーツ政策を対象に、韓国におけるスポーツに関する基本的な制度において、実際に競技スポーツ政策がどのように位置づけられ実施されているのかについて紹介する。
第122回 5月27日(月) 12:10より
演題
潜水反射試験を用いた副交感神経活動の測定とその評価方法の確立に向けた課題
演者
小西 真幸 先生(早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
交感神経の緊張や副交感神経の減弱は循環器系疾患との関連が極めて強い。特に、副交感神経の減弱は循環器系疾患の発症や総死亡率の独立の危険因子である。しかしながら、その自律神経の活動を簡便に測定する方法は存在しない。これまで、自律神経活動の評価には侵襲的な方法として筋交感神経活動や採血によるカテコラミン濃度、非侵襲的な方法として心拍変動解析などが用いられていたが、いずれの方法も被測定者にとって痛みや時間的負担が生じ、機材などのコスト面でも施設の負担は大きいと考えられる。すなわち、循環器系疾患や加齢を取り扱う臨床および研究現場において、簡便に自律神経活動を評価する方法の確立は可及的課題と言える。そこで、我々は潜水反射試験に着目した。ヒトは顔面を冷却し、止息することで、大きな徐脈を引き起こす。この徐脈反応は副交感神経活動を反映すると考えられている。しかしながら、潜水反射試験による副交感神経活動の評価方法はまだ確立されていない。具体的に、既存の副交感神経活動の指標との関連、循環器系疾患リスクとの関連、運動トレーニングとの関連を検討する必要がある。 本研究会において、潜水反射試験の概要および最新の知見を紹介することにより、副交感神経活動の評価方法としての可能性を示す。さらに、我々がこれまでに測定を終えた水泳選手、若年男性のデータを中心とした研究成果を紹介したい。
第121回 5月20日(月) 12:10より
演題
身体活動と抗酸化物質が生体内の酸化ストレスに及ぼす影響
演者
高橋 将記 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院助手)
内容
運動や身体活動によって生体内における活性酸素の生成が増加し、抗酸化能力を上回った状態を酸化ストレスという。急性の酸化ストレスは、運動時の筋力や運動パフォーマンスの低下に関与することが報告されている。また、慢性的な酸化ストレスは、心血管疾患や動脈硬化症といった種々の病態形成に関与することが示されている。従って、活性酸素の生成を消去する抗酸化物質を用いて、酸化ストレスを抑制することを目的とした検討が多く報告されてきた。しかし、急性あるいは慢性的な酸化ストレスに対しての抗酸化物質摂取の有効性について科学的根拠が少ないのが現状である。さらに2008年以降、運動トレーニング時に抗酸化物質を摂取することが、運動によるインスリン感受性の亢進や酸化防御を担う抗酸化酵素の発現量の増加までも低下させることが明らかになってきた。発表者は若年者および高齢者を対象として「一過性運動および運動トレーニング時での酸化ストレス状態に及ぼす抗酸化物質摂取の影響」を検討してきた。本研究会では、「一過性運動および運動トレーニング時での酸化ストレスの抑制に抗酸化物質の摂取は有効か」という視点でこれまでの研究成果を紹介する。
第120回 5月16日(月) 16:30より
演題
OpenMAT Human Motion Analysis Toolkit for LPMS and LPEMG Sensing Devices
演者
Dr. Klaus Peterson(LP-Research Inc.)
内容
Two important sources of information for the analysis of the condition of the human body during sports training and medical rehabilitation exercises are human motion tracking and measurement of the human muscle activity. In this talk we present methods to measure human motion by using inertial measurement units and human muscle activity by using EMG probes. We would like to present two devices that we have developed at Takanishi laboratory and commercialized through our company LP-RESEARCH for this purpose: The inertial measurement unit LPMS-B uses highly integrated, miniaturized MEMS accelerometers, gyroscopes, magnetometers and altitude sensors to calculate orientation, linear acceleration and (to a certain degree) displacement. The sensor uses a sensor fusion algorithm based on a Kalman filter to merge the information from the single sensors into high quality measurement results. Sampling rates of up to 200 Hz are supported. Dynamic orientation measurements are calculated at an accuracy of down to 1 degree. In the laboratory we have used the sensor for various human measurement applications like gait tracking for rehabilitation research, micro-invasive surgery training and mastication analysis. The second device we would like to present is a wireless EMG (Electromyography) sensor (LPEMG-B). The sensor can measure muscle activity by being attached directly to the muscle area of the human body. The sensor is very small and light. It connects to a host system (e.g. Android device, Windows PC) through a wireless Bluetooth interface. Data can be measured and transferred at high frequencies (up to 100 Hz) and high resolution (16-bit). Data from the IMU units and the EMG units can be sampled and recorded on the host system. Alternatively can the data be streamed over the network to other applications using the Open Motion Analysis Toolkit (OpenMAT). With this application the user can apply the orientation information from the sensors to a physical human model. The result is not only orientation information about the human model’s joints, but also their position in 3-D space. This data can be used for characterizing the motion of the human, e.g. during a sports activity for further medical analysis. To guarantee that the timing of the measurement of the EMG data and the motion tracking is correct, all data from the different sensors is centrally synchronized. As the timers in the sensors attached to the system do not always run at exactly the same speed, the devices are re-synchronized at regular intervals. In this talk we will give an introduction to the hardware structure of the sensors, their internal algorithms / calculation methods, the calibration of the sensors, the software system on the OpenMAT host and the programming API that we offer to developers. After this purely technical introduction we will show results of experiments we have done at Takanishi lab using the LPMS and LPEMG sensors.※発表,質疑応答全て原則日本語です.ワイヤレスモーションセンサーおよびEMGセンサーの 簡単なデモンストレーションを行っていただけるとのことです.
第119回 5月13日(月) 12:10より
演題
アスリートの皮膚コンディショニング指標の検討
演者
枝 伸彦 先生 (早稲田大学スポーツ科学学術院 助手)
内容
近年、皮膚感染症の対策はアスリートのコンディショニングにおいて重要な課題となっている。アスリートは様々な皮膚感染症に対して罹患リスクを有しているが、特にフットボール, バスケットボール, ラグビー, ホッケー, レスリングなどのコンタクトスポーツで感染が多いと報告されている。アスリートの皮膚表面は, 練習やトレーニング時の発汗によってふやけ, 日常的に黄色ブドウ球菌などの病原性微生物が繁殖しやすい状態であると考えられる. また, スポーツ活動に伴う皮膚の外傷によって, 病原性微生物が皮膚のより深くまで侵入し, 感染を引き起こす可能性がある. 従って, アスリートにおいて皮膚のコンディショニングは重要であると考えられるが、アスリートの皮膚コンディション評価に有用な指標の検討は未だに行われていない。そこで、発表者は皮膚コンディショニング指標の確立を目的として、運動と皮膚バリア機能の関係を研究している。発表者は、これまでの研究で皮膚の分泌型免疫グロブリンAの測定方法を確立させ、一過性の高強度運動と皮膚バリア機能の関係を明らかにしている。本研究会では、アスリートにおける皮膚感染症の実態や皮膚バリア機能について解説し、高強度持久性運動が皮膚バリア機能に及ぼす影響に関する知見を紹介する。
- Tags
- 研究活動