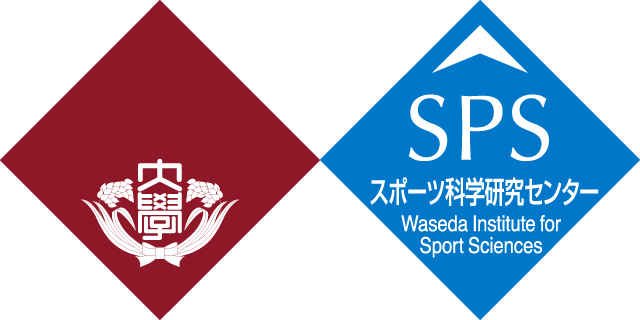- その他
- 東伏見スポーツサイエンス研究会(2010年度)
東伏見スポーツサイエンス研究会(2010年度)
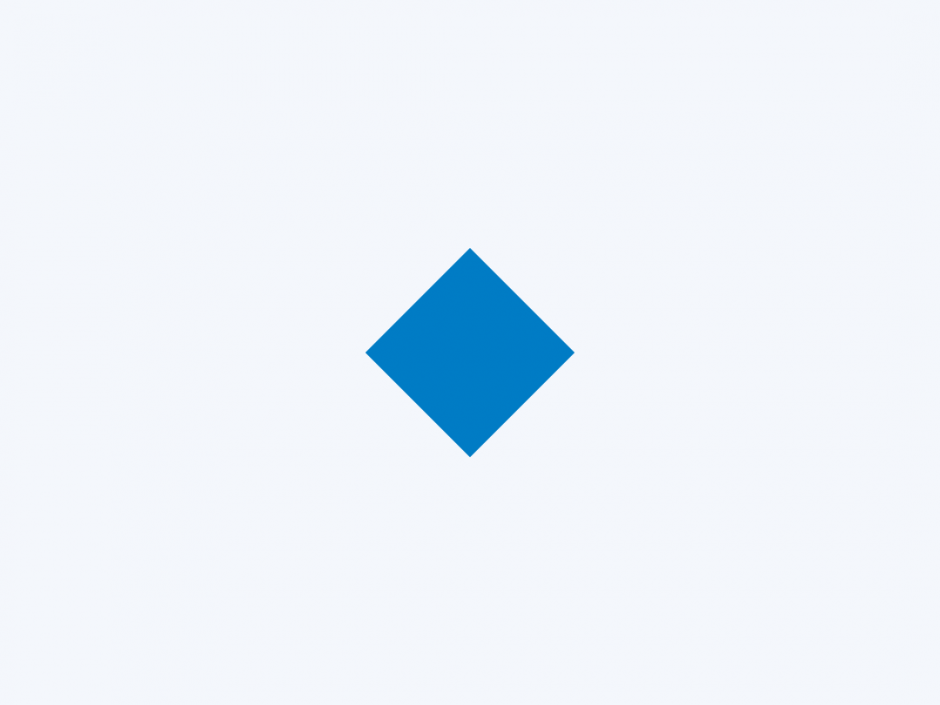
- Posted
- Sun, 02 Jan 2011
第9回 1月24日(月)18:10~19:40@早稲田大学79号館303号室
演題1
The World of the Hanshin Tigers: An Anthropology of Contemporary Sport
演者
William Kelly教授(Professor of Anthropology and Sumitomo Professor of Japanese Studies at Yale University.)
内容
Abstract: For the last three decades of the twentieth century, the Hanshin Tigers were the heart and soul of Kansai professional sports and emblematic of a sport that was so central to the development of transportation, media, and leisure in that region. To an anthropologist, the Hanshin Tigers represent an intriguing lifeworld centered on the production and presentation of what was arguably the most important sport in twentieth-century Japan. In this talk, I will first outline the five key elements of Hanshin Tigers sports world: the stadium, the team, the management, the fans, and the media. I will then introduce four themes embodied in this sports world: the uncanny mimicry of Bushido baseball; Japanese baseball as edu- tainment; Osaka’s second-city complex and Hanshin Tigers baseball as the nobility of failure; and the Hanshin Tigers baseball as workplace melodrama.
第8回 2010年10月25日(月)18:10~19:40@早稲田大学79号館303号室
演題1
スポーツマンシップの誕生
演者
石井昌幸先生(早稲田大学スポーツ科学学術院准教授)
内容
「スポーツマンシップ」という言葉は、こんにちではほとんど使われることがなくなったが、 かつてはスポーツをめぐる中心的な規範として大きな影響力を持っていた。19世紀イギリス の新聞・雑誌におけるsportsmanshipの語の用例を検討してみると、それは世紀中葉から次 第に見られるようになるが、そのほとんどは狩猟をめぐるものである。ところが、世紀末の 最後の10年になって、この語は飛躍的に多く用いられるようになり、また競技スポーツをめ ぐる用例が頻出するようになる。本報告では、この急増の原因を、それまではエリートの狭 いサークルのなかで行われてきたスポーツが、急速に外部(階級的にも地理的にも)へと広 まり始めたことと関連づけながら論じる。
第7回 2010年10月22日(金)16:30~18:00 @早稲田大学79号館303号室
演題1
“The Beijing Games in the Western Imagination of China: The Weak Power of Soft Power”
演者
Wolfram Manzenreiter, Dr. Phil.(Associate Professor, University of Vienna, Institute of East Asian Studies/Japanese Studies Division)
内容
Mega-events focus the world’s attention on a particular place and a nation and the success thereof, in either hosting or performing well in the event. Throughout the world, expectations were running high that China would make usage of hosting the Beijing Games to promote a positive image to the world. This paper takes a critical look at the discourse on the Beijing Games as a public diplomacy tool. Empirical data from global opinion polls are analyzed to demonstrate the weak impact of even the world’s largest sport mega-event on altering global perceptions. Two main propositions will be advanced: Firstly, expectations that a sports event can improve the image of a country are overrated; secondly, having been locked in the Olympic “double-bind”, a system of contradictory messages to which the host is simultaneously obliged, China had no chance in the contest for meaning-making which the Western media won hands down.
第6回 2010年8月5日(木)18:00~19:30 @東伏見キャンパス79号館(教室は調整中)
演題1
『情動の生理的、社会的意味』
演者
彼末一之先生(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)
内容
われわれが行動をするときの意思決定は”理性的”に行っているつもりでも、 多くの場合”情動”が重要な役割をはたす。「あるチームを応援する」、 「体によい運動をするようになる」といったことがどうして起こるのか、 その生理的メカニズム、脳機構について概説したい。
第5回 2010年6月28日(月)18:10~ @東伏見キャンパス79号館201教室
演題1
『スポーツとメディアの長~い付き合い:明治期の新聞と大相撲の優勝制度』
演者
リー・トンプソン先生(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)
内容
現在のスポーツのあり方は「自然」なものではない。私たちにとって当たり前 で本来あるべき姿でも、歴史的な過程をたどって形成されている。その過程を跡 付けることは結構スリリングであり、ドキドキするような発見がある。 本発表では大相撲の優勝制度を取り上げる。江戸時代の中期から相撲は定期的 に興行されているが、優勝制度は当時としてはなかった。明治42年(1909年) 5月場所から、時事新報社(新聞社)が定期的に個人優勝者を表彰することは優 勝制度の始まりとされている。 しかし優勝制度はいきなり導入された訳ではない。それ以前にも、力士が成績 によって表彰されることがしばしばあった。ただし、表彰されたのは全勝や土付 かずなどであり、最も良い成績を残した一人の力士とは限らなかった。 優勝制度は、場所を評価の単位として、場所を通しての成績という意識に基づ いている。本発表ではその意識の形成に貢献した「星取表」の導入と役割、力士 の成績に対する意識の変化、力士の表彰とその条件など、新聞の報道から優勝制 度の形成過程をたどる。 積み木が一個一個積み上げられ、現在の優勝制度の形がそろう。それまでにな かった何かが新聞紙上で初めて現れた記事は感動的である。
第4回 2010年4月26日(月)18:10~ @東伏見キャンパス79号館201教室
演題1
『なぜ「柔術は武芸の父母」と呼ばれたのか? 柔道・剣道の接点技法としての柔術』
演者
志々田文明先生(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)
内容
平成20年3月の中学校学習指導要領の改訂告示によって保健体育科で武道が必修化されることになった。現在、学校現場では、柔道や剣道の「何を、どのように」教え たらよいのかで教員に不安が交錯し、議論が喧しい。これに対して2009年夏の武道学会大会でこの問題に関するシンポジウムが行われ、各武道の専門指導者がそれぞれ の武道の対策案を開陳し、聴衆も交えて相互に議論した。だが、柔道や剣道などを総称して武道といいながらも、武道技術の中核部分についての共通認識がこれまで学会 や各武道団体レベルでなされてこなかったために一方的な自武道の対策紹介にとどまる退屈な議論となった。これは武道のスポーツ的専門化つまり闘いにおける総合性の 性格の欠如から生まれた現象であり、いわば必然であろう。しかし、もし武道技法の本質的な問題を捉えることができれば、それを教材化して生徒に提供することも容易 であり、生徒にとって意義深いであろう。また、各武道の視点から武道技術の中核部分へのアプローチに基づく興味深い議論が展開されたかもしれない。 そこで本報告では、日本武道を代表する柔道と剣道の技術特性を術理的、歴史的に紹介する。それは標記の問題への解答であり、また、日本武道の現状と将来に関する 本質的問題の提起となろう。史料としては主にこれまで無視される傾向のあった嘉納治五郎の言説を用いる。
- Tags
- 研究活動