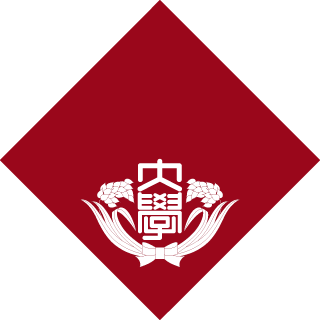- 海外派遣学生
- 樋沢 拓真Takuma HIZAWA
樋沢 拓真
Takuma HIZAWA

- Posted
- Thu, 31 Mar 2016
- 派遣期間:
平成27年9月~平成27年10月 - 派遣先大学:
University of Connecticut - 派遣先国・地域名:
アメリカ・コネチカット州
派遣プログラムの内容について
留学先では、発展途上国で使用される胎児の心拍計が正確に動いているかを評価する安価な胎児模型の設計を行った。具体的にはスピーカーから出力される音が小さいという問題を解決するためにアンプを設置し、ボリュームを変えた時の出力の測定、心拍数を変えた時の出力の測定を行った。また、胎児模型を作成する上で実際の妊婦の人と同じ測定条件にする必要のある条件を洗い出し、他の論文で必要と言われていた減衰率を再現する必要がない可能性を示した。
学習成果について
この実習を通して学んだことは論文を自分の頭で理解し、吟味することの大事さである。今回設計したのは胎児模型であり、これは実際の妊婦の女性と同じ測定条件にする必要がある。本研究は以前滞在先の研究室で行われていた実験を引き継いで改良を行ったが、初期の胎児模型を作成する上で音源の減衰率に関して実際の妊婦と同じ測定条件にする必要があることが納得できなかった。この減衰率を考慮する必要がないことが明らかになり、胎児模型の構造の簡略化を行うことができれば、より安価に胎児模型を作成することができる。 このため数多くの文献を調べ、構造の簡略を行うことができる根拠を探した。結局どの文献を見ても自分に有利なものを見つけることができなかった。しかし構造の簡略化を行うことができるかどうかを確かめる実験を考え、構造の簡略化の見込みを立てることができた。
海外での経験について
毎日の研究時間が早く終わるという環境で自由な時間が多く、夕方以降は多くの活動に参加することにした。 この目的は日本で経験できないことの体験と英語力向上ためである。 具体的には空手クラブや日本クラブといったクラブに積極的に参加した。これらのクラブを通して食事時の会話やホームパーティへ招かれる機会があり異文化体験を行った。 これらの経験を通して英語でのコミュニケーション能力の上達を実感したほか、相手の国の文化を理解することができた。

今後の進路への影響について
留学前は修士以後については就職以外の選択肢を持っていなかった。しかし、留学先に修士以上の学生が多く在籍していて、そのメリットについて伺う機会が多かったため、修士より先の課程へ進むという選択肢が増えた。