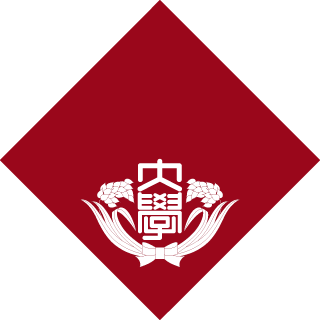- 海外派遣学生
- 平山 三千昭Michiaki HIRAYAMA
平山 三千昭
Michiaki HIRAYAMA

- Posted
- Sun, 31 Mar 2019
- 派遣期間:
令和元年5月~令和元年11月 - 派遣先大学:
スイス連邦工科大学ローザンヌ校 - 派遣先国・地域名:
ローザンヌ・スイス
派遣プログラムの内容について
スーパーグローバル大学創成支援 (SGU) のプログラムにより、スイスのEcole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) のDistributed Intelligent Systems and Algorithms Laboratory (DISAL) へ半年間留学させていただいた。私は、専門であるソーシャルロボットの移動に関する研究を行っている世界中の一流研究機関から、最も面白いと感じたEPFLのDISALを選び、留学した。
私が利用させていただいたSGUの学生派遣プログラムの目的の一つは、早稲田大学が海外大学との連携を強化することだ。そこで留学の目標は、菅野研究室とDISALの双方の組織に貢献できる研究成果を残すこととした。
留学中はDISALのA.WasikとA.Martinoliのご指導の下で研究を進めた。

学習成果について
研究成果
チームでタスクを行う複数の移動ロボットが通信の不安定な状況でも安定して活動するためには、搭載センサを用いたロボット同士の相互位置推定技術が必要になる。私は留学中、その技術の開発や評価を行った。
組織への貢献
貢献できる成果を世に出すため、現在も引き続き研究に取り組んでいる。
学習した事
ロボット同士の相互推定に必要な確率論の学習や、複数ロボットの制御に必要なグラフ理論などについて学習した。暇な時間で興味のあったゲーム理論についての勉強も少し進めた。ROSでの大規模なプログラム開発に携わり、技術面も伸ばすことができた。

海外での経験について
これまで長期の海外旅行をした経験はあったが、一つの場所に腰を落ち着けて活動することは初めてだったため、非常に有意義で貴重な経験ができた。研究では、指導者とのディスカッションや日々の業務、1時間を超える研究成果報告会などを経験した。早稲田とDISALの研究対象への興味の持ち方の違いを実感し、価値観が広がった。研究以外でも、ホストファミリーや研究室メンバー、研究室外の友人達との日々の交流を通して文化の多様性を実感した。スイスの人々を見習い、日本でもオンとオフをはっきりさせて充実した研究生活を送りたいと思う。

今後の進路への影響について
もともと、留学の経験を踏まえて自分の今後の進路を決めたいと考えていた。そして、現在まだ悩んでいるところではあるが、留学をしていなかったら考えられなかった進路も選択肢としてある。今回の留学を通して視野を広げる事ができたと思う。

その他
菅野先生、その他先生方、SGUの事務所の方々には大変お世話になりました。また、EPFLでも人に非常に恵まれていたと思っております。本当にありがとうございました。