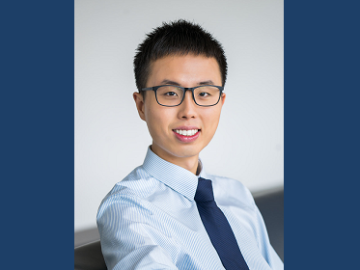研究概要
課題(研究領域)
日本企業のコーポレート・ガバナンスに関するグローバルな発信
研究テーマ名
日本の企業統治の比較実証分析:所有構造・戦略選択・パフォーマンス
研究目的の概要
かつて「日本型」と呼ばれた日本企業の統治構造は近年大きく変化し、この変化が米国型の構造への収斂を意味するのか否かをめぐって活発に議論が展開されてきた。研究代表者らは、20世紀を包括する長期データの構築、コーポレートガバナンス評価システムの開発、これらを利用した企業金融、所有構造、取締役会構成の変化の実証分析を通じて、銀行危機以降、リーディング企業の企業統治が、市場ベースのガバナンスと関係ベースの内部組織・雇用制度とが結合するという意味でハイブリッド化し、また、1980年代に比べて大きく多様化したことを明らかとした。
もっとも、上記のハイブリッドな統治構造の持つ特性(そのベネフィットとシステム効果の喪失や調整費用の発生などのコスト)や、企業統治の多様化をもたらした要因はいまだ十分に解明されていない。また統治構造の変化が、企業の戦略・組織選択を介して「失われた20年間」といわれるパフォーマンスの低迷にどのような影響を与えているかに関する認識も一致していない。さらにグローバル化を通じて各国の統治構造が進化する中で、変容した日本の企業統治の国際的特徴は何かについても明確な像を結んでいない。
本研究の目的は、以上の問題意識から、企業統治構造が投資家や経営者などステークホルダー間の信頼やコミットメントなどを通じて内生的に決定されるとする分析枠組みを新たに開発する一方、これまで構築してきた日本企業の統治構造に関する長期データを増補・拡充し、さらに、それに照応する形で各国のデータを新たに構築することによって、国際比較の視点から、国際共同研究を通じて、日本の企業統治をめぐる諸問題を包括的に解明する点にある。具体的な課題は、企業統治構造を決定する要因は何か、各国の特性差は何によって規定されているのか、企業統治構造は企業パフォーマンス、さらに経済成長に本当に実質的な影響を与えているのか、与えているとすれば如何なるメカニズムを通じてか、企業統治に関連する経済制度はいかに進化しているのか、という一連の問題を、銀行危機以降の日本企業の経験を中心に、比較企業統治論的視点から解明する点にある。さらに、海外との共同研究、国際シンポジウムでの発信、英文単行本の公刊、データ公開などを通じて、日本の企業統治に対する国際的理解の促進を図る。

研究計画の概要
本研究は、代表者・宮島の総括のもと、1)企業統治構造の分析、2)統治構造と戦略・組織選択、3)パフォーマンスの分布と統治構造の3チームによって組織される。また、この3チームの分析成果を総括する形で、代表者は、比較企業統治論の視点に立った日本の企業統治の進化に関する英文単行本をまとめ、公刊する。
- 企業統治構造の分析では、近年劇的に変化した日本企業の株式保有構造の特性と機能の解明が焦点の一つであり、これまで代表者が海外研究者と進めてきた所有構造の進化に関する国際比較の共同研究を完成させる。いま一つの焦点は、取締役会組織の決定要因であり、国際比較を通じて英・米の一層構造とも大陸欧州の二層構造とも異なる日本の取締役会の特性と機能を明らかにする。
- 統治構造と戦略・組織選択では、上場、IPOの決定、M&Aと事業再組織化、持株会社の採用、内部資本市場の機能、技能形成における内部訓練か外部委託かの選択を取り上げ、そうした戦略・組織選択に対する統治構造の影響を解明する。
- パフォーマンスの分布と統治構造では、日本企業のパフォーマンスの分布(Heterogeneity)の長期動向、他国との差異、その資源配分効率性に関する含意を解明した上で、この資源配分効率に対する統治構造の影響を分析する。分析の基礎となるデータについては、これまで早稲田大学に蓄積してきた日本企業の統治関連データを延長・拡充する一方、所有構造・取締役構成・内部組織に関する独自の変数を開発し、さらに海外企業のデータベースを新たに構築する。
本研究は国際比較に基づく日本の企業統治の分析結果の国際発信を課題とするため、これまで共同研究を続けてきた海外研究協力者と密接な連携のもとに研究を進める。フランスの社会科学高等研究院(EHESS)、ブリティッシュコロンビア大(UBC)、オックスフォード大などが海外協力機関となる。また本計画では、上記の各機関に、若手研究者を短期に派遣する。若手研究者を共同研究のアシスタント等として、問題設定・データの作成の段階から関与させることによって、基礎的な研究力の向上を図る一方、協力機関のセミナーへの参加を通じて、日本企業に対する海外の関心の在り方を理解し、さらに各協力機関の進める米・英、大陸欧州、新興地域のデータベースの構築に参加し、今後これらのデータを利用した国際共同研究の展望を拓く。