「文学と美術における〈古典〉の変容と生成」(12/5)
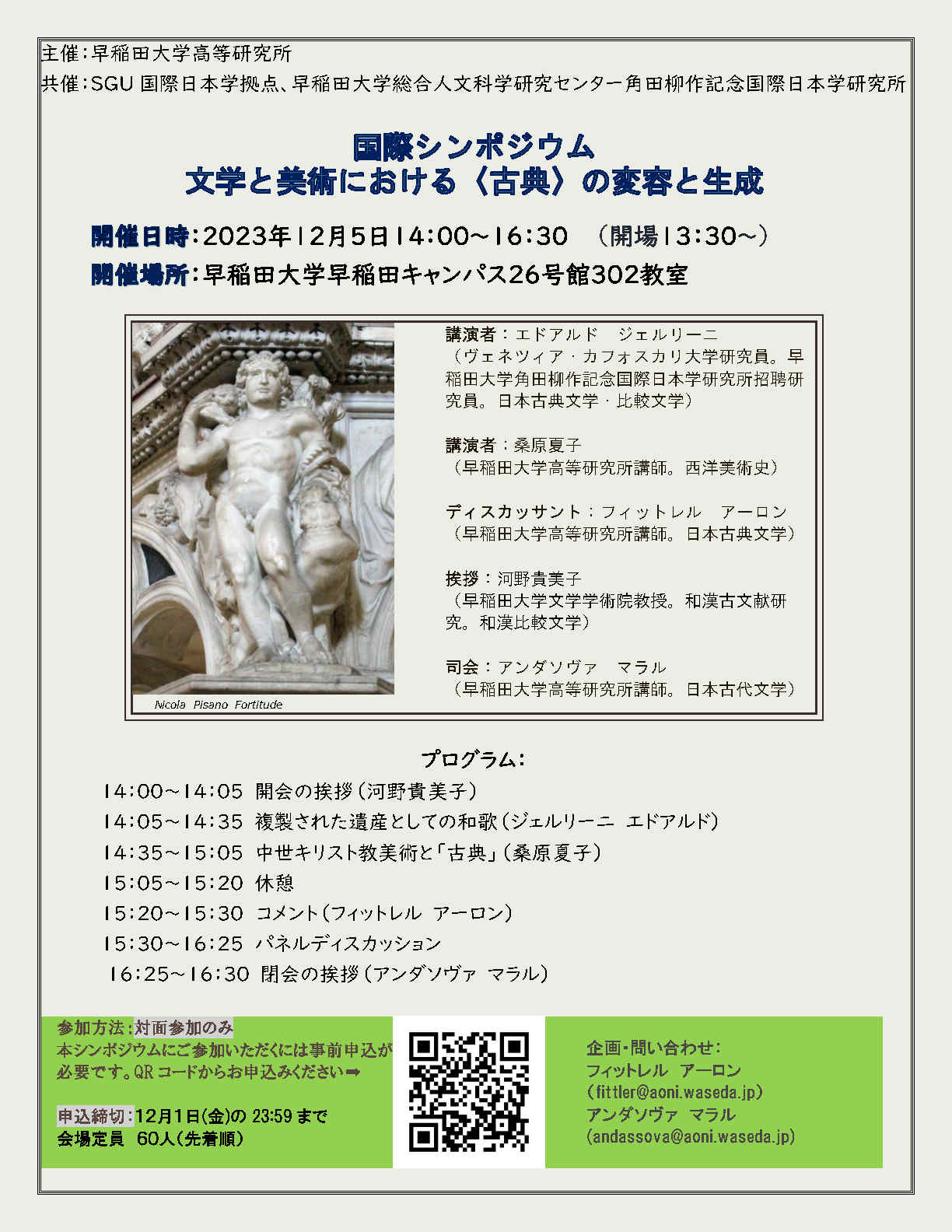
趣旨説明
本シンポジウムでは〈古典〉の在り方について、日本古典文学と西洋美術という広い領域から議論を提供する。〈古典〉と向き合っていた者たちがオリジナリティをどのように捉えていたのだろうか。「原典」を踏まえつつ、それとは異なるものを作る、この過程は単なる再現あるいは複写としてではなく、テクストあるいは美術作品の創造とみることができる。近代的なオリジナルとコピーの概念を離れて、文学と美術における〈古典〉の変容と生成をとらえる視野を示していく。
登壇者
講演者:
エドアルド ジェルリーニ(ヴェネツィア・カフォスカリ大学研究員、早稲田大学角田柳作記念国際日本学研究所招聘研究員)
日本古典文学・比較文学専攻。東京大学、国際日本文化研究センター、早稲田大学にて研究活動やフェローシップを行った。編集には『古典は遺産か?日本文学におけるテクスト遺産の利用と再創造』(勉誠出版、2021年)や『Antologia della Poesia Giapponese vol. 1(日本詩歌アンソロジー)』(Marsilio 2022)などがある。
桑原夏子(早稲田大学高等研究所 講師)
専門は西洋美術史。2018年フィレンツェ大学(Università degli Studi di Firenze)にて博士号を取得。
マックス・プランク美術史研究所(Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max Planck Institut)サマースクール研究員、ロベルト・ロンギ美術史研究財団(Fondazione di Studi di Storia dell’Arte, Robereto Longhi)フェロー、オランダ大学機関美術史研究所(Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut, NIKI-Florence)ポストドクトラル・フェロー、日本学術振興会特別研究員SPDを経て、現職に至る。
「トリエステ近郊ムッジャ・ヴェッキアの聖母晩年伝壁画―イタリアにおける聖母晩年伝図像生成初期の様相の再検討と終末思想との関わり」『西洋中世研究』第8巻、2016年、118―138頁(第1回西洋中世学会学会賞受賞);「ラクイラ近郊フォッサ、サンタ・マリア・アド・クリプタス聖堂北壁装飾研究―聖母晩年伝図像を手がかりに」『美術史』第182巻、2017年、201―216頁(第16回『美術史』論文賞(美術史学会)受賞); 『聖母の晩年―中世・ルネサンス期イタリアにおける図像の系譜』(名古屋大学出版会)(2023年12月刊行予定)
ディスカッサント:
フィットレル アーロン(早稲田大学高等研究所 講師)
専門は日本古典文学。主要業績に「平安時代の和歌と草木成仏説」『国語国文』 88(10)、2019年10月、京都大学、 1~21頁や、「和歌における同音異義表現の物象と人事との間の関連性について」『人文』21号、2023年3月、学習院大学、 47~68頁などがある。
挨拶:
河野貴美子 (早稲田大学文学学術院 教授)
専門は和漢古文献研究。和漢比較文学。共編著に『日本「文」学史』全三冊、勉誠出版、2015~2019年、『古典は遺産か? 日本文学におけるテクスト遺産の利用と再創造』勉誠出版、2021年等がある。
司会:
アンダソヴァ マラル(早稲田大学高等研究所 講師)
専門は日本古代文学。主要業績に『古事記 変貌する世界』ミネルヴァ書房、2014、『ゆれうごくヤマトーもう一つの古代神話』青土社、2020などがある。
日 時
2023年12月5日(火)14:00~16:30
会 場
対面参加のみ(要事前申し込み)
会場:早稲田大学早稲田キャンパス26号館302号室
参加をご希望の方は以下<事前登録フォーム>またはポスターのQRコードからご登録ください。
※事前登録締切:12月1日(金)23:59まで。
※参加者人数が定員(60名)に達した場合は申し込みを締め切ります。
◆会場参加<事前登録フォーム>
言語
日本語
プログラム
| 14:00~14:05 | 開会の挨拶(河野貴美子) |
| 14:05~14:35 | 複製された遺産としての和歌(ジェルリーニ エドアルド): 藤原定家の歌論『詠歌大概』は「情は新しきを以て先となし、詞は旧きを以て用ゆべし」という名句で始まる。ここでの旧き詞とは、三代集、とりわけ『古今和歌集』の歌詞を意味するのだが、その『古今集』もまた、「古」と「今」の歌を合わせてできた作品であるというまでもない。更に、『古今集』の仮名序には『万葉集』の代表的歌人柿本人麻呂を「歌のひじり」として讃美するなど、古歌を復活させながら新しい和歌の時代の開幕を宣言する。 『古今集』や『新古今集』という「古典」は、部立てや本歌取などの技巧及び仕組みを軸に、既存するテクストを複製し、再利用して形成された作品だという共通点がある。その過程を通じて当時の歌人たちは自分の現況と、理想された過去との絆をどのように意識していたのか、それでどのような価値観を正当化しようとしていたのか。一次資料を読みながら、このような過去と現在の緊張感から生まれる遺産と、日本の古典テクストとの関係を検討する。 |
| 14:35~15:05 | 中世キリスト教美術と「古典」(桑原夏子): 西洋美術において「古典」という語が用いられるようになるのは19世紀以のことである。この「古典」という語は、古代ギリシャ・ローマ美術か、またはラファエッロ(1483―1520年)やプッサン(1594―1665年)の作品のように、規範としての価値を持つ美術に対して用いられてきた。中世キリスト教美術は、いくつかの例外を除いて古代ギリシャ・ローマ美術のモチーフを扱うことはなく、その点において「古典」とは親和性を持たないように思われる。しかし、「古典」が「規範とみなされる美術」をも指すことに考えを巡らせたとき、中世キリスト教美術の文脈における「古典性」の存在が浮き彫りとなるだろう。それはまた、19世紀以降の西洋美術をめぐる言説において、何に対して「規範としての価値」が見出され、何が排除されたのかという問題意識とも関わってくるだろう。 |
| 15:05~15:20 | 休憩 |
| 15:20~15:30 | コメント(フィットレル アーロン) |
| 15:30~16:25 | パネルディスカッション |
| 16:25~16:30 | 閉会の挨拶(アンダソヴァ マラル) |
対 象
学部生、大学院生、研究者、教職員
主 催
早稲田大学高等研究所
共 済
SGU国際日本学拠点
早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所
企 画
早稲田大学高等研究所講師 フィットレル アーロン
早稲田大学高等研究所講師 アンダソヴァ マラル








