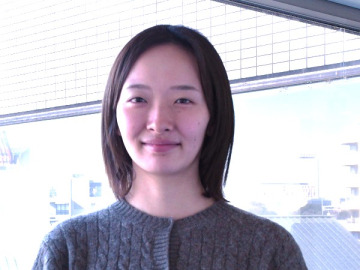高等研究所セミナーシリーズ 【グローバル・ヒストリー研究の新たな視角】 公開講演会:
「幕末維新期における西洋兵学の受容―翻訳兵書の分析視点―」(10/30)
趣旨
日本における近代軍隊の形成は、幕末期に欧米各国からもたらされた兵書の翻訳に依拠する所が大きい。これは天保年間(1830年代初頭)に本格化してから、慶応年間(1860年代後半)に至るまで40年ほど続き、500種類近い兵書の翻訳が行われた。この間、西欧における軍事技術の進歩をトレースする形で、新たな知識を貪欲に吸収していった。同時期の火器(小銃や大砲)についてみると、前装滑腔式→前装施条式→後装単発式→後装連発式といった変遷を短期間で遂げており、それに伴って教練の方式や戦術が目まぐるしく変化した。幕末の日本には、主としてオランダ・イギリス・フランスから軍事知識がもたらされ、各々の翻訳兵書にもとづく兵式が幕府や諸藩の間で雑然と採用された。今回の報告では、こうした翻訳兵書を教練書・戦術書・戦略書というカテゴリーに区分し、幕末維新期の日本でこれらがどのように受容されていたのかを考えたい。
講演者
淺川道夫(日本大学国際関係学部教授)
日本大学法学研究科博士前期課程修了(政治学修士)、同博士後期課程満期退学。日本大学理工学部に提出した学位論文「品川台場における西洋築城術の影響」により、博士号(学術博士)を取得。現職は日本大学国際関係学部教授、軍事史学会理事、編集委員。専門は日本の幕末維新期における軍事史。19世紀の欧米との関係を踏まえた軍制史・用兵思想史のほか、軍事技術史や軍装史なども研究している。
コメンテーター
竹本知行(安田女子大学現代ビジネス学部准教授)
同志社大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程(後期課程)満期退学、博士(政治学)。現職は安田女子大学現代ビジネス学部准教授、軍事史学会理事、編集委員。専門は幕末・維新期の政治史・軍事史。主著に『幕末・維新の西洋兵学と近代軍制-大村益次郎とその継承者-』(2014年)、最近の論文に「長州藩の慶応期軍制改革に関する一考察」『軍事史学』第57巻第1号(2021年6月)。
日 時
2021年10月30日(土)14:00~17:30
会 場
Zoomによるオンライン開催
プログラム
14:00~14:10 開会挨拶(谷口眞子)
14:10~15:10 講演「幕末維新期における西洋兵学の受容―翻訳兵書の分析視点―」(淺川道夫)
15:10~15:30 休憩
15:30~16:00 コメント(竹本知行)
16:00~17:30 討論
司 会
谷口眞子(早稲田大学文学学術院教授)
対 象
大学院生・教員・一般
主 催
早稲田大学 高等研究所
申込み
事前登録が必要です。以下URLよりご登録をお願いします。
https://zoom.us/meeting/register/tJYkd-2vqTooHdWVKa-Rv_FTHNZF-bEc_2aV
ポスター
こちらをご覧ください。