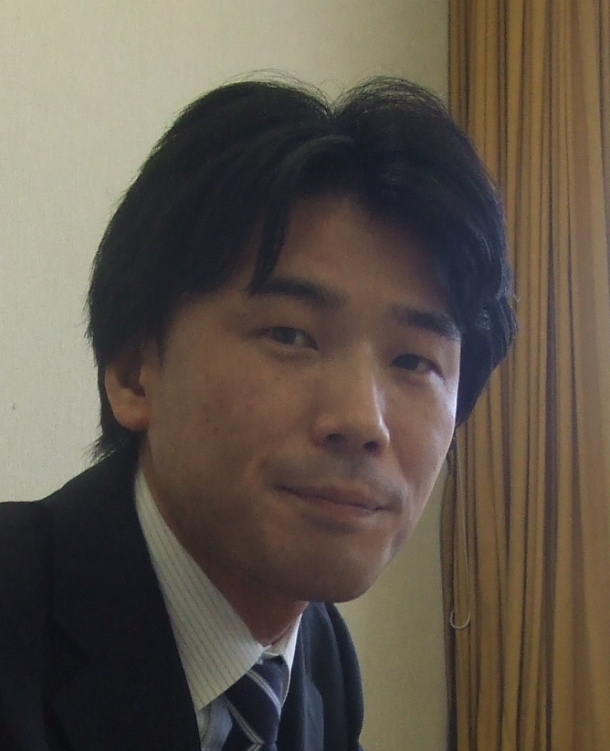
- 川本 真哉(Shinya Kawamoto)助教(2009年6月当時)
「塹壕に身を隠す」経営者
私は経済学を専門に、Entrenchment(エントレンチメント)の実証研究をしています。Entrenchmentは塹壕を意味するtrenchの派生語で、経済学では「塹壕の中に身を隠す」ことから「経営者の保身」という意味で使われています。
経営者の保身と聞いて、思い浮かべる状態は人それぞれ違うかもしれません。私は、企業の業績が悪化しても経営者が何の努力もせずトップに居座り続ける状態を保身と考えています。そのうえで、経営者の保身はどのように生じるのか?経営者が保身に走るとどのような問題が生じるのか?経営者の保身をどうすれば抑制できるのか?など、エントレンチメントに関する諸問題に取り組んでいます。
自分の工夫で“ありきたり”から“新事実”を
もっとも、大学院生になったころは日本経済史、とりわけ産業史に関心がありました。当時は、戦時経済についての研究が盛んで、戦時から戦後への連続性が強調されていた時期でもありました。その風潮から、私も戦時産業、とくに航空機産業に興味を持ちました。戦時期の航空機産業の遺産がどのように戦後の高度成長に寄与したのか、を明らかにしたいという気持ちがあったのです。そこで、財閥解体時に十大財閥の一つとして数えられた中島飛行機の企業経営を調べようと、経済史を専門とする先生のゼミの門をたたきました。
ただ、その研究はあまり長く続きませんでした。歴史家や経済史家の使命は、昔の貴重な資料を発掘し、世の中に広く問うことにあるという考え方があります。それは大切な学問的営みであることに間違いありません。ただ、勉強を進めるうちに、資料やデータがありきたりな内容でも、自分の工夫で新しいことを明らかにできるような研究スタイルに関心を持つようになりました。そこで、文献調査を離れ、計量経済学の手法を用いた実証研究のほうへ転換することにしました。
買収防衛するのも保身から?
博士課程からは、M&A(企業の合併・買収)を題材とした実証研究に取り組み始めました。当時は、経営危機に瀕した企業の救済合併などの友好的買収に加えて、ターゲット企業の経営陣の同意を得ずに経営支配権の取得を目指す敵対的買収が増えてきた時期でした。
法学者の間では敵対的買収やそれに対抗する買収防衛策の是非が論じられており、買収防衛策導入の要因として経営者の保身も指摘されていました。これはとても新しい話題で、数年前までは実証的な研究蓄積がほとんど進んでいない分野でした。そこで私は、関心が集まりはじめた「事前警告型」の買収防衛策に焦点をあて、その導入要因に関する検証をしようと思い立ちました。
事前警告型とは、買収者が大量に株式を買付ける際には事前に対象企業に情報提供するなど、一定のルールをあらかじめ設けておき、そのルールに違反した場合は対抗措置として買付者以外に新株予約券を発行して大量買付者の持株率を下げるといった防衛策です。近年、事前警告型の買収防衛策を導入する企業は急増しており、現在では約15 %もの上場企業が導入しています。
私の研究では、防衛策導入の動機として、①経営者の保身、②従業員(人的資産)の保護、③株主の利害、これら3つ要素が影響を与えているという仮説を立てました。すると、意外なことに株主構成のみが買収防衛策の導入に影響を与えていることがわかりました。それまで議論されていたような経営者の保身や従業員の保護といった観点では説明がつかなかったのです。経営者保身の観点から日本企業の買収防衛策の導入をどのように捉えるのか。ここでの実証結果と照らし合わせ、現実を適切に説明しうるような答えはないか、日々模索している最中です。
保身をさまざまな方面から見据えて
エントレンチメントをメインに研究している研究者は、ほとんどいないのではないでしょうか。そのため、どのようなアプローチで研究していくか手探りの状態です。現在は一次接近的に、経営者の保身に関係する課題にいろいろと挑戦しています。
その一環として昨年は、本学商学学術院の先生と共同で、戦前期の経営者交代に関する論文を書きました。戦前期は、経営者の自社株保有の比率が非常に高かったため、外部からの経営規律が働きにくく、経営者が保身に走るケースが多々ありました。今日でも、ファミリー企業のコーポレート・ガバナンスは、最も注目されている研究分野でもあります。ファミリー企業のオーナーは、自らの努力水準が劣り業績が悪化しているのにもかかわらず、トップの地位に居座る(=エントレンチメント)傾向が強いのか。この問に対する解答を、戦前日本の経営者交代の実態から与えようとしたのが、この論文の目的の一つでした。
また、企業のリストラクチャリングに関する研究も行っています。事業の成長見込みが乏しいにもかかわらず、自らの経営責任を問われるような事業撤退を先送りしているような状況も、経営者保身の目安になると考えるからです。このテーマに関しても、事業売却と企業の収益性、および株式所有構造などの観点から、いくつか論文を発表しました。
保身とは何か?をはっきりさせることが課題
最近の私自身の研究課題として、「エントレンチメント」の定義が弱いという点が挙げられます。買収防衛策を導入しているから、自社株を保有しているから、だけでは保身とは見なせません。会社の業績を含めた総合的な判断が必要です。これは、経営者の保身に関わる研究を行うすべての研究者にとって、共通の課題といえます。
これまでエントレンチメントに関しては、国内に限らず国外の研究者に関しても、それほど明確に定義してこなかったように思われます。“保身”とは何かを具体的に定めて研究者全体のコンセンサスを得ることが、今後、エントレンチメントに関する研究の発展、ひいては一国の経済厚生向上ためにも重要となってくるでしょう。
取材・構成:吉戸智明/伊藤容子
協力:早稲田大学大学院政治学研究科MAJESTy










