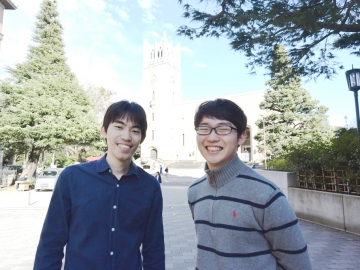活動に対し、何をどう受け止めているのかをあらためて整理することができた
狩り部
教育学部 3年 細原 千聖(ほそはら・ちさと)

2022年2月19日、2021年度ワボプロ報告会「オンライン謎解き 暴走するAIを食い止めろ」が開催されました。ワボプロとは、「早稲田ボランティアプロジェクト」の通称であり、今回報告をしたのは、パラリンピック・リーダープロジェクト、災害ボランティア研究会、Food Glocal Project、狩り部の4団体。各団体が制作した10分程度の動画による活動紹介と報告が粛々と行われるかと思いきや、参加者はその動画からヒントやキーワードを受け取り、さらには団体のTwitterやInstagram、Webサイトをも駆け巡り謎を解くという、積極的な参加が必須となるドラマチックな報告会となりました。ワボプロに所属する団体の活動内容や考え方、取り組む姿勢を楽しみながら垣間見ることができる内容で、参加者からは「謎解きが思ったよりも難しかった」、「楽しんでもらおうとしているのが伝わってきた」などの感想をいただきました。この報告会をきっかけにワボプロへ興味を持った方もいるのではないでしょうか。

私はこのイベントにおいて、狩り部の動画制作に携わりました。掲げたテーマは「活動を通して自分の価値観や考え方はどう巡っていったか」。狩り部は、野生動物と人間の生活との関係のほころびが生々しく出ている「獣害」に対して、少しでも繕うことのできる方法を模索しようと、勉強会や、獣害に難儀している里山へ赴き現地で活動することなどを柱としています。
私自身、わなを仕掛ける手伝いをしたり、捕獲された獣を解体して精肉、調理したりした時に、「命をいただく」ということをひしひしと体感しました。一方で、現地の方と私たち部員との間で命をいただくことに対する感じ方に違いがあったことも大切な気付きでした。また、獣害対策において実はとても重要である、草刈りをはじめとする環境整備の大変さにも驚きました。

狩り部の現地活動(千葉県鴨川市)の様子。猿が木の上から私たちを眺めていました
では、動画をどう組み立てようか。まずは活動を通じて私が感じたことを羅列し、内容を膨らませていきました。しかし、それだけでは個人の感想を取り上げるにとどまってしまい、何か大切なピースが欠けている感覚がありました。そんな引っ掛かりを頭の隅に抱えながらも動画制作を進め、部内で進捗(しんちょく)報告をする際にアドバイスをもらうことに。すると、活動を受けて私の中に生まれた感情や新たな考え方という一面は取り上げていても、活動に向かって私や部員が考えている、「なぜ」にあたる部分に触れていなかったことに気付いたのです。
「なぜ、獣害対策の活動に参加するのか」
何度草刈りをしても数日で元に戻ってしまう夏の耕作放棄地(※)を見て、ここはもう森に返して人間の手から離した方が良いのではないかと考えたり、「撤退の農村計画」という言葉が頭に浮かんだこともあります。ですが、現地の方々の、自分たちの暮らしを慈しみ守っていこうという気持ちや、その土地で生きているという力強さにも深く魅了されていたことをあらためて思い出しました。
(※)農作物が1年以上作付けされず、数年以内に再び作付けする予定のない土地。
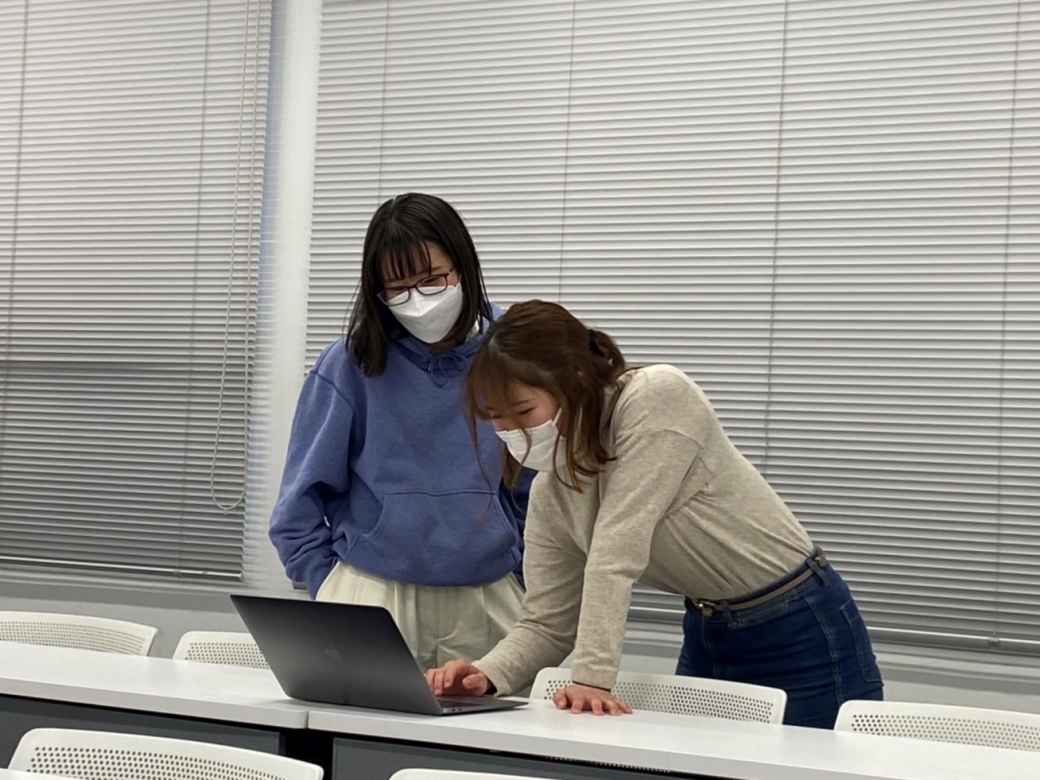
動画を制作している様子
そこで、狩り部の活動には現地の方々の思いが欠かせず、部員はその思いと共に活動していることが伝わるよう、そのエッセンスが動画の初めから終わりまで、川の水よろしく絶え間なく流れるように制作しました。
今回のイベントに参加したことで、私自身を含めた部員が、狩り部の活動に対し何をどう受け止めているのかをあらためて整理することができました。また、イベントを一緒に盛り上げてくれた各団体の皆さんも、それぞれのボランティアに関わる人々の思いと共に活動していることが伝わる動画を発表していて、ボランティア団体に共通するキーワードを見つけられたと感じました。
絵本を読むような動画となりました
※狩り部は2021年度をもってワボプロでの活動は終了し、現在はサークルとして活動しています。