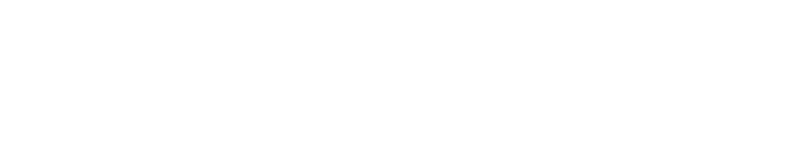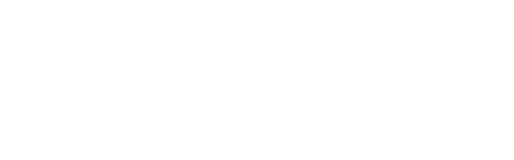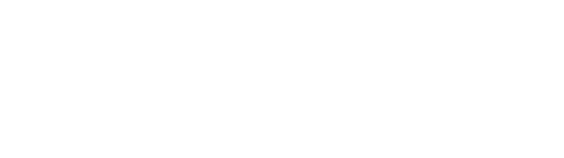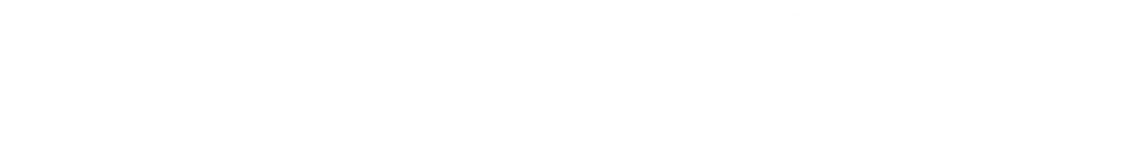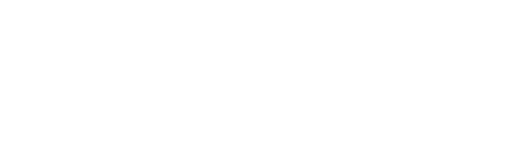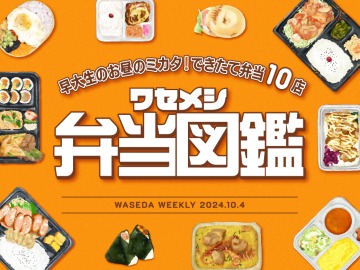大学時代に何度も足を運んだカフェです。足を運びすぎて私の靴底が床を何ミリ削ったか計り知れません。ここにはそうして勝手に床にカンナ掛けをするために来ていたわけではなく、ほとんどはネタを書くために来ていました。
在学中、私は早稲田大学お笑い工房LUDO(公認サークル、以下LUDO)に入っていて、大学3年生からはワタナベエンターテインメントに所属しプロの芸人として活動をしていたことから、学生時代とネタを書くという行為は切っても切り離せないものでした。つらいときも面白いネタが書ければドン底からでも這い上がれるし、評価されれば人生で何よりもうれしいし、当時の自分の中の浮き沈みの全てはネタにガッツリ掌握されていました。
そんな学生時代に注力していた大切なものを支えてくれたのが、こちらのカフェです。コーヒーがおいしいのはもちろんのこと、一番のお気に入りポイントは、店内の2面が大きな窓になっていて太陽の光が注ぎまくるところです。自分を海沿いの店だと思ってるんじゃないかというほど、開放的で気分の上がるカフェです。
- 住所
- 東京都新宿区高田馬場1-33-13千年ビル1F
- TEL
- 03-3208-9037
- 営業時間
- 月~土:7:00〜22:00、日・祝日:7:30〜22:00
- 定休日
- なし