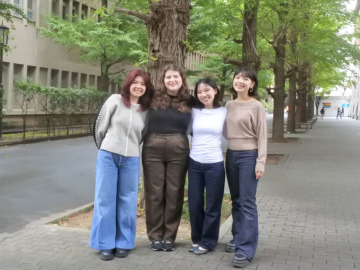「自分たちの声を、判例として後世に残したい」
政治経済学部 2年 二本木 葦智(にほんぎ・よしとも)

早稲田キャンパス 3号館横にて
2024年8月、全国から集まった10~20代の若者たちが大手電力会社10社に対し提起した、国内初の気候訴訟「若者気候訴訟」。その原告団メンバーの一人が、政治経済学部2年の二本木さんです。将来も安定した気候の下で過ごせるよう、さまざまなアクションを起こし続ける二本木さんに、訴訟に至った経緯、活動の根幹となる思い、今後の展望などについて聞きました。
――環境問題に関心を抱いたきっかけと、大学入学前の活動について教えてください。
中学2年生の時、スウェーデン出身の環境活動家であるグレタ・トゥーンベリさんの取り組みを知ったことがきっかけです。それまで、気候変動は少し先の将来の話くらいにしか考えていませんでしたが、各国で気候変動対策がなかなか進まない現状に対して率直に怒りをあらわにしたグレタさんのスピーチに触れ、「こんなに温暖化の問題に関心を抱いている人が同世代にいるんだ」「自分と同じ若い世代が動かなければならないほど重大な問題なんだ」と考えがガラッと変わりました。
出身の早稲田大学高等学院には、部活動や同好会、委員会の他に、学校の公認でありつつも活動の自由度が高い「プロジェクト」という組織があったんです。自分も気候変動に関する活動を何かしたいと思い、「環境プロジェクト」に所属しました。ただ、活動範囲が基本的に学内だったので、次第に政治や社会に強くアプローチする学外活動にも興味が湧き、高校2年生の時に気候危機への対策を求める運動「Fridays for Future Tokyo」に加わって、活動を始めました。これを機に、同じ意識を持った仲間と対外的に自分たちの意見を発信する環境が整い、デモやスタンディングといったストリートでの活動の他、国会議員や官僚、企業の方々と接する貴重な機会が得られました。多様なアプローチで気候変動対策を広めることを意識しており、その方針は今でも変わっていません。

Fridays for Future Tokyoの一員としてデモに参加する高校生時代の二本木さん(右から2番目)。「気候危機はみんなの問題」というプラカードを持っている
――どのような経緯で若者気候訴訟の原告団メンバーに加わったのですか?
自分を含めさまざまな人や団体が行政や立法に訴え続けていますが、依然として日本の気候変動対策は世界的に出遅れており、「なぜ変わらないんだろう」という手詰まり感がありました。そもそも、一般の市民が国政に直接訴え掛けることは制度的な困難も大きいんです。
そこで、もっと司法へアプローチした方が良いんじゃないか、という以前から持っていた考えを実行することに。デモやスタンディングは、メディアに取り上げられなければ歴史に残らないかもしれない。でも訴訟は、判例として残るんです。公害訴訟で市民が勝訴した例は多く、たとえ勝てなくても公的な記録や報道の形で後世につながります。
2024年4月、欧州人権裁判所で「人権を守るために国家は気候変動対策をとる責任がある」と認めた画期的な判決が出ました。これに共鳴して、国内で気候危機に関する運動をしているコミュニティーでも訴訟を起こす機運が高まり、環境系のNGOや市民団体、知り合いの弁護士の方のご協力を得られたため、全国からこの考えに賛同して集まった若者16人で、2024年8月に名古屋地方裁判所で民事訴訟を起こしました。被告は国内最大の温室効果ガス排出源である大手電力会社10社で、排出削減の法的な義務付けと、その義務の履行を求めています。

原告団メンバーと幕を掲げて歩く二本木さん(右から2番目)
――訴訟で直面している困難はどんなことですか?
私たち原告側は、被告の取り組みが不十分であることの立証責任を果たすべく、弁護士の方々と苦心して論を練っています。対して被告側は、私たちにそもそも原告適格(※)がないと主張。この訴訟へ臨むモチベーションが低いようで、被告側の代理人や社員の方が法廷に現れることはほとんどなく、こちら側との温度差に違和感を覚えることも多々あります。
※裁判において訴えを起こすことができる資格のこと。
一方、訴訟という形を選んだことで、Fridays for Future内だけで活動しているときよりも明らかに注目度が上がっていることに手応えを感じています。デモやスタンディングを実施するよりも、裁判傍聴や報告会への参加を呼び掛ける方がたくさんの市民の方に集まっていただけて、裁判傍聴の倍率が2倍近くになったことも。テレビのニュースに取り上げられるなど、メディア取材も増えました。

2024年8月、若者気候訴訟の提訴の際に行われた報告会で、原告として訴訟への思いを語った
――活動にあたって大切にしている考えはありますか?
気候変動対策というと、省エネのためにすごく無理をしなければいけないようなイメージが強いですが、私は、暑い日は冷房を、寒い日は暖房を我慢せず使うのは悪いことではないと考えています。個人が過剰な無理をするのではなくて、例えば、再生可能エネルギーで電力が賄われる環境が整えられ、快適に生活していても環境への負荷が無意識に抑えられるような社会構造が構築されるべきだと思うんです。だからこそ、この訴訟をきっかけに政府や企業が主体となって、気候変動対策に取り組んでいってほしいですね。
――政治経済学部に進学した理由や、学部で学んでいることは何ですか?
当初はテクノロジーという道筋から環境問題に携わることができる創造理工学部に興味があったのですが、環境対策を推し進めるムーブメントを社会に働き掛ける方法について考えるべきだと思い、政治経済学部政治学科を選びました。私が思う政治経済学部の良いところは、データなど数理的な見方で政治を研究しているところです。3年生から所属する尾野嘉邦教授(政治経済学術院)のゼミでは、さまざまな分野を横断しつつ、心理学や統計学などの手法を用いて人間の政治行動を研究したいと考えています。
――今後の展望を教えてください。
社会に何かを訴え掛ける活動には、質も量も求められます。若者気候訴訟ではもちろん勝ちたいですが、自分たちだけでやれることには限りがあり、特に今は活動量が圧倒的に足りていないと感じています。そこで、同じ目標を持った人々が仲間を集めてその輪を広げていくコミュニティーオーガナイジングという手法を自分たちの活動に応用して、もっとたくさんの人が、さまざまな形で環境問題に関わることができるようなムーブメントを起こしたいです。
そのためには、人々により受け入れられやすい伝え方をするべきだと考えています。試行錯誤の一環として、最近はデモやスタンディングでメガホンを使うのをやめてみました。代わりにマイクを手に取り、落ち着いて一人一人に伝えていく。プラカードの内容を工夫し、明るい雰囲気を忘れない。大衆に大声を張り上げて社会に対する意見表明を行うマイナスイメージのステレオタイプを打破し、よりたくさんの人と環境問題に取り組むために、これからも最善を尽くします。

2024年11月15日新宿駅南口にて、政府に対して再エネ推進を求めるFridays for Futureのスタンディングの様子。国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29) にあわせて行われた
第914回
取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)
法学部 2年 金井 秀鴻