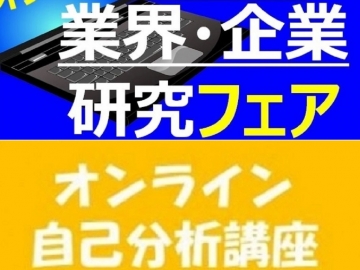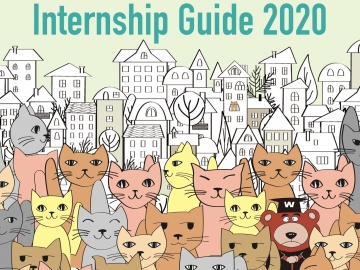1976年兵庫県生まれ。2000年、早稲田大学第一文学部卒業後、IT関連会社と不動産会社にて法人営業を担当。退職後、2009年から1年半、千葉県佐倉市の有機農家にて農業研修を受ける。2011年、農業を志すきっかけとなった大豆「小糸在来」の原産地である千葉県君津市に移住し、農業を始める。
ある地方で長年栽培され、地域の食文化にも根付いた、昔ながらの野菜の品種を総称して“在来種”と呼ぶ。京野菜の賀茂ナスや金時ニンジンなどが有名だ。その在来種をはじめ、風土に即した品種にこだわって野菜作りを行っているのが千葉県君津市の農家・宮本雅之さん。在来種の魅力を知ったのは「小糸在来(こいとざいらい)」という大豆がきっかけだった。
「とある農業イベントで初めて小糸在来の豆ご飯を食べたんですが、それがあまりにもおいしくて驚いたんです。普段、豆の味なんて意識したことがなかったので。その後、いろいろな農家を訪ねましたが、自分がおいしいと感じた野菜には在来種のものがとても多かった」。
在来種が持つ野菜本来の味に魅せられた宮本さんは、2011年に東京から君津へ移住。新米農家として試行錯誤の日々を送っている。「農家になるつもりなんてなかったんです」と話すとおり、以前の宮本さんは、その地に根を張り生きる農家とはまるで正反対、興味の向くままに生き方を模索していた。
転々としていた日々が、農業を介して一つに
宮本さんがまずのめり込んだのは“中国語”。大学では「中国語学習会」というサークルに入り、仲間と熱心に中国語を学んだ。卒業後はIT関連会社に就職するも3年半で退職。一転、デイトレーダーに。その間に並行して、親戚の不動産管理を手伝う中で「宅地建物取引主任者(宅建)」の資格まで取得してしまった。
続いて情熱を注いだのが“天気”。トレーダーとして商品先物取引をするうちに農作物と天気の関係に興味を持った。「大豆の先物取引をしていると、台風の進路が変わるだけで価格が大きく変動するんです。それが面白くて、本格的に気象学を勉強することにしました」。
ここでも持ち前の凝り性を発揮。合格率5%ともいわれる難関を突破し、気象予報士の資格も手に入れた。
「このころ小糸在来と出合い、千葉の有機農園で在来種の勉強をさせてもらいましたが、このときもまだ農家になるとは思いもよりませんでした。妻もそのうち飽きると思っていたみたいです(笑)」。
そう振り返る宮本さんだが、いざ君津での就農を決意すると、以前取得した宅建の知識を生かして土地を購入し、自らの手で家造りを進めていった。そして、種まきや収穫などの作業に気象予報士としての知見が役立っているのは言うまでもないだろう。さらには今年、海外に販路を求めてシンガポールへ。現地で宮本さんを助けたのは、大学時代に学んだ中国語だった。一見、何の脈絡もなかったこれまでのキャリアが、農業を介して一つにつながった。
野菜の多様性とは?“在来種”を広めるために
 現在、在来種の野菜を有機農法で育てている宮本さんは、毎週首都圏の消費者に採れたての野菜を届けている。そんな中、今最も心配しているのが“雄性不稔(ゆうせいふねん)”の問題だという。
現在、在来種の野菜を有機農法で育てている宮本さんは、毎週首都圏の消費者に採れたての野菜を届けている。そんな中、今最も心配しているのが“雄性不稔(ゆうせいふねん)”の問題だという。
「今多くの野菜では、種の生産過程において、花粉が付かない遺伝子異常の株を大量に増やして使用しています。これは自然由来のものではありますが、何万に一つしか出てこないはずの株が膨大な量に増やされ、それが流通のほとんどを占めていることに違和感があります。こうした品種改良のメリットは計り知れないのですが、農産物の種類や、ひいては食文化に多様性がなくなることを危惧しています。その意味でも在来種の野菜をもっと広めていきたいです」。
忙しい消費者のニーズに寄り添うため、野菜を手軽に楽しんでもらえる「にんじんミックスジュース」も手がける。農業は、好奇心旺盛な宮本さんをいまだとりこにしてやまない。