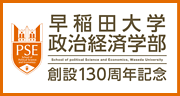研究分野
日本政治史、東アジア国際関係学、国際政治学
学位
- 博士(学術)、東京大学、2009年
略歴
2015年から着任し、15年ぶりに早稲田大学に戻りました。歴史と理論の双方に配慮しつつ、日本とアジアの関係を探求していますが、最近は、和解学の創成という大型科研費のプロジェクトを代表として推進中です。
東アジアにおける歴史問題が、国民感情とそれを支える歴史的記憶そして記憶を選択せしめる価値の問題とが絡まった複雑な現象であることに注目してそれらを研究しています。
授業では、ラクスマン来航時期から、米国による日本占領と米ソ冷戦終結までの日本政治の大きな流れを四つの開国をコンセプトに、大きくとらえられるための概念と能力の育成を主眼としています。グローバルヒストリーも担当し、国民という集団や近代国家自体の歴史性にも理論的に焦点を当てています。
最近の研究テーマとしては、敗戦で失われた東アジアという地域を、平和や民主主義という新しい価値を基盤としながら、いかに再生することができるのかを、経済協力の歴史を焦点に問い続けたいです。
詳しくは、『帝国日本の植民地法制』(名古屋大学出版、2008年)と、『戦後日本の賠償問題と東アジア地域再編―請求権と歴史認識問題の起源―』(慈学社、2013年)をぜひ、ご覧ください。帝国の法秩序の上に存在していた「いのち」や「権利」を、条約と国内法の上に置き換えていく作業こそが、国交正常化であり、また、占領であったことを論証してきました。
こうした成果の上に、現代とのつながりを歴史のみならず、構築主義的国際関係学とナショナリズム研究を踏まえながら研究していきたいと思っています。