- News
- 研究部門「東アジアの人文知」共催◆国際シンポジウム「新世紀:越境する東アジアの文化を問う—カルチュラルスタディーズ・文学・サブカルチャー・そして人々の心—」のお知らせ
研究部門「東アジアの人文知」共催◆国際シンポジウム「新世紀:越境する東アジアの文化を問う—カルチュラルスタディーズ・文学・サブカルチャー・そして人々の心—」のお知らせ
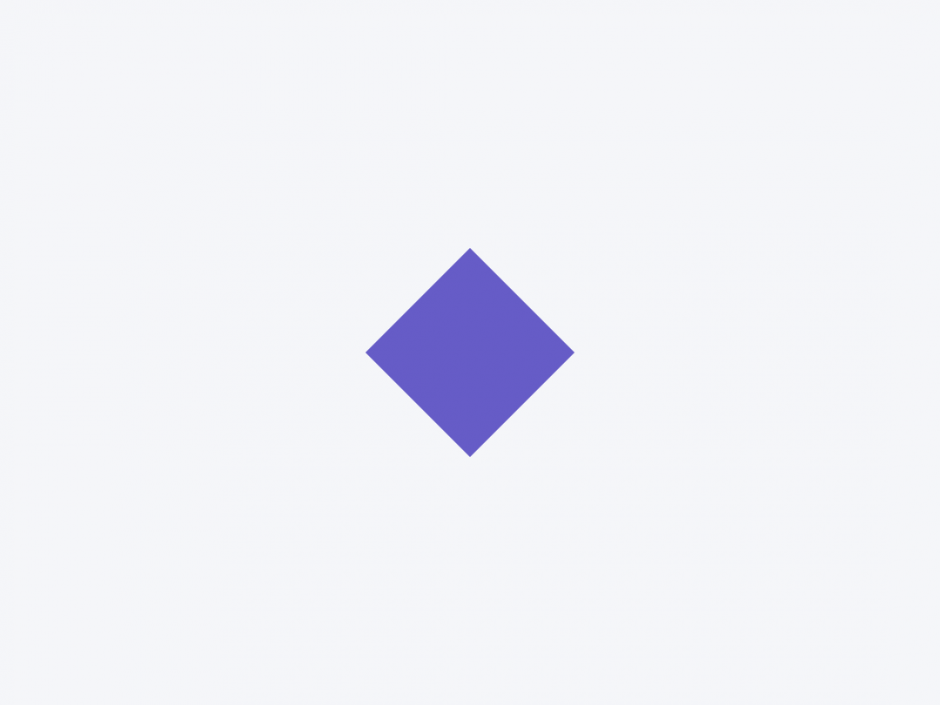
- Posted
- Thu, 09 Mar 2017
国際シンポジウム
新世紀:越境する東アジアの文化を問う
—カルチュラルスタディーズ・文学・サブカルチャー・そして人々の心—
主催:私立大学戦略的基盤形成事業第2グループ
共催:総合人文科学研究センター研究部門「東アジアの人文知」
中国現代文化研究所
開催日:2017年3月18日、19日
場所:早稲田大学戸山キャンパス33号館3階第1会議室
プログラム:
3月18日午後:
第1部:文化研究(カルチュラル・スタディーズ)の来し方行く末
13:00 開会の挨拶 千野拓政 (日本 早稲田大学)
13:10〜14:00 問題提起 千野拓政
この30年間東アジアの文化に何が起こってきたのか?
14:00〜15:00 王暁明(中国 上海大学)
「利」の先行する時代と向き合って:中国のカルチュラル・スタディーズ
15:00〜16:00 Meaghan Morris(オーストラリア シドニー大学)
誰が美的相違に心を配るのか?−−危機の時代のカルチュラル・スタディーズ
16:00〜16:15 休憩
16:15〜17:15 毛利嘉孝(日本 東京芸術大学)
ポストメディア時代の文化研究:2010年代の日本のメディア文化と政治
17:15〜18:45 パネルディスカッション 司会:千野拓政
3月19日午後
第2部:混迷する思想に向けて
12:00 第2部の説明 千野拓政
12:05〜13:05 賀照田(中国 社会科学院)
今日の中国における精神的困難、その歴史と思想的背景:一つの要点整理
13:05〜14:05 李南周(韓国 聖公会大学)
民主化大闘争(1987年)からキャンドル闘争(2016・17年)に至る思想状況の変化
−革命のディスコースを中心に
14:05〜14:20休憩
14:20〜15:50 パネルディスカッション(全員)司会:千野拓政
15:50〜16:00 休憩
第3部:文学とサブカルチャーのはざまで
16:00 第3部の説明 千野拓政
16:05〜18:00 トークセッション:上田岳弘(日本 作家)、笛安(中国 作家)
陳栢青(台湾 作家)
司会:小沼純一(日本 早稲田大学)
18:00〜19:00 パネルディスカッション(全員)
19:00閉会の辞 千野拓政
要旨
1980年代以来、グローバリゼーションの進展とともに、文学・映像・演劇・音楽・サブカルチャー(マンガ・アニメ・ゲームその他)など、あらゆる文化の領域で、それまでと大きく異なった状況が生まれてきました。
その一端は、例えば、テクストの読み方(見方・聞き方)の変化などに現れています。文学に関連する領域では、若い読者を中心に、ストーリーや作品の思想・文体とともに、キャラクターがテクストを読む(見る)上で重要な要素になりつつあります。それは、読者が作品に求めるものが変化しつつあることを物語っています。言い換えれば、作品と読者・視聴者の関係が変化しつつある訳です。そして、その背景には、若者たちの強い閉塞感や疎外感が横たわっているようなのです。しかも、そうした現象は、日本のみならず、東アジアさらには世界各地に共通して見られるようになっています。
2010年代後半を迎え、貧富の差の拡大、テロ事件の頻発、民族紛争や難民の激増など、世界中で混迷が深まる中、人々の閉塞感や精神的危機がますます広がっているように見受けられます。そうした状況の広がりは先に見た文化や社会の変化と決して無縁ではありません。だとすれば、この大きな状況の転換を、わたしたちはどのように捉えるのでしょうか。また、その背景にある社会状況、精神状況の変化にどのように切り込むことが可能なのでしょうか。
そうした問題意識から、2015年度を皮切りに、毎年、世界から文化の創造・研究に携わっておられる方をお招きして、語り合う企画を進めています。昨年は、東アジアに共通する文化現象の起源となった1980〜90年代のサブカルチャーについて、音楽・マンガの創作や、文化批評に携わって来られた方々をお招きし、日本のみならず韓国や中国も含めて当時の状況について語り合っていただきました。
今年度は2000年から現在に至る東アジアの状況について、語り合っていただく機会を設けたいと考えています。議論は三つのパートに分かれています。
一つは、文化研究(カルチュラルスタディーズ)についてです。文化研究は新たな文化状況に切り込む方法の一つとして発達してきました。しかし、東アジアの文化研究の発達は、欧米と異なる文脈をたどっています。文化研究は新たな文化状況にどのように切り込んで、あるいは切り込めずにきたのでしょうか。それぞれの地域で文化研究が歩んできた道、抱えている課題、これからの展望などについて、中国、オーストラリア、日本から現場で研究に携わってこられた方々をお招きして、語り合っていただきます。
二つ目は、文化的・社会的変容の背景にある精神状況・思想状況についてです。今日、東アジアは緊張が高まり、それぞれの地域で人々の精神状況・思想状況は混迷を深めているように見受けられます。しかし振り返ってみれば、1980年代の東アジアは精神的には比較的開かれた空間がありました。日本では高度経済成長が終わって人々の目が社会や精神生活に向き、中国では改革開放の進展とともに自由・平等・民主などが語られ、韓国では民主化が一気に進んで日本の大衆文化が許容され、未来の希望が語られた時代でもありました。今日の文化・社会状況の背後にある精神的・思想的な混迷をどのように捉えるのか、中国、韓国、日本から思想の現場で活躍してこられた方々をお招きして、語り合っていただきます。
三つ目は、文学とサブカルチャーについてです。文化の問題を考えるうえで最も重要なのは、創造と受容の現場です。中国、台湾、日本から、文化の変容を目の当たりにしてこられた、80年代生まれの若い作家の皆さんにお集まりいてだき、それぞれの地域の文学やサブカルチャーをめぐる状況や、その中での創作が抱える課題などについて語り合っていただきます。
今回の試みが、混迷する現在の世界を見つめ直し、理解する小さなっきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。
すべて通訳あり
お問い合わせ:千野研究室 e-mail:[email protected]
phone&fax:03-5286-3695
