- News
- 【開催報告】GenTime プロジェクトへの招待:時間構造からみた東アジアと欧米諸国のジェンダー不平等
【開催報告】GenTime プロジェクトへの招待:時間構造からみた東アジアと欧米諸国のジェンダー不平等

Dates
カレンダーに追加0506
SAT 2023- Place
- 早稲田大学戸山キャンパス33号館3階第1会議室
- Time
- 15:00〜17:15
- Posted
- Mon, 31 Jul 2023
早稲田大学戸山キャンパスにおいて、「知の蓄積と活用にむけた方法論的研究部門」の主催により2023年5月6日にMan-Yee Kan(https://www.sociology.ox.ac.uk/people/man-yee-kan)氏(オックスフォード大学教授,社会学)による研究会が開催されました。司会には長年にわたり生活時間研究を続けてこられ、現在IATUR(国際生活時間学会)の理事でもある水野谷武志(https://econ.hgu.jp/teaching-staff/list/profile-takeshimizunoya.html)氏(北海学園大学教授,経済学)をお招きしました。ゴールデンウィーク期間中の土曜日にもかかわらず、全国津々浦々から多彩な分野の専門家が数多く参加し、活発な議論が交わされました。

Kan氏は生活時間を中心に、ジェンダー不平等や結婚、家族と社会政策などを包括的に研究されており、現在は東アジア4カ国と欧米12カ国を比較する大規模な研究プロジェクトGentime(https://www.gentime-project.org)を組織しています。プロジェクトの期間は2018年から2026年で、ほぼ中間で区切りにあたる今年度は、日本でサバティカル期間を一部過ごされています。研究者の方々と議論、交流を含めるよい機会でもあるとのことで、研究会が急遽企画され実現に至りました。
研究会では、初めにGentimeプロジェクトの概要が説明され、これまでの研究で明らかになったことが2つの論文からわかりやすく紹介されました。最後には、今後の研究にむけた計画および協働可能性についても報告がありました。生活時間研究は社会政策を立案する基礎的データとして欧米ではかなり中核的な領域を占めていますが、日本ではさほど広範に用いられている状況にはありません。世界共通の企画で行われていない調査データに頼らざるを得ない大規模な国際比較プロジェクトについて、データを比較可能とするための地道な処理“Harmonisation”が重要な鍵となります。その苦労が語られるなかでは、特に日本データのアクセスと比較しにくさについて言及もあり、国際比較研究の難しさを乗り越えた貴重な分析結果が報告されました。
結論の一部を簡単に紹介します。有償労働と無償な家庭内労働(家事やケア行動、買い物等)の時間変化に関して、3つの期間(1985-1996、1997-2007、2008-2016)で区切ると、ジェンダーギャップの解消が全ての国々で漸進したわけでないと明らかになりました。特に直近の区間では日本を含むいくつかの国ではジェンダー平等化が足踏みをしているとのことです。分析の進んでいる欧米の社会福祉レジームを保守主義(フランス、オランダ、オーストリア、ドイツ)、南欧(イタリア、スペイン)、社会民主(ノルウェー、デンマーク、フィンランド)、自由主義(カナダ、イギリス、アメリカ)と4区分した上で、東アジアの国々は個別に分析されています。とりわけ日本と韓国ではジェンダーギャップの解消が極端に遅く、同じ東アジアでも北京(中国の一部として)と台湾が欧米の自由主義国と同様な収束を見せているのと対照的だそうです。世界の趨勢としてのジェンダー不平等の変化には文化や社会規範、そして政策が全て関わっており、家族は特に南欧や日本・韓国でケアの供給のためにあてにされ続けています。最後に、日本・韓国2カ国の根強い男性の長時間労働がバリアーとなっている現実が、シンプルに指摘されました。
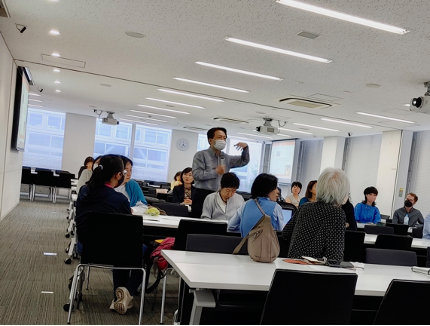
もう1つの論文は未発表のためここでの記録は割愛しますが、1992年から2019年にかけてのイギリスのパネルデータを用いた研究で、結婚や出産に伴う男女の時間配分変化に関する興味深い変化が語られました。質の高い社会調査が持続的に行われ、学者が分析をし結果が政策に生かされていくという確固たるサイクルの存在に、イギリスの学問における実証の伝統と奥深さを感じさせられます。われわれの部門が関心を向けている「知の蓄積と活用」の今後を考える上で示唆的であったと思います。やや予定時間を過ぎてもフロアからは活発な質問が相次ぐなかの閉会となりました。交流会場に移動した後も、学術を含む議論と対話が続き、Kan氏のお人柄と参加された方々の個性が作り上げた濃厚な研究会であったと振り返ります。(記:品田知美 招聘研究員)
開催詳細
- 日時:2023年5月6日(土)15:00-17:15(JST)
- 会場:早稲田大学戸山キャンパス33号館3階第1会議室
- 参加:学生(学外)、研究者(学内外)
- 使用言語:英語、日本語
- 参加費:無料
- 主催:早稲田大学総合人文科学研究センター「知の蓄積と活用にむけた方法論的研究」部門
