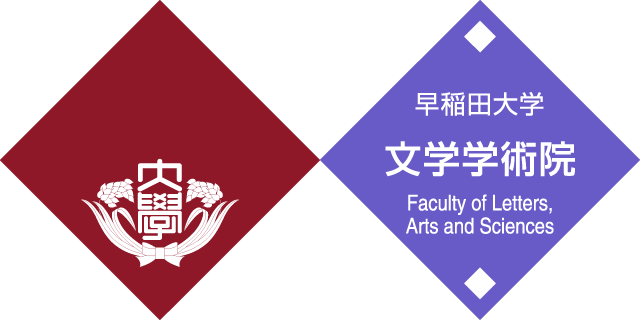- Student Report
- Shogo Enokido Cultural Sciences Japanese Studies Graduate School of Letters, Arts and Sciences
Shogo Enokido Cultural Sciences Japanese Studies Graduate School of Letters, Arts and Sciences
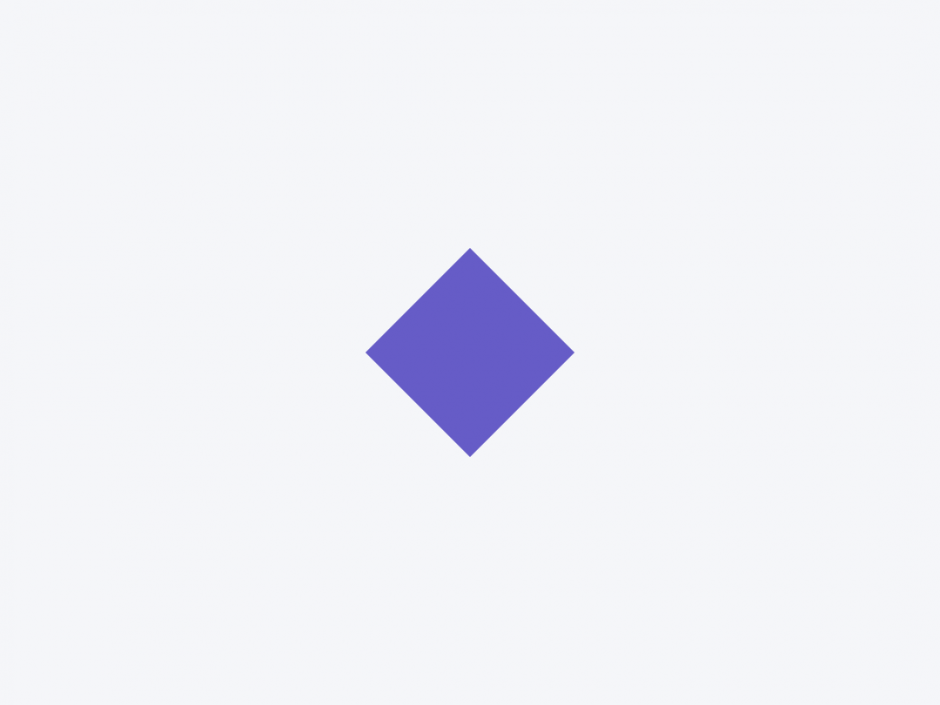
- Posted
- Thu, 13 Apr 2023
The Tadashi Yanai Initiative for Globalizing Japanese Humanities
UCLA-Waseda Research Fellowship Program Report
Shogo Enokido
4th year student, Doctoral Program
Cultural Sciences Japanese Studies, Graduate School of Letters, Arts and Sciences
この度、柳井正イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクトによって、UCLAのThe department of Asian Languages and Culturesに3か月の間(2023年1月〜3月、Winter Quarter)留学する機会を得た。現地ではUCLAの学生とともに授業を受けながら、博士論文の執筆を進めた。
現地では、UCLAの大学院生用の寮(個室)に滞在しながら、週3日ほど大学に出かける生活であった。授業は1コマ3時間弱であり、予習がそれなりに求められるため、授業のない日は予習と自身の研究で手一杯というスケジュール感である。
授業は、嶋崎聡子先生による古文を英語に訳すという演習と、私と同じ期間日本からいらしていた木村朗子先生による現代文学の講義に出席した。ほかに、授業とは別に、トークィル・ダシー先生とダシー先生のゼミ生との3人で『萬葉集』の講読を行っていた。
一点残念だったのは、今季は私の専門である古典文学の授業がほとんど開講されていなかったことである。古典文学について日本の研究手法とは異なる視点を学びたいと思っていたのだが、授業という形ではそれは叶わなかった。とはいえ、ほとんど読んだことのなかった現代文学作品について、研究手法や考え方を学べたのは大きな収穫であった。さらに、木村先生には研究者としてのキャリアについてや、研究会や海外の学会の情報についても教えていただけた。
授業は、嶋崎先生のものもダシー先生との講読も基礎的な事柄を扱っていたため、私にとっては基礎の確認という側面が強かった。そのため、UCLAの授業によって新たに視野を広げていったいうよりは、留学したことによる時間的な余裕(私は日本では働きながら大学院に通っている)と学生との交流によって、自身の研究やキャリア、アメリカの研究事情についての知見を深めていくことができたと言えると思う。
UCLAでの3か月の滞在は、授業を通してなにかを学ぶというよりも、人との交流によって能動的に情報を得ていくことを期待して行ったほうが良いと感じた。特に、現地の学生と関係が持てたことは大きく、今後の研究活動につなげていける可能性に満ちたものであると確信している。また、現地の大学院の仕組みは日本とは全く異なるものであるため、そういった点を目の当たりにできたことも大きな収穫の一つである。
たった3か月ではあるが、現地の教員や大学院生との関係を作れるという点は、自身の研究に有益なだけでなく、今後研究者として就職するということを考えても、様々な面で恩恵は少なくないものと思われる。
私は英語がほとんど話せない状態で滞在したが、現地の大学院生の親切なサポートのおかげで拍子抜けするほど普通に生活することができた。当プログラムに応募するか悩んでいる学生は、環境が許すならばぜひともチャレンジすることをおすすめする。