- その他
- 凸記号・浮き出し文字・触知記号の触知容易性評価~触覚を活用したアクセシブルデザインの実践~
凸記号・浮き出し文字・触知記号の触知容易性評価~触覚を活用したアクセシブルデザインの実践~
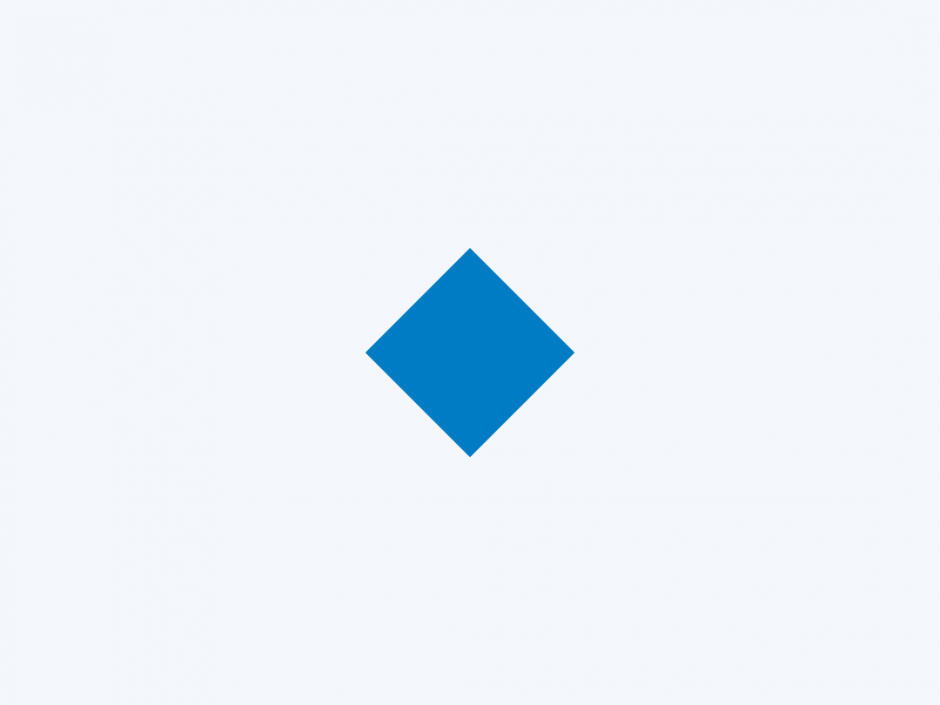
- Posted
- Fri, 16 Apr 2010

研究代表者
藤本 浩志
FUJIMOTO Hiroshi
人間科学部教授
本プロジェクトの概要と目的
我が国をはじめとする世界的な高齢者・障害者の増加によって、幅広いユーザーにとってアクセシブルな社会環境・製品設計(以下、アクセシブルデザイン)へのニーズが高まっている。このような背景を踏まえて、国際機関とりわけ環境整備や製品設計にかかわるガイドラインを定める国際標準機構(ISO)においても、日本を中心にして提案されたアクセシブルデザインという概念が現在国際標準(IS)の中で認められ、その概念に基づいてその後に制定された個々の国際規格とともに世界的に普及しつつある。
国内ではバリアフリー新法の制定(2006年)によって公共施設の分かり易いサイン看板や音声案内システム、触知案内図が設置されつつあり、多くのメーカーが製品の操作性に関して高齢者・障害者配慮を積極的に行うようになってきた。
しかし、視覚や聴覚を活用した高齢者・障害者配慮が主であり、情報入手障害とも言われている視覚障害者への配慮の観点から、第3の感覚器である触覚を有効に活用していくことが求められる。実際に、公共施設案内の触知案内図や家電製品の操作部への凸記号、エレベーターのボタンの浮き出し文字、触知記号等少しずつ増えていきている。
そのような背景には、触知案内図や凸記号に関する表示法の標準化がなされていることも大きく関係している。申請者は触知案内図の表示法の日本工業規格(JIS)検討委員会の委員長としてJIS制定に寄与しており、現在では凸記号の表示法(例えば、携帯電話の5番キーに付される凸点)に関する国際標準(IS)の提案者としてISOの委員会において制定に向けて議論を進めており、浮き出し文字・触知記号に関する新たなJIS制定に向けても積極的に取り組んでいる。
しかし、JISやISの検討の際には、ヒトの皮膚感覚特性に基づく人間工学的な客観的なデータが必要である。具体的には、凸記号や浮き出し文字・触知記号に関する触知覚特性を明らかにする必要がある。
そこで本研究では、凸記号や浮き出し文字・触知記号と触知し易い各寸法の関係に明らかにすることを目的とする。本研究により得られる知見は、それぞれの標準化の議論の際の有用なデータになると共に、視覚・聴覚に対して不足する触知覚の知見として学術的にも価値が高い。また、触覚による情報入手支援の進展という観点から、また、より良き生活の実現を支援する意味からも、本学術院が目指すwell beingの実現に向けた研究プロジェクトとして、人間科学の学際領域で取り上げていただきたい研究課題と考えている。
研究構成員
- 藤本 浩志(早稲田大学人間科学学術院教授)
- 土井 幸輝(国立特別支援教育総合研究所研究員)
- 和田 勉(社会福祉法人日本点字図書館課長)
プロジェクト期間
2010年4月~2013年3月
- Tags
- 研究活動
