- その他
- 環境資源の持続的活用
環境資源の持続的活用
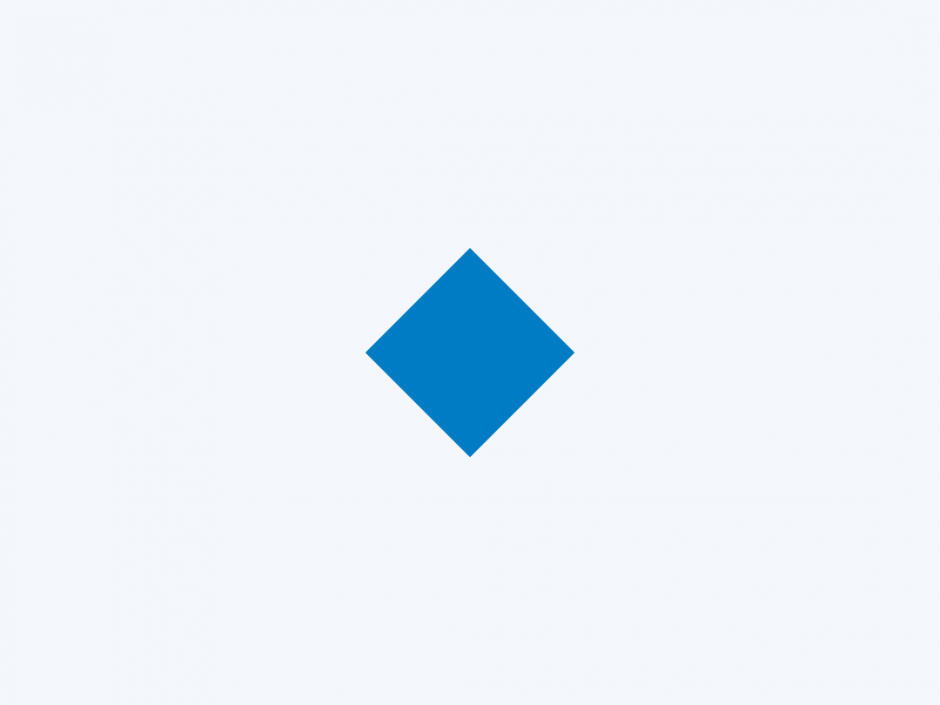
- Posted
- Fri, 16 Apr 2004

研究代表者
天野 正博
AMANO Masahiro
人間科学部教授
本プロジェクトの概要と目的
-
世界人口の60%を占めるモンスーンアジアでは、人間活動の進行にともない、炭素の重要な貯蔵庫である森林資源が大幅に減少し、それに伴って大量の地球温暖化ガスを排出している。しかし、本来は森林は光合成により大気中の炭素を固定する機能を有しており、新規植林や再植林を進め森林生態系中の貯蔵する炭素量を増加させるとともに、そこから生産する木材も長期的な炭素貯蔵庫の役割を果たしている。そのため、無秩序な森林伐採ではなく、木材需要を見込み、計画的な管理にもとづいた新規植林や再植林によってどれだけの炭素を長期的に固定できるかは非常に重要なテーマであり、その定量的な評価を行う必要がある。木材需要の観点では、木材のような重量産物を運搬する際のエネルギー効率を考慮すると地域で生産し同地域で利用することが最も効率がよい。アジア諸国に対して、日本からの資金的・技術的な援助を行うためには、建築部材に対する木材利用の現状を把握する必要がある。また、日本国内の需要を高めることも重要である。とくに、大規模構造物が多い公共施設等に、積極的に木材を利用する方策の検討が求められている。
2004年度から2005年度中盤において、1. モンスーンアジアの森林による長期的炭素貯蔵量の定量化、2. 人間活動によるその低下量の概算、を行う。構築環境への木材資源の積極的利用による炭素固定量を見積もるために、3. アジア諸国内の建築物への木材利用実態の調査、4. 国内外の木材利用のための技術の調査・整理(構造技術、火災安全技術)を行う。とくに従来は内装材としての木質バイオマスの利用研究が多かったが、構造材としての木材活用への防災面等の問題の整理とその実現可能性を評価し、構築環境での炭素固定量の試算を行う。
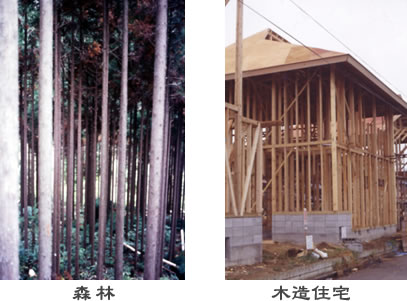
- 森林を中心とした陸域の炭素固定の定量化は社会からの要請も極めて高く、成果の還元は非常に具体的である。京都議定書の実行を考慮すると数年以内に結論を出さざるをえず、人間社会の経済システムに与える影響は大きい。また、京都議定書の第2約束期間から木材の固定している炭素についても評価する国際交渉がすでに始まっており、IPCCでも各国が利用している木材の増加に伴って炭素貯蔵量がどれだけ増えたかを報告するためのガイドラインは2005年から整備が開始される。国土交通省の木質ハイブリッドプロジェクトも技術開発中心に同様の観点から研究を推進しようとしている。このような国内外の研究状況からも本研究プロジェクトは今日的、中心的な話題を提供することになる。本プロジェクトでは森林の炭素固定量や安全な構築環境の形成のための建築、都市基盤整備の在り方を提案し、吸収源としての森林や構築環境の科学性、透明性を高めていくことを目的とする。
プロジェクト期間
2004年4月~2007年3月
- Tags
- 研究活動
