- その他
- 生活・生命支援機器との共生
生活・生命支援機器との共生
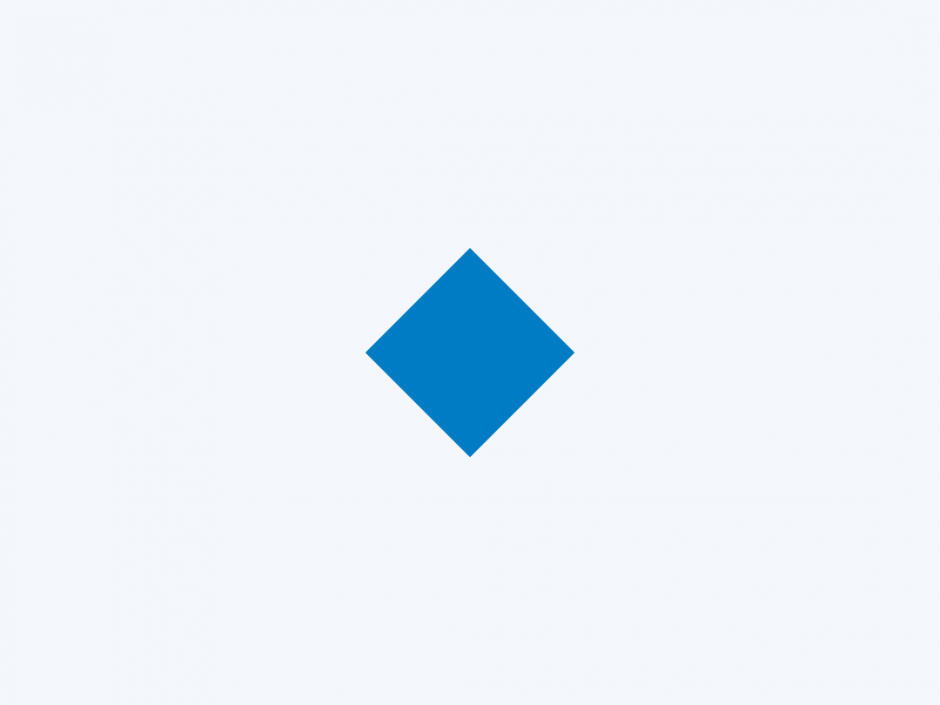
- Posted
- Fri, 16 Apr 2004

研究代表者
藤本 浩志
FUJIMOTO Hiroshi
人間科学部教授
本プロジェクトの概要と目的
現在我が国が直面している問題の一つに急激な高齢化があげられる。この速度は欧米先進諸国と比較しても群を抜いており、さらに少子化の傾向と相まって超高齢社会が目前に迫っている。増え続ける高齢者が自立して生き甲斐のある生活を送れるということはそれ自体が高齢者のQOLの向上に資するばかりでなく生産活動に従事できる人口の増加につながり、他方では高騰する医療費を抑えることにもなり社会全体のコスト削減の観点からも火急の問題である。
高齢者の自立ために支援すべきステージは、生命支援・日常生活支援・社会参加支援の3段階に大別され、この順に『医療機器』から『福祉機器』の性質が強くなり、QOLの向上と対応している。これらの支援の実現に向けては、人的資源によって支えられる社会保障制度からのアプローチの重要性は言うまでもないが、少子化による介護人口の不足を補う意味からも適切な支援用具や機器の開発も不可欠である。本プロジェクトでは、主に後者の機器開発の立場からQOLの向上を目指して、上記の3段階の支援ステージを縦糸とし、それぞれにおけるユーザと機器との関係を横糸とし、各々のステージで適切な機器によって支援された状態を『新たな共生システム』として捉え、ユーザにとって適切で有用な用具や機器を今後開発するうえでの可能性や問題点を様々な観点から検討する。

共同で研究開発を行うプロジェクトとしての支援ステージの考え方に基づいて『医療機器』と『福祉機器』の2グループを構成する。
医療機器グループでは、従来から医療機器のナショナルプロジェクトとしても取り上げられている人工心臓の研究を行う。共生という考え方から、ハードウェアを開発する研究者や、循環器の特性の計測・評価に関する研究者等の多岐にわたる領域からメンバーを構成し、適合性の高い人工心臓の開発を目指すうえでの問題点を検討する。
また医療機器と福祉機器との境界領域と位置づけられる機能代替およびリハビリテーション機器分野のテーマも取り扱う。要介護人口を抑える目的から、寝たきりやそれにつながる転倒を予防する方策の重要性と必要性が指摘されている。そこで二足歩行時における転倒原因の検討をはじめ、実際に怪我や病気により下肢運動機能に障害を持った際に自立歩行機能を再獲得するためのリハビリテーション支援機器の開発を目指すうえでの問題点を検討する。
福祉機器グループについては、まずヒトが外界からの得る情報の8割を占めるとされている視覚機能に障害を持つ人たちの自立支援を考える。情報入手手段として点字や触図等に代表される皮膚感覚を介した感覚機能を代行する支援機器の可能性を検討する。
プロジェクト期間
2004年4月~2007年3月
- Tags
- 研究活動
