- その他
- 子どもとおとなの新たな共生システム:大学と現場の連携による模索
子どもとおとなの新たな共生システム:大学と現場の連携による模索
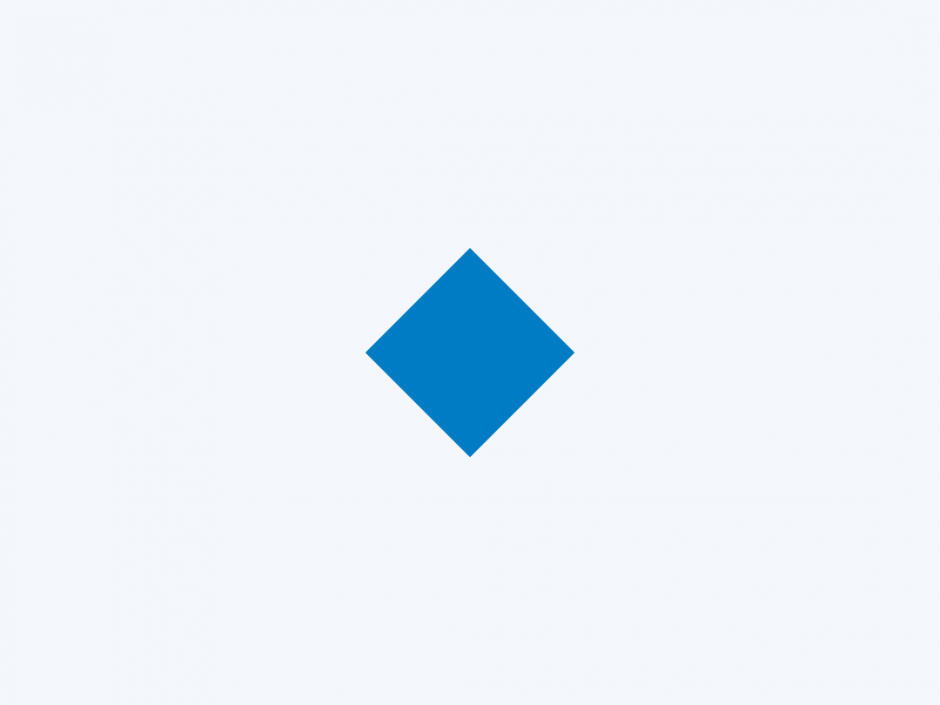
- Posted
- Fri, 16 Apr 2004

研究代表者
根ケ山 光一
NEGAYAMA Koichi
人間科学部教授
本プロジェクトの概要と目的

子どもと大人は社会において共生システムをなしているが、それは今日必ずしも調和的なものであるとは言い難い。そのあるべき姿を模索するには、単に親子関係だけでなく、子どもが育つ地域や環境・制度といった人的・物的要因を総合的に視野に入れて考察する必要がある。
本研究プロジェクトでは、子どもと大人の共生の舞台として特に「保育」に焦点化して、保育園と家庭・地域の関係を現場と連携して調査し、そこで生じる子どもと大人のコンフリクトや調和・相補性などについて考察するとともに、今後のあるべき保育の仕組みについても検討を加えることを目的とする(概念図参照)。
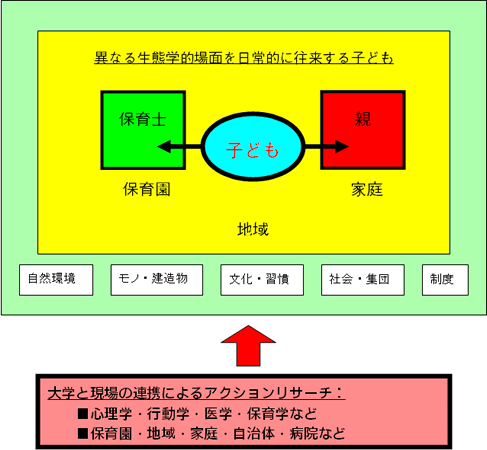
保育は大人が子どものために用意したモノ・ヒト・コトのシステムであり、それは家庭や保育園、あるいはそこで行われる子育て支援や地域交流といった具体的な場で実践されている。しかも子どもは、単に個々の場面にばらばらに曝されているわけではなく、それらの場面間を日常的に往来している。したがって、子どもと大人の共生システムを正しく理解するには、その間の移行を十分視野に入れなければならない。
従来このようなダイナミックな観点は乏しかったが、保育園と家庭・地域という現場を積極的につなぎ、その間を移行する子どもの姿を見つめるという観点を堅持することが本研究の大きな特色である。子どもは保育園と家庭・地域を日常的に往復する中で、それらの場の連続性と断続性にさらされ、行動の調節・適応に迫られる。ところが個々の場にいる大人たちはもう一方の場について十分知り得ず、それが子どもに様々な不整合を生じさせている可能性がある。研究者はそれを俯瞰し、両者をつなぐコーディネーターとして、それぞれの場での子どもを均等に見て対応づけ、その知見をそれぞれの場の大人に返し、それぞれの場からフィードバックを得て再検討を加え、さらにその成果を元に提案を出すといった役割を期待されている。ここには、研究活動以外に現場の大人への啓蒙や広報活動も有機的に絡みあう。
この活動は、家庭・地域・行政と大学とのinteractiveな展開を想定した、アクションリサーチというべきものである。本研究は、保育における子どもと大人の共生という視点を共有する心理学・保育学・教育学・体育学・医学・環境学の諸研究者が協力し、保育園と家庭という具体的な保育の場との連携を通じて、地域に開かれた大学としての役割を模索しようとする試みの端緒である。今後は医療・教育や子育て支援の状況も視野に入れて、より広い見地から大人と子どもの共生を総合的に考えていきたい。
プロジェクト期間
2004年4月~2007年3月
- Tags
- 研究活動
