- その他
- 東洋医学の人間科学的研究
東洋医学の人間科学的研究
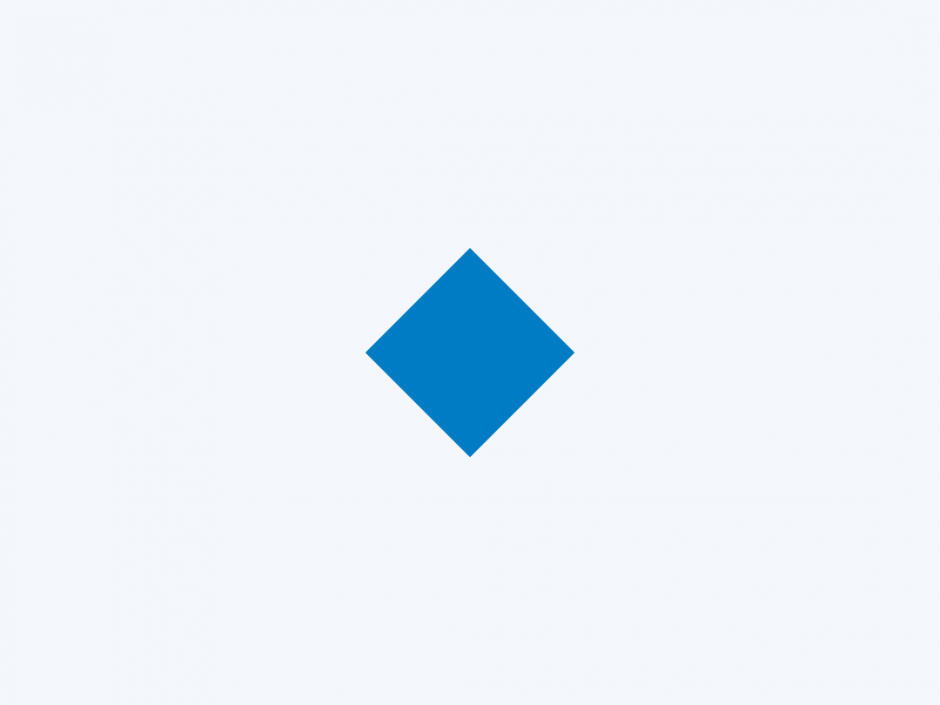
- Posted
- Fri, 16 Apr 2004

研究代表者
石井 康智
ISHII Yashutomo
文学学術院教授
本プロジェクトの概要と目的
長い歴史の中に培われた伝統医療、特に東南アジアの伝統医療に見られる発想と実践との関係を含め、その本質的生命観とその実践内容に心理-社会-生物的視点から光を当て、科学的に明らかにしていくことを目的とする。そこから知恵や知見・技術を社会に還元していく道が開けるであろう。
中国の中医学、チベットのチベット医学、インドのアーユルヴェーダ医学等は世界に誇る伝統医療である。日本は中国の影響下に東洋医学を発展させてきた。明治時代に入り、ドイツ医学を中心とした医学教育が導入され、西欧の医学を柱に据えた医学・医療を押し進めたのである。その結果、漢方医学・鍼灸・按摩の伝統的東洋医学は、明治時代以降、急速に勢いをなくす結果になった。しかし民間では細々ではあるが根強く利用され引き継がれてきたのである。
自然治癒力を引き出すための医療技術として実利的経験的知見を積み上げ、生命そのもの働きに呼応する医療システムを創り上げ、“未病を治す”医療・養生の実践を心掛ける長い歴史であり、西洋医学の予防医学と類似するが考え方は質的に異なる。しかし伝統医療には診断体系と医療実績があるにもかかわらず、西洋科学的な検討が立ち遅れ、実証性に欠けるものとして西洋医学に比べ劣るものとされた経緯がある。
しかし現在、西欧医学の診断と治療に関して、一部見直しが行われるようになって来ている。西欧医学は、病原体と感染症の直接的関係からくる原因-結果観から、今日、細菌性・ウイルス性等の感染症に対する保健医療には多くの成果を生み出し、その恩恵は計り知れない。全世界的に今でもその研究と医療は必要不可欠のである。一方、人々の生活の質が変わることによる疾病構造は、近年急速に変わりつつある。特に先進諸国と言われる国では、いわゆる生活習慣病が増加し、国家予算にも影響するまでになった。西洋医学も一種の伝統医学の発展型といえるが地域の伝統医療は見直されている。中国伝統医学である中医学は、考え方そのものはもの的であるが、心身論的であり、心と体全体を見ていく視点を持つ有力な人間観を持っている。従来の医学・生物学的側面のみならず、心理学領域からのアプローチによる「東洋医学の人間科学」を強力に推し進めてきた。心と体を含む全体の場、生命力や自然治癒力を重んじる視点を念頭に研究を進めている。豊富な知恵が蓄積された東洋の伝統医療に現代科学の光を当て直し、東西の医療と哲学思想の融合を図った心身論を求め、ホリスティックな立場から心理学的検討を加え、人間の健康と福祉に寄与できる科学的検討を推し進めている。
プロジェクト期間
2004年4月~2007年3月
- Tags
- 研究活動
