- その他
- ネットワークの人間科学:人・モノ・ネットワークのダイナミクスに関する広域システム科学的探究
ネットワークの人間科学:人・モノ・ネットワークのダイナミクスに関する広域システム科学的探究
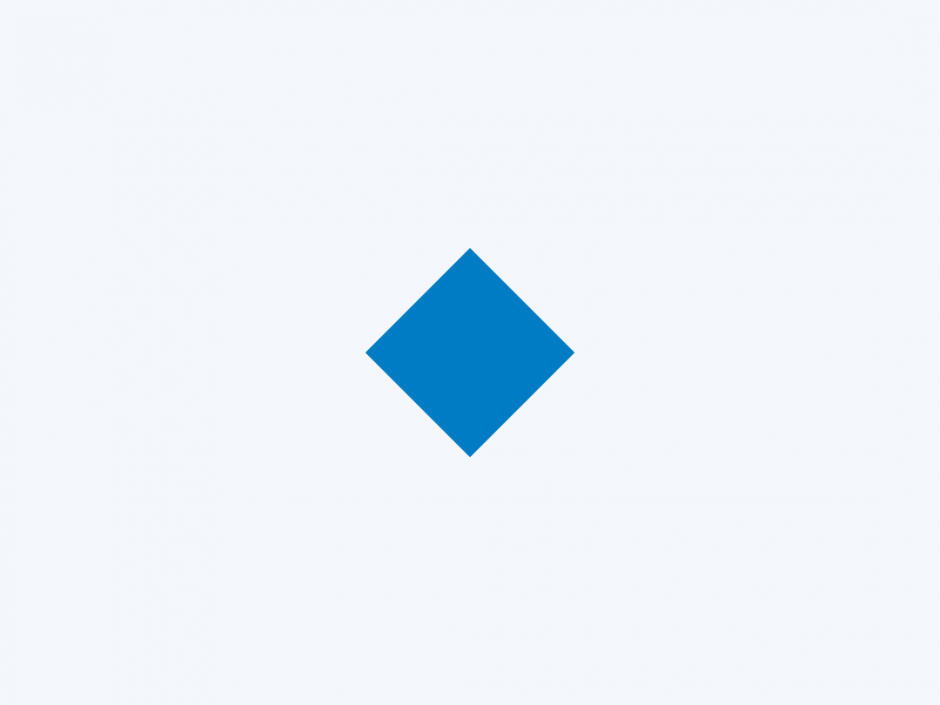
- Posted
- Fri, 16 Apr 2010

研究代表者
竹中 宏子
TAKENAKA Hiroko
人間科学部准教授
本プロジェクトの概要と目的
現代社会においては、それまで人間活動の基本的単位とされてきた血縁関係や地縁関係の脆弱化が進行し、個人の社会的位置づけが難しく、人と人との関係が捉えにくくなってきている。その背景には、近代というプロジェクトが推し進めてきた「個人化」のプロセスが介在する。その結果、家族や地域社会よりも、より自由だが個人の社会的位置づけとしては不安定な「友だち」を含む個人がとり結ぶ多様な社会的ネットワークが、個々人にとって重要になっている現状がある。
しかし、こうした社会的ネットワークに関する研究は、社会学や人類学において、その重要性は指摘されながらも個別の事例提示に止まり、未だ、多角的あるいは立体的に捉える理論的な構築には至っていない。1950年代に、バーンズ(J.A.Barnes)によるノルウェー漁村の階層研究と、ボット(E.Bott)によるロンドンの夫婦の役割研究によってその端緒がひらかれた社会的ネットワーク分析は、当初の人類学および社会学にとどまらず、自然科学にも逆輸入されて大きな広がりをみせている。
しかし、研究の端緒をひらいた人類学と社会学のネットワーク研究間の交流も十分とはいえず、その後に展開した心理学や情報科学等の研究領域との交流や対話は、これからの課題となっている。この現状を踏まえて、本プロジェクトは、学際的な研究領域から構成される人間科学部の特徴を活かし、社会的ネットワーク分析に関連した研究領域の交流と対話の場を提供し、そこから現代社会における人と人、人とモノの関係性を異なる視座から立体的に分析することを目標にしている。
本研究組織は、社会学、文化人類学、生態人類学、科学哲学、情報工学、生体情報工学、生態心理学といった異なる領域の研究者によって学際的に構成されている。しかし、単なる多分野からの寄せ集めではなく、「ネットワーク」をキーワードに異なる領域の研究者がその概念から議論する形をとる。この議論を通じて、これまで主に「モノ」に関心を寄せてきた自然科学系と、「人」に関心を寄せてきた人文社会科学系とが、従来の関心領域を超えて同じ土台で対話をする、まさに人間科学の理念に沿う共同研究を目指すものである。
研究構成員
- 竹中 宏子(早稲田大学人間科学学術院准教授)
- 池岡 義孝(早稲田大学人間科学学術院教授)
- 加藤 茂生(早稲田大学人間科学学術院専任講師)
- 金子 孝夫(早稲田大学人間科学学術院教授)
- 蔵持 不三也(早稲田大学人間科学学術院教授)
- 三嶋 博之(早稲田大学人間科学学術院准教授)
- 百瀬 桂子(早稲田大学人間科学学術院准教授)
- 矢野 敬生(早稲田大学人間科学学術院教授)
プロジェクト期間
2010年4月~2013年3月
- Tags
- 研究活動
