- ニュース
- 3月9日(月)日本の対外発信研究部会(部会主任:砂岡 和子)開催のお知らせ
3月9日(月)日本の対外発信研究部会(部会主任:砂岡 和子)開催のお知らせ
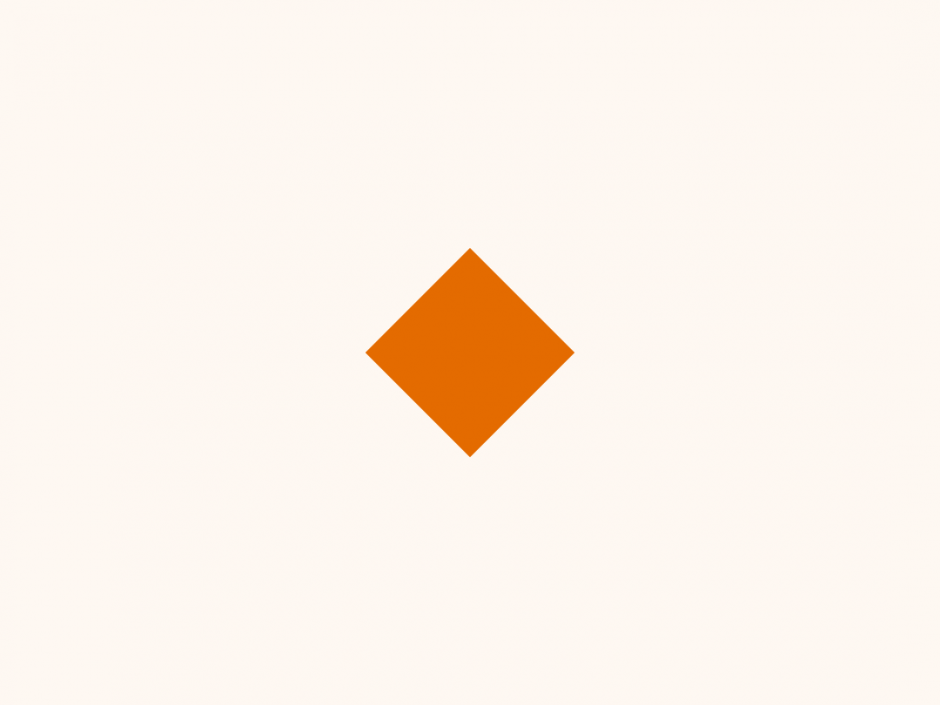
- Posted
- Mon, 02 Mar 2015
中国語教育学会の国際交流活動とネットワーク 講演会
日時:3月9日(月)17時30分-18時30分
場所:早稲田大学 早稲田キャンパス政治経済学部3号館914室
講師:平井 和之先生(日本大学文理学部教授)
コーディネーター:村上 公一先生(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)
講演題:中国語教育学会の国際交流と国際発信
発表概要:本報告では、報告者が会長を務める中国語教育学会の活動について報告すると同時に、 中国語教育に関連するその他の団体や活動を紹介する。世界的に見ると、中国語教育の対外発信に関しては 中国及び台湾との学術交流活動が盛んである。中国語母語圏との往来自体は隋唐代以来の長い歴史を有するが、 実は中国が対外中国語教育に本格的に力を入れだしたのは20世紀後半の改革・開放以降であり、 台湾もそれに続いたと言える。
一方、日本は中国語研究においては世界的なレベルにあると言えるものの、中国語教育の成果を国内で 一体となって海外に積極的に発信している状況では残念ながらなく、個別の大学等や個人がインターネット上で 教材等を発表しているに留まる。こうした現状についても、報告者の知るところを紹介したい。
中国語教育学会は歴史もまだ浅く規模も大きくはないが、今後は対外的・対内的にアピールして行かねばならない。 対外的には、「日本人に対する中国語教育」という面を前面に打ち出していくべきである。対内的には、 大学等の中国語履修者の減少という問題への対策が急務であろう。これらの目標実現は容易ではないが、 他外国語教育の専門家から御助言,御示唆等いただければ幸いである。
連続講演会の開催趣旨
早稲田大学現代政治経済研究所「日本の対外発信」特別部会では、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、 スペイン語、中国語、韓国語、日本語の各文化圏における国際学術交流について、連続シンポジウムを開催中です。 各言語の国際ネットワークの現状把握を通し、世界における日本の研究者の国際学術活動の展望を得るための企画です。
すでにドイツ語、ロシア語学会、韓国語学会、スペイン語学会、および日本の国際報道に関しては論文を公開中です。 併せご覧ください。
・早稲田大学現代政治研究所WorkingPaperシリーズ http://www.waseda-pse.jp/ircpea/jp/publish/working-paper-j-series/
coming soon 原田 康也『言語情報・英語教育関連学会・研究会の国際交流と国際発信』
No.J1409 木下 登『スペイン語学文学系学会・研究会の国際交流と国際発信』
No.J1407 西山 教行『日本フランス語教育学会の国際化と対外発信』
No.J1406 伊藤 英人『朝鮮語研究の国際交流活動とネットワーク-朝鮮語研究会・韓漢語言学研討会等の国際学術交流について(2014年)
No.J1404 黒岩 幸子『ロシア文学語学学会の国際交流活動とネットワーク』(2014年)
No.J1302 室井 禎之『ドイツ語学文学の国際交流・国際発信 -日本独文学会の国際交流事業を中心に- 』(2013年)
No.J1301 加藤 青延『日本の国際放送の実情と課題』(2013年)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
早稲田大学現代政治経済研究所「日本の対外発信」部会
砂岡 和子(部会代表 専門:中国語教育、遠隔教育) 宗像 和重(専門:日本文学研究) ソジエ内田 恵美(専門:応用言語学、日本研究、政治ディスコース分析) 生駒 美喜(専門:ドイツ語音声研究、会話分析、学習者言語の分析)
- Tags
- イベント
